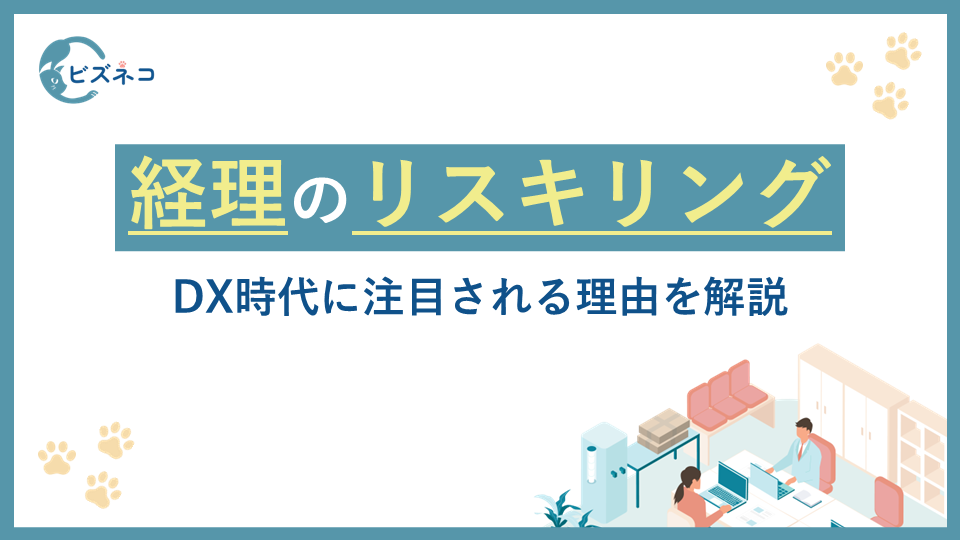
デジタル技術の進化がビジネスのあり方を大きく変えるなか、経理部門も例外ではありません。従来の帳簿入力や請求書処理といった業務に加え、今ではクラウド会計やAIによる自動仕訳など、新たなスキルへの対応が求められています。
こうした背景から注目されているのが「リスキリング」です。本記事では、DX時代における経理部門のリスキリングの重要性やメリット・デメリット、そして導入のポイントについて詳しく解説します。
目次
リスキリングとは?
リスキリングとは、現在の業務や将来的な仕事の変化に対応するために、新たなスキルを学び直す取り組みを指します。単なるスキルアップや知識の習得とは異なり、業務の構造そのものが変わる場面で必要とされるのが特徴です。
例えば、経理業務において紙の書類からクラウド会計ソフトへの移行が進むなかで、操作方法やデータ分析の基礎などを身につけることは、まさにリスキリングの一例といえるでしょう。DXが進む今の時代において、企業が変化に適応し続けるためには、個人のリスキリングが欠かせないものとなっています。
リスキリングとリカレント教育の違い
リスキリングとリカレント教育はどちらも学び直しを意味する言葉ですが、誰が主導するかによって異なります。リスキリングは、企業が主体となって、現在の仕事や企業のニーズに合わせて新たなスキルを短期間で習得することを指します。一方で、リカレント教育は、従業員が主体となって、より長期的な視点で人生の節目ごとに学びと仕事を繰り返す仕組みです。
例えば、リスキリングではITツールの操作やデータ活用のスキルを短期間で習得するのに対し、リカレント教育では大学や専門機関で体系的に学び直すといった方法が選ばれることもあります。それぞれの特性を理解することで、自身や組織の状況に応じた学習方法の選択が可能になります。
リスキリングと生涯学習の違い
リスキリングと生涯学習の違いは、学ぶ内容の範囲です。リスキリングはより仕事に直結した実践的なスキルの再習得を目指す学習を指します。一方で、生涯学習という言葉には、年齢や職業を問わず、生涯にわたって学び続けるという幅広い意味が込められています。
例えば、リスキリングは新しい業務に対応するためにプログラミングやデジタルツールの使い方を習得するといったケースが該当し、生涯学習では趣味や教養を深めるために語学や歴史を学ぶことやボランティア活動も含まれます。どちらも知的成長を促す点では共通していますが、リスキリングはとりわけ業務変革やキャリアの転換期に重視される学びの形といえるでしょう。
経理部門のリスキリングが注目される理由
経理部門のリスキリングが注目される理由として、以下のような点があげられます。
- DX化の加速による業務環境の変化
- 人材不足への対策としての社内人材の育成
- 定型業務の自動化で求められるスキルの転換
ここでは、それぞれの理由について詳しく解説していきます。
DX化の加速による業務環境の変化
デジタル技術の進展により、経理業務のあり方はこれまでとは大きく変わってきました。紙での帳簿管理や手作業での仕訳入力は減少し、代わりにクラウド会計やAIを活用した業務が一般化しつつあります。
例えば、請求書のデータを自動で読み取り、仕訳まで処理するツールの導入が進んでいます。こうした変化に対応するには、新たな知識や操作スキルを身につける必要があり、そのためのリスキリングが重要視されています。経理の現場に求められる役割が変わるなか、変化に適応できる人材の育成が急務となっているのです。
なお、経理のDX化については、こちらの記事でもまとめています。
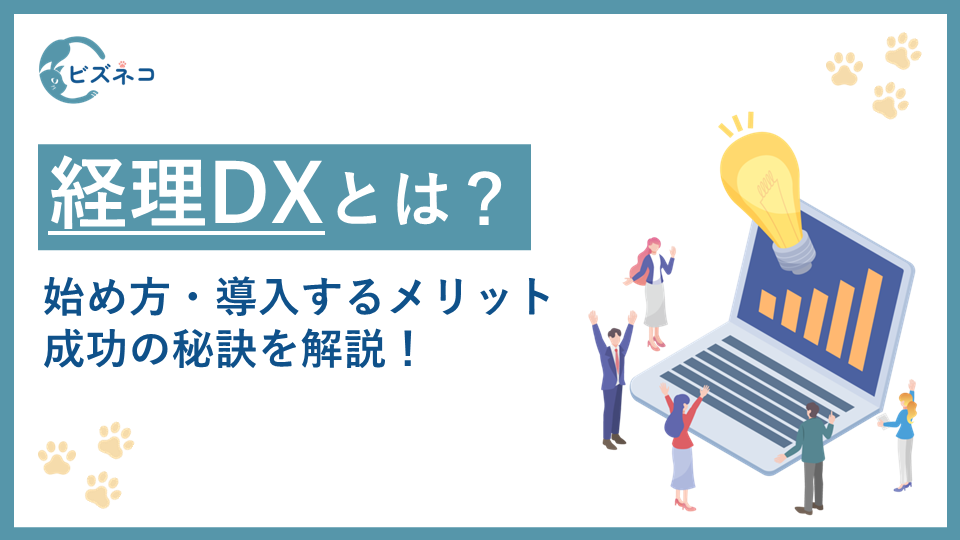
人材不足への対策としての社内人材の育成
慢性的な人手不足が多くの企業で課題となるなか、外部から人材を採用するだけでなく、社内の人材を育成して新たな業務に対応させる動きが広がっています。特に経理部門では、専門知識と業務の正確性が求められるため、既存の社員をリスキリングによって戦力化する方が現実的なケースもあります。
例えば、長年請求処理を担当していた社員が、研修を通じてRPAの設定を学び、業務の自動化に携わるようになった事例もあります。こうした取り組みは、人材の有効活用とともに、組織の柔軟性や持続性を高めるうえでも重要な施策となっています。
なお、経理の人材不足については、こちらの記事でも解説しています。
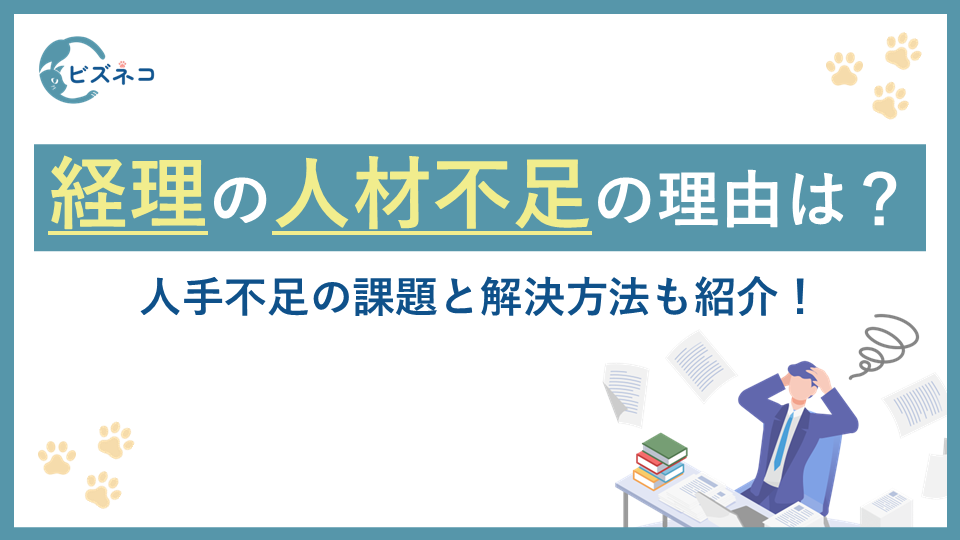
定型業務の自動化で求められるスキルの転換
経理業務のなかでも、伝票入力や帳簿記帳といった定型作業は、自動化の進展によって大きな転換期を迎えています。これまで人の手で行っていた作業がツールによって自動処理されるようになる一方で、人にはより分析的かつ判断的な役割が求められるようになってきました。
例えば、月次決算の報告においても、数値の集計ではなく、異常値の原因分析や部門別の収支傾向を把握するといった業務が重視されるようになります。こうした変化に対応するためには、単なる業務経験だけでなく、データリテラシーや論理的思考といった新たなスキルが必要とされるのです。
なお、自動化やAIの発展における経理の今後については、こちらの記事でもまとめています。
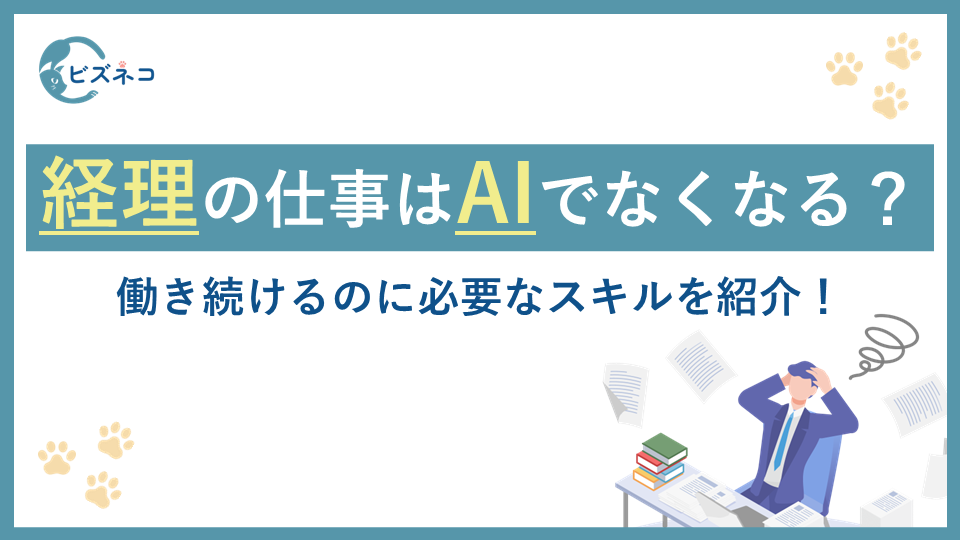
経理部門のリスキリングにおけるメリット
経理部門のリスキリングにおけるメリットとして、以下のような点があげられます。
- デジタルツールの活用による業務効率化ができる
- 社員のモチベーションやキャリア意識の向上につながる
- 組織の変化に強い人材の育成が可能になる
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
デジタルツールの活用による業務効率化ができる
デジタルツールの活用による業務効率化ができる点がリスキリングのメリットです。経理部門のリスキリングが進むことで、業務の中でデジタルツールを効果的に使いこなす力が身につき、日々の作業効率が大きく改善される可能性があります。
例えば、これまで時間をかけて行っていた仕訳作業が、AIツールの導入によって数分で完了するようになれば、担当者は空いた時間でより重要な業務に集中できるようになります。Excelやクラウド会計ソフト、RPAなどを適切に使いこなすには一定の知識が必要ですが、それを身につけることで、経理の現場全体の生産性向上にもつながっていきます。
社員のモチベーションやキャリア意識の向上につながる
社員のモチベーションやキャリア意識の向上につながる点もリスキリングのメリットです。新たなスキルを学び、成長を実感できる機会があることは、社員一人ひとりのモチベーションやキャリアに対する意識の変化を生み出す要因となります。
特に経理業務はルーティンが多いため、自身の業務の幅が広がったり、新しい分野に挑戦できたりすることが刺激となることもあります。
例えば、これまで仕訳入力を中心に行っていた社員が、データ分析やコスト管理のスキルを習得し、経営層へのレポート作成に携わるようになると、自分の仕事が会社に与える影響を実感できるようになります。こうした変化は、長期的に働くうえでの意欲や満足度にも関わってくるでしょう。
組織の変化に強い人材の育成が可能になる
組織の変化に強い人材の育成が可能になる点も、経理のリスキリングのメリットです。企業を取り巻く環境がめまぐるしく変わるなかで、経理部門も変化に対応できる柔軟な人材を求められるようになっています。
リスキリングによって、特定の業務だけにとどまらず幅広い分野に対応できるスキルを持つ人材を育てることが、組織全体の安定性や適応力の向上にもつながります。例えば、新しい会計基準やITシステムが導入された際に、自ら情報を取得し、現場で活用方法を提案できるような社員が増えれば、組織としても変化に対して素早く動ける体制を整えることができます。
経理部門のリスキリングにおけるデメリット
経理部門のリスキリングにおけるデメリットとして、以下のような点があります。
- 教育や研修に時間とコストがかかる
- 現場の業務と並行することで負担が増える
- 習得スピードや成果に個人差が出やすい
ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。
教育や研修に時間とコストがかかる
リスキリングを導入する際、最初に直面するのが「教育にかかるコスト」と「業務時間の確保」という課題です。新たな知識やスキルを身につけるには、学習の場を設けたり外部講師を招いたりする必要があり、一定の時間と予算が求められます。
例えば、経理部門向けにクラウド会計ソフトの操作研修を実施する場合、研修費だけでなく、その間の業務調整や代替要員の手配といった間接的なコストも発生します。業務効率化を目的とした取り組みであっても、導入初期は企業にとって少なからず負担がかかることを考慮しておく必要があります。
現場の業務と並行することで負担が増える
リスキリングは業務に直結する学びである一方で、現場の仕事と並行して行うことが多く、担当者にとっては負担が増える点がデメリットです。特に経理部門は月次や年次などの締め処理が集中する時期があり、ただでさえ業務量が多い中で新たな学習時間を確保するのは簡単ではありません。
例えば、決算期と研修期間が重なってしまえば、どちらの対応にも支障が出る恐れがあります。また、OJT形式での学習の場合、教える側にも手間がかかり、部門全体の負担が増してしまうこともあるため、スケジュール調整やサポート体制の構築が重要になります。
習得スピードや成果に個人差が出やすい
リスキリングは一律の教育ではなく、個々の理解度や経験に大きく左右される点もデメリットになります。経理業務に必要なデジタルスキルや分析能力は、すでに類似の経験がある人には吸収しやすい反面、初めて触れる人には大きな壁となる場合があります。
例えば、年齢や職歴にかかわらず、RPAツールの活用方法やデータの可視化手法に対して適応できるスピードにはばらつきが出がちです。このような個人差が、学習の進捗や業務への適用に影響を与えることもあるため、一人ひとりに合ったサポート体制や柔軟な運用が求められます。
経理部門におけるリスキリングの導入手順
経理部門におけるリスキリングの導入手順は以下の流れで進みます。
- step1:現在のスキルと業務内容を把握する
- step2:必要なスキルを明確化して学習計画を立てる
- step3:学んだスキルを実務で活かす環境を整える
ここでは、それぞれのステップについて具体的に解説します。
step1:現在のスキルと業務内容を把握する
リスキリングを効果的に進めるためには、まず現状を正しく把握することが重要です。現時点でどのような業務を行っており、どの程度のスキルを持っているのかを明確にすることで、今後の学習方針を具体的に立てることができます。
例えば、帳簿入力や経費精算が中心の担当者と、月次決算や分析業務に関わっている担当者とでは、求められるスキルも学習の優先順位も異なります。現場ごとの業務内容を丁寧に棚卸しすることで、リスキリングの対象や目標がぶれにくくなり、組織としての投資効果も高まります。
step2:必要なスキルを明確化して学習計画を立てる
現在のスキルと業務の実態を把握したあとは、将来的に必要とされるスキルを明確にし、段階的な学習計画を立てていきます。目指す姿に向かって、どのような知識やツールの習得が必要かを整理することが、学びの道筋を見える化する第一歩です。
例えば、会計ソフトの操作だけでなく、Excelでのデータ分析やRPAツールの活用など、実務と直結する内容を組み込むことで、研修の実効性も高まります。また、個人の習熟度に応じて学習ステップを柔軟に設計することで、挫折しにくい仕組みを作ることも可能です。
step3:学んだスキルを実務で活かす環境を整える
リスキリングで得た知識やスキルは、実務に活かしてこそ意味があります。そのため、学習後にスキルを試せる環境や、実際の業務で活用する機会を用意することが欠かせません。
例えば、研修で学んだ関数を使って経費集計のフォーマットを改良してみたり、RPAで作業の一部を自動化してみたりすることで、習得内容を定着させやすくなります。こうした実践の場があることで、学びが単なる座学で終わらず、現場にとっての「使えるスキル」として根付きます。また、継続的に振り返りや改善の仕組みを設けることも、スキル活用を定着させるうえで効果的です。
経理部門におけるリスキリングのポイント
経理部門におけるリスキリングのポイントとして、以下のような点があげられます。
- 経理業務に直結するスキルから優先的に学ぶ
- OJTと座学のバランスを考慮する
- 経理代行会社に相談する
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
経理業務に直結するスキルから優先的に学ぶ
リスキリングを効率的に進めるには、まずは経理業務に直結するスキルから学ぶことが重要です。限られた時間とリソースの中で成果を上げるためには、実務にすぐ役立つ内容を優先する必要があります。
例えば、会計ソフトの新機能やExcelの関数スキル、電子帳簿保存法への対応など、日々の業務で活用される場面が多い知識を習得すれば、学習の効果も実感しやすくなります。基礎から応用に向けて段階的に学ぶことで、業務への定着もしやすく、モチベーション維持にもつながります。まずは目の前の業務課題に必要なスキルを明確にすることが出発点となるでしょう。
OJTと座学のバランスを考慮する
リスキリングの実効性を高めるには、OJT(実務を通じた学習)と座学(知識の習得)のバランスを適切に取ることが求められます。どちらか一方に偏ると、習得した内容が実務で活かされなかったり、理解が浅いまま作業を進めてしまったりするリスクがあります。
例えば、新しい経費精算システムを導入する際には、まず操作方法や背景知識を座学で学んだうえで、実際の申請処理をOJTで体験することで、知識と実践を結びつけることができます。そのため、学ぶ順番や方法を工夫しながら、段階的にスキルを習得していくことで、より確実なスキル定着につながっていくといえるでしょう。
経理代行会社に相談する
社内でリスキリングを進めるにあたり、専門知識や指導ノウハウが不足している場合には、外部の経理代行会社に相談することもおすすめです。とくに最新の会計ソフトや法令対応に関する知識は、外部の専門家からの支援を受けることで、より実践的かつ効率的に習得できる可能性があります。
例えば、インボイス対応の運用方法や、ペーパーレス化の実務的な流れを現場目線でアドバイスしてもらえることで、机上の知識では得られない実務力が身につきやすくなります。自社に足りない部分を補いながら、無理のない学習環境を整えるためにも、外部の力を柔軟に活用することは大切な手段といえるでしょう。
なお、経理代行についてはこちらの記事も参考にしてください。
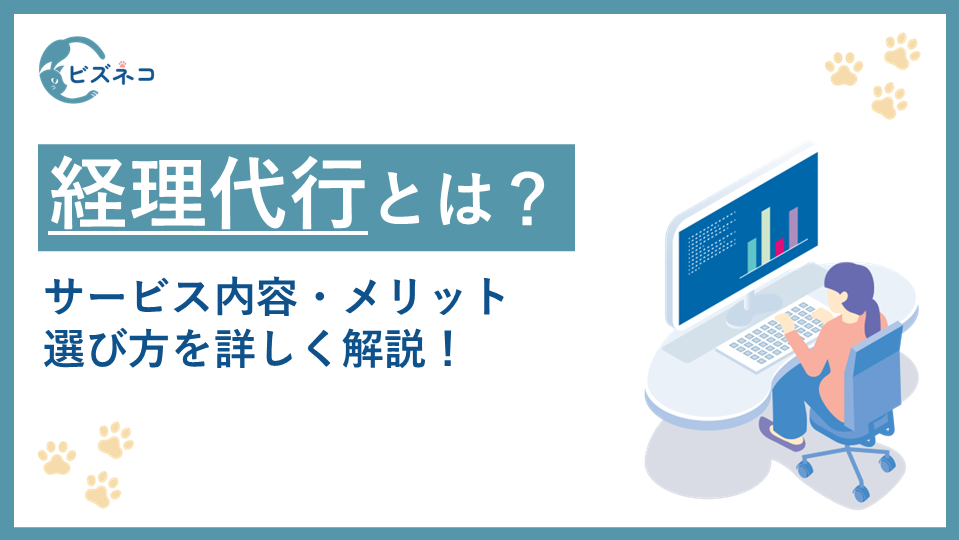
まとめ
リスキリングとは、現在の業務や将来的な仕事の変化に対応するために、新たなスキルを学び直す取り組みを指します。単なるスキルアップや知識の習得とは異なり、業務の構造そのものが変わる場面で必要とされるのが特徴です。
経理業務においては、業務効率化につながり、社員のモチベーションやキャリア意識の向上につながる点がメリットです。また、組織変化に強い人材育成も可能になります。しかし、教育に時間がかかり、現場の業務と平行することで業務負担が増えてしまう点が課題です。そのため、経理代行会社に相談することもひとつの手です。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
経理部門のリスキリングに関するよくあるご質問
経理部門のリスキリングについてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、経理部門のリスキリングに関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
OJTとリスキリングの違いは何ですか?
OJTとリスキリングの違いは、学ぶ内容が「現在」か「将来」かにあります。OJTは現場での実務を通じてスキルを身につける方法で、日々の業務をこなしながら学ぶのが特徴です。一方、リスキリングは業務の構造変化やDXに対応するために、従来とは異なるスキルをあらためて学び直す取り組みを指します。
リスキリングが進まない理由は何ですか?
リスキリングが進まない要因としては、教育にかかる時間やコストが大きいこと、現場の業務と並行して取り組む難しさがあげられます。例えば、決算期の多忙な時期に研修を実施しても、業務との両立が難しく効果が薄れてしまうこともあります。そのため、業務時間と学びの時間を用意するマネジメントが企業に求められます。
リスキリングとリカレント教育の違いは何ですか?
リスキリングとリカレント教育はどちらも「学び直し」を意味しますが、目的と主導者に違いがあります。リスキリングは企業が主体となり、今の仕事や業務変化に対応するための短期的かつ実践的なスキル習得を促すものです。一方、リカレント教育は本人が主体となり、人生の節目で体系的に学ぶ長期的な取り組みです。




