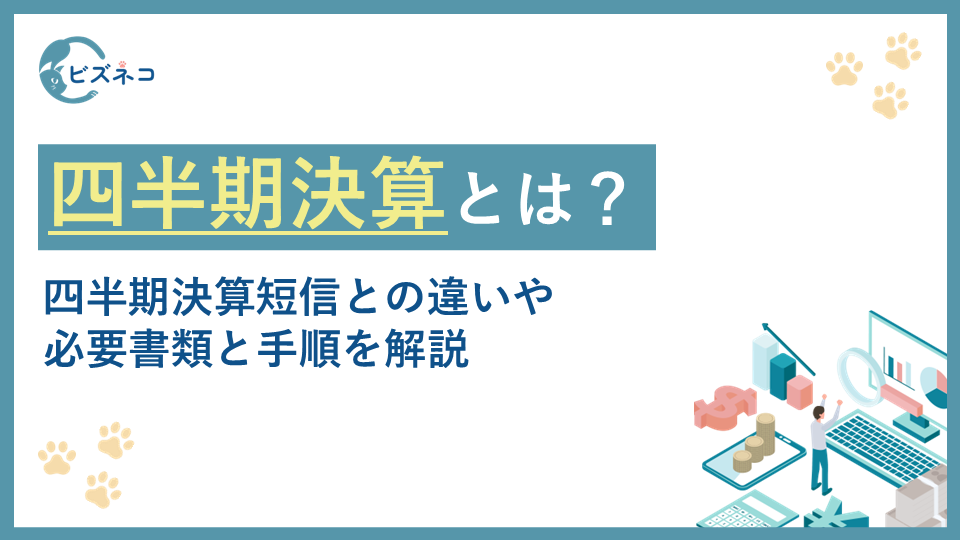
四半期決算とは、企業が1年間を4つの期間に区切って業績を集計する決算のことを指します。投資家や金融機関、経営陣にとっては、企業の経営状況をタイムリーに把握するための重要な資料となります。
この記事では、四半期決算の基本的な仕組みや、月次・半期・年次決算との違いをはじめ、作成に必要な財務三表や決算手続きの流れをわかりやすく解説します。また、決算の正確性を高めるための注意点や、効率化に役立つ実務的な工夫についても紹介します。
目次
そもそも決算とは?
決算とは、一定期間の企業活動を数値で整理し、その成果を明らかにする会計手続きです。主に損益計算書や貸借対照表、キャッシュフロー計算書といった財務諸表を作成し、経営成績や財務状況を客観的に示します。例えば、損益計算書では売上や費用の推移から利益の構造を分析でき、貸借対照表では資産や負債のバランスを確認することが可能です。
決算は、経営者にとって今後の戦略を見直す機会であると同時に、株主や金融機関などの利害関係者に対して経営の透明性を示す重要な役割を担っています。また、税務申告や配当決定など法的な手続きとも密接に関わるため、正確な会計処理が求められます。
なお、決算についてはこちらの記事もご覧ください。
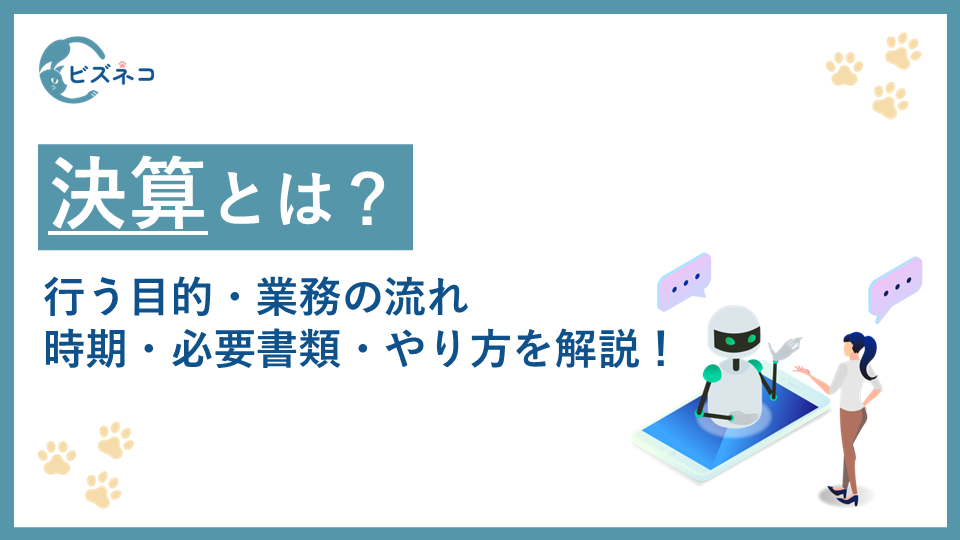
決算の種類
決算には主に「月次決算」「四半期決算」「半期決算(中間決算)」「年次決算(本決算)」の4つの種類があります。それぞれの期間で企業の経営成績や財務状況をまとめる決算手続きです。ここでは、それぞれの決算の役割について具体的に解説します。
月次決算
月次決算は、毎月の経営状況を迅速に把握するために行う短期的な決算です。売上や費用、利益などを定期的に集計することで、経営の現状を正確に把握し、次の月の方針を早期に立てることができます。
例えば、特定の月に販売費が急増している場合、その要因を分析して翌月以降の予算配分を見直すといった対応が可能になります。月次決算はスピードと正確性の両立が求められますが、タイムリーな経営判断や資金繰りの改善に役立ちます。継続的に実施することで、年間を通じた業績の推移を把握しやすくなり、年次決算や四半期決算の準備にもつながります。
四半期決算
四半期決算は、1年間を4つの期間に分け、3か月ごとに業績を集計する決算です。本決算のように正確な財務情報をまとめつつ、経営の中間報告としての役割も果たします。例えば、新規事業を開始した場合、四半期ごとに収益やコストを確認することで、早い段階から改善策を検討できます。
四半期決算は、企業内部の経営分析だけでなく、投資家や取引先など外部関係者への情報提供にも重要です。決算短信を通じて業績の進捗を明らかにすることで、企業の信頼性向上にもつながります。
半期決算(中間決算)
半期決算(中間決算)は、会計年度の前半6か月の業績を集計し、企業の経営状況を確認するために行われます。本決算の中間地点として、進捗の把握や目標達成に向けた修正に活用されます。例えば、上期の販売実績が計画を下回っている場合、下期に向けた販売戦略の見直しやコスト削減策の検討が可能になります。
半期決算は、金融機関や株主などの利害関係者に対する報告資料としても重視され、企業の信頼性を支える要素のひとつです。特に上場企業では、透明性の高い情報開示が求められます。
年次決算(本決算)
年次決算(本決算)は、1年間の企業活動を総括し、経営成績や財務状態を明らかにする最終的な決算です。損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を作成し、株主総会や税務申告の基礎資料として活用されます。
例えば、売上総利益や営業利益を通じて、年間の経営成果を客観的に評価できるほか、来期の経営計画や投資判断にも役立ちます。年次決算は、企業の信用力や成長性を示す重要な指標となるため、正確な会計処理と内部統制の整備が求められます。
廃止された四半期報告書とは?
四半期報告書とは、かつて金融商品取引法に基づいて上場企業に提出が義務付けられていた書類で、各四半期ごとに企業の経営成績や財務状況を開示する役割を担っていました。例えば、投資家が企業の業績を早期に把握できるよう、損益計算書や貸借対照表などの財務情報を詳細に記載することが求められていました。
しかし、年4回の提出義務は企業の事務負担が大きく、実務上の効率性にも課題がありました。そのため、2023年の制度改正によって四半期報告書は廃止され、現在は「四半期決算短信」による任意開示に移行しています。これにより、より柔軟かつ迅速な情報発信が可能となり、企業は開示コストを抑えながらも投資家との情報共有を継続できるようになりました。
四半期決算短信とは?
四半期決算短信とは、企業が3か月ごとの業績を外部に公表するために作成する開示資料であり、投資家や取引先に向けて経営状況をわかりやすく伝える役割を持ちます。例えば、売上高や営業利益、純利益といった主要な数値を簡潔にまとめ、経営の進捗や今後の見通しを示すことが一般的です。
従来の四半期報告書よりも形式がシンプルであり、上場企業では信頼性の確保や株主への説明責任の観点から義務付けられ公表されています。迅速な開示が求められるため、決算整理や資料作成の効率化が重要となり、経理部門には正確性とスピードの両立が求められます。
四半期決算に用いられる財務三表
四半期決算に用いられる財務三表とは、企業の財政状態や経営成績を明確に示すために作成される重要な財務報告書のことです。通常、四半期ごとに作成され、主に「四半期損益計算書(P/L)」、「四半期貸借対照表(B/S)」、「四半期キャッシュフロー計算書(C/F)」と呼ばれる「財務三表」で構成されます。
四半期損益計算書(P/L)
四半期損益計算書は、3か月間の企業活動における収益と費用を整理し、最終的な利益を明らかにする財務諸表です。売上高や原価、販売費、一般管理費などの項目を通じて、短期間の経営成果を把握することができます。
例えば、新商品の販売を開始した場合、その四半期でどの程度の収益が得られたかを分析することで、戦略の妥当性を検証することが可能です。四半期ごとに利益の構造を確認することで、季節変動や一時的な費用増減の影響を把握しやすくなり、次期の経営判断にもつながります。こうした定期的な分析は、安定した収益基盤を築くうえで欠かせません。
なお、損益計算書についてはこちらの記事をご覧ください。
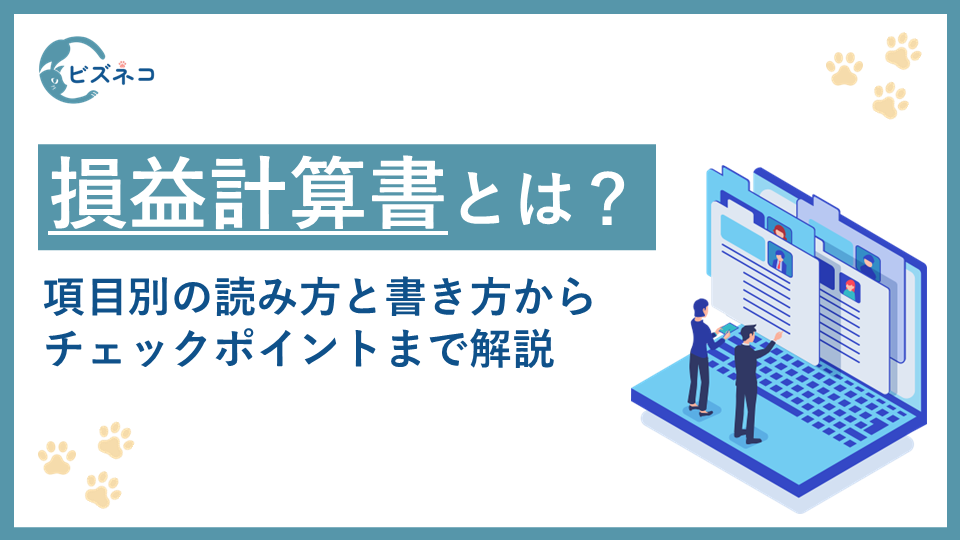
四半期貸借対照表(B/S)
四半期貸借対照表は、四半期末時点の企業の財務状態を示す表で、資産・負債・純資産のバランスを明確にします。例えば、現金や売掛金などの流動資産の増減を確認することで、資金繰りの状況や回収スピードを把握でき、同時に負債の構成を見ることで、返済計画や資金調達の健全性を評価できます。
年次決算に比べて期間が短い分、変化の兆しを早期に捉えることができるのが特徴であり、経営上のリスク管理や財務改善に活用されます。四半期ごとに貸借のバランスを確認することで、企業は安定した財務基盤を維持しやすくなります。
なお、貸借対照表についてはこちらの記事をご覧ください。
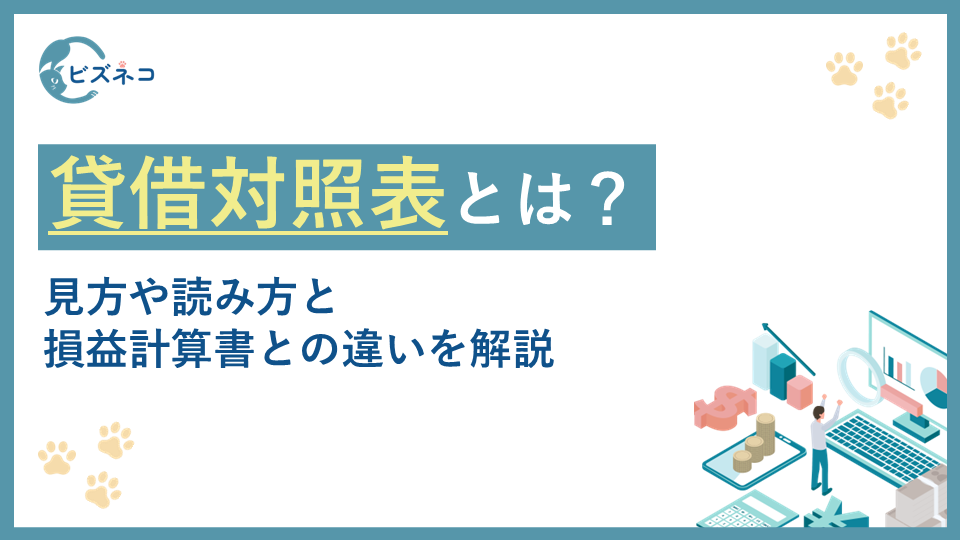
四半期キャッシュフロー計算書(C/F)
四半期キャッシュフロー計算書は、3か月間の資金の流れを示し、現金の増減要因を明確にするための財務諸表です。営業・投資・財務活動の3つの区分で構成され、企業がどのように資金を得て、どこに使ったかを把握できます。
例えば、営業活動によるキャッシュフローがプラスであれば、本業が順調に利益を生んでいることがわかり、逆にマイナスであれば早急な改善が必要です。短期的な資金繰りの安定性を確認するうえでも重要であり、四半期単位で作成することで、資金の過不足を早期に察知し、次の経営施策に反映できます。
なお、キャッシュフロー計算書についてはこちらの記事をご覧ください。
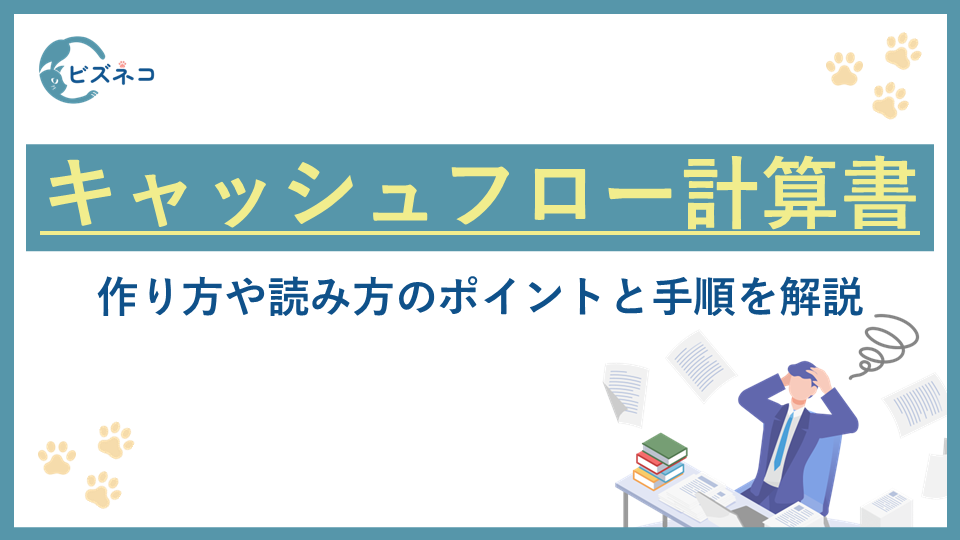
四半期決算の手順と流れ
四半期決算の手順は以下の流れで進みます。
- step1:四半期の記帳を完了させる
- step2: 決算整理仕訳を進める
- step3:財務諸表(財務三表)を作成する
- step4: 取締役会や会計監査人から承認を得る
- step5:四半期決算短信を公表する
ここでは、それぞれのステップについて具体的に解説します。
step1:四半期の記帳を完了させる
四半期決算の最初のステップは、四半期内の取引をすべて記帳し、会計帳簿を正確に整えることです。売上や仕入、経費など、期間中に発生した取引をもれなく反映させることで、次の決算整理や財務諸表作成の精度が高まります。
例えば、請求書や領収書の処理が遅れていると、売上や費用が正しく計上されず、利益額に誤差が生じるおそれがあります。そのため、日次・月次の段階から記帳を習慣化し、残高の突合や証憑の確認を行うことが大切です。正確な記帳を完了させることは、四半期決算全体の信頼性を支える基盤となります。
step2: 決算整理仕訳を進める
四半期の取引記帳が完了したら、次に行うのが決算整理仕訳です。実際の経済活動に合わせて会計帳簿を正しく修正するための重要な工程です。例えば、まだ支払っていない費用を「未払費用」として計上したり、受け取っていない売上を「未収収益」として記録するなど、発生主義に基づく調整が必要です。
また、減価償却や引当金の計上もこの段階で行います。これらの仕訳を正確に行うことで、期間損益が適切に反映され、信頼性の高い財務諸表を作成する準備が整います。ミスを防ぐためには、過去データとの整合性を確認することも重要です
step3:財務諸表(財務三表)を作成する
決算整理仕訳が完了したら、四半期の業績や財務状況を明らかにするために財務諸表を作成します。主なものは損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書の3つで、これらを総称して財務三表と呼びます。
例えば、損益計算書では利益構造を、貸借対照表では資産や負債の状態を、キャッシュフロー計算書では資金の動きを確認できます。これらを四半期ごとに作成することで、経営の現状を正確に把握し、投資家や取引先に対して透明性のある情報を提供できます。作成時は、整合性や勘定科目の分類ミスに注意しながら慎重に仕上げることが大切です。
step4: 取締役会や会計監査人から承認を得る
財務諸表が完成したら、社内外の承認プロセスに進みます。上場企業の場合、取締役会での承認や会計監査人によるレビューを経て、四半期決算としての正当性を確認する必要があります。例えば、取締役会では業績の進捗や課題の共有が行われ、経営戦略の見直しや次期方針の検討にもつながります。
また、会計監査人の確認を通じて、会計処理の妥当性や開示内容の信頼性が担保されます。こうした承認手続きを経ることで、外部公表に耐えうる正確な決算情報となり、企業の信頼性を高めることができます。
step5:四半期決算短信を公表する
承認を得た後は、四半期決算短信を作成し、投資家や取引先などの利害関係者に向けて公表します。四半期決算短信は、損益計算書や貸借対照表などの主要情報をまとめた資料で、企業の業績を簡潔に伝える役割を担います。
例えば、売上高や営業利益の推移を開示することで、企業の成長性や収益性を判断する材料を提供できます。非上場企業では提出義務はありませんが、上場企業では透明性の確保や市場からの信頼維持のために公表が義務づけられています。正確かつわかりやすい資料を作成することで、企業価値の適切な評価につながります。
四半期決算における注意点
四半期決算における注意点として、以下のような点を意識しましょう。
- 図やグラフを用いてわかりやすく作成する
- 四半期決算に定めた期日を守る
- 難しい表現や専門用語をなるべく避ける
ここでは、それぞれの注意点について具体的に解説します。
図やグラフを用いてわかりやすく作成する
四半期決算を作成する際は、数値や文章だけでなく、図やグラフを用いて視覚的にわかりやすくまとめることが大切です。例えば、売上や利益の推移を折れ線グラフで示すと、前期比や前年同期比の変化を一目で確認でき、経営陣や投資家が状況を素早く把握できます。
複雑なデータも、円グラフや棒グラフを活用すれば直感的に理解でき、報告書全体の説得力も高まります。また、視覚化は誤解を防ぐ効果もあり、資料を共有する場面でも有効です。決算書の正確性だけでなく、見やすさや伝わりやすさを意識することが、情報開示の質を高めるポイントになります。
四半期決算に定めた期日を守る
四半期決算は、定められた期日を厳守して公表することが求められます。期日を守ることで、投資家や取引先に対して誠実な経営姿勢を示すことができ、企業への信頼を維持することにつながります。
例えば、提出が遅れると、業績に不安を抱かせたり、証券取引所の開示ルールに抵触するおそれもあります。特に上場企業では、開示スケジュールが市場関係者の分析や投資判断に影響を与えるため、計画的なスケジュール管理が欠かせません。日々の記帳や月次決算を確実に行い、早期に資料を整備しておくことで、期日遵守を実現しやすくなります。
難しい表現や専門用語をなるべく避ける
四半期決算書を作成する際は、読み手の理解度を考慮し、専門用語や難解な表現をできるだけ避けることが重要です。例えば、経営層や投資家の中には会計の専門知識を持たない人も多いため、抽象的な会計用語や複雑な説明が多いと、内容の正確な理解を妨げるおそれがあります。
専門的な用語を使う場合は、注釈や補足を加えて背景を説明すると効果的です。誰が読んでも同じ認識を持てるよう、簡潔で具体的な表現を心がけることが信頼性の高い決算書づくりにつながります。明確な言葉選びは、情報開示の透明性を高める役割を担っているといえるでしょう。
四半期決算を効率化するポイント
四半期決算を効率化するポイントとして以下のような点があげられます。
- 業務フローを見直してムダな作業を減らす
- 自動仕訳やDX化を進める
- 経理代行や記帳代行に相談する
ここでは、それぞれのポイントについて具体的に解説します。
業務フローを見直してムダな作業を減らす
業務フローの見直しは、四半期決算の効率化に欠かせない第一歩です。作業手順を整理し、重複している工程や不要な確認作業を削減することで、無駄な時間や人的コストを抑えることができます。例えば、請求書処理や経費精算のフローを細かく洗い出すと、承認ルートの複雑さや入力作業の二重化といった課題が明確になります。
そのうえで、承認段階の簡略化や担当範囲の再定義を行えば、決算作業のスピードと精度が向上します。限られた期間で正確な数値をまとめる四半期決算では、日常業務の効率化が成果を左右するため、フロー全体の見直しは重要な取り組みといえます。
なお、経理の業務フロー改善については、こちらの記事も参考にしてください。

自動仕訳やDX化を進める
自動仕訳やDX化の推進は、四半期決算を効率的に進めるうえで欠かせない手段です。仕訳の入力や集計を手作業で行うと、どうしてもミスや遅延が発生しやすく、確認作業にも時間を取られます。例えば、クラウド会計ソフトを活用して銀行口座やクレジットカードのデータを自動連携すれば、仕訳作業を大幅に省力化でき、担当者は分析やチェックなどの付加価値業務に注力できます。
また、経費精算や請求書処理など関連業務もデジタル化することで、情報の一元管理が可能となり、データの整合性を保ちながら迅速な決算が実現します。テクノロジーを積極的に取り入れることが、今後の経理体制の強化にもつながるでしょう。
なお、経理のDX化についてはこちらの記事も参考にしてください。
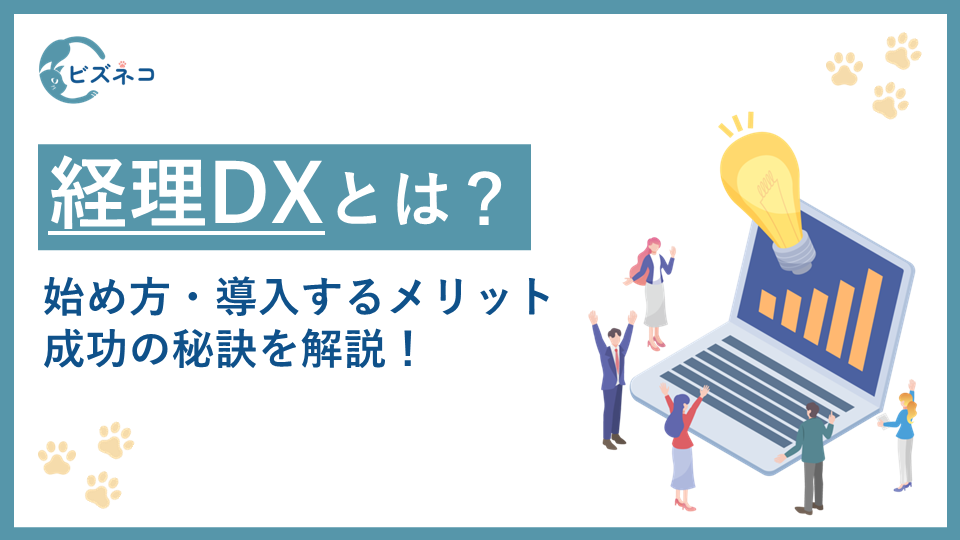
経理代行や記帳代行に相談する
四半期決算をスムーズに進めるためには、経理代行や記帳代行への相談もおすすめです。人手不足や属人化によって業務が滞りがちな企業にとって、外部専門家のサポートが効果的なシーンも多くあります。
例えば、取引量の多い期間に記帳代行を活用すれば、仕訳入力や帳簿作成を効率的に進められ、社内担当者は分析や報告資料の作成といったコア業務に専念できます。また、経理代行を活用すれば、決算資料のチェックや仕訳の精度向上も期待でき、全体のスケジュール管理も安定します。限られたリソースを補いながら、品質を保った決算を実現するうえで、外部リソースの活用は効果的な手段といえるでしょう。
なお、決算業務を代行するサービスもあります。決算代行についてはこちらの記事も参考にしてください。
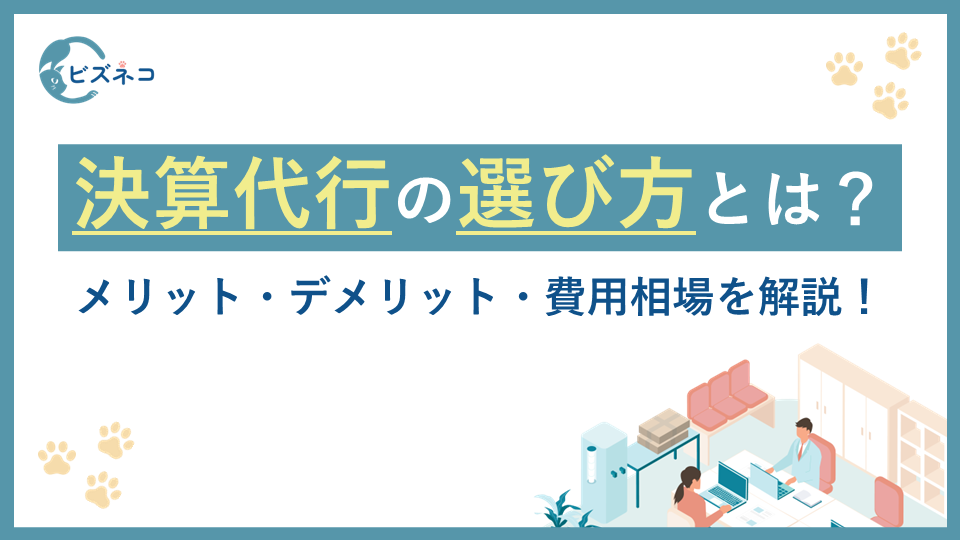
まとめ
四半期決算は、年4回の決算を通じて企業の経営状況をタイムリーに把握するための重要な手続きです。例えば、利益の変動や資金繰りの課題を早期に発見し、次の経営戦略に反映できる点が大きなメリットです。以前は「四半期報告書」の提出が義務付けられていましたが、現在は事務負担の軽減を目的に「四半期決算短信」へと移行し、柔軟かつ迅速な情報開示が可能になっています。
決算書類の作成にあたっては、正確な記帳や決算整理仕訳、財務三表の整備が欠かせません。また、必要に応じて経理代行を活用することで、品質とスピードの両立も図れるでしょう。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
四半期決算に関するよくあるご質問
四半期決算についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、四半期決算に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
四半期決算の開示は義務ですか?
四半期決算そのものの提出義務は2023年の制度改正により廃止されました。しかし、上場企業は四半期ごとの業績をまとめた「四半期決算短信」を開示することが義務付けられています。決算短信には売上高や営業利益、純利益など主要な数値が簡潔にまとめられ、投資家や取引先に経営状況を適切に伝える役割を持っています。
四半期決算はいつまでに提出しますか?
上場企業の場合、四半期決算短信の公表には提出期限が設けられています。通常、各四半期末から45日以内を目安に開示する必要があります。期限を守ることで、投資家や市場関係者に対して誠実な経営姿勢を示せるだけでなく、証券取引所のルール遵守にもつながります。そのため、日々の記帳や月次決算の整備が大切です。
四半期決算と本決算の違いは何ですか?
四半期決算は1年間を4分割した3か月ごとの業績集計で、短期間の経営状況をタイムリーに把握することを目的としています。一方、本決算(年次決算)は1年間の総括で、税務申告や株主総会資料として法的な役割も担います。四半期決算は中間報告として用いられ、本決算は企業の最終的な決算として位置付けられます。




