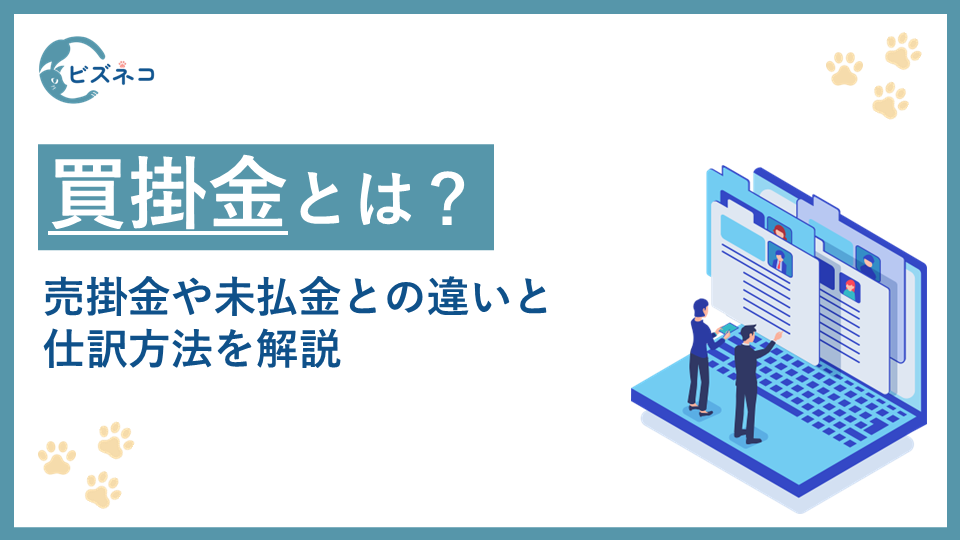
企業間の取引において、商品やサービスを受け取ったにもかかわらず、代金の支払いがまだ済んでいない状態を「買掛金」といいます。日々の経理業務においてよく使う「買掛金」は、似たような用語である「売掛金」や「未払金」と混同しやすく、正確な理解が求められます。
この記事では、買掛金の基本的な意味から、実際の仕訳方法や処理の流れまでを詳しく解説します。買掛金の残高が合わない場合の対処法や管理のポイント、回転率や時効などについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
買掛金とは?
企業が取引先から商品やサービスを仕入れた際、代金の支払いを後日にすることがあります。このように、受け取った商品やサービスに対する未払いの金額を「買掛金」と呼びます。
例えば、月末に仕入れた商品を翌月に支払う契約をした場合、支払義務が生じている間は買掛金として会計処理されます。買掛金は負債の一種であり、企業の財務状況を把握する上で欠かせない項目です。現金での取引に比べて、資金繰りに柔軟性をもたらす一方で、未払金と混同されることも少なくありません。
買掛金と売掛金の違い
買掛金と売掛金は、どちらも掛け取引に関連する用語ですが、その意味するところは異なります。結論からいえば、買掛金は「支払う側」の立場であり、売掛金は「受け取る側」の立場を示します。
例えば、同じ取引でも仕入先から見れば売掛金、購入側から見れば買掛金として処理されるのです。このように、取引の当事者によって勘定科目の名称が変わるため、混乱しやすいポイントでもあります。両者はともに貸借対照表に計上されますが、買掛金は負債、売掛金は資産として扱われます。
なお、売掛金については、こちらの記事も参考にしてください。

買掛金と未払金の違い
同じ「支払いが未了である負債」として分類される買掛金と未払金ですが、両者には明確な違いがあります。買掛金は、主に商品の仕入れなど営業活動に伴う未払い金であり、一方の未払金は、物品の購入以外の費用に関する支払義務を指します。
例えば、会社が事務用品を購入してその代金を後払いにした場合は未払金ですが、商品を仕入れて支払いを後日にした場合は買掛金として処理されます。見た目には似ていますが、会計処理の場面で混同すると財務諸表の正確性に影響を及ぼします。
買掛金と未払費用の違い
買掛金と未払費用は、いずれも将来的に支払う義務があるという点で似ていますが、性質や使用される場面には違いがあります。買掛金は商品などの仕入れに伴い発生する負債です。一方で、未払費用は、継続的なサービスの提供に基づく費用に対して使われます。
例えば、水道代や電気代といったインフラ費用は、一定期間の使用に基づき定期的に請求されるもので、買掛金や未払金には分類されません。こうした支払いがまだ済んでいない状態で、決算日を迎えた場合に、発生済みの当期分の費用だけを計上するために未払費用という勘定科目が用いられます。取引の内容だけでなく、発生のタイミングや契約の継続性をもとに、これらの勘定科目は適切に使い分ける必要があります。
買掛金の会計処理の流れ
買掛金の会計処理は主に以下の流れで進みます。
- step1:商品を注文する
- step2:商品を仕入れて買掛金の仕訳をする
- step3:取引先から請求書を受け取る
- step4:商品の代金を支払う
- step5:買掛金残高を確認する
ここでは、それぞれの流れについて詳しく解説していきます。
step1:商品を注文する
買掛金の処理は、実際に支払いが発生するよりも前の段階から始まります。最初のステップが、取引先に対して商品の注文を行うことです。例えば、販売に必要な在庫を確保するために定期的に仕入先へ注文をかけるようなケースでは、注文時点で今後発生する買掛金の準備を意識することが大切です。
注文そのものは会計上の仕訳を必要としない場合が一般的ですが、この段階で発注書を発行したり、取引条件を再確認したりすることで、後々のトラブルや処理ミスを防ぐことができます。
step2:商品を仕入れて買掛金の仕訳をする
注文した商品が届いた段階で、実際の仕入れが成立し、初めて買掛金としての仕訳が必要になります。例えば、仕入れた商品が検品を経て受領された場合、その時点で「仕入」と「買掛金」の勘定科目を用いた仕訳処理を行います。
なお、まだ現金の支払いが発生していない状態でも、すでに債務が確定しているため、負債として記録する必要があるからです。仕訳を適切に行うことで、会計帳簿上に正確な負債残高が反映され、後続の処理との整合性が保たれます。
step3:取引先から請求書を受け取る
商品を受け取った後、取引先から請求書が届くことで、金額や支払条件が正式に確認できるようになります。例えば、商品と一緒に納品書が届いていても、請求書には消費税や支払期限などの詳細が記載されているため、請求書をもとに仕訳や支払い準備を進める必要があります。
請求書の受領と内容確認は、経理業務において小さく見えて重要な業務であるため、誤記や条件の違いに気づかず処理を進めてしまうと、後のトラブルにつながりかねないため注意しましょう。
step4:商品の代金を支払う
請求書に基づき、定められた支払期限までに代金を送金することで、買掛金の負債が消滅します。例えば、月末締め翌月末払いといった契約条件に従って支払う場合、期限を守ることで取引先との信頼関係を保つことができます。
支払いの際には、現金または預金の減少と、買掛金の減少を正確に仕訳する必要があります。また、振込手数料の扱いについても注意が必要です。支払処理を怠ると信用不安を招くだけでなく、遅延損害金が発生するリスクもあります。そのため、金額の確認や振込先情報の誤りなどにも十分注意を払い、確実に処理を進めることが求められます。
step5:買掛金残高を確認する
支払いが完了した後も、帳簿上の買掛金残高が正確に反映されているかを確認する作業が欠かせません。例えば、仕訳の入力ミスや請求書との不一致があると、残高が実態とずれてしまい、月次や年次の決算に影響が出る可能性があります。
買掛金残高の確認は、取引先ごとの管理台帳や買掛金元帳と突き合わせることで行い、過不足がないかをチェックすることが重要です。確認作業を怠ると、未払いのまま放置されていた取引が後から発覚したり、過剰な支払いが生じたりする可能性があります。そのため、定期的なチェックを習慣化することで、より正確で信頼性の高い会計処理が実現します。
買掛金の仕訳方法
買掛金は、取引先から商品や原材料などを仕入れた際に、代金を後日支払う約束のもとで発生する負債であり、日々の会計処理において適切な仕訳が欠かせません。例えば、月末に商品を仕入れてその代金を翌月末に支払う場合には、仕入れた時点で「仕入」と「買掛金」の勘定科目を使って仕訳を行う必要があります。
支払いのタイミングでは、「買掛金」を減らす処理とともに「現金」や「預金」の減少を記録します。また、仕訳の際には、消費税の取り扱いや割引条件の有無など、取引内容に応じた細かな判断も求められます。
帳簿の整合性を保つためには、取引の都度、仕訳を正確に行い、実態を反映した記録を残しておくことが基本です。仕訳の誤りが決算や資金繰りに影響することもあるため、日常的な仕訳処理の見直しと理解の深掘りが大切です。
買掛金が発生したときの仕訳例
例えば、取引先から掛け取引で100万円の商品を仕入れた際の仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕入 | 1000,000円 | 買掛金 | 1000,000円 |
買掛金を支払ったときの仕訳例
例えば、翌月に当座預金から掛仕入100万円を支払った際の仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 1000,000円 | 当座預金 | 1000,000円 |
買掛金の残高が合わない場合の原因と対処方法
買掛金の残高が合わない場合の原因として以下のようなケースがあります。
- 原因1:会計処理の計上漏れ
- 原因2:経理担当者の計算ミス
- 原因3:検収漏れと検収基準のズレ
ここでは、それぞれの原因における対処方法を詳しく解説します。
原因1:会計処理の計上漏れ
買掛金の残高が合わない原因として最も多いのが、取引の計上漏れです。例えば、商品を仕入れて検収が完了しているにもかかわらず、仕訳処理がされていない場合、買掛金としての負債が帳簿に反映されず、残高にズレが生じます。
計上漏れは、取引量が多い企業や月末に業務が集中するタイミングで発生しやすく、特に請求書が未着だったり、担当者が複数に分かれていると見落としが起こりがちです。計上漏れは、取引先との支払トラブルや決算時の数字の誤りにつながるため、小さな見落としであっても早期の発見と修正が必要です。帳簿と請求書、納品書などの突き合わせを定期的に行うことが、ミスの防止につながります。
原因2:経理担当者の計算ミス
帳簿と実際の買掛金残高が一致しない原因のひとつに、人為的な計算ミスがあります。例えば、仕訳入力時に金額の桁を誤って入力したり、複数の請求書を合算する際に足し間違えたりすることで、正しい残高が記録されなくなることがあります。
経理担当者のミスは一見単純に見えますが、気づかないまま決算や月次報告に反映されてしまうと、財務状況の誤認を招きかねません。特に締め作業の時期には作業量が増え、確認作業が疎かになることでミスが埋もれてしまうこともあります。確認のためのダブルチェック体制や、数字入力をサポートする会計ソフトの活用は、こうした人的ミスを減らすうえで有効です。
なお、経理の人材不足として「一人経理」という状態もあります。「一人経理」のリスクについては以下の記事を参考にしてください。
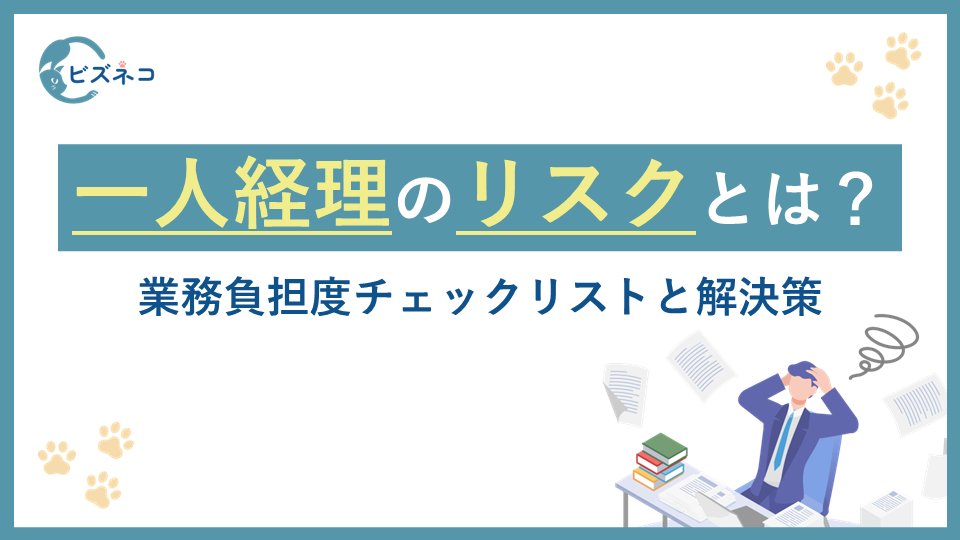
原因3:検収漏れと検収基準のズレ
買掛金の管理において見過ごされがちなのが、検収の処理に関するミスや基準の違いです。例えば、仕入れた商品が届いていても、社内の検収が完了していなければ、仕訳を先延ばしにするという運用をしている企業では、買掛金の認識時期がズレてしまうことがあります。
また、検収日を起点に計上する企業と、納品書や請求書の日付で処理する企業では、買掛金の発生タイミングが異なり、帳簿上の数字に差が出ることもあります。こうしたズレは、会計処理が曖昧なまま進行している場合に起こりやすく、原因が判明しにくいため注意が必要です。明確な検収ルールを設け、関係部門間で共有しておくことが、精度の高い買掛金管理につながります。
買掛金の回転期間
買掛金の回転期間は、仕入から支払いまでにかかる平均的な日数を表すもので、企業の支払能力やキャッシュフローの安定性を測る指標として重要です。具体的には、以下の式で計算できます。
- 買掛金の回転期間(日数)=買掛金残高÷(売上原価÷365日)
仕入をしてからすぐに支払いを済ませている企業は、回転期間が短く、資金繰りの健全性が比較的高いと考えられます。反対に、回転期間が長いと、仕入先との信用や支払い条件の面で問題が生じるリスクもあります。
回転期間を把握することで、どの取引にどれくらいの支払い猶予があるのかを見極めやすくなり、資金管理の精度が上がります。定期的に買掛金の回転期間の数値を見直し、実態に合った支払い体制を整えることが、安定した経営の土台となります。
買掛金の回転率
買掛金の回転率とは、仕入に対してどれだけ効率的に買掛金を支払っているかを示す指標で、企業の資金繰りや支払体制の健全性を判断するうえで参考になります。具体的には、以下の式で計算できます。
- 買掛金の回転率(%)=(売上原価÷買掛金残高)×100
例えば、同じ仕入額であっても、回転率が高ければ買掛金の支払いサイクルが短く、取引先への支払いをスムーズに行っていることがわかります。逆に回転率が低い場合は、支払いまでの期間が長く、資金を寝かせている可能性もあります。
買掛金の回転率の数値を把握することで、過剰な買掛金残高を避け、無理のない支払い計画を立てる手がかりになります。そのため、財務指標のひとつとして、単に帳簿を管理するだけでなく、取引の流れを客観的に見直す視点として活用できます。
買掛金の時効
買掛金には時効があり、2020年4月の法改正により、売掛金同様に買掛金の時効期間は原則として5年とされています。ただし、5年間の間に支払い請求を受けている場合や、すでに買掛金の一部を支払っている場合には、支払い義務は消滅しないため注意しましょう。
例えば、5年の間に取引先から督促状や請求書が送付されていた場合や、こちらが一部でも支払いを行っていた場合には、その時点で時効がリセットされ、再び一定期間が経過しない限り消滅しません。
時効の成立を一方的に判断すると、後に支払いを求められるリスクもあるため、取引の履歴や対応状況を正確に記録しておくことが重要です。継続的な仕入がある取引先であるほど、請求漏れや記録の曖昧さがトラブルの原因となるため、きちんとした管理が求められます。
買掛金を管理するポイント
買掛金を管理するポイントとして、以下のような点があげられます。
- 買掛金元帳を作成する
- 請求書の到達を早期に確認する
- 経理代行会社に相談する
ここでは、それぞれのポイントについて具体的に解説します。ぜひ参考にしてください。
買掛金元帳を作成する
買掛金の管理を正確に行うためには、仕入先ごとに取引内容を記録する「買掛金元帳」の作成が不可欠です。例えば、毎月同じ取引先から複数回仕入れを行っている場合、どの取引が未払いで、どの取引がすでに支払い済みかを整理するには、一覧で管理できる元帳が役立ちます。
買掛金元帳には、仕入日・請求書番号・金額・支払期日などを記載し、帳簿や請求書との整合性を確認しながら記録を積み重ねていきます。こうした管理を継続することで、決算時の買掛金残高の確認や、支払い予定の把握がスムーズになり、支払い遅延などのリスクも防ぎやすくなります。また、取引先とのトラブル回避にもつながるため、日々の記録を正しく残すこともおすすめです。
なお、記帳についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

請求書の到達を早期に確認する
請求書が予定通りに届いているかどうかを確認することは、買掛金管理において見落とせないポイントです。例えば、仕入先からの請求書が郵送の途中で遅延した場合や、社内の確認ルートで停滞した場合、支払処理が後手に回り、支払期日を過ぎてしまう恐れがあります。
請求書の到着を迅速にチェックできれば、仕訳処理や支払準備を早めに進めることができ、月次決算や資金繰りにもゆとりが生まれます。また、請求書の内容に不明点や誤りがある場合にも、早期に発見できることで対応の時間が確保され、取引先との関係を損なわずに済みます。こうした確認作業をルール化しておくことは、ミスや遅延を防ぐための有効な手段といえるでしょう。
なお、請求書のスピードや支払サイトについては、こちらの記事でもまとめています。

経理代行会社に相談する
社内での経理体制に不安がある場合や、買掛金の管理が煩雑になっている場合は、経理代行会社に相談するという選択あります。例えば、請求書の処理が月末に集中し、ミスや漏れが起こりやすい環境では、外部の専門家に処理を任せることで業務の正確性が保たれ、社内の負担も軽減されます。
経理代行会社では、買掛金の仕訳処理から元帳作成、支払期日の管理まで幅広くサポートしてくれるため、自社の状況に応じて業務を柔軟に委託できます。経理担当者の退職や人手不足によってリスクが高まる局面でも、安定した経理体制を維持するうえで有効な手段となるでしょう。継続的なサポートを受けることで、会計業務全体の質を保つことにもつながります。
なお、経理代行については、こちらの記事も参考にしてください。
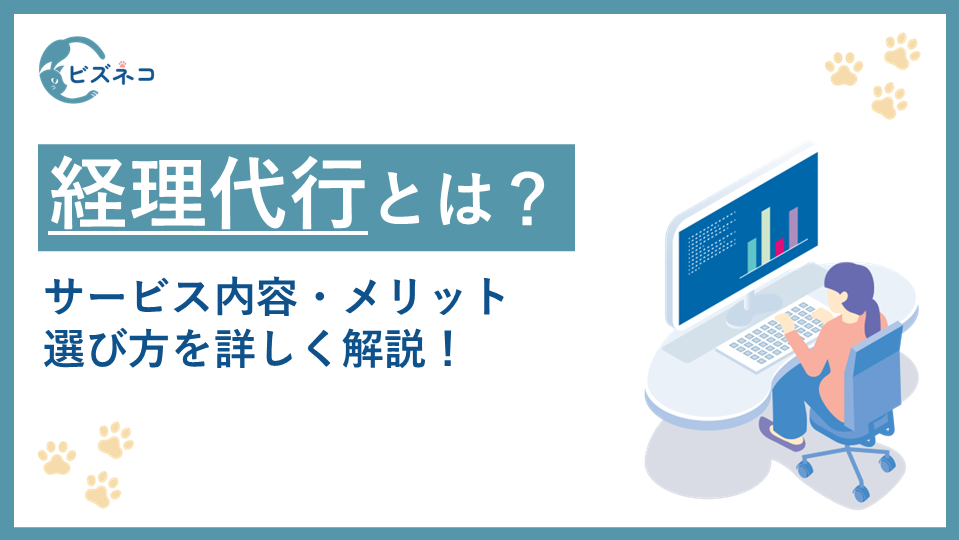
まとめ
買掛金は、企業が取引先から商品やサービスを仕入れた際、代金の支払いを後日にする際に発生する、受け取った商品やサービスに対する未払いの金額のことです。買掛金は負債の一種であり、企業の財務状況を把握する上で欠かせない項目です。
買掛金の残高が合わない際には、会計処理の計上漏れや、経理担当者の計算ミス、検収基準のズレなどの原因があるため確認してみましょう。また、買掛金を管理するには、買掛金元帳の作成や、請求書の到達を早期に確認することがポイントです。なお、経理代行会社に相談することもひとつの手です。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
買掛金に関するよくあるご質問
買掛金についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、買掛金に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
売掛金と買掛金の違いは何ですか?
売掛金と買掛金はどちらも取引の際に発生する未決済の金額を示しますが、立場が異なります。売掛金は商品やサービスを提供した側が、後日代金を受け取るために計上する資産です。一方、買掛金は商品やサービスを受け取った側が、代金を後日支払う義務として計上する負債です。売掛金は資産であり、買掛金は負債です。
買掛金と未払金の違いは何ですか?
買掛金と未払金はいずれも将来支払う義務がある金額ですが、発生する取引の種類が異なります。買掛金は主に商品の仕入れなど、営業活動に関わる継続的な取引で発生する負債です。一方、未払金は設備の購入や備品代、広告費など、継続的ではない単発的な取引で発生する負債を指します。
買掛金の勘定科目は何ですか?
買掛金は貸借対照表における負債の部に分類される勘定科目です。主に営業活動で仕入れた商品や原材料に対して、まだ支払いが済んでいない代金を記録するために使われます。例えば、販売目的の商品を取引先から仕入れた際、代金を掛け取引とする場合には、仕訳上「買掛金」として記録されます。




