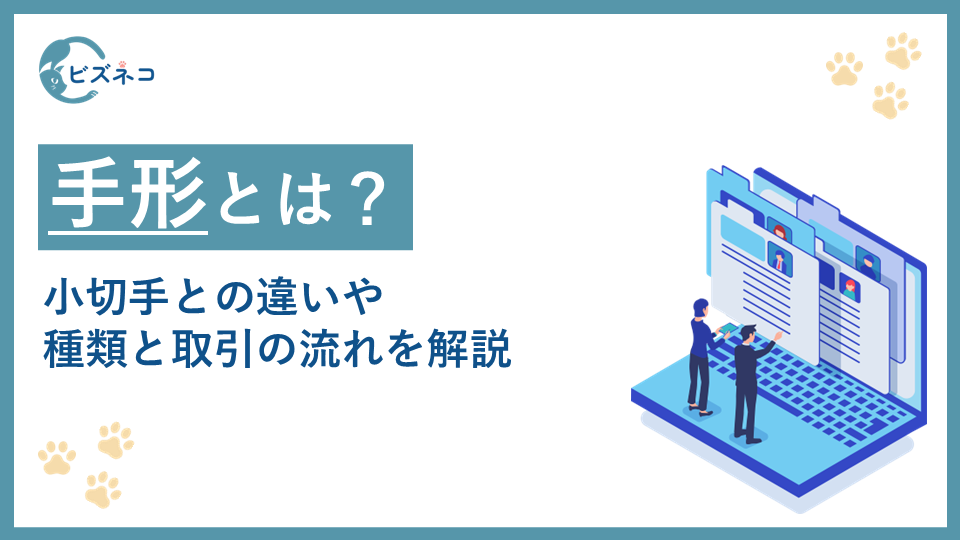
企業間の取引では、現金のやり取りではなく手形を用いる場面が長らく存在してきました。手形は将来の一定期日に支払いを約束する証券であり、資金繰りや取引の信頼関係を支える役割を担ってきました。一方で、小切手と混同されることも少なくなく、両者の違いを理解しておくことは経理や財務を扱う上で重要です。
本記事では、手形の基本から小切手との違い、具体的な種類や仕組み、利用する際の注意点を解説します。手形取引に関わる方は、ぜひ実務に活かしてください。
目次
手形とは?
手形とは、将来の一定期日に支払いを約束する有価証券です。企業間の取引では現金の代わりに使われ、資金繰りや信用取引を円滑に進めるための仕組みとして発展してきました。
例えば、商品を仕入れた際にすぐ現金を用意できなくても、手形を振り出すことで後日の支払いを約束できます。その一方で、期日までに資金を準備しなければ不渡りとなる可能性があるため、発行する側には責任が伴います。
受け取る側にとっても、すぐに現金化できないという制約はありますが、金融機関で割引を受けることで早めに資金化する方法も存在します。このように、手形は単なる支払い手段にとどまらず、取引先との信頼関係や資金調達の工夫が絡み合う金融取引です。
手形と小切手の違い
手形と小切手は、いずれも紙面で支払いを約束する証券ですが、決済のタイミングが異なります。小切手は受け取った時点で即座に現金化できるのに対し、手形はあらかじめ定められた期日にならなければ資金を受け取ることができません。
例えば、取引先への支払いを先送りしたい場合には手形が利用される一方、急ぎで現金を受け取りたい場面では小切手が適しています。また、手形には約束手形や為替手形といった種類があるのに対し、小切手は主に即時決済を目的とするため用途が限定されます。
手形の種類と取引の流れ
手形にはいくつかの約束手形・支払手形・為替手形の3種類があり、それぞれの性質や使い方によって取引の仕組みが異なります。種類を理解し流れを把握することは、手形を適切に利用しリスクを軽減するために重要です。
約束手形
約束手形は、振出人が一定期日に指定金額を支払うことを約束する手形です。企業間取引ではもっとも多く利用され、信用取引を支える基本的な仕組みといえます。
例えば、商品を仕入れたがすぐに資金を用意できない場合でも、約束手形を振り出すことで支払いを先送りしつつ取引を成立させることができます。一方、受取人にとっては現金化まで待つ必要があるため、資金繰りに影響する可能性があります。
ただし、金融機関で割引を行えば早期の資金化も可能です。こうした特徴から、約束手形は発行する側と受け取る側双方にメリットとリスクをもたらす取引手段となっています。
支払手形
支払手形は、企業が仕入代金の決済に利用する手形であり、経理上も重要な科目として処理されます。振出人は約束した期日までに資金を準備する必要があり、信用を損なわないよう管理が欠かせません。
例えば、商品を仕入れた際に支払手形を振り出すと、その時点では現金が動かなくても取引が成立します。しかし期日が来れば必ず支払いが発生するため、資金計画を怠れば不渡りのリスクにつながります。受取人にとっては確実な債権として扱える点がメリットですが、現金化には時間を要する点は注意が必要です。このように支払手形は企業の資金繰りに直結するため、管理体制と信用力が重要な意味を持ちます。
為替手形
為替手形は、振出人が第三者に支払いを依頼する形で成立する手形で、複数の当事者が関与する点が特徴です。一般的に、輸出入取引など国際的な場面で利用されることが多く、資金のやり取りを安全に行う仕組みとして発展してきました。
例えば、輸出者が海外の輸入者に代金を請求する際、直接送金ではなく為替手形を用いることで、銀行を通じて確実な決済を実現できます。受取人にとっては信頼性の高い取引方法ですが、為替相場や国際ルールに左右される点もあります。
一方、振出人や支払人にとっても信用管理が重要となり、手続きの煩雑さを伴う場合があります。このように為替手形は国内取引だけでなく、国際ビジネスにおける資金決済の手段として活用されています。
手形のメリット
手形の活用には、発行する側と受け取る側の双方にとってメリットがあります。振出人にとっては資金繰りを調整しやすく、受取人にとっては金融機関の利用による資金化やリスク分散が可能です。例えば、支払いを先延ばしにすることで取引を円滑に進められるほか、受け取った手形を割引して早期に現金化できるなど、手形は取引の柔軟性を高める役割を果たします。
振出人側の手形のメリット
振出人にとって手形は、資金繰りを柔軟に調整できる手段となります。現金の即時支払いを避け、一定の余裕を持たせることが可能だからです。また、大口の取引や長期にわたる契約においても、手形を使うことで信頼関係を維持しながら円滑に進められます。このように、手形は振出人にとって資金管理の選択肢を広げる重要な仕組みとなっています。
支払いを先延ばしにできる
手形を利用するメリットは、支払いを期日まで延期できる点です。現金で即時に支払いを行う必要がないため、手元資金を他の用途に回せる余裕が生まれます。
例えば、仕入れ代金を手形で支払えば、受取人は期日まで現金を受け取れませんが、その間に振出人は販売や回収を進めて資金を準備することが可能です。
このように、手形を使うことで支払いと資金回収のタイミングを調整し、事業運営に必要な流動性を保ちやすくなります。ただし、延期はあくまで一時的なものであり、期日までに準備を怠れば信用に関わるため注意が必要です。
大口や長期的な取引がしやすくなる
手形は、まとまった金額や長期的な取引に適した支払い方法として機能します。現金をすぐに用意できない場合でも、期日を設けることで信頼関係を保ちながら契約を進められるからです。
例えば、設備投資のように金額が大きく一括で支払いにくい場面では、手形を活用することで分割的に資金を調達する余裕が得られます。さらに、長期的な取引先に対して手形を継続的に利用すれば、双方の資金繰りを安定させると同時に取引の信頼性を高める効果も期待できます。こうした点から、大口や長期契約において手形は有効な手段とされています。
受取人側の手形のメリット
受取人にとって手形は、現金と同様に価値を持ちながら資金調達の柔軟性を広げる手段です。手形を保有している間も金融機関を通じて現金化が可能であり、必要に応じて譲渡によって第三者への支払いにも利用できます。このように、受取人にとって手形は資金繰りの安定や信用維持に有益な役割を果たします。
手形の割引や譲渡で資金化できる
受け取った手形は、金融機関に持ち込むことで期日前に現金化できます。これを「手形割引」と呼び、金融機関が一定の利息分を差し引いて資金を提供する仕組みです。
また、手形は第三者に譲渡することもでき、これを「裏書譲渡」といいます。例えば、仕入先から受け取った手形を別の支払いに充てることで、現金を用意せずに取引を進められます。
割引や譲渡は資金繰りの幅を広げる一方、信用に基づく取引であるため適切な管理が求められます。このように、受取人にとって手形は現金以外の柔軟な資金調達手段となっています。
貸倒れリスクを軽減できる
手形は、期日に支払いが保証される債権としての性質を持つため、貸倒れリスクを一定程度抑えることができます。貸倒れとは、取引先が資金不足や倒産などにより債務を履行できなくなる状態を指します。
例えば、口約束だけで代金を後払いにした場合、相手が突然経営不振に陥れば回収不能となる危険があります。その点、手形を受け取っていれば法的に支払い義務が明確化され、金融機関での割引など資金化の手段も確保できます。ただし、完全にリスクをなくすわけではなく、不渡りの可能性もあるため信用調査と併せた活用が重要です。
手形のデメリット
手形は便利な取引手段ですが、発行する側と受け取る側の双方に負担やリスクが伴います。振出人は期日までの資金準備や手数料負担があり、受取人は現金化までの時間や不渡りといった問題に直面するため注意が必要です。
振出人側の手形のデメリット
振出人にとって手形は資金繰りを助ける一方で、期日を迎えると必ず支払いが発生するため強い責任が伴います。また、発行時にかかる手数料や管理コストも無視できません。このように、手形の発行はメリットと同時に明確なデメリットを抱えていることを理解する必要があります。
期日までに資金を準備しなければならない
手形を振り出す以上、期日までに確実に資金を用意する必要があります。支払いが滞れば不渡りとなり、取引先からの信用を大きく損ないます。
例えば、売上の入金が想定より遅れた場合、その分の資金が手形決済に間に合わず経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。手形は一時的に資金繰りを調整できる反面、期日を守らなければ信用問題に直結するため、計画的な資金管理が欠かせません。この点は振出人にとって避けられない負担といえます。
発行手数料などのコストがかかる
手形の発行には、印紙税や銀行の取扱手数料といったコストが発生します。現金払いであれば不要な費用が積み重なり、長期的には経営を圧迫する要因となるのです。
例えば、毎月複数枚の手形を振り出す企業では、印紙代や振込手数料が大きな負担となり、経費の増加を招くことがあります。さらに、手形の管理や事務処理にかかる時間や人件費も見逃せません。このように、利便性を得る一方でコスト面の負担が避けられない点はデメリットとして認識する必要があります。
受取人側の手形のデメリット
受取人にとっても手形は便利な反面、すぐに現金化できないことや不渡りのリスクといった問題が伴います。また、振出人の信用状況によっては、受け取った手形が不渡りとなる危険も否定できません。このように、受取人にとっても手形は必ずしも安心できる資金手段ではないのです。
現金化まで時間がかかる
手形は受け取ってもすぐには現金にならず、期日まで待つ必要があります。そのため、急な資金需要が発生した場合に対応が難しいという問題があります。
例えば、仕入代金の支払いが迫っているのに手形の期日がまだ先であれば、そのままでは使えず、金融機関で割引して資金化しなければなりません。しかし、割引には利息や手数料がかかり、手元に残る金額は少なくなります。このように、流動性の低さが受取人にとっての大きなデメリットです。
不渡りのリスクがある
手形には不渡りというリスクが存在します。不渡りとは、期日に振出人が資金を準備できず支払いが行われないことを指し、受取人に大きな損失をもたらします。例えば、長年取引していた企業が急に資金難に陥った場合、約束された金額が支払われず回収不能になる恐れがあります。
不渡りは単なる未払いにとどまらず、受取人の資金繰りや信用にも影響し、取引先全体との関係を揺るがす事態になりかねません。そのため、手形を受け取る際は信用調査を行い、相手の支払能力を見極めることが重要です。
手形の期日(手形サイト)
手形の期日とは、支払いが行われる約束の日のことで、一般的に「手形サイト」と呼ばれます。日本では商慣習として手形サイトは原則60日以内とされており、取引条件に応じて30日や60日といった期間が設けられるのが一般的です。
例えば、発行日から60日後に期日が設定された手形であれば、受取人はその期日を迎えるまで現金化できず、資金繰りに影響することがあります。振出人にとっては資金準備の時間を確保できる一方、受取人にとっては支払いを待つ必要があるため、双方に異なるメリットと注意点が存在します。このため、手形取引を行う際には、サイトの長さや条件を十分に理解し管理することが重要となります。
なお、商品やサービスの納品から実際に代金が支払われるまでの期間を「支払サイト」と呼びます。「支払サイト」についてはこちらの記事を参考にしてください。

手形の売却(手形割引)
手形割引とは、受取人が期日前の手形を金融機関に売却し、現金化する仕組みです。割引料として利息や手数料が差し引かれるため、手元に残る金額は額面より少なくなります。
例えば、60日後が期日の手形を割引すると、利息分が控除された金額が即座に手に入ります。急な資金需要がある場合には有効な方法ですが、割引率や手数料によって受取額が変動するため、計画的に利用する必要があります。
また、割引を利用する場合も、振出人の信用状況を確認しておくことが重要です。手形割引は、受取人にとって流動性を確保できる便利な資金調達手段となります。
手形の裏書譲渡
手形の裏書譲渡とは、受取人が手形を第三者に譲渡する方法で、裏面に署名や捺印をすることで権利を移転できます。これにより、手形は現金のように流通性を持つ取引手段となります。
例えば、60日後が期日の手形を受け取り、それを別の取引先への支払いに利用する場合、現金を使わず決済を行うことが可能です。ただし、裏書を行った受取人は、もし振出人が期日までに支払いを行えず不渡りとなった場合、責任を負う可能性があります。そのため、裏書譲渡は信用のある取引先との間で利用することが望ましい方法です。
手形取引の注意点
手形取引には利便性がありますが、一方で注意すべきリスクも存在します。振出人や受取人双方にとって、資金準備や現金化のタイミングに加え、信用や安全性の管理が重要です。また、紛失や盗難による不正利用の可能性もあるため、手形の保管や管理方法に注意を払う必要があります。適切な管理がなければ、手形のメリットを十分に活かせないこともあるのです。
取引先の信用調査をしておく
取引先の信用調査は、手形取引における重要なリスク管理のひとつです。手形は期日までの支払いを前提としているため、相手が資金を用意できなければ不渡りとなり、受取人に損失が生じます。
例えば、過去の決算情報や支払履歴を確認し、経営状態や信用状況を把握しておくことで、リスクをある程度軽減できます。手形は便利な取引手段ですが、相手の信用が担保されていなければ、流動性の確保や貸倒れリスクの回避といったメリットが失われることになります。
紛失や盗難で不正利用の恐れがある
手形は現金同様の価値を持つため、紛失や盗難によって不正利用されるリスクがあります。例えば、手形を第三者に盗まれ、裏書や割引で現金化されると、受取人は法的手続きを行わなければ資金を回収できません。
また、振出人も不正利用によって支払義務の混乱に巻き込まれる可能性があります。さらに、紛失や盗難を防ぐためには、保管場所を限定したり、取引記録を正確に残すことも重要です。必要に応じて保険に加入することで、不測の事態への備えを強化でき、手形取引の安全性を高めることができます。
まとめ
手形は、将来の一定期日に支払いを約束する有価証券で、企業間取引における資金繰りや信用の維持に役立ちます。小切手との違いは決済のタイミングで、手形は期日まで現金化できません。約束手形、支払手形、為替手形など種類ごとに仕組みや流れが異なり、割引や裏書譲渡により資金化や取引の柔軟性を高められます。
一方、振出人は期日までの資金準備や手数料負担、受取人は現金化までの時間や不渡りリスクに注意が必要です。適切な管理と信用確認を行うことで、手形のメリットを安全に活用できます。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
手形に関するよくあるご質問
手形についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、手形に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
手形はなぜ廃止されるのですか?
手形は、将来の支払いを約束する伝統的な決済手段ですが、近年は電子決済や銀行振込など迅速で安全な決済手段が普及しています。そのため、手形取引の管理コストや不渡りリスクが課題となっていました。こうした背景から、手形制度は段階的に廃止されることとなり、日本では2026年度末をもって廃止される予定です。
手形にはどんな種類がありますか?
手形には主に約束手形、支払手形、為替手形の3種類があります。約束手形は振出人が一定期日に支払うことを約束するもので、国内取引で広く使われます。支払手形は仕入代金などの決済に利用され、資金繰りを調整しやすい点が特徴です。為替手形は第三者に支払いを依頼する形で、輸出入など国際取引で活用されます。
手形の主なルールは何ですか?
手形には、振出人・受取人・期日・金額などの記載事項や署名・捺印が必須です。期日までに支払う義務が発生することや、裏書譲渡によって権利を第三者に移せることも重要なルールです。さらに、手形は原則60日以内の手形サイトが一般的で、紛失や盗難時の不正利用防止や信用調査も求められます。




