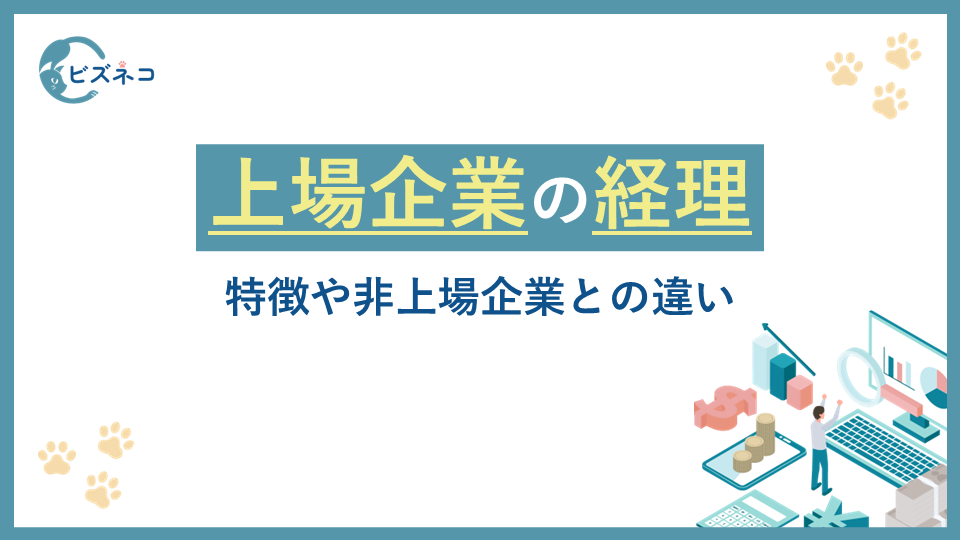
上場企業の経理業務は、単なる帳簿管理にとどまらず、投資家や株主に向けた情報開示や法令遵守といった重要な役割を担っています。例えば、四半期ごとに開示を行い、決算書類の正確性を確保するため内部統制や会計監査人によるチェックを受ける必要があります。非上場企業と比べると、連結決算やIFRS対応など業務範囲が広がる点も特徴です。
上場企業では、日次・月次・年次の定型業務を効率的に進めるためには、経理DXの推進や業務フローの見直し、場合によってはアウトソーシングの活用もおすすめです。本記事では、上場企業の経理の特徴や非上場企業との違い、求められるスキル、効率化のポイントまで詳しく解説します。
目次
上場企業の経理の特徴
上場企業の経理の特徴として、以下のような点があげられます。
- 投資家に向けた情報開示が必要になる
- 財務報告の信頼性のために内部統制がある
- 会計監査人による監査がある
ここでは、それぞれの経理の特徴を詳しく解説します。
投資家に向けた情報開示が必要になる
上場企業では、投資家や株主が適切に判断できるよう、正確かつ迅速な情報開示が求められます。例えば、四半期ごとの決算短信や有価証券報告書の作成、開示資料の公表などが代表的な業務です。
経理担当者は会計基準を踏まえた財務諸表の作成や開示スケジュールの管理を担い、経営陣や開示担当部門と連携して情報を整えます。投資家やステークホルダーへの情報開示プロセスを通じて、投資家との信頼関係を構築し、企業価値を維持や向上させる役割を果たします。
財務報告の信頼性のために内部統制がある
上場企業では、財務報告の信頼性を確保するために内部統制を整備することが義務付けられています。例えば、仕訳や支払の承認を複数人で行う構造や、取引内容をダブルチェックする仕組みなどが該当します。
内部統制により担当者のミスや不正を未然に防ぎ、投資家に提供する情報の正確性を高めます。経理担当者は内部統制のルールに従って日々業務を進めるだけでなく、必要に応じて改善提案を行い、体制の有効性を維持することも重要な役割です。
会計監査人による監査がある
上場企業では、作成した財務諸表が会計監査人による外部監査を受けることが法律で義務付けられています。例えば、監査法人が決算書や内部統制の有効性を確認し、適切に作成されているかどうかを意見表明します。
経理担当者は監査対応として資料を整理や提出をして、指摘事項に対して修正や改善を行います。会計監査人による監査プロセスは負担もありますが、結果として財務情報の透明性と信頼性が高まり、投資家や市場に安心感を与えることにつながります。
上場企業と非上場企業の経理の違い
上場企業と非上場企業の経理の違いは、業務範囲の広さがあげられます。上場企業の経理は、非上場企業に比べて求められる業務範囲が広く、高い精度で遂行する必要がある点が特徴です。例えば、上場企業では投資家や株主に向けた情報開示義務があるため、四半期決算や有価証券報告書の作成、開示対応が欠かせません。また、内部統制の整備や会計監査人による監査も行われるため、日々の仕訳から決算書作成まで一貫して正確性と透明性が求められます。
一方で非上場企業では、情報開示の義務はなく、決算書は主に金融機関や社内向けの資料として利用されるため、スピードや柔軟性を重視する傾向があります。上場企業と非上場企業の経理の違いを理解することで、求められるスキルや体制整備の方向性が見えてきます。
なお、上場準備企業の経理についてはこちらの記事も参考にしてください。
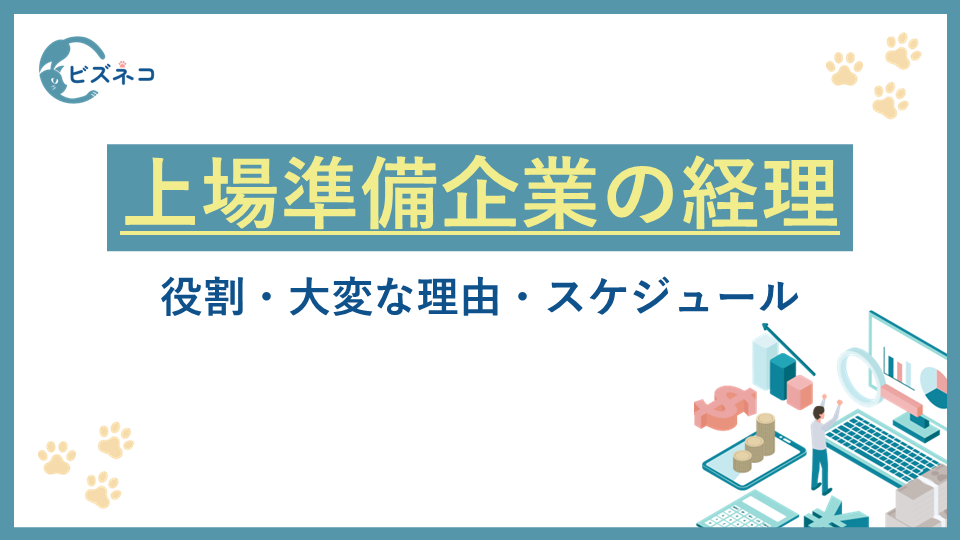
個別決算と連結決算の違い
個別決算と連結決算では、対象となる企業の数が異なります。個別決算は、単体の会社の財務状況や経営成績を明確にするための決算であり、法人税申告の基礎資料としても利用されます。
一方、連結決算は親会社と子会社などグループ全体をひとつの企業として見なして作成される決算です。例えば、子会社の損益や資産負債も親会社の財務諸表に取り込み、グループ全体の実態を投資家に示す役割があります。
上場企業では連結決算が必須であり、海外子会社を含む場合には国際会計基準や通貨換算への対応も求められます。経理担当者は、個別決算で正確な数値を確定させるだけでなく、グループ会社間の取引調整や内部取引の消去など連結特有の処理を行う必要もあります。
なお、連結決算についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
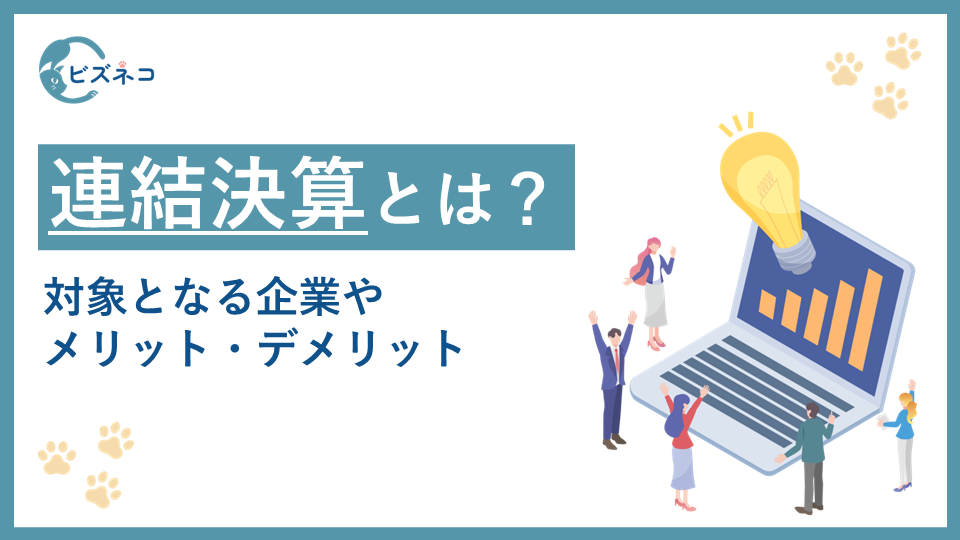
上場企業の経理の業務内容
上場企業の経理の業務内容は、「日次業務(毎日の仕事)」「月次業務(毎月の仕事)」「年次業務(毎年の仕事)」にわけられます。また、四半期や半期ごとに決算業務も発生するため、一年を通して責任のある業務が多い点が特徴です。
上場企業の経理の日次業務(毎日の仕事)
上場企業の経理の日次業務は、取引データを正確に記録し、日々の数字を整えることから始まります。例えば、仕入や売上の仕訳入力、入出金の確認、経費精算のチェックなどがあげられます。
日次業務を怠ると、月末や決算時に大きな修正作業が発生するため、スピードと正確性が求められます。特に上場企業では、内部統制の観点から承認フローや記録の保存が厳密に管理されるため、日々の業務を積み重ねることで信頼できる財務データを作り上げることが重要です。日次業務は小さな作業の連続ですが、正確な決算の土台となる欠かせない役割を担っています。
上場企業の経理の月次業務(毎月の仕事)
月次業務は、月ごとの経営状況を把握するために欠かせない仕事です。例えば、月末時点の売上や費用の計上、未払費用や未収入金の整理、試算表の作成などが行われます。月次業務を正確に行うことで、経営陣は素早く業績を把握し、意思決定に役立てることができます。
上場企業では四半期決算や適時開示のために月次決算のスピードも重視されるため、業務フローの効率化やシステム活用が欠かせません。月次業務は単なる集計作業ではなく、次の四半期決算や年次決算を見据えた準備という役割も担っています。
上場企業の経理の年次業務(毎年の仕事)
年次業務は、一年間の経営成績と財政状態をまとめる決算作業を中心に進められます。例えば、棚卸資産の評価や減価償却費の計上、税金計算、決算短信や有価証券報告書の作成など幅広い業務です。
上場企業では会計監査人による監査対応も必要となるため、資料の準備や質疑への対応に多くの時間を割きます。年次決算は投資家や株主にとって企業の健全性を判断する重要な情報源であるため、正確性と透明性が重視されます。経理担当者にとっては一年間の集大成となる業務であり、事前準備やスケジュール管理が円滑な進行のポイントといえるでしょう。
上場企業の経理担当者に求められるスキル
上場企業の経理担当者に求められるスキルとして、以下のような点があげられます。
- 会計基準に則った決算書の作成スキル
- 申告書作成や税務の知識
- 連結財務諸表の作成スキルと簿記の資格
- 会計システムやIT・AIに関する知識
- 社内外における円滑なコミュニケーション能力
ここでは、それぞれのスキルや知識について詳しく解説していきます。
会計基準に則った決算書の作成スキル
上場企業の経理担当者には、会計基準に従った正確な決算書を作成するスキルが求められます。例えば、日本基準や国際会計基準(IFRS)といった会計基準を理解し、適切に仕訳や評価を行う必要があります。
特に上場企業では四半期決算や有価証券報告書の作成も行うため、スピードと精度の両立が重要です。決算書は投資家や株主が企業の健全性を判断するための重要な資料となるため、数値の裏付けや開示内容の妥当性まで意識した作成が欠かせません。決算書作成のスキルは経験によって磨かれる部分も多く、日常業務を通じて知識と実践力を積み重ねることが大切です。
なお、決算書の作り方についてはこちらの記事も参考にしてください。
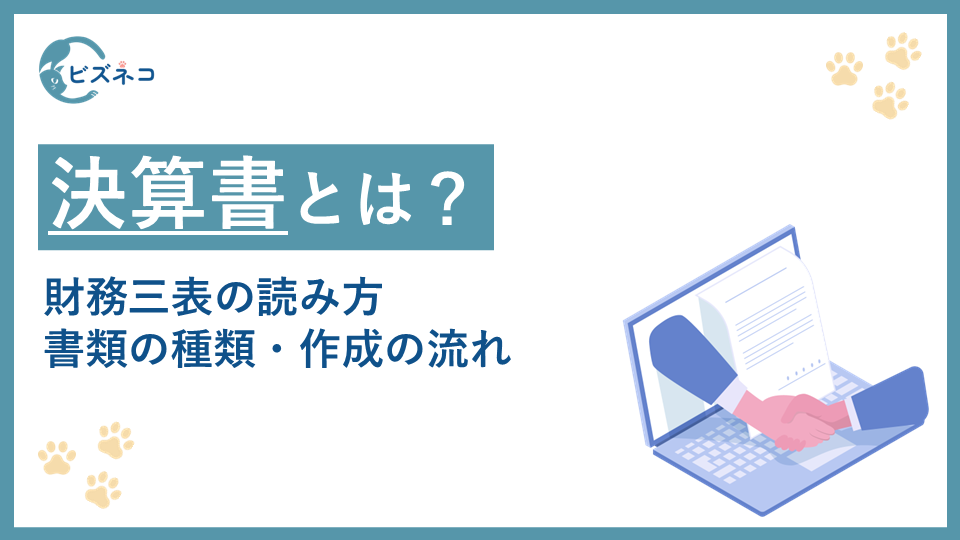
申告書作成や税務の知識
上場企業の経理には、税務申告や税効果会計の処理など、税務に関する幅広い知識が求められます。例えば、法人税や消費税の申告書を正しく作成するためには、税法改正への対応や税額計算の正確性が欠かせません。
また、会計上の利益と課税所得の差異を調整する税効果会計も重要な業務です。ミスがあれば追徴課税や税務調査への対応が必要になるため、知識だけでなく慎重な判断力も必要です。そのため、経理担当者は社内外の税理士や顧問と連携しながら、適切な税務戦略を立てる役割も担います。
連結財務諸表の作成スキルと簿記の資格
上場企業では、グループ全体の業績を示す連結財務諸表の作成が必須です。例えば、子会社の試算表を集計し、内部取引や未実現利益を消去するなど連結特有の処理が必要になります。
連結財務諸表の作成を正確に行うためには、会計基準への理解に加え、簿記や連結会計に関する専門知識が欠かせません。そのため、簿記2級や1級の資格を持つことで理論的な裏付けができ、実務でも精度が高まるでしょう。また、連結決算は四半期ごとに行われるため、効率的な進行のためにスケジュール管理力や調整力も求められます。
会計システムやIT・AIに関する知識
経理業務の効率化が進む中で、会計システムやITに関する知識は重要なスキルとなっています。例えば、ERPシステムを活用した仕訳自動化や、AIによる経費精算の効率化など、新しい技術を導入する機会が増えています。
システムの仕様や運用方法を理解することで、トラブル発生時の対応や業務改善の提案が可能になります。また、データ分析やBIツールの活用ができれば、経営層に有益な情報を提供する付加価値も高められます。経理担当者にとって、ITスキルは数字を扱う力と同じくらい重要な武器になりつつあります。
なお、経理のIT化についてはこちらの記事も参考にしてください。
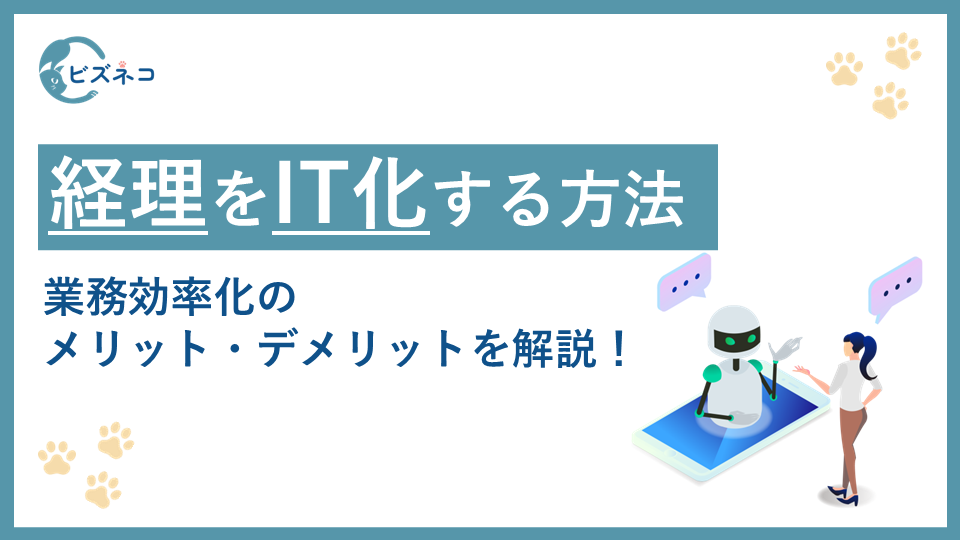
社内外における円滑なコミュニケーション能力
経理担当者には、数字を扱うスキルだけでなく、関係者と円滑にやり取りするコミュニケーション能力も求められます。例えば、営業部門からの情報収集や、監査法人への説明、経営層への報告など、社内外とのやり取りは多くあります。
適切なタイミングで必要な情報を集めるためには、信頼関係の構築とわかりやすい説明が不可欠です。また、複数部門と協力しながらスケジュールを調整する力も重要です。コミュニケーション能力は、正確な数値作成だけでなく、スムーズな決算進行や業務効率化にもつながるでしょう。
上場企業における経理を効率化するコツ
上場企業における経理を効率化するコツとして、以下のような点に注目してみましょう。
- 会社全体で経理DXを進める
- グループ会社間での業務フローを見直す
- 経理代行会社にアウトソーシングする
ここでは、それぞれの効率化のコツや注意点を詳しく解説します。
全社規模で経理DXを進める
経理業務の効率化には、会社全体でDXを推進することが効果的です。例えば、請求書の電子化やクラウド会計システムの導入により、入力作業や確認作業の負担を軽減できます。単なるシステム導入にとどまらず、業務フローそのものを見直して自動化の余地を探ることがポイントです。
経理部門だけでなく、営業や管理部門とも連携し、情報をデジタルで一元管理することで、集計や承認にかかる時間を短縮できます。全社的な取り組みとしてDXを進めることで、決算の早期化やミスの防止にもつながり、経営判断に必要な情報をより迅速に提供できるようになります。
なお、経理のDX推進についてはこちらの記事も参考にしてください。
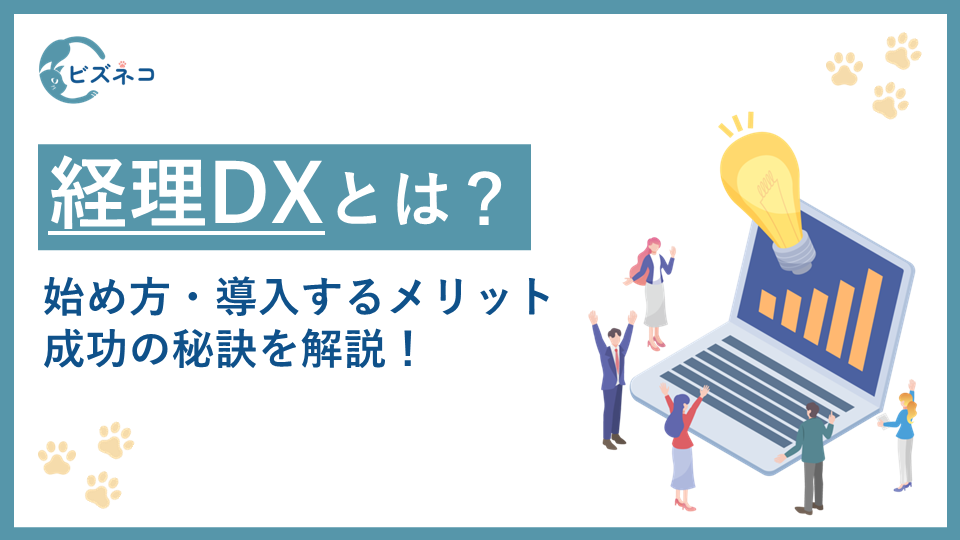
グループ会社間での業務フローを見直す
上場企業では、複数の子会社や関連会社を含むグループ全体の数字を集計する必要があるため、業務フローの見直しが効率化のコツとなります。例えば、子会社からの試算表提出日を統一したり、取引内容や勘定科目のルールを標準化したりすることで、連結決算時の調整作業を減らすことができます。
情報がバラバラだと集計や確認に余分な時間がかかるため、グループ全体で共通のフォーマットやシステムを使用することが望ましいです。また、業務フローを整えることで、数字の精度も向上し、決算スケジュールの短縮や監査対応の負担軽減にもつながります。
なお、経理の業務フローの見直しについてはこちらの記事も参考にしてください。

経理代行会社にアウトソーシングする
経理業務の一部を代行会社に委託することも、効率化の有効な手段です。例えば、仕訳入力や経費精算の確認、支払業務などを外部に任せることで、社内の経理担当者は決算や分析といったより付加価値の高い業務に集中できます。
上場企業では内部統制や開示スケジュールを守る必要があるため、信頼できる代行会社を選定し、業務範囲や責任分担を明確にすることが大切です。アウトソーシングをうまく活用することで、人員不足の解消や残業時間の削減にもつながり、経理部門全体の生産性を高めることができます。
なお、経理のアウトソーシングについてはこちらの記事も参考にしてください。
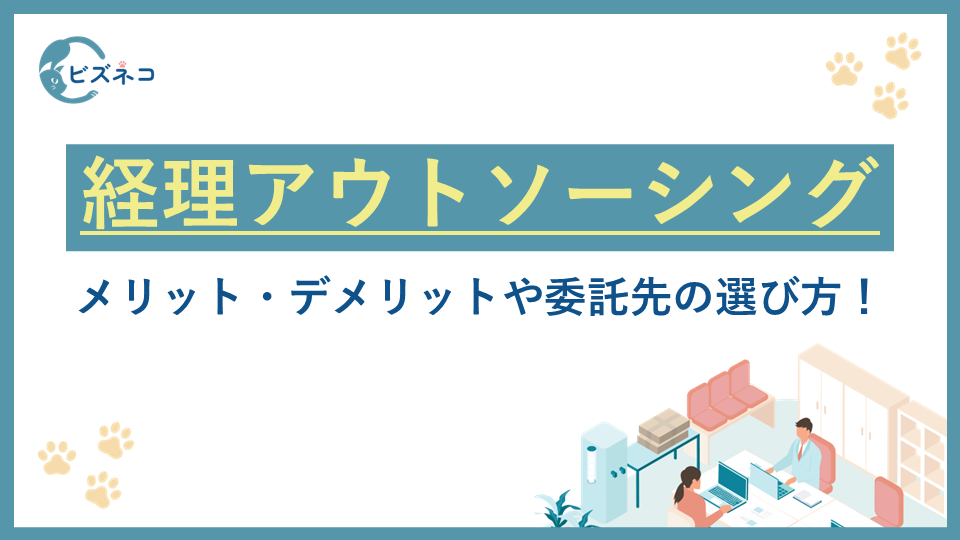
上場企業における経理代行会社の選び方とポイント
上場企業における経理代行会社の選び方とポイントを紹介します。
- 自社のニーズにあった対応範囲の会社を選ぶ
- 円滑なコミュニケーションの取れる担当者で選ぶ
- スピーディで柔軟な対応のできるサービスを選ぶ
ここでは、選び方の注意点についても詳しく解説します。
自社のニーズにあった対応範囲の会社を選ぶ
経理代行会社を選ぶ際は、自社のニーズに合った業務範囲を提供できるかどうかを見極めることが大切です。例えば、仕訳入力や支払業務だけでなく、月次決算や連結決算まで対応可能な会社もあれば、限定的な業務に特化している会社もあります。
自社でどこまでを内製化し、どこから外部に委託するのかを明確にしなければ、期待していた効果が得られずコストだけがかかる恐れがあります。現状の業務フローを整理し、必要なサービス範囲を明確にしたうえで、複数社を比較検討することで、長期的に安心して任せられるパートナーを選びやすくなるでしょう。
円滑なコミュニケーションの取れる担当者で選ぶ
経理代行では、担当者とのコミュニケーションが業務の正確性やスピードを左右します。例えば、経理処理の背景や社内ルールをきちんと理解してくれる担当者であれば、伝達ミスや修正依頼が減り、結果として工数削減にもつながります。
一方で、連絡が取りづらかったり対応が遅かったりすると、締め日や申告期限に影響が出かねません。初期面談の際には、担当者のレスポンスの速さや質問への理解度、提案力なども確認しておくと安心です。円滑なやり取りができる相手を選ぶことで、日々の業務がスムーズに進行し、トラブルを未然に防ぐことができます。
スピーディで柔軟な対応のできるサービスを選ぶ
経理業務は月末や決算期に集中しやすいため、スピード感のある対応が可能な会社を選ぶことが重要です。例えば、急な請求書の処理や支払データの変更などにも柔軟に対応できるサービスであれば、締め日や申告日までに必要な作業を確実に終えられます。
加えて、クラウド会計ソフトやオンライン共有ツールを活用できる会社なら、承認フローも効率化しやすく、リモートワークとの相性も良くなります。契約前に対応スピードやサポート体制、追加依頼時の柔軟性について確認しておくことで、繁忙期でも安心して業務を委託できるでしょう。
まとめ
上場企業の経理業務は、日々の仕訳入力や月次決算、年次決算といった定型業務に加え、投資家や株主への情報開示、内部統制の維持、会計監査対応など、責任を伴う仕事が多くあります。非上場企業と比べると業務範囲や精度の要求が高く、連結決算や国際会計基準対応も求められます。
上場企業の経理の効率化には、経理DXの推進やグループ会社間での業務フローの見直し、信頼できる経理代行の活用がおすすめです。その結果、正確性を保ちながら業務負荷を軽減し、経営判断に必要な情報を迅速に提供できるでしょう。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
上場企業の経理に関するよくあるご質問
上場企業の経理についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、上場企業の経理に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
上場企業の経理は何をするのでしょうか?
上場企業の経理は、日々の仕訳入力や入出金管理から、月次決算や年次決算、四半期決算まで幅広く担当します。さらに、投資家や株主向けの情報開示資料の作成や内部統制の維持、会計監査人への対応も行います。連結決算ではグループ会社間の調整や内部取引の消去も必要で、正確性と透明性を保つことが求められます。
上場企業の経理が「しんどい」「きつい」のはなぜですか?
上場企業の経理が負担を感じやすいのは、業務範囲が広く、開示スケジュールや監査対応などの責任が重いからです。四半期ごとの決算作業や内部統制の遵守、税務申告対応などが重なり、月末や年度末には業務量が集中します。こうしたプレッシャーが継続するため、「しんどい」と感じられることが多いのです。
上場企業は決算を開示する義務がありますか?
上場企業には決算を開示する法的義務があります。四半期ごとの決算短信や年次の有価証券報告書を作成と公表をし、投資家や株主が企業の財務状況を適切に判断できるようにする必要があります。また、財務諸表の正確性を確保するために内部統制や会計監査人による監査も行われ、透明性の高い情報提供が義務付けられています。




