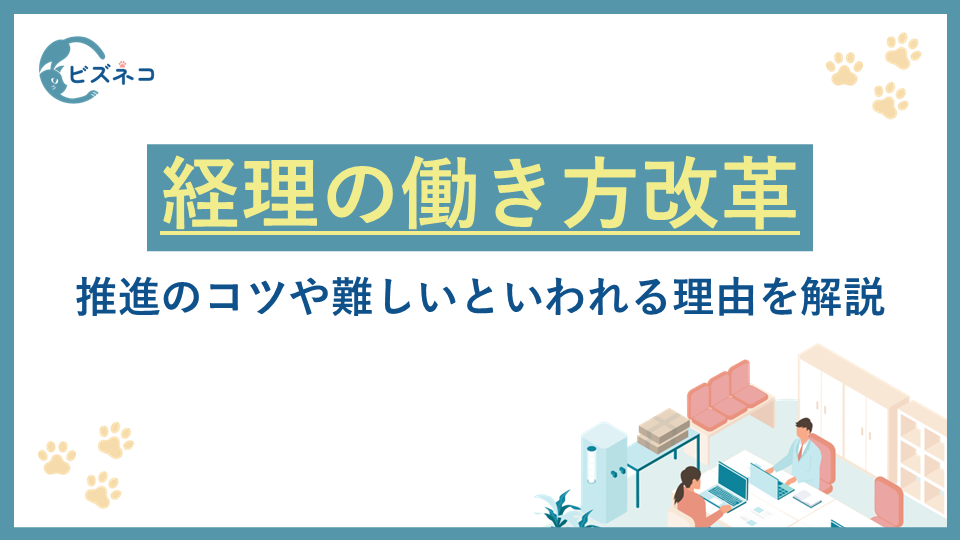
経理部門でも「働き方改革」の必要性が叫ばれるようになりました。しかし、実際の現場では「経理の働き方改革は難しい」と感じている声も少なくありません。また、2024年問題や2025年問題といった外的な変化が、経理の働き方を見直すきっかけにもなっています。契機にもなっています。例えば、労働時間の上限規制やDX化の流れは、業務フローの見直しや人的リソースの再配分を促しています。
本記事では、経理部門における働き方改革の背景や難しさからメリット・デメリットを解説します。また、推進のコツもまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
そもそも「働き方改革」とは?
働き方改革とは、労働時間や雇用形態の多様化などを見直し、誰もがより柔軟に働ける環境を整える取り組みです。例えば、長時間労働の是正やテレワークの導入、副業解禁などが挙げられます。
働き方改革の背景には、少子高齢化による人手不足や、働き手の価値観の変化があります。単に業務時間を減らすだけでなく、生産性の向上やワーク・ライフ・バランスを実現することが目的です。企業にとっては人材確保の面でも重要な施策であり、各部門において対応が求められています。もちろん経理業務も例外ではなく、業務の見直しやIT活用が今後の課題となっています。
働き方改革と2024年問題や2025年問題の関係
2024年問題とは、主に物流・運送業界における働き方改革による懸念です。2024年4月からトラックドライバーの労働時間に上限が設けられることにより、モノを輸送することができなくなってしまうことが課題です。一方で、2025年問題とは、日本の超高齢化と人口減少によって、現役世代への負担が増加してしまうことです。
これらの問題は特定の業界に限らず、日本社会全体の働き方に見直しを迫るものであり、経理を含む企業全体の業務体制の見直しが求められています。人手不足に対応するためには、業務の効率化やデジタル技術の活用が避けて通れないテーマとなりつつあります。
経理部門が取り組むべき働き方改革とは?
経理部門が取り組むべき働き方改革は、業務の見直しとデジタル化を通じた効率化が中心となります。例えば、毎月のルーティン業務である請求書処理や仕訳作業などを自動化すれば、人的負担の軽減が可能になります。
また、繁忙期と閑散期の業務量の差を見える化することで、柔軟な働き方の設計にもつながります。経理業務は企業の数字を正確に扱う責任があるため、慎重さが求められる一方で、形式にとらわれすぎると改善の余地を見逃しがちです。従来のやり方に固執せず、業務フローや人員配置の見直しを進めることが、持続可能な働き方を実現する第一歩といえるでしょう。
働き方改革が経理部門に与える影響
働き方改革が経理部門に与える影響として、以下のような点があげられます。
- 労働時間の上限による業務の圧迫
- DX化やデジタル化の推進
- 人員体制や業務分担の見直し
ここでは、それぞれの影響について詳しく解説していきます。
労働時間の上限による業務の圧迫
労働時間に上限が設けられたことで、経理部門では従来の働き方をそのまま維持するのが難しくなっています。例えば、月末月初の締め作業や決算対応など、時間に追われる業務が多いなかで、時間外労働の制限は大きな課題となります。
これまで残業で補ってきた業務量を、限られた時間内でこなす必要があり、効率化や作業の優先順位の見直しが求められています。現場では「人手も時間も足りない」という声が上がりやすくなっており、根本的な業務設計の見直しを迫られるケースも増えています。働き方改革に対応するには、業務の平準化や自動化を含めた対応が欠かせません。
DX化やデジタル化の推進
DX化やデジタル化の流れは、経理部門の働き方改革にも密接に関わっています。例えば、紙の領収書や請求書を手入力で処理していた業務を、クラウド会計ソフトやAIを使って自動化することで、作業負担の軽減やミスの削減が期待できます。
これにより、単純作業に費やしていた時間を削減でき、より分析的で戦略的な業務に注力できる環境が整います。ただし、ツールの導入にはコストや教育が伴い、すぐに効果が出るとは限りません。それでも、デジタル化は長期的に見て持続可能な働き方への転換につながるため、従来の方法に固執せず、変化を受け入れる姿勢が求められます。
なお、経理DXについてはこちらの記事も参考にしてください。
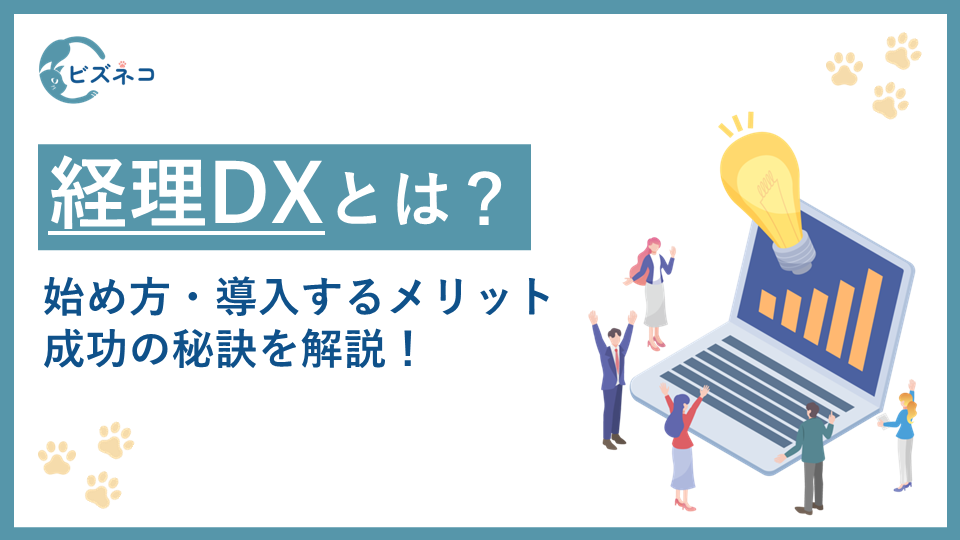
人員体制や業務分担の見直し
人員体制や業務分担の見直しは、経理部門が働き方改革を進めるうえで避けて通れない課題です。例えば、特定の担当者に業務が集中している場合、その人が休んだだけで業務が滞ってしまうリスクがあります。
また、誰もが業務全体を把握できていないと、業務の属人化が進み、効率化の妨げとなります。こうした状況を改善するには、業務を棚卸して、役割や責任のバランスを調整する必要があります。
体制の見直しには一時的な負荷がかかることもありますが、長期的には業務の安定性や働きやすさを向上させる効果が期待できます。
経理部門で働き方改革が難しいといわれる理由
経理部門で働き方改革が難しいといわれる理由として、以下のような点があげられます。
- 日々の締め切りに追われて時間がないから
- 働き方改革を進める人員が足りないから
- 利益に直結する部門の業務ではないから
- 現場視点では業務は滞りなく回っているから
ここでは、それぞれの理由について詳しく解説していきます。
日々の締め切りに追われて時間がないから
経理部門では月次決算や年次決算、請求書処理など定期的に期限が決まっている業務が多く、働き方改革に取り組む時間を確保するのが難しくなっています。例えば、月末月初には通常業務に加えて支払いや帳簿の整理が集中し、残業に頼らざるを得ない状況が発生しやすいのです。
また、改善の必要性を理解していても、短期的には目の前の作業に追われて改革が後回しになりがちです。結果として、効率化や業務フローの見直しに手を付けられないまま、従来の負担が積み重なってしまうケースも多く見られます。
働き方改革を進める人員が足りないから
経理部門は限られた人数で幅広い業務を担っているため、改革を推進する余力が不足しがちです。例えば、経費精算や給与計算、決算対応など日常業務だけで手一杯になり、改善プロジェクトを担当できる人材を割くのが難しいのが現実です。
新しい仕組みを導入するには、検討や調整、運用準備などに時間を割く必要がありますが、余裕がないため後回しになってしまいます。結果として、改革は理念として掲げられても実行に移しづらく、現場レベルでは変化を実感できないまま業務が続いてしまうのです。
利益に直結する部門の業務ではないから
経理部門の業務は企業運営に欠かせないものの、売上や利益を直接生み出す活動ではないため、働き方改革の優先度が低く見られる傾向があります。例えば、営業や製造のように業績に直結する部門は改革が進みやすい一方、経理は「現状維持でも業務が回っている」と判断されがちです。
そのため、システム導入や業務改善にかかる投資が後回しにされ、改革のスピードが遅れることがあります。しかし、経理の効率化は間接的にコスト削減や意思決定の迅速化につながるため、軽視すると中長期的に不利益を招く可能性もあるのです。
現場視点では業務は滞りなく回っているから
経理部門では日々の業務が一見スムーズに進んでいるように見えるため、改革の必要性が伝わりにくいという課題があります。例えば、担当者が残業をして帳簿を整えれば、外部からは「問題なく処理されている」と評価されることがあります。
その結果、現場が抱える負担や非効率な作業が表面化せず、改善が後回しになってしまいます。長期的に見れば人材の定着や業務品質に影響を及ぼす可能性がありますが、目に見える不具合が少ないと改革の優先度が下がりやすいのです。経営層と現場のギャップが、働き方改革を進めにくくする要因のひとつとなっています。
経理部門の働き方改革を推進するメリット
経理部門の働き方改革を推進するメリットとして、以下のような点があげられます。
- ムダな手作業や確認作業を削減できる
- 長時間労働が減り職場環境が整う
- 企業のコスト削減につながる
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
ムダな手作業や確認作業を削減できる
経理の働き方改革を進めることで、これまで時間を取られていたムダな手作業や確認作業を減らすことができます。例えば、請求書の金額を手入力で転記する作業や、Excelで同じ数値を何度も突き合わせるような作業は、システムを導入することで自動化や一括処理が可能になります。
その結果、担当者は単純な入力や照合作業に追われることなく、分析や戦略的な判断に活かせる業務へと時間を割くことができます。効率化によって作業ミスも減り、業務全体の精度が高まることも期待できるでしょう。
長時間労働が減り職場環境が整う
経理部門で働き方改革を進めると、業務の効率化や分担の見直しによって長時間労働が減り、働きやすい職場環境の整備につながります。例えば、決算期や月末月初に集中する業務を平準化することや、自動化ツールを取り入れて残業に頼らなくても処理できる体制を作ることが可能です。
その結果、従業員はワーク・ライフ・バランスを保ちやすくなり、心身の負担が軽減されます。加えて、働きやすい環境は人材の定着や採用にも好影響を与え、結果的に組織全体の活力を高める効果も期待できます。
企業のコスト削減につながる
経理部門の働き方改革は、単なる効率化にとどまらず、企業全体のコスト削減にも直結します。例えば、紙の伝票や請求書を電子化すれば印刷費や保管スペースにかかる費用を抑えられますし、システムを導入して手作業を削減すれば人的リソースをより有効に活用できます。
さらに、入力や確認のミスが減ることで修正に伴う時間やコストも抑制できます。こうした積み重ねにより、経理部門の改善は間接的に経営効率を高めることにつながります。そのため、短期的には投資が必要でも、中長期的には大きな経済効果をもたらす点がメリットといえるでしょう。
経理部門の働き方改革を推進するデメリット
経理部門の働き方改革を推進するデメリットとして、以下のような点に注意が必要です。
- 導入や業務改善にコストがかかる
- 従来の慣習やこだわりの変更に抵抗がある
- 短期間では働き方改革の成果が見えづらい
ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
導入や業務改善にコストがかかる
経理部門の働き方改革には一定のコストが発生するため、短期的には負担が大きく感じられることがあります。例えば、会計システムの導入やクラウドサービスの利用にはライセンス料や設定費用がかかり、従業員への研修など追加の投資も必要です。
業務改善のために外部コンサルタントを活用すれば、外注費用も発生します。長期的には効率化による効果が期待できますが、初期段階では投資と成果のバランスが見えにくく、社内で導入をためらう要因となる場合があります。
従来の慣習やこだわりの変更に抵抗がある
経理部門では正確性が重視されるため、従来の慣習や手順を大きく変えることに抵抗感が生じやすい傾向があります。例えば、紙の請求書や手作業の確認を長年続けてきた企業では、電子化や自動化に移行する際に「本当に正確に処理できるのか?」と不安を抱く担当者も少なくありません。
こうした心理的な抵抗が、改革のスピードを鈍らせる要因となります。また、過去の経験や実績に基づいたこだわりが強い場合、新しい仕組みを受け入れるまでに時間がかかることもあります。
短期間では働き方改革の成果が見えづらい
働き方改革は継続的な取り組みであり、短期間では目に見える効果が出にくいというデメリットがあります。例えば、業務フローを見直しても、最初のうちは慣れない作業が増え、かえって効率が落ちるように感じるケースもあります。システム導入に伴うトラブルや研修の時間も必要であり、その時点では負担が増えたと認識されやすいのです。
しかし、中長期的に見れば労働時間の削減やコスト圧縮につながる可能性があります。そのため、短期的な評価だけで判断すると、本来の効果が正しく見えない点がデメリットといえるでしょう。
経理部門の働き方改革を推進するコツ
経理部門の働き方改革を推進するコツとして、以下のような点を意識してみましょう。
- 繁忙期ではなく閑散期に着手してみる
- 業務の棚卸と見える化から始めてみる
- トップダウンではなく現場の声を取り入れる
- 経理代行会社に相談してみる
ここでは、それぞれのコツについて具体的に解説します。
繁忙期ではなく閑散期に着手してみる
経理部門で働き方改革を進める際は、繁忙期ではなく閑散期に取り組むことが効果的です。例えば、月末や決算期は日常業務に追われるため、新しい仕組みの導入や改善活動を行う余裕がなく、結果的に改革が形だけで終わってしまう可能性があります。
一方で比較的業務量が落ち着いている時期なら、現場に負担をかけずに試行錯誤を繰り返すことができます。小さな改善を積み重ねて慣れをつくることで、繁忙期にも活用できる体制が整い、結果的にスムーズな定着につながっていきます。
業務の棚卸と見える化から始めてみる
働き方改革を推進するには、まず現状の業務を整理し、どの作業にどれだけ時間や人員がかかっているのかを明らかにすることがポイントです。例えば、経費精算や伝票処理にかかる時間を洗い出せば、どの業務を自動化すべきかが見えてきます。
こうした「棚卸」と「見える化」によって、改善の優先順位がつけやすくなり、無理のない改革の道すじを描けるようになります。加えて、現場の感覚だけで進めるのではなく、データに基づいて課題を明確化することで、取り組みの実効性が高まります。
トップダウンではなく現場の声を取り入れる
経理部門で働き方改革を進めるには、経営層からの指示だけでなく、実際に業務を担っている現場の声を反映させることが大切です。例えば、システム導入をトップダウンで決めても、現場の実態に合わなければ逆に作業が増えてしまうこともあります。
現場の課題や悩みを聞き取ることで、改善策が机上の理論ではなく実務に即したものとなり、浸透しやすくなります。また、経営と現場が一体となって進めることで、改革のスピードや定着度も高まり、長期的な効果につながります。
経理代行会社に相談してみる
働き方改革を進めるにあたり、外部の専門機関を活用するのもおすすめです。例えば、日常的な記帳や経費精算の処理を経理代行会社に任せれば、社内の人員をコア業務や改善活動に振り向けることができます。
外部の知見を取り入れることで、自社では気づきにくい改善策や最新の効率化手法を学べる点も大きなメリットです。もちろん費用はかかりますが、業務負担を軽減し改革を加速させる効果を期待できます。内部の努力だけで限界を感じる場合は、外部リソースの活用を検討する価値があります。
なお、経理代行会社についてはこちらの記事も参考にしてください。
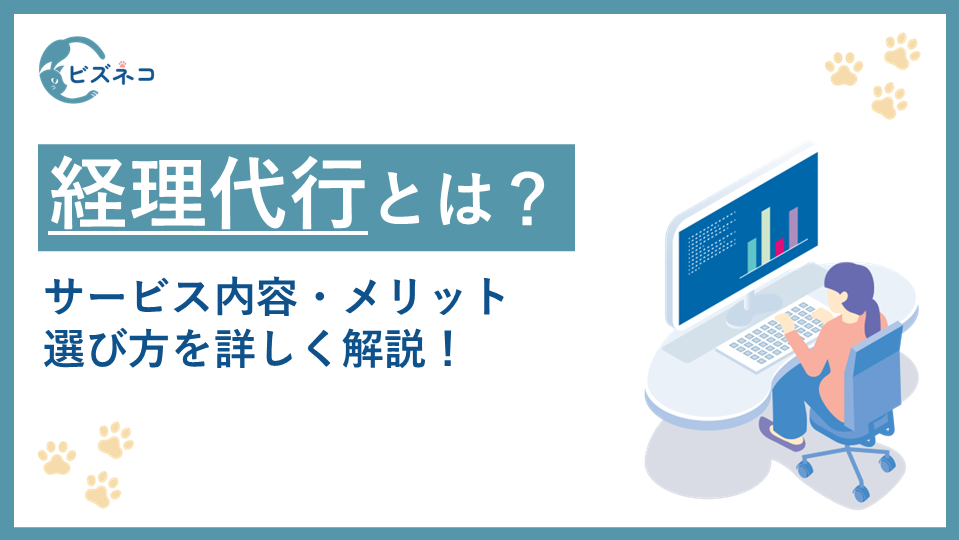
まとめ
働き方改革とは、労働時間や雇用形態の多様化などを見直し、誰もがより柔軟に働ける環境を整える取り組みです。例えば、長時間労働の是正やテレワークの導入、副業解禁などが挙げられます。
経理部門が取り組むべき働き方改革は、業務の見直しとデジタル化を通じた効率化が中心となります。例えば、毎月のルーティン業務である請求書処理や仕訳作業などを自動化すれば、人的負担の軽減が可能になります。また、経理部門の働き方改革を推進するコツとして、経理代行会社の活用があげられます。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
経理の働き方改革に関するよくあるご質問
経理の働き方改革についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、経理の働き方改革に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
働き方改革の3つの柱は何ですか?
働き方改革の3つの柱は「長時間労働の是正」「正規、非正規の格差解消」「多様で柔軟な働き方の実現」です。例えば、残業規制や有給休暇取得の推進は労働時間の是正にあたり、テレワークや副業解禁は多様性のある働き方の一例です。さらにIT活用や業務効率化によって限られた時間で成果を高めることが求められています。
2024年問題とは何ですか?
2024年問題とは、働き方改革関連法により医師や建設業、運輸業などに時間外労働の上限規制が適用されることで起こる課題を指します。運送業界ではドライバー不足や配送遅延が懸念され、建設業では工期の遅れが発生する可能性があります。労働環境の改善が目的ですが、産業全体の供給体制に影響します。
働き方改革の2025年問題とは何ですか?
2025年問題とは、団塊の世代が75歳以上となり、日本の人口構造が大きく変化することで生じる社会的課題を指します。医療や介護の需要が急増する一方で、支える現役世代が減少し、社会保障費の増大や人材不足が深刻化すると懸念されます。超高齢化による負担の増加は、医療制度や労働環境の見直しが求められています。




