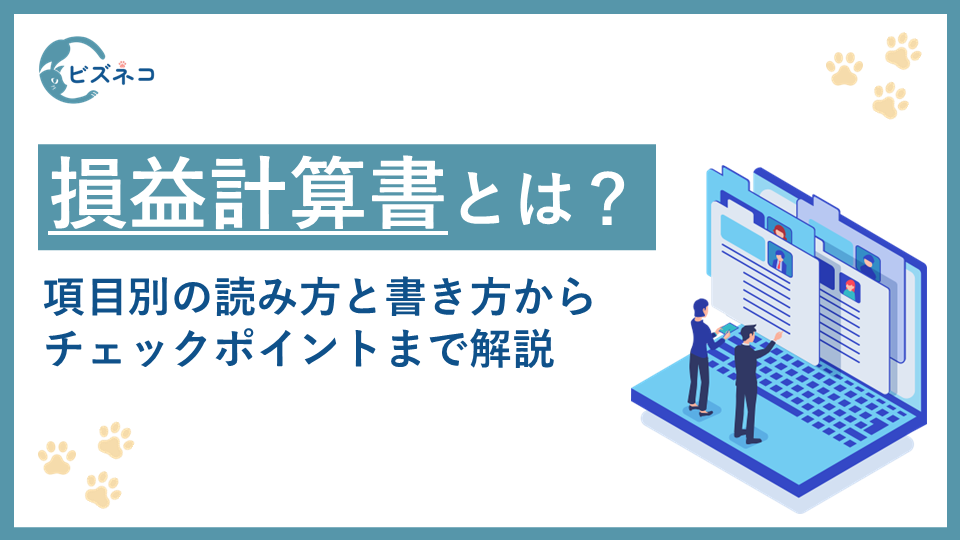
損益計算書(P/L)は、企業の一定期間における収益と費用をまとめ、その結果として利益や損失がどのように生じたのかを示す重要な財務諸表のひとつです。例えば、売上から仕入や人件費などの費用を差し引くことで、どの程度の利益が残ったのかを明確に把握できます。
本記事では、財務三表のひとつである損益計算書の基本的な役割から、貸借対照表やキャッシュフロー計算書との違い、各部の構成や具体的な読み方について解説します。また、実際に作成する手順も紹介します。ぜひ、最後までご覧ください。
目次
損益計算書(P/L)とは?
損益計算書(P/L)とは、一定期間における企業の収益と費用を整理し、その差額として利益や損失を明らかにする財務諸表です。例えば、売上高から仕入や人件費などの費用を差し引いた結果として、どれだけの利益が残るのかが一目でわかります。
損益計算書は、経営成績を外部に示すと同時に、経営者が今後の方針を検討するうえでも重要な役割を果たします。また、投資家や金融機関にとっても企業の健全性を判断する指標となるため、正確な作成と理解が求められるのです。
財務三表とは?
財務三表とは、企業の経営状況を把握するために用いられる「損益計算書」「貸借対照表」「キャッシュフロー計算書」の3つの基本的な財務諸表を指します。例えば、損益計算書で収益と費用の関係を確認し、貸借対照表で資産や負債のバランスを把握し、キャッシュフロー計算書で現金の流れを追うことができます。
財務三表を組み合わせることで、利益の有無だけでなく、資金繰りの健全性や財務基盤の強さを総合的に理解できるのが特徴です。
なお、財務三表については、こちらの記事も参考にしてください。
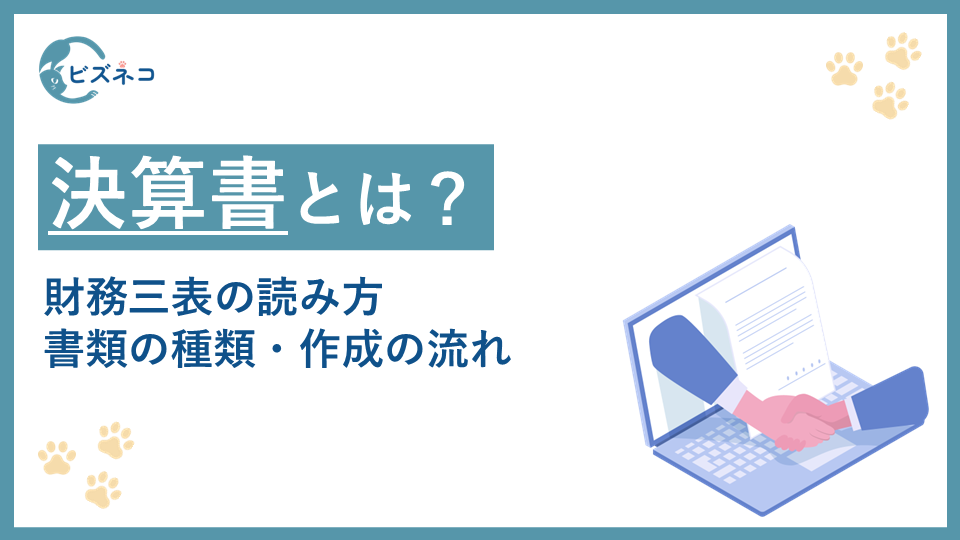
損益計算書(P/L)と貸借対照表(B/S)の違い
損益計算書(P/L)と貸借対照表(B/S)の違いは、表す対象と期間にあります。損益計算書は一定期間の収益と費用を示し、その結果としての利益や損失を明らかにします。
一方で貸借対照表は、決算時点における資産・負債・純資産の状況をまとめたもので、財務状態を静的に把握できます。例えば、利益が出ている企業であっても、貸借対照表を見ると資金繰りに余裕がない場合があるため、両者を合わせて確認することで初めて正確な経営状況を理解できるのです。
なお、貸借対照表については、こちらの記事をご覧ください。
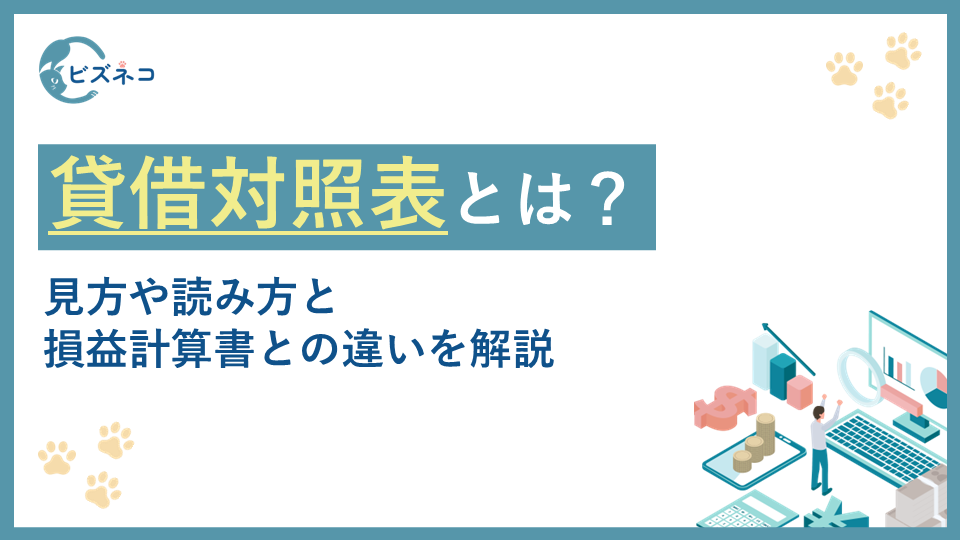
損益計算書(P/L)とキャッシュフロー計算書(C/F)の違い
損益計算書(P/L)とキャッシュフロー計算書(C/F)の違いは、利益と現金の動きをどう捉えるかという点にあります。損益計算書は発生主義に基づき、売上や費用を計上するため、実際に現金が動いていなくても利益が計算されます。例えば、売掛金が多ければ利益は出ていても現金が不足することがあります。
一方、キャッシュフロー計算書は現金の収支を中心にまとめるため、資金繰りの健全性を確認するのに適しています。損益計算書とキャッシュフロー計算書の両方を合わせて読むことで、利益と現金の両面から企業の実態を把握できます。
なお、キャッシュフロー計算書についてはこちらの記事をご覧ください。
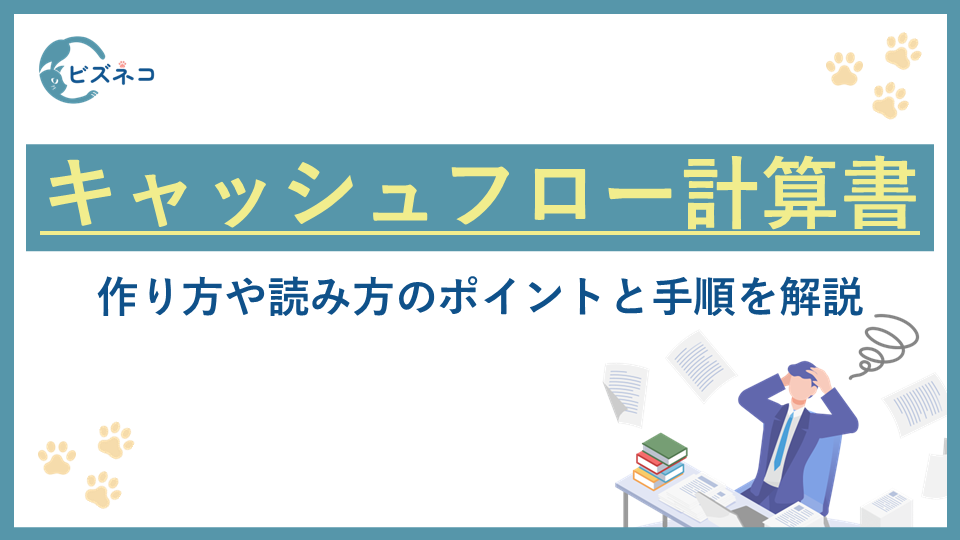
損益計算書(P/L)の構成と各部
損益計算書(P/L)の構成は以下の部に分けられます。
- 営業損益の部
- 営業外損益の部
- 経常利益の部
- 特別損益の部
- 当期純利益の部
ここでは、それぞれの部について詳しく解説します。
営業損益の部
営業損益の部は、企業が本業で得た収益と、それに直接かかわる費用を集計して算出される利益を示します。例えば、商品の売上から仕入原価や販売費、人件費などを差し引いた結果がここに反映されます。
営業損益の部は企業の主力事業の採算性を確認するうえで欠かせない指標であり、事業の収益力や効率性を把握する手がかりとなります。金融機関や投資家もまず注目する項目であるため、営業損益を正確に理解することは経営分析の基盤ともいえるでしょう。
営業外損益の部
営業外損益の部は、企業の本業以外から発生する収益や費用を整理したものです。例えば、受取利息や配当金といった金融収益、逆に支払利息や為替差損などが該当します。
営業外損益の部は、企業の資金運用や財務活動が経営成績にどのような影響を与えているのかを確認できる点が特徴です。また、営業外損益が安定しているかどうかは、本業以外に依存していないかを判断する要素にもなり、経営の健全性を測る指標としても大切な役割を担っています。
経常利益の部
経常利益の部は、営業損益と営業外損益を合算して算出される利益を示しています。例えば、本業で安定的に利益を生み出していても、支払利息が多ければ経常利益は圧縮されてしまいます。
一方で、営業外で得られる収益が大きければ企業の全体的な利益を底上げすることもあります。経常利益の部は企業の通常の経営活動から得られる成果を把握するための中核となる指標であり、金融機関や投資家が企業の収益力を評価する際に重視されます。
特別損益の部
特別損益の部は、日常的な経営活動とは異なる臨時的な収益や費用を示します。例えば、固定資産の売却益や損失、災害による損害損失、事業再編に伴う費用などが含まれます。
特別損益の部は一時的な性質を持つため、通常の収益力を判断する材料にはなりませんが、企業のその期の純利益に大きな影響を与えることがあります。したがって、特別損益の内容を確認することは、経営の安定性や将来にわたる持続性を分析する上で欠かせません。
当期純利益の部
当期純利益の部は、経常利益に特別損益を加減した後、さらに法人税などを差し引いた最終的な利益を示します。例えば、営業段階で黒字であっても、特別損失や税金の影響により当期純利益が赤字となることもあります。
当期純利益の部は、株主や投資家にとって企業の最終的な成果を表す重要な数値であり、配当や将来の投資余力にも直結します。そのため、当期純利益を正しく理解することは企業価値を判断するうえで欠かせない視点といえるでしょう。
損益計算書(P/L)の見方とチェックポイント
売上高総利益率(粗利率)
- 売上高総利益率 = 売上総利益 ÷ 売上高 × 100
売上高総利益率は、売上総利益を売上高で割って算出される、企業の収益性を測る基本的な指標です。例えば、売上が同じでも仕入や製造コストを抑えられる企業ほど粗利率は高くなり、効率的な経営が行われていると判断できます。
売上高総利益率を確認することで、商品やサービスの価格設定やコスト構造が適切かどうかを見極めることができます。売上高総利益率は単年度だけでなく、複数年の推移を比較することで改善傾向や課題を把握することにも役立ちます。
売上高営業利益比率
- 売上高営業利益比率 = 営業利益 ÷ 売上高×100
売上高営業利益比率は、営業利益を売上高で割って求められる指標で、本業の収益力を測る際に活用されます。例えば、売上が増えていても販売費や人件費が膨らんでいれば比率は下がり、効率的に利益を上げられていないことが分かります。
売上高営業利益比率は企業の本業の強さを示すものであり、業種ごとに平均値が異なるため、同業他社との比較で特に有効です。安定的に高い比率を維持できている企業は、本業の基盤がしっかりしていると考えられます。
売上高経常利益比率
- 売上高経常利益比率 = 経常利益 ÷ 売上高 × 100
売上高経常利益比率は、経常利益を売上高で割ることで算出され、企業の総合的な収益力を示します。例えば、本業で利益が出ていても、借入金の利息負担が大きければこの比率は低下し、財務面の課題が見えてきます。
売上高経常利益比率は営業活動だけでなく財務活動や投資活動の影響も反映するため、企業の経営全体の健全性を確認するのに役立ちます。安定した経常利益比率は、収益構造がバランス良く整っていることを示す重要な要素といえるでしょう。
損益計算書(P/L)の書き方と作成手順
損益計算書(P/L)の書き方は以下の手順で進みます。
- step1:伝票と仕訳帳を作成する
- step2:総勘定元帳に転記する
- step3:決算整理仕訳を行う
- step4:試算表を作成する
- step5:損益計算書(P/L)を作成する
ここでは、それぞれのステップについて詳しく解説していきます。
step1:伝票と仕訳帳を作成する
伝票と仕訳帳の作成は、損益計算書作成の出発点となります。例えば、売上が発生した際には売掛金や売上高を仕訳として記録し、現金支払では現金や費用を対応させます。こうした取引を正確に伝票へ起こし、仕訳帳へ整理して記録することで、後続の処理が正しく進められる基盤が整います。
日々の記録を漏れなく残すことが、最終的に損益計算書の信頼性を高める第一歩となるのです。さらに、伝票と仕訳帳を整えることで、取引の根拠が残り、後から監査や確認が必要になった場合にもスムーズに対応できるというメリットがあります。
なお、仕訳帳の作り方についてはこちらの記事も参考にしてください。
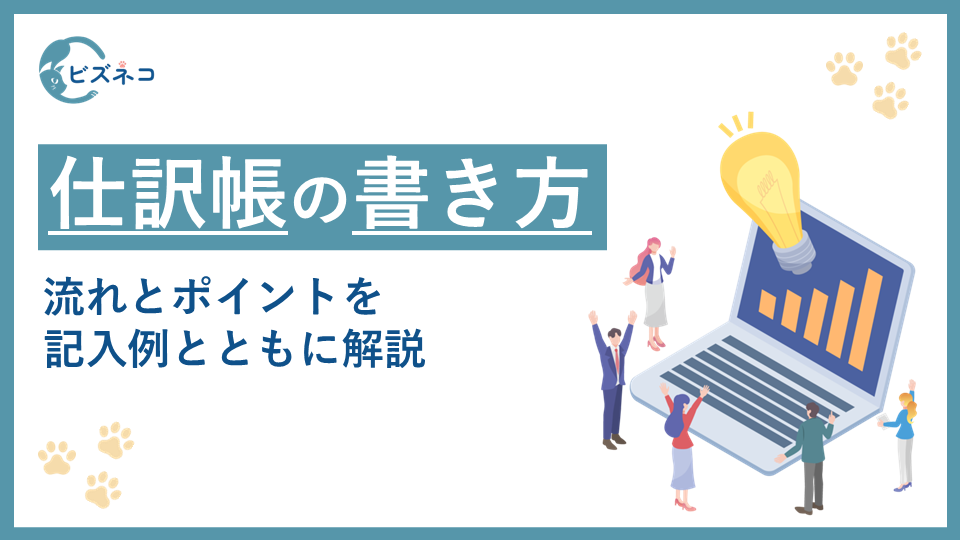
step2:総勘定元帳に転記する
仕訳帳に記録した内容を総勘定元帳へ転記する作業は、取引を勘定科目ごとに整理するために欠かせません。例えば、売掛金に関する仕訳をすべてまとめることで、その科目の増減や残高を一目で確認できるようになります。転記を丁寧に行うことで勘定残高の正確性が担保され、試算表や損益計算書の作成に直結します。
そのため、転記での正確な処理が後の決算手続きの効率性を大きく左右し、慎重さが求められます。また、総勘定元帳は会計データを体系的に管理する役割も持つため、経営分析や予算管理の基盤としても活用されます。
なお、総勘定元帳の書き方については、こちらの記事も参考にしてください。
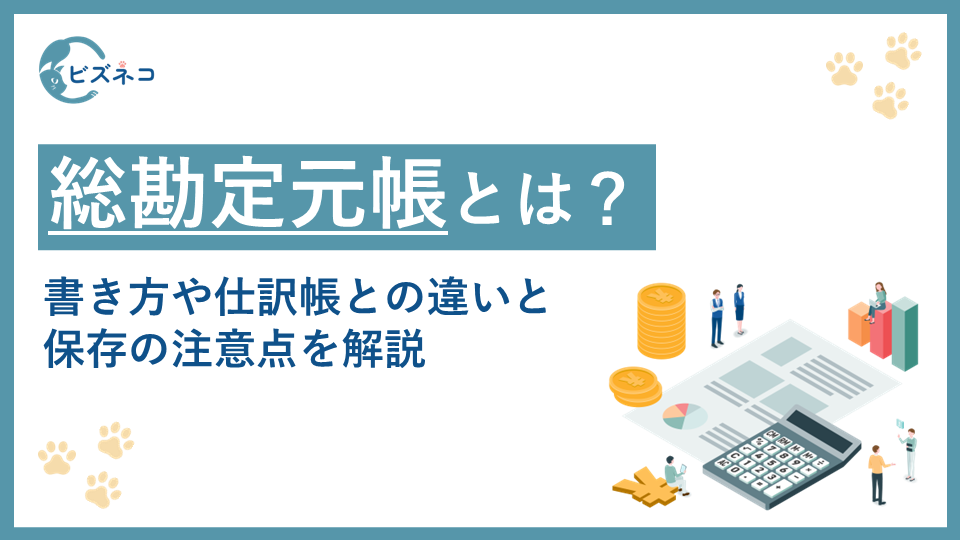
step3:決算整理仕訳を行う
決算整理仕訳は、期間中に発生した収益や費用を正しく反映させるための重要な調整作業です。例えば、まだ支払っていない費用を未払費用として計上したり、受け取った前受金を収益から除外したりします。こうした処理によって、発生主義の会計原則に基づいた正確な損益を計算できるようになります。
決算整理仕訳を適切に行うことで、損益計算書に表示される利益や費用が実態に即したものとなるのです。さらに、減価償却や貸倒引当金の設定といった処理も含まれるため、企業の財務状況を現実に近づける意味で欠かせない工程です。
step4:試算表を作成する
試算表は、総勘定元帳に記録された残高を集計し、貸借の均衡を確認するために作成されます。例えば、貸方と借方の合計額が一致していれば仕訳や転記の誤りがない可能性が高く、逆に不一致があればミスを探す必要があります。試算表はその後の決算書作成に直結するため、誤りの有無を洗い出すチェックの役割を持ちます。
正確な試算表を整えることは、損益計算書作成の前段階として欠かせない工程です。さらに、試算表は内部管理にも役立ち、経営者が現状の収益や費用の動きを確認するための簡易的な指標としても活用されています。
なお、試算表の作り方についてはこちらの記事も参考にしてください。

step5:損益計算書(P/L)を作成する
試算表をもとに損益計算書を作成する工程では、収益と費用を整理し、最終的な利益や損失を明らかにします。例えば、売上高から売上原価を差し引いて売上総利益を算出し、さらに営業費用や営業外収益、費用を加減していきます。その結果として経常利益や当期純利益が導き出されます。
損益計算書作成の段階までの処理が正確に行われていれば、損益計算書は企業の経営成績を正しく表す資料となり、社内外の意思決定に役立ちます。加えて、損益計算書は投資家や金融機関への説明資料としても利用されるため、正確な内容での作成が求められます。
損益計算書(P/L)を作成する際の注意点
損益計算書を正確に作成するためには、基本的な会計ルールに従い、勘定科目や帳簿の扱いに注意することが欠かせません。誤った処理や表記は経営判断や外部への説明に影響するため、適切な方法で整理する必要があります。
複式簿記での帳簿が必要になる
損益計算書を正しく作成するためには、複式簿記による帳簿が前提となります。複式簿記では、すべての取引を借方と貸方に分けて記録するため、資産や負債、収益や費用の動きを二面的に捉えることができます。例えば、商品の販売で売掛金が発生した場合は、借方に売掛金、貸方に売上高を記録することになります。
このように二重で記録を行うことで、帳簿全体の整合性が保たれ、損益計算書に誤りなく数値を反映できるのです。単式簿記でも簡易的な収支計算は可能ですが、企業会計に求められる精度や信頼性を担保するには不十分です。複式簿記を基礎とした帳簿作成が、損益計算書を正確に仕上げるための大前提である点を理解しておく必要があります。
なお、複式簿記についてはこちらの記事も参考にしてください。
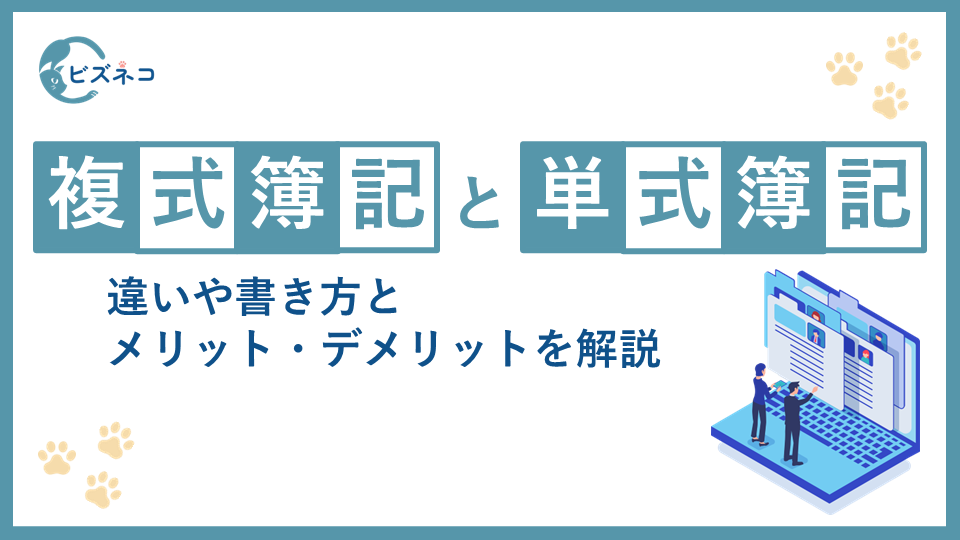
表示名の変更が必要な勘定科目がある
損益計算書を作成する際には、勘定科目の表示名を整理して変更する作業が必要になります。仕訳帳や総勘定元帳では日常的な取引を分かりやすく記録しますが、決算書にそのまま転記すると利用者に理解されにくい場合があるからです。例えば、「売上」という勘定科目は損益計算書上では「売上高」として表記され、「仕入」は「売上原価」として示されます。
勘定科目の変更は、財務諸表が外部の投資家や金融機関などに読みやすく、比較可能性を高めるために欠かせない対応です。さらに、売上高の計上は現金を受け取った時点ではなく、商品を引き渡した時点で行うなど、会計基準に沿った正確な処理も求められます。このように、勘定科目の表示名を正しく整えることが、信頼性ある損益計算書の完成につながります。
なお、勘定科目については、こちらの記事でもまとめています。
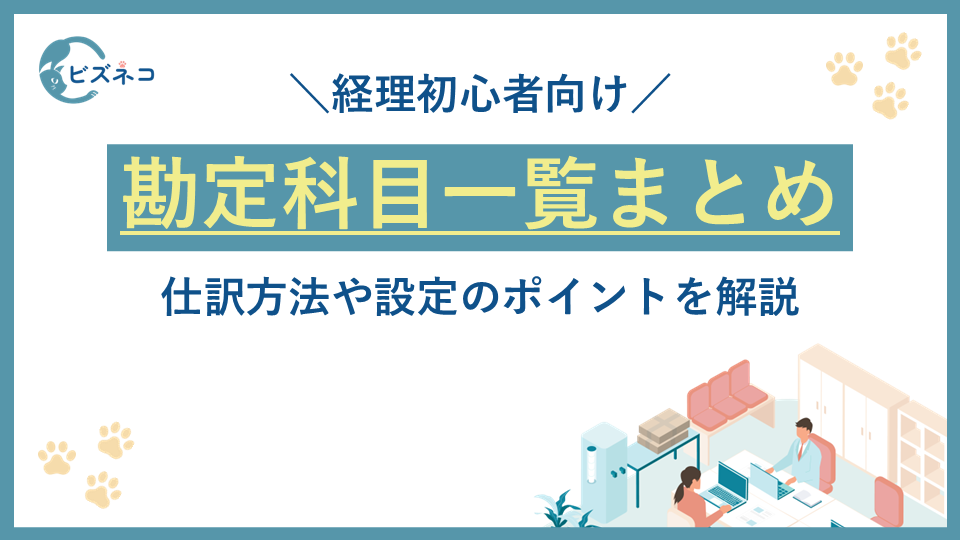
まとめ
損益計算書(P/L)とは、一定期間における企業の収益と費用を整理し、その差額として利益や損失を明らかにする財務諸表です。例えば、売上高から仕入や人件費などの費用を差し引いた結果として、どれだけの利益が残るのかが一目でわかります。
損益計算書を作成する際には、複式簿記での帳簿が必要になる点と、表示名の変更が必要な勘定科目がある点に注意しましょう。また、作成の前には仕訳帳の作成や、総勘定元帳への転記、試算表の作成も必要になります。そのため、経理代行会社に相談して、業務の効率化を進めることもおすすめです。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
損益計算書(P/L)に関するよくあるご質問
損益計算書についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、損益計算書に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
損益計算書(P/L)とは何ですか?
損益計算書(P/L)は、企業の一定期間における収益と費用を整理し、その結果として利益や損失を示す財務諸表です。売上から費用を差し引き、営業利益や経常利益、最終的な当期純利益を明らかにします。企業がどのように利益を生み出しているのかを把握できる資料であり、経営判断や投資家への情報提供に欠かせません。
損益計算書(P/L)と貸借対照表(B/S)はどちらが大事ですか?
損益計算書(P/L)と貸借対照表(B/S)は、どちらも重要で一方だけで十分とはいえません。P/Lは企業が一定期間にどれだけ利益を上げたかを示し、経営成績を把握するために役立ちます。一方でB/Sは資産や負債、純資産の状況を表し、財政状態の健全性を確認できます。企業分析や投資判断では両者ともに大切です。
損益計算書(P/L)は誰が作るのですか?
損益計算書(P/L)は、通常は企業の経理部門や会計担当者が中心となって作成します。日々の仕訳や帳簿管理をもとに、決算期に試算表を整え、会計基準に沿ってまとめられます。小規模な事業者の場合は経営者自身が作成することもありますが、税理士や会計士、経理代行会社に依頼するケースも一般的です。




