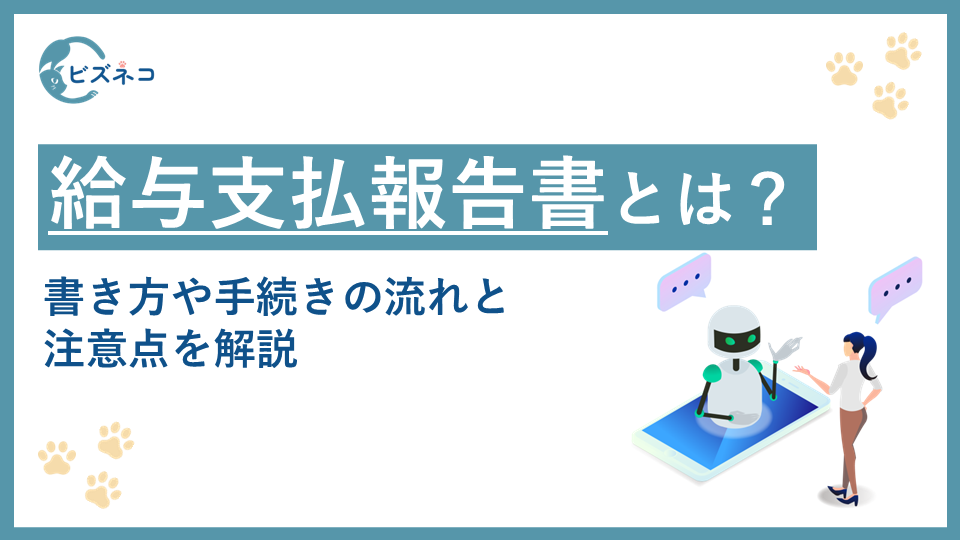
会社が従業員に給与を支払う際、年末調整の手続きだけでなく、市区町村に対しても「給与支払報告書」を提出する必要があります。しかし、源泉徴収票との違いが分かりにくかったり、書き方や提出手続きに不安を感じている担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、給与支払報告書の概要や種類、書き方、手続きの流れ、注意点までをわかりやすく解説します。実務に役立つポイントを押さえて、正確かつスムーズな対応の参考にしてください。
目次
給与支払報告書とは?
給与支払報告書は、従業員の1年間の給与や源泉徴収額などの情報を市区町村に報告するための書類です。例えば、1月に市区町村から送られてくる総括表に基づいて、企業は従業員一人ひとりの情報を記載した個人別明細書を添えて提出します。
給与支払報告書は、翌年度の住民税を正しく算出するための基礎資料となるため、記載内容に不備があると従業員に影響が及ぶ可能性もあります。給与の支払いや年末調整が完了したあとに作成し、翌年1月末までに提出する必要があります。企業にとっては年初に行う重要な業務のひとつであり、内容の正確さと期限厳守が求められる書類です。
給与支払報告書と給与支払証明書の違い
給与支払報告書と給与支払証明書の違いは提出先と用途です。給与支払報告書は市区町村に提出する公的な書類であり、従業員の住民税を計算するために使用されます。一方で給与支払証明書は、従業員が保育園の入園申請や住宅ローンの審査などで自身の収入を証明するために会社から個別に発行してもらう書類です。
例えば、転職して間もない社員が前職の収入証明として給与支払証明書を提出するよう求められることがあります。どちらも給与情報を含みますが、目的と使われる場面が異なります。混同しやすい名称ではありますが、企業の経理担当者は違いを正しく理解し、適切に対応することが求められます。
給与支払報告書と源泉徴収票の違い
給与支払報告書と源泉徴収票の違いは提出先と使途にあります。給与支払報告書は市区町村に提出され、住民税の計算に使用されます。一方で、源泉徴収票は従業員本人に交付する書類で、確定申告や住宅ローンの申請などで利用されます。
年末調整が終わった後、会社は1月末までに源泉徴収票を従業員に配布し、同時にその内容に基づいた給与支払報告書を各自治体に提出します。
両者とも給与や税額の情報を記載する点では似ていますが、それぞれの提出先と目的が異なるため、取り扱いを間違えると税務上のトラブルに発展する可能性もあります。年末から年始にかけて忙しい時期ですが、両方の書類を正しく理解し、整理しておくことが大切です。
なお、年末調整や確定申告という言葉もよく耳にするでしょう。年末調整についてはこちらの記事もご覧ください。
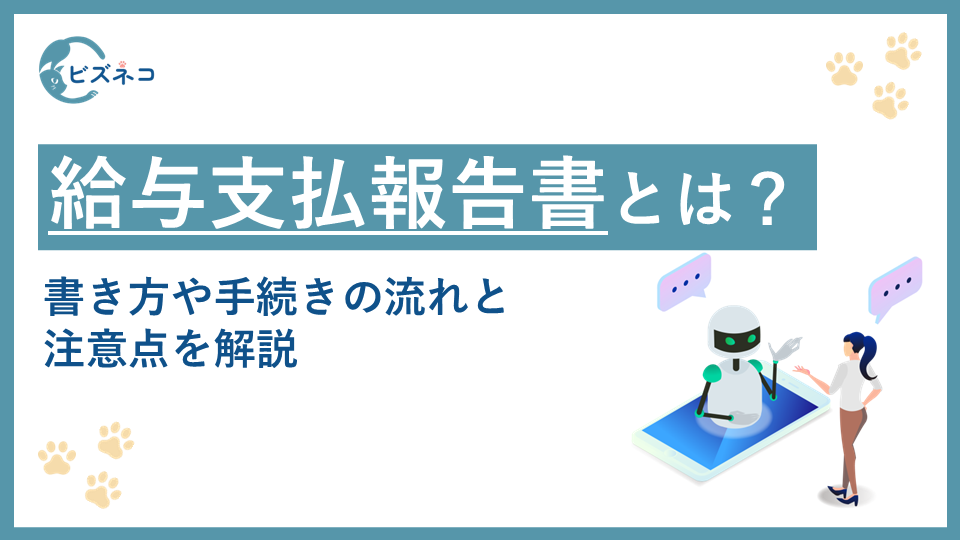
給与支払報告書の種類と書式
給与支払報告書の種類と書式として、主に以下の3種類の書式があります。
- 総括表(給与支払報告書 総括表)
- 個人別明細書(給与支払報告書 個人別明細書)
- 普通徴収切替理由書
ここでは、それぞれの種類や書式について詳しく解説していきます。
総括表(給与支払報告書 総括表)
総括表は、事業所単位で提出する給与支払報告書の一覧表であり、提出対象となる従業員の人数や支払者情報などを記載する書類です。例えば、10人の従業員に給与を支払っている企業であれば、その10人全員の個人別明細書をまとめて提出する際、総括表が必要になります。
提出先の市区町村ごとに1枚作成する必要があり、基本的には年に一度、年末調整後に作成します。記載内容に不備があると、個人別明細書が受理されなかったり、住民税の課税が正しく行われなかったりする可能性もあります。そのため、事業所全体の給与支払い状況を網羅する資料として、正確に作成する必要があります。
個人別明細書(給与支払報告書 個人別明細書)
個人別明細書は、従業員一人ひとりの給与や控除額、源泉徴収税額などの詳細を記載するもので、給与支払報告書の中心を担う書類です。例えば、年末調整の結果を反映した源泉徴収票の内容をもとに、氏名やマイナンバー、支払金額などを記載します。
個人別明細書は、翌年度の住民税を正確に計算するための基礎資料となるため、記載ミスや漏れがあると課税額に影響を与えることがあります。また、提出先が従業員の住民票上の市区町村である点も注意が必要です。各従業員ごとに1枚ずつ作成する必要があるため、年末調整が完了した段階で速やかに準備を始めることが、スムーズな提出につながります。
普通徴収切替理由書
普通徴収切替理由書は、本来「特別徴収」が基本とされる住民税について、やむを得ず「普通徴収」に切り替える場合に、その理由を記載して提出する書類です。例えば、パート社員が年の途中で退職したため、翌年の住民税を給与から天引きすることができないといったケースでは、普通徴収切替理由書を添付して個人別明細書を提出する必要があります。
市区町村は普通徴収切替理由書に基づいて、普通徴収への切り替えを判断するため、正確かつ明確な記載が求められます。なお、理由が曖昧であったり正当と認められない場合、特別徴収のまま処理されてしまうこともあるため注意しましょう。
給与支払報告書の書き方
給与支払報告書の個人別明細書は、手書きでも電子データでも作成可能ですが、それぞれ注意すべき点があります。例えば、手書きの場合は複写式の用紙を使用するため、下の用紙に正しく転写されるよう、しっかりとした筆圧で記入する必要があります。電子データで作成する場合は、市区町村のホームページからダウンロードしたExcelファイルに入力することで、複数のシートに自動反映され、作業効率が向上します。
ただし、いずれの方法でも記載漏れや入力ミスがあると、住民税の計算に支障をきたす恐れがあります。ここでは、給与支払報告書に記載する各項目について、意味や記入方法を具体的に解説していきます。
支払いを受ける者
給与の受給者に関する基本情報を記載する欄です。例えば、氏名や住所、生年月日、マイナンバーなどが該当し、住民税の算定に欠かせない情報です。記載ミスがあると、課税に支障が出るおそれがあるため注意しましょう。
種別
対象者の所得の種類を区別するための項目です。例えば、通常の給与所得だけでなく、退職所得や報酬などが該当する場合もあります。誤った区分で申告すると、課税処理に影響が出る可能性があります。正しい判断には、支給内容を確認することが重要です。
支払金額
その年に実際に支払った給与などの合計額を記入します。例えば、基本給に加え、通勤手当や賞与なども含める必要があります。年末調整後の確定金額をもとに正確に記載しましょう。明細の積み上げ計算により確認しておくと、入力ミスを防げます。
給与所得控除後の金額
給与所得控除を差し引いた後の金額を記載する欄です。例えば、年収が400万円であれば、その額に応じた控除額を差し引いて算出されます。計算された金額が住民税の課税対象額のベースになります。なお、控除額は自動計算される様式を使うと便利です。
所得控除の額の合計額
所得控除として、社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの合計金額を記載します。例えば、年末調整をしていない従業員は、この欄は空欄のままとなります。なお、控除額の確認は、申告書との照合を忘れずに行いましょう。
源泉徴収税額
1年間に源泉徴収された所得税の合計額を記載します。例えば、毎月の給与から引かれた税額に加えて、賞与から引かれた分も含まれます。源泉徴収簿などで確認しながら記入します。間違いを防ぐには、税額表との突合も有効です。
控除対象配偶者の有無等
対象者に配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる配偶者がいる場合に記載します。例えば、配偶者の所得が一定額以下であれば控除対象となり、その旨を反映する必要があります。ここでは、適用要件に該当するかどうかの確認が欠かせません。
社会保険料等の金額・控除額
健康保険や厚生年金保険など、給与から差し引かれた社会保険料の合計額を記載します。例えば、企業が給与から天引きして納付した分が該当し、税額計算の際の控除対象になります。控除証明書を参考に正確な金額を入力することが大切です。
配偶者の合計所得
配偶者がいる場合、その年間の合計所得金額を記入します。例えば、パート勤務の配偶者が一定の収入を得ている場合、その金額を正しく記載することで、控除額の適用判断に使われます。所得金額の見積もりでなく、確定値を用いることが重要です。
扶養親族
扶養している家族がいる場合、その人数や氏名、生年月日などを記載します。例えば、18歳未満の子どもや、所得のない親を扶養している場合などが該当し、扶養控除の判断材料となります。対象者の生年月日は、控除対象年齢の判定に必要です。
国民年金保険料等の金額
本人が支払った国民年金保険料などの金額を記入します。例えば、個人事業主から転職してきた人が、自身で支払った分を申告している場合などがあり、一定の所得控除が適用されます。記入の際は、日本年金機構の控除証明書を参照しましょう。
住宅借入金等特別控除の金額
住宅ローン控除の適用がある場合、その年の控除額を記載します。例えば、マイホームの取得や増改築のローンが対象であれば、住宅借入金等特別控除として税額控除が受けられます。控除の適用には、確定申告済みであることが前提です。
摘要
特記事項や補足事項がある場合に記載する欄です。例えば、非課税通勤手当の金額や、退職理由などが記載されることがあり、住民税の判断に影響する可能性があります。空欄で問題ない場合もありますが、必要に応じて丁寧に記載しましょう。
支払者
給与を支払った法人または個人事業主の情報を記載します。例えば、会社名、所在地、法人番号、電話番号などが含まれます。記載漏れがあると、提出書類が受理されないこともあります。押印欄がある様式では、代表者印の押印も忘れずに行いましょう。
給与支払報告書の手続きの流れ
給与支払報告書の手続きは、以下の流れで進みます。
- step1:市区町村から総括表が送付される
- step2:年末調整を行う
- step3:総括表を作成する
- step4:市区町村に提出する
ここでは、それぞれの手順について詳しく解説していきます。
step1:市区町村から総括表が送付される
年末が近づくと、企業の所在地を管轄する市区町村から総括表が郵送されてきます。総括表は翌年1月末までに提出する給与支払報告書の取りまとめに使用する書類です。
例えば、従業員が複数の市町村に居住している場合、それぞれの市区町村から総括表が届くことになります。受け取った後は、記載内容や提出先に漏れがないか確認しておくと、後の作業がスムーズです。郵送物の開封や仕分けを怠ると、作成の準備が遅れる恐れもあるため、年末の繁忙期でも早めの確認が重要です。
step2:年末調整を行う
総括表を受け取ったら、次は従業員の1年間の給与と所得税額を確定させる年末調整の作業に入ります。例えば、保険料控除申告書や扶養控除等申告書の内容を確認し、源泉徴収額と本来の所得税額との差額を調整します。
年末調整が完了すると、源泉徴収票や給与支払報告書の作成に必要な情報が確定します。手間のかかる作業ではありますが、年末調整が正確に行われていないと、その後の報告書作成や税務処理に影響が出るため、慎重な対応が求められます。
step3:総括表を作成する
年末調整が完了したら、従業員の情報をもとに総括表を作成します。総括表は、企業がどの市区町村に何人の従業員の給与支払報告書を提出するかを一覧でまとめるもので、提出先ごとに1枚ずつ作成します。
例えば、従業員がA市とB市にそれぞれ在住していれば、A市用とB市用に2枚の総括表が必要です。記入する項目は比較的少ないですが、提出先の記載ミスや人数の誤りがあると受理されないこともあるため、正確な確認が欠かせません。
step4:市区町村に提出する
総括表と個人別明細書がそろったら、市区町村への提出に進みます。提出期限は原則として翌年の1月31日で、それまでに各市区町村へ書類を届ける必要があります。
例えば、100人以上の報告書を提出する場合は、紙ではなくeLTAXなどを使った電子申告が義務付けられることもあるため、提出方法にも注意が必要です。期限を過ぎると従業員の住民税に影響するため、事前のスケジュール管理と余裕を持った作業が求められます。
給与支払報告書の作成における注意点
給与支払報告書の作成では、以下のような点にも注意が必要です。
- マイナンバーの記載が必要になる
- 100枚以上の提出は電子申告になる
- 退職者の給与支払報告書も提出が必要になる
ここでは、それぞれの注意点について詳しく解説していきます。
マイナンバーの記載が必要になる
給与支払報告書には、従業員本人のマイナンバーを記載する必要があります。例えば、年の途中で入社した社員や短期雇用のアルバイトなども対象となるため、従業員のマイナンバーを事前に把握しておかなければなりません。
また、マイナンバーを取り扱う際には、漏えい防止のための適切な管理措置が求められます。報告書の記入ミスや情報の漏えいは、企業としての信頼にも関わるため、正確性と安全性の両方に配慮した取り扱いが重要になります。
100枚以上の提出は電子申告になる
給与支払報告書の提出枚数が100枚以上となる場合、原則として紙による提出は認められず、電子申告が義務化されます。例えば、複数の事業所を抱える企業でパートやアルバイトを含めた従業員数が多い場合、提出枚数がすぐに100枚を超えるケースもあります。
電子申告にはeLTAXなどのシステムを使用する必要があり、事前の利用者登録や環境設定が必要です。紙提出と同じ内容であっても、提出方法の違いによって準備すべき作業が異なるため、早めの対応が求められます。
退職者の給与支払報告書も提出が必要になる
その年の途中で退職した従業員についても、給与支払報告書の提出が必要です。例えば、3月に退職した社員に対して支払った給与や源泉徴収税額なども、他の従業員と同様に個人別明細書に記載しなければなりません。
年末に在籍していないからといって報告対象から外してしまうと、市区町村での住民税の課税処理に支障が生じる可能性があります。退職時に交付した源泉徴収票と照らし合わせながら、正確に記載と提出をすることが大切です。
なお、日々の給与計算業務の効率化には給与計算代行サービスがおすすめです。給与計算代行サービスについては、こちらの記事詳しく解説しています。
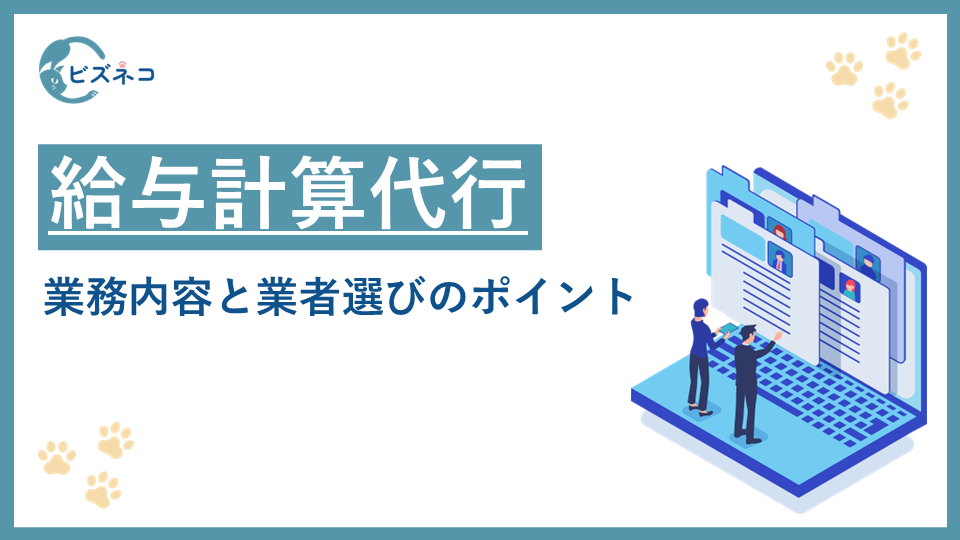
加えて、給与の支払いも代行業者に委託することができます。給与支払い代行サービスについてはこちらの記事をご覧ください。
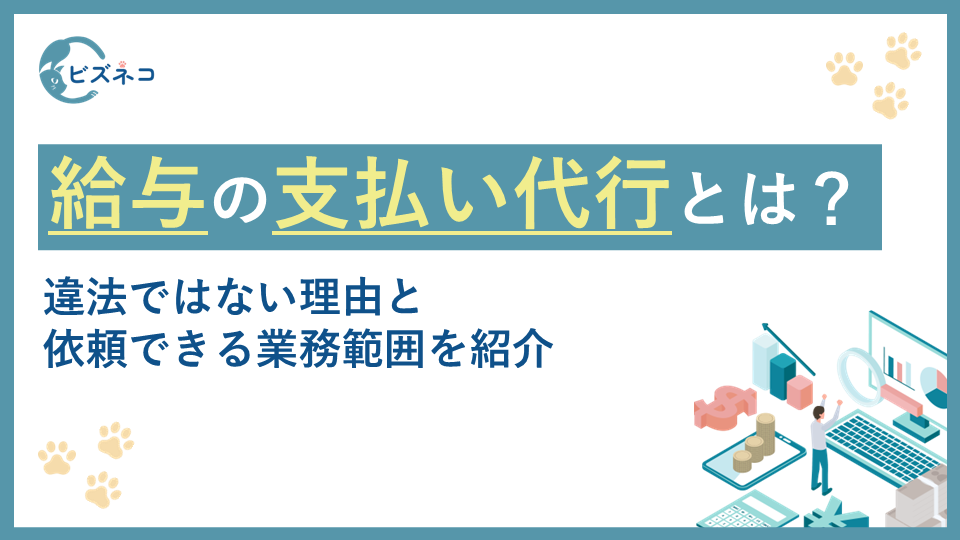
まとめ
給与支払報告書は、従業員の1年間の給与や源泉徴収額などの情報を市区町村に報告するための書類です。例えば、1月に市区町村から送られてくる総括表に基づいて、企業は従業員一人ひとりの情報を記載した個人別明細書を添えて提出します。
給与支払報告書の作成では、マイナンバーの記載が必要になり、退職者の給与支払報告書も提出が必要になる点には注意が必要です。また、100枚以上の提出は電子申告になることも意識しておきましょう。従業員の給与計算は事前に行っておくことが大切ですが、経理担当者の方のリソース不足という課題もあるでしょう。そのような際には、経理代行会社に相談することもひとつの手です。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
給与支払報告書に関するよくあるご質問
給与支払報告書についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、給与支払報告書に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
給与支払報告書とは何ですか?
給与支払報告書とは、会社が従業員に支払った給与や源泉徴収税額、所得控除の内容などを、従業員の居住地にある市区町村へ報告するための書類です。例えば、住民税の計算の基礎となる情報を提供する目的があり、原則として毎年1月末までに提出が求められます。市区町村はこの情報をもとに、翌年度の住民税を決定します。
給与支払報告書に提出義務はありますか?
給与を支払った事業者には、原則として給与支払報告書の提出義務があります。正社員だけでなく、パートやアルバイトに対して給与を支払った場合も対象になります。提出先は従業員の居住地の市区町村であり、提出期限は毎年1月31日です。事業者側の判断で省略することはできないため注意しましょう。
給与支払報告書と年末調整の違いは何ですか?
給与支払報告書と年末調整は、それぞれ目的が異なる手続きです。年末調整は、所得税の過不足を精算するために企業が年末に行う社内処理で、保険料控除や扶養控除の情報をもとに所得税額を確定します。一方で、給与支払報告書は、その年の給与や源泉徴収税額などを市区町村に報告するための書類で住民税の計算に使われます。




