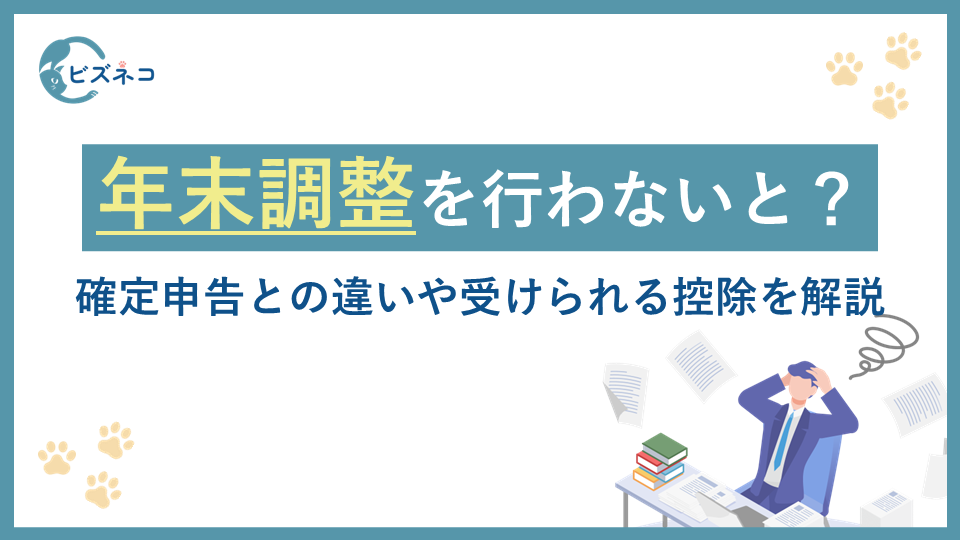
年末が近づくと、企業の経理担当者や従業員にとって欠かせない業務のひとつが「年末調整」です。毎月の給与から天引きされた所得税を年末に正しく精算する手続きであり、会社が従業員に代わって税金を調整する重要な役割を果たします。一方で「確定申告」との違いが曖昧なまま、なんとなく手続きを進めている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、年末調整と確定申告の違いや、年末調整で受けられる控除と受けられない控除、企業にとってのメリット・デメリットなどをまとめて紹介します。年末調整の手順や効率化のポイントまでも解説していますので、経理担当者の方だけでなく、従業員の方もぜひ参考にしてください。
目次
年末調整とは?
年末調整とは、毎月の給与からあらかじめ差し引かれている所得税について、年末に1年間の所得や控除をもとに正しく再計算し、過不足を精算する作業のことを指します。会社員やパート・アルバイトとして働く人にとって、年末調整は毎年行われるおなじみの手続きであるでしょう。
例えば、年の途中で扶養家族が増えた場合や、生命保険料を支払っている場合など、年末のタイミングで調整することで納税額が変わることもあります。会社が従業員に代わって実施することで、本人が確定申告を行う必要がなくなるのが特徴です。
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告の違いは、税金の計算と申告を「誰がどの範囲で行うか」という点にあります。年末調整は、企業が従業員の年間所得税を自動的に再計算し、税額を精算する制度です。
一方、確定申告は、納税者本人が自らの所得と控除をまとめて申告し、税金を確定させる手続きです。例えば、複数の収入源がある人や医療費が高額になった人、住宅ローン控除の初年度などは、年末調整だけでは税額の調整ができず、確定申告が必要となります。どちらも所得税を正しく計算するための制度ですが、対象者や手続き内容に明確な違いがあります。
年末調整で受けられる控除一覧
年末調整では、一定の条件を満たせば各種控除を受けることができ、結果として所得税の軽減や還付が行われます。受けられる控除には、以下の13種類があります。
| 控除の種類 | 控除の概要 |
|---|---|
| 基礎控除 | 所得が2,500万円以下のすべての納税者に適用され、所得に応じて16万円~48万円が差し引かれる仕組み |
| 配偶者控除 | 所得税法上の配偶者がいる場合に適用される控除で、配偶者の年間収入が一定基準以下であることが条件 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の収入が一定額を超える場合でも段階的に控除が認められる制度 |
| 扶養控除 | 生計を一にする16歳以上の親族や子どもを扶養している場合に受けられる控除 |
| 寡婦控除 | 配偶者と離婚または死別し、一定の要件を満たす女性に対して適用される控除制度 |
| ひとり親控除 | 子を扶養するひとり親に対して適用される控除で、男女を問わず対象になる仕組み |
| 社会保険料控除 | 健康保険、厚生年金、介護保険など年間を通じて支払った社会保険料の全額が対象 |
| 生命保険料控除 | 一般の生命保険・介護医療保険・個人年金保険の各区分に応じて保険料が控除対象となる制度 |
| 地震保険料控除 | 住宅や家財に対する地震保険料を支払った場合に適用される控除 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済やiDeCoなどの掛金を支払った際に対象となる控除 |
| 勤労学生控除 | 学業と労働を両立している学生で、一定の所得要件を満たす場合に適用される控除 |
| 障害者控除 | 本人または同一生計の配偶者・親族が障害者である場合に認められる控除 |
| 住宅ローン控除(2年目以降) | 一定条件を満たした住宅ローンを利用した場合、2年目以降は年末調整で控除が可能となる制度 |
これらの控除は企業が従業員から提出された情報をもとに計算し、年末の給与に反映されます。正しく控除を受けるためには、必要な書類の準備と提出期限を守ることが重要です。
年末調整で受けられない控除一覧(確定申告が必要)
年末調整で対応できない控除もあり、それらは確定申告によって申請する必要があります。対象とならない控除は主に以下の4種類です。
| 控除の種類 | 控除の概要 |
|---|---|
| 寄附金控除 | ふるさと納税を含む国や地方自治体・認定NPO法人などへの寄附が対象となる控除(※ワンストップ特例を利用しない場合) |
| 医療費控除 | 自身や扶養親族のために1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合に認められる控除制度 |
| 雑損控除 | 火災や地震などの災害、または盗難・横領といった突発的損失に対して適用される所得控除 |
| 住宅ローン控除(初年度) | 自宅の購入や新築などで住宅ローンを利用した場合、初回に限り確定申告が必要となる制度 |
また、副業などで給与以外の所得がある場合も同様に確定申告が必要です。こうした控除の存在を知らないまま年末調整だけで済ませてしまうと、本来受けられる税の還付を逃す可能性があります。必要な控除が年末調整の対象かどうかを事前に確認しておきましょう。
年末調整の対象となる人
年末調整の対象となるのは、原則として企業や団体などに雇用されている給与所得者であり、かつ年末時点で在職している人です。対象となるかどうかは、勤務形態や支払い回数、雇用期間などによっても左右されます。具体的には、以下の条件に当てはまる人が対象です。
- 企業や団体に雇用されており、年末時点で在籍している人
- 正社員・契約社員・パート・アルバイトなど継続的に雇用されている人
- 年の途中で入社し、年末まで在職している人
- 給与が主たる収入であり1か所からのみ受け取っている人
- 2か所以上から給与を受けていても、主たる勤務先が年末調整を行う場合の本人
例えば、正社員や契約社員はもちろん、一定の条件を満たすアルバイトやパートも対象に含まれることがあります。また、年の途中で入社しても年末に在籍していれば調整の対象となります。一方で、複数の会社から給与を受けている場合には主たる給与を支払っている会社でのみ年末調整が行われます。対象者の要件を理解しておくことは、手続きの漏れを防ぐためにも重要です。
年末調整の対象とならない人
年末調整の対象とならないのは、給与所得者の中でも以下のような特定の条件に該当する人です。
- 年の途中で退職し、年末時点で再就職していない人
- 2か所以上の勤務先から給与を受け取っており、副業先など主たる勤務先でない会社からの収入がある人
- 年間の給与収入が2,000万円を超える高額所得者
- フリーランス、個人事業主、士業、外注契約など、雇用関係にない人
- 非居住者として扱われる海外勤務者(日本国内に住所がない場合)
- 日雇い労働者など雇用が継続的でない場合
例えば、年の途中で退職し、その後再就職していない人や、年内に2つ以上の会社から給与を受けている人のうち副業側の勤務先では年末調整が行われません。また、報酬や謝礼などが支払われるフリーランス、士業、外注スタッフといった非雇用契約の人も対象外となります。
さらに、海外勤務で非居住者となっている場合や、給与が年間2,000万円を超える高額所得者も年末調整の対象から除かれます。対象外となる理由を理解しておくことで、確定申告の対象者が誰であるかを判断しやすくなるでしょう。
年末調整を行わないとどうなるのか?
企業にとって、年末調整は所得税法で定められた給与支払者としての義務になります。会社側が故意に年末調整をしない場合、法律違反とみなされてしまうため注意しましょう。
年末調整を行わないと「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」や、悪質な場合では「10年以下の懲役または200万円以下の罰金」を科せられることが所得税法で定められています。
なお、そもそも年末調整を行わないまま年を越してしまうと、本来受けられるはずの控除が反映されず、税金を多く支払ったままになるおそれがあります。手続きを怠ると、過不足が反映されず、本来の納税義務や還付の機会を逃すことになりかねないため、正しく実施することが大切です。
年末調整を企業が行うメリット
年末調整を企業が行うメリットとして、以下のような点があげられます。
- 従業員の税務負担を軽減できる
- 税務処理の一元管理ができる
- 社内の給与情報を分析しやすくなる
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
従業員の税務負担を軽減できる
企業が年末調整を実施することで、従業員の税務手続きを大幅に効率化できるメリットがあります。給与所得者は通常、所得税の精算のために確定申告を行う必要がありますが、年末調整によって企業が代行することで手続き負担が軽減されます。
例えば、保険料控除や扶養控除などの申告を企業が一括して処理し、過不足のある税金を調整することで、従業員は確定申告をしなくても正確な税額が反映されます。これにより従業員の負担が減るだけでなく、税務ミスの防止にもつながるため、企業と従業員双方にとってメリットが高い仕組みといえます。
なお、経理や労務の業務効率化については、こちらの記事も参考にしてください。
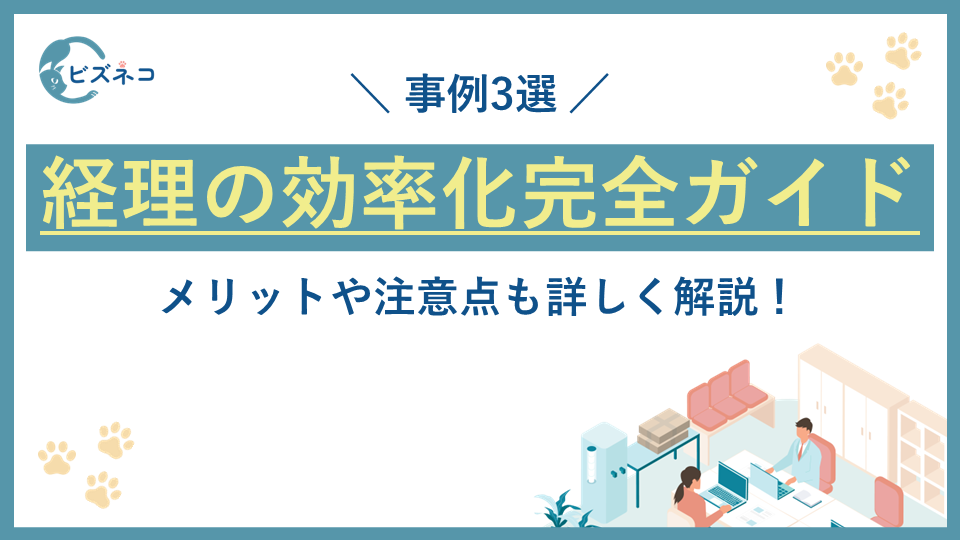
税務処理の一元管理ができる
年末調整を企業が実施することで、税務に関する処理を社内で一元的に管理できます。給与や控除に関する情報が集約されるため、所得税の計算や申告に必要なデータの整合性が保たれやすくなります。
例えば、源泉徴収票の作成や法定調書の提出もまとめて行うことで、処理の漏れや誤りを防止できます。また、税務署からの問い合わせ対応も一元化できるため、経理部門の業務効率が向上し、リスク管理もしやすくなります。こうしたメリットは、企業のコンプライアンス強化にも役立つでしょう。
社内の給与情報を分析しやすくなる
年末調整を通じて集まる給与データや控除情報は、社内での分析に活用しやすい特徴があります。企業はこれらのデータを基に、給与構成や福利厚生の利用状況、税負担の傾向などを把握できます。
例えば、扶養控除の適用状況や保険料の支払い状況から、従業員の生活状況の変化を推察することも可能です。こうした分析は人事戦略や経営判断の材料となり、従業員満足度の向上やコスト管理の精度向上にもつながります。年末調整は単なる税務手続きにとどまらず、企業経営に役立つ情報源としても重要です。
年末調整を企業が行うデメリット
年末調整を企業が行うデメリットとして、以下のような点が課題になります。
- 毎年の経理担当者の負担が大きい
- 制度変更への対応が求められる
- 従業員からの質問や対応が増える
ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。
毎年の経理担当者の負担が大きい
年末調整を企業が実施すると、経理担当者の業務負担が毎年増す傾向にあります。手続きは複雑で、控除の申告書類の回収や計算、源泉徴収票の作成など、幅広い作業を期限内に正確に終わらせなければなりません。
例えば、従業員の数が多い企業では、一人ひとりの控除内容が異なるため、その確認と計算に膨大な時間がかかります。また、計算ミスが税務調査につながるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。こうした負担は毎年繰り返されるため、経理担当者の業務量が圧迫されやすいことがデメリットのひとつといえるでしょう。
制度変更への対応が求められる
年末調整に関わる税制や控除の制度は頻繁に変更されるため、企業は最新の情報を常に把握し対応しなければなりません。例えば、控除対象の範囲が変わったり、控除額の計算方法が改訂されたりすると、これまでの運用方法を見直す必要があります。
こうした変更に遅れると、誤った処理をしてしまい税務上の問題に発展することもあります。そのため、経理担当者は税制改正の動向に敏感である必要があり、制度改正の都度マニュアルの更新や社員への説明も求められるため、業務負担が増加する要因となってしまいます。
従業員からの質問や対応が増える
年末調整を企業が実施すると、従業員からの質問や対応要請が増える傾向があります。例えば、控除対象となる項目や必要書類についての疑問、申告内容の修正依頼など、多種多様なお問い合わせが経理担当者に寄せられます。
こうした対応は電話やメール、直接面談などさまざまな形で発生し、業務時間を圧迫します。また、従業員の知識レベルや理解度が異なるため、丁寧かつ的確な説明が求められ、対応に時間がかかる場合も少なくありません。このように従業員対応が増えることも年末調整業務のデメリットとしてあげられます。
年末調整の流れと手順
年末調整の流れとして、主に以下のような手順で進みます。
- step1:従業員から必要書類を回収する
- step2:源泉徴収額と年税額を計算する
- step3:法定調書や源泉徴収票を作成して提出する
ここでは、それぞれのステップについて詳しく解説します。
step1:従業員から必要書類を回収する
年末調整の最初のステップは、従業員から控除申告書や保険料控除証明書など必要な書類を回収することです。これらの書類は所得税の計算に欠かせない情報を含んでいます。
例えば、生命保険料控除や扶養控除の申告には証明書類が必要であり、提出漏れがあると正しい計算ができません。回収時期は通常、年末調整の開始前に設定され、従業員に提出を促すことでスムーズな業務進行が可能となります。また、書類の内容確認もこの段階で行うため、正確な回収が後の業務の効率化にもつながります。
step2:源泉徴収額と年税額を計算する
書類回収が終わった後は、給与から源泉徴収されている税額と、実際に支払うべき年間の所得税額を計算します。ここでは、扶養控除や社会保険料控除などの各種控除を反映し、過不足を調整します。
例えば、年間の保険料支払額や扶養家族の人数の変化を考慮し、正確な税額算出が求められます。計算は正確さが求められ、誤りがあると従業員への還付金額や追加徴収額に影響するため、慎重に行う必要があります。また、近年は計算がスムーズになる年末調整ソフトの活用も増えており、効率化とミス防止の両面で効果を発揮しています。こうしたツールを導入することで、作業負担の軽減も期待できます。
step3:法定調書や源泉徴収票を作成して提出する
最後のステップは、法定調書や源泉徴収票を作成し、税務署や従業員に提出することです。法定調書は企業が税務署へ提出する書類で、従業員の年間所得や源泉徴収額を記載します。
例えば、源泉徴収票は従業員が確定申告や住宅ローン控除の申請で必要となる重要な書類です。これらの書類は期限内に正確に作成し提出することが法令で義務づけられており、遅延や不備はペナルティの対象になるため注意が必要です。
さらに、従業員への配布も重要で、受け取った従業員が内容を確認できるようにすることも義務付けられています。企業は提出期限を守り、正確な書類作成を徹底することで、税務リスクの回避につなげる必要があります。
年末調整業務を効率化するポイント
年末調整業務を効率化するポイントとして、以下のような点があげられます。
- 年末調整システムや給与計算システムを導入する
- 業務フローを見直して役割分担をする
- 経理代行会社に相談する
ここでは、それぞれの業務効率化について詳しく解説します。
年末調整システムや給与計算システムを導入する
年末調整業務を効率化するために、専用の年末調整システムや給与計算システムを導入する企業が増えています。これらのシステムは、控除申告書の管理や計算を自動化し、手作業のミスを減らすことに役立ちます。
例えば、従業員がWEB上で申告書を提出できる仕組みを導入すれば、紙ベースの管理が不要となり、収集や確認の時間を大幅に削減できます。また、税制改正に対応したアップデートも自動で行われるため、最新の法令に基づいた処理が可能です。結果として、経理担当者の負担軽減や業務の正確性向上につながるでしょう。
なお、給与計算のやり方についてはこちらの記事もご覧ください。
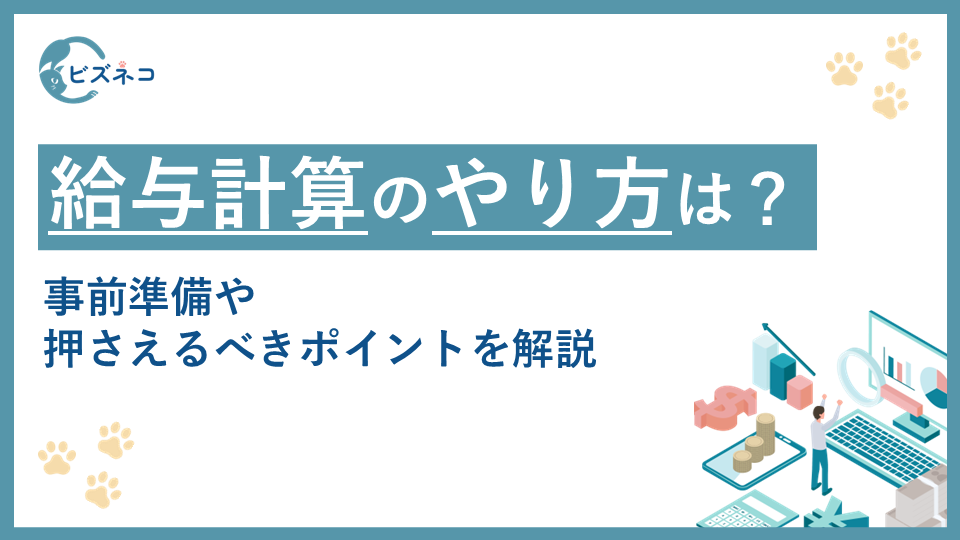
業務フローを見直して役割分担をする
年末調整の効率化には、業務フローの見直しと適切な役割分担が欠かせません。作業全体を細分化し、誰がどの工程を担当するのか明確にすることで、業務の抜け漏れや二重作業を防止できます。
例えば、書類の回収は総務部が担当し、計算業務は経理部が行うといった分担を決めることで、担当者ごとの負担が偏らずに済みます。また、進捗状況の共有やチェック体制の強化も重要で、定期的なミーティングで問題点を洗い出し改善を図ることが求められます。こうした取り組みは、業務効率だけでなく社員の負担軽減にもつながります。
なお、業務フローの改善方法についてはこちらの記事もご覧ください。

経理代行会社に相談する
年末調整業務の効率化を図る手段として、経理代行会社に相談する方法もあります。専門業者に業務の一部または全部を委託することで、社内リソースの不足を補い、作業の正確性とスピーディさを高められます。
例えば、控除申告書のチェックや税額計算などを代行してもらうことで、経理担当者はより戦略的な業務に集中できるようになります。また、最新の税制対応やシステム運用も代行会社に任せられるため、制度変更の影響を受けにくいというメリットもあります。最近では、年末調整をはじめとした経理業務のアウトソーシングは中小企業を中心に注目を集めています。
年末調整代行サービスについてはこちらの記事をご覧ください。
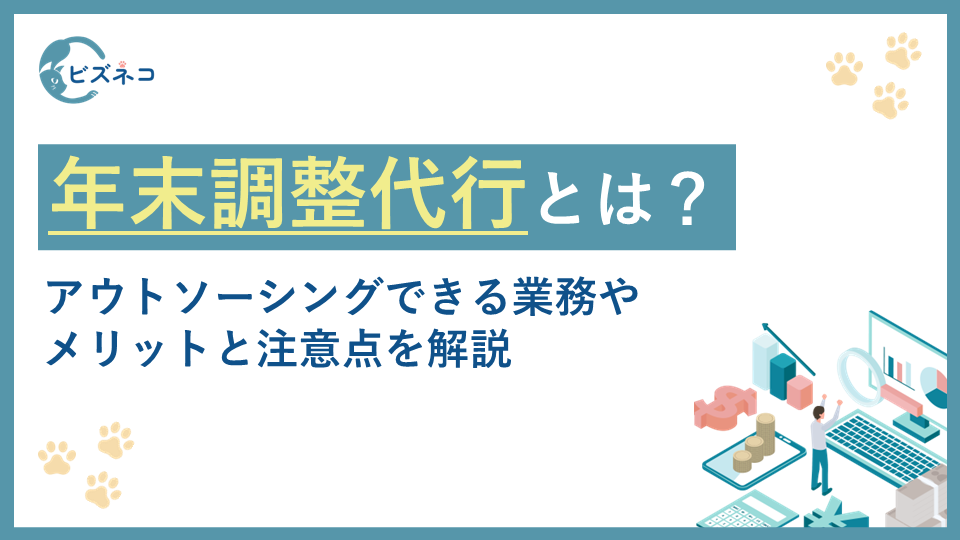
なお、日々の給与計算を代行するサービスについてはこちらの記事をご覧ください。
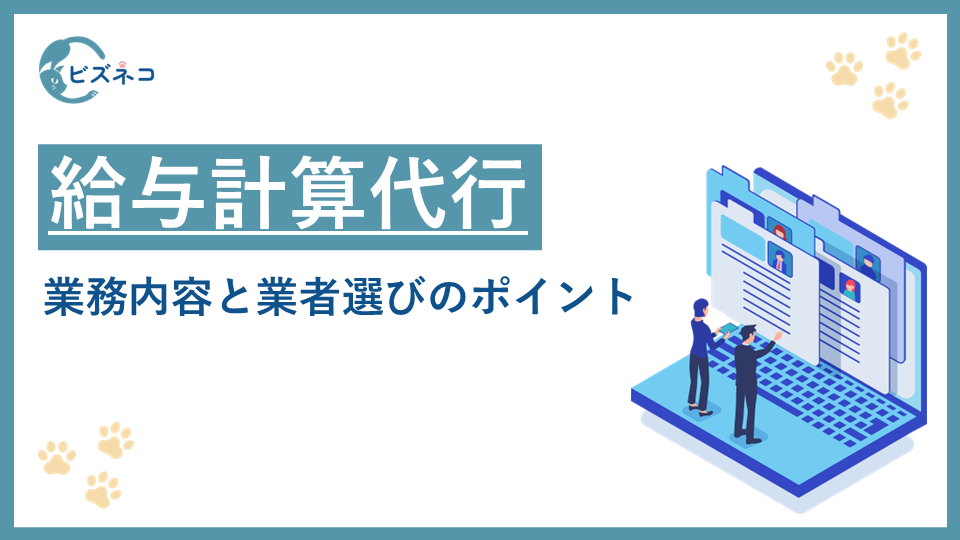
加えて、給与の支払いも代行業者に依頼することができます。詳細はこちらの記事で触れています。
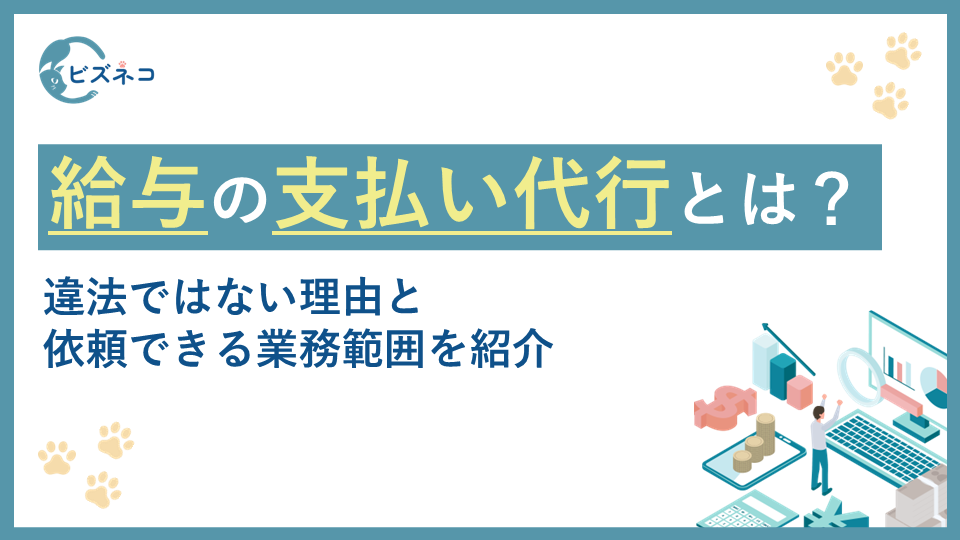
まとめ
年末調整とは、毎月の給与からあらかじめ差し引かれている所得税について、年末に1年間の所得や控除をもとに正しく再計算し、過不足を精算する作業のことを指します。年末調整と確定申告の違いは、税金の計算と申告を「誰がどの範囲で行うか」という点にあります。
年末調整は、企業が従業員の年間所得税を自動的に再計算し、税額を精算する制度です。一方、確定申告は、納税者本人が自らの所得と控除をまとめて申告し、税金を確定させる手続きです。
年末調整は企業の義務ですが、経理担当者の方の負担も大きくなってしまう点がデメリットです。そのため、経理代行会社に依頼することもひとつの手です。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
年末調整に関するよくあるご質問
年末調整についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、年末調整に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
年末調整とは何ですか?
年末調整とは、毎月の給与から差し引かれている所得税を年末に1年間の所得や控除に基づいて再計算し、過不足を精算する手続きです。会社が従業員に代わって行い、扶養家族の増加や生命保険料の支払いといった状況変化を反映して税額を調整します。年末調整を会社が行うことで従業員は基本的に確定申告を行わずに済みます。
年末調整と確定申告は同じですか?
年末調整と確定申告は異なる制度です。年末調整は企業が従業員の年間所得税を自動的に計算し精算する手続きで、主に給与所得者が対象となります。一方、確定申告は納税者本人が自ら所得や控除をまとめて申告し、税額を確定させる手続きです。ただし、副業収入がある人や医療費控除を受けたい人は確定申告が必要になります。
年末調整をやらなくていい人はどんな人ですか?
年末調整の対象とならないのは、年の途中で退職し年末に再就職していない人や、複数の勤務先から給与を得ている場合の副業先、給与収入が2000万円超の高額所得者です。また、フリーランスや個人事業主、非居住者も対象外です。複数の会社から給与を受ける場合は主たる勤務先のみ年末調整を行います。




