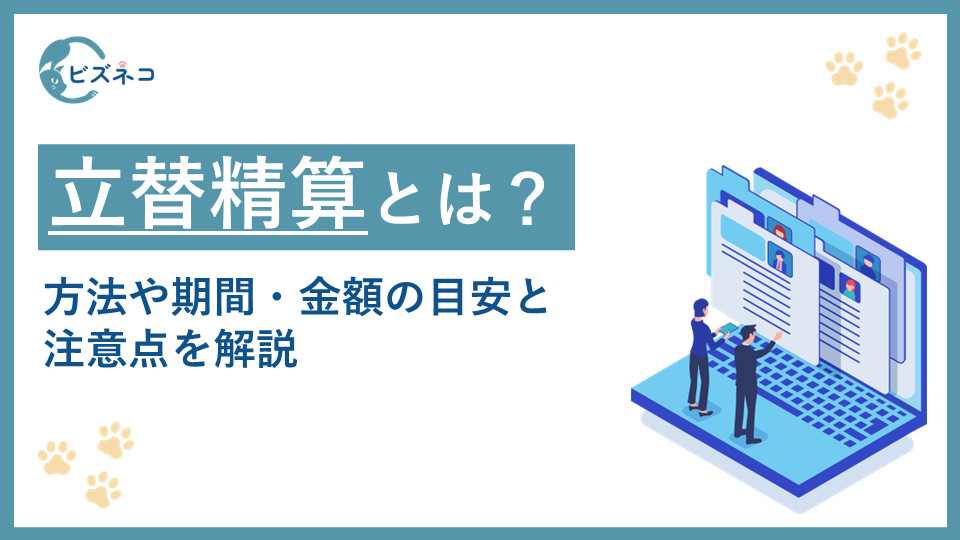
立替精算は、従業員が業務上必要な費用を一時的に自己負担し、後日会社から精算してもらう仕組みを指します。例えば出張時の交通費や会議で使用した消耗品費など、業務に関連する支出が対象です。立替精算は仮払いとは異なり、事前に会社から資金を受け取らずに支払う点が特徴です。
精算の期間や金額に明確なルールがないと従業員の負担が増したり、処理が遅れて経理業務が滞るリスクもあります。本記事では、立替精算のルール設定や仕組みづくりにおける注意点を解説します。
目次
立替精算とは?
立替精算とは、従業員が業務で必要な費用を一時的に個人の資金で支払った後、会社に請求して精算する仕組みです。例えば、取引先訪問のための電車代や宿泊費、急遽購入した消耗品などが対象となります。
会社は領収書や申請書類をもとに内容を確認し、承認後に従業員へ払い戻します。精算ルールを決めずに運用すると、申請漏れや支払遅延が起こりやすく、従業員に不公平感が生じる可能性もあります。そのため、明確な申請期限や提出書類の形式をあらかじめ定め、円滑に精算できる体制を整えておくことが重要です。
立替払い(立替経費)と仮払いの違い
立替払いと仮払いはどちらも業務に必要な費用を処理する方法ですが、支払うタイミングが異なります。立替払いは、例えば従業員が自分の財布から交通費や会議費を先に支払い、後日会社に請求して精算します。
一方で仮払いは、出張旅費など事前に支出が想定される場合に会社が先に現金を渡し、後で使った分を精算します。立替払いは従業員の負担が先行するため、金額が大きいと負担感が強くなる傾向があります。適切な使い分けを行うことで、従業員のキャッシュフローへの影響を減らし、経理処理のスムーズさも確保できます。
立替精算の期間と金額の目安
立替精算は、期間や金額の基準をあらかじめ決めておくことでスムーズに運用できます。例えば、精算の申請が半年も遅れると経費計上のタイミングがずれて決算に影響する可能性がありますし、金額が大きすぎると従業員の負担が増します。実務では1か月単位で処理するケースが多く、金額も日常的に支払える範囲に抑えるのが望ましいといえるでしょう。
立替精算の期間
立替精算の期間は法的な期限が決まっているわけではありませんが、経理処理の観点からはおおむね1か月ごとに申請するのが基本です。例えば、毎月末に領収書をまとめて提出し、翌月の給与と一緒に精算するといった運用が一般的です。
期間を決めずに運用すると、半年分や一年分の領収書がたまってしまい、経費の計上漏れや決算への影響が発生する恐れがあります。従業員側も申請を忘れたり、古い領収書を紛失したりするリスクが高まります。そのため、月次での精算ルールを設けることで、会計処理の正確性と従業員の負担軽減の両方を実現できるでしょう。
立替精算の金額
立替精算の金額にも法律上の上限や下限はありませんが、従業員のキャッシュフローに影響しない範囲で設定することが望ましいといえます。例えば、1回あたり数千円から数万円程度であれば個人の財布で対応できることが多いですが、宿泊を伴う出張や高額な備品購入では立替負担が大きくなります。
こうした場合は仮払い制度を併用するなど、従業員に過度な負担をかけない工夫が必要です。会社としても一定金額を超える立替が続くと精算処理の負担が増えるため、事前承認制や上限額の設定を行うと管理がしやすくなります。
経費の立替を従業員に命じるのは違法なのか?
経費の立替を従業員に命じることは法律で禁止されているわけではなく、違法にはあたりません。例えば、営業担当者が取引先訪問の交通費を一時的に自己負担し、後日会社が精算するケースは日常的に行われています。
ただし、過度な立替が続くと従業員の生活費に影響を及ぼしたり、不満が高まる要因となる可能性があります。特に高額な出張費や備品購入を立て続けに負担させると、個人のキャッシュフローが圧迫されやすくなります。そのため、会社は精算のスピードを早めたり、必要に応じて仮払い制度を活用したりするなど、従業員が安心して業務に集中できる環境を整えることが求められます。
立替精算の発生するケースと勘定科目
立替精算は業務上のさまざまな場面で発生し、勘定科目ごとに処理方法が異なります。立替精算が発生するケースと勘定科目を以下の表にまとめました。
| 勘定科目 | 概要 | 立替精算が発生するケース |
|---|---|---|
| 交通費 | 業務での移動にかかる費用 | 電車・バス代、タクシー代、高速料金、駐車場代を自費で払った場合 |
| 出張費 | 出張に伴う費用全般 | 宿泊費、現地移動費、出張手当、食事代などを従業員が立て替えした場合 |
| 消耗品費 | 短期で使い切る備品の購入費 | 文房具、コピー用紙、PC周辺機器などを購入した場合 |
| 交際費 | 取引先との関係維持費用 | 会食代、贈答品代、接待交通費を立て替えした場合 |
| 会議費 | 会議や打ち合わせにかかる費用 | 会議室利用料、弁当代、飲料代を従業員が支払った場合 |
| 通信費 | 通信や郵送にかかる費用 | 宅急便、切手代、Wi-Fiレンタル料などを立て替えした場合 |
| 福利厚生費 | 従業員の福利厚生に関する費用 | 懇親会費、社員イベント費用、健康診断代を立て替えした場合 |
例えば交通費や出張費のような移動関連費用、会議費や交際費といった社外対応の支出、さらには消耗品や通信費など日常的に発生する経費も対象となります。どの科目で計上すべきかを明確にし、適切に精算することで経理処理の正確性が保たれます。
交通費
交通費は立替精算の中でも頻度の高い項目です。例えば電車やバス、タクシーなどの運賃、業務で利用する高速道路料金や駐車場代などが該当します。
従業員が自費で切符を購入したり、ICカードを利用して移動した後に領収書や利用明細を添えて申請するのが一般的です。精算時には区間や利用目的を明確に記載しないと経費計上が認められない場合もあるため注意が必要です。交通費精算は件数が多くなりやすいため、定期的にまとめて申請するルールを設けると経理の負担軽減につながります。
出張費
出張費は宿泊費や現地での移動費、出張手当など複数の支出が含まれる立替精算です。例えば遠方の取引先訪問や展示会参加では、宿泊先の費用や出張先での食事代も立替対象となります。金額が高額になるケースも多く、従業員への負担が大きくなりやすいため、仮払いを活用する企業も少なくありません。
精算時には出張命令書や宿泊証明書、領収書を添付して内容を確認できるようにする必要があります。社内規程に基づいた日当や交通手段の上限設定を明確にし、精算処理がスムーズに進む仕組みを整えることが重要です。
消耗品費
消耗品費は文房具やコピー用紙、PC周辺機器など、短期間で使い切る物品を購入した際の経費です。例えば急ぎで必要になった備品を従業員が近隣の店舗で購入し、後日精算する場面がよくあります。
少額の支出であっても領収書が必要であり、品名や数量が明記されていないと経理処理ができないことがあります。頻繁に発生する場合は購買申請や社内在庫の活用を検討するなど、立替が過度に増えない仕組みづくりもおすすめです。定期的にまとめて精算するルールを設けることで経理の作業効率も高まります。
交際費
交際費は取引先との関係構築や維持のために支出される費用で、立替精算の対象になることが多い項目です。例えば取引先との会食代や贈答品代、接待の際の交通費などが含まれます。
税制上は交際費に上限が設定されているため、用途や参加者、金額を明確に記録する必要があります。領収書には支払先や日付が記載されているかを確認し、交際目的を申請書に記載しておくと経理の確認作業がスムーズになります。無駄な支出を防ぐため、社内規程に沿った承認フローを徹底することが重要です。
会議費
会議費は社内外の会議や打ち合わせに必要な費用で、軽食や飲料、会議室レンタル代などが含まれます。例えば社外の会議室を利用した場合の利用料や、社内会議で用意したコーヒーやお弁当の代金を従業員が立替精算することがあります。
交際費と混同されやすいですが、会議費は参加者や議題が業務に直結していることが条件です。申請時には会議の目的や参加人数を明記し、経費区分を正しく判断できるようにする必要があります。適切な仕訳を行うことで、税務上のリスクを避けられます。
通信費
通信費は業務で利用する電話代やインターネット料金、郵便・宅配便の費用などが対象です。例えば急ぎで書類を送るために宅急便を利用したり、出張先でWi-Fiをレンタルした場合も立替精算の対象になります。
精算時には領収書や利用明細を添付し、業務利用であることを明確にする必要があります。私的利用と混同しないように、使用目的や送付先を記載しておくと経理処理がスムーズです。頻度が高い場合は法人契約や社内でまとめて精算する仕組みを整えると負担が軽減されます。
福利厚生費
福利厚生費は従業員の働きやすい環境づくりのために支出される費用で、立替精算が発生することもあります。例えば懇親会の費用や社員イベント、健康診断時の一部費用を立替で支払うケースです。
福利厚生費として計上するには、支出が全従業員または一定の範囲の従業員に公平に提供されていることが必要です。精算時には領収書に加え、参加者リストや実施内容を記録しておくと確認がスムーズになります。ただし、経費区分を誤ると課税対象となる可能性があるため、社内規程に沿って正しく処理することが大切です。
なお、経理でよく用いれられる勘定科目については、以下の記事でまとめて紹介しています。
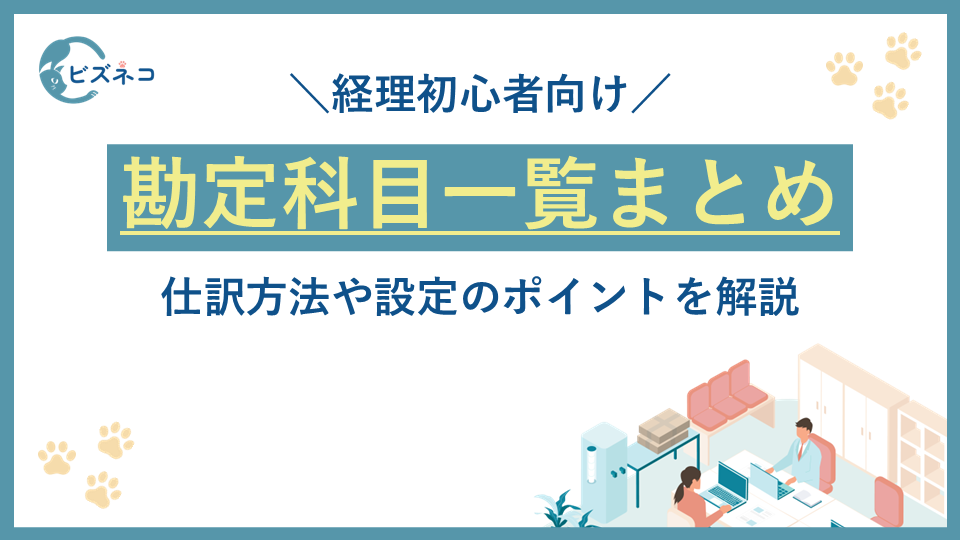
立替精算の方法と流れ
立替精算の方法は以下の流れで進みます。
- step1:【従業員】領収書を受け取る
- step2:【従業員】稟議書を作成する
- step3:【上長】稟議を承認する
- step4:【経理】内容を確認して仕訳をする
- step5:【経理】従業員に支払う
ここでは、それぞれの手順について具体的に解説します。
step1:【従業員】領収書を受け取る
立替精算は、支払い時に領収書を受け取ることから始まります。例えばタクシー代や会議用の弁当代など、業務上必要な支払いを行った際に必ず領収書を受領しておく必要があります。
宛名や日付、金額が明確に記載されていないと精算時に差し戻しになることもあるため、受け取ったら内容を確認することが大切です。電子領収書の場合はメール保存やスクリーンショットを残しておくと安全です。領収書を紛失すると経理上認められない場合もあるため、支払い直後にまとめて保管する習慣をつけておくと後の処理がスムーズになります。
step2:【従業員】稟議書を作成する
領収書を確保したら、次に稟議書を作成します。例えば出張費なら出張先や日程、目的を明記し、交通費・宿泊費の内訳を記載します。稟議書には立替の内容や金額、支払日などの詳細を記載する必要があり、不備があると承認が遅れてしまいます。
会社によっては専用の精算システムを用意している場合もあり、その場合はオンラインで申請することになります。作成時には領収書と金額が一致しているかを確認し、必要な添付書類がそろっているかをチェックすることで、後続の承認や経理処理がスムーズに進みます。
step3:【上長】稟議を承認する
従業員が作成した稟議書は、上長の承認を得る必要があります。例えば出張や交際費の精算では、社内規程に沿った内容かどうかを上長が確認します。金額が妥当か、業務に必要な支出かをチェックし、承認または差し戻しを行います。
差し戻しが発生すると精算が遅れるため、従業員は事前に規程を確認し、記載漏れがない状態で提出することが望ましいです。上長が迅速に承認することで、経理への回覧がスムーズになり、従業員への支払いも早く行えます。承認フローを明確に定めておくと、複数の承認者が必要な場合でも処理が滞りにくくなります。
ただし、立替精算は、購入前に上長の稟議や承諾が必要な場合もあるため、社内のルールを確認しておきましょう。
step4:【経理】内容を確認して仕訳をする
承認済みの稟議書は経理担当者が確認し、仕訳を行います。例えば電車代なら「交通費」、会議用のお弁当代なら「会議費」といった勘定科目を適切に選びます。金額や日付、領収書との一致をチェックし、仕訳帳に記入するか会計システムに入力します。
誤った科目で計上すると決算や税務申告に影響が出る可能性があるため、慎重な確認が必要です。複数の領収書をまとめて精算する場合は、合計金額と内訳が一致しているかも確認します。内容が整えば支払処理に進み、従業員への立替金返金準備が整います。
step5:【経理】従業員に支払う
最後の段階は、従業員への立替金の支払いです。例えば給与と同じタイミングで振り込む会社もあれば、別日に精算分だけを支払う会社もあります。支払方法は現金ではなく銀行振込が主流で、振込先の口座情報が最新かどうかも合わせて確認します。
支払いが遅れると従業員の負担が続くため、経理部門は締め日と支払日を明確にし、定期的に処理することが重要です。精算が完了したらシステムや台帳に記録を残し、後からでも内容を確認できるようにしておくと監査対応にも役立ちます。
立替精算の注意点
立替精算の対応では以下のような点に注意しましょう。
- 従業員の負担が大きくなりやすい
- 立替期限を設定しないと処理が滞る
- ミスや紛失などが起こりやすい
ここでは、それぞれの注意点について具体的に解説します。ぜひ参考にしてください。
従業員の負担が大きくなりやすい
立替精算では従業員が一時的に自己資金を使うため、心理的にも金銭的にも負担になりやすい点に注意が必要です。例えば高額な出張費や備品購入を立て替えた場合、次の給与日まで資金繰りが苦しくなることもあります。
立替金額が増えるほど従業員の不安や不満も大きくなる傾向があり、精算の遅れが退職理由になるケースもあります。そのため、経理部門は立替を前提としない運用や早めの精算対応を検討し、従業員の負担を軽減する仕組みづくりが求められます。
立替期限を設定しないと処理が滞る
立替精算は期限を明確にしておかないと、処理が後回しになりがちで経費計上が遅れる原因になります。例えば出張から帰った後に精算書を提出し忘れると、翌月の決算に間に合わないこともあります。
期限が曖昧だと経理側も未処理の立替を把握しづらく、損益計算書の正確性に影響する可能性があります。定期的な精算日を設定したり、経費精算システムでリマインド通知を活用することで、処理の遅れや漏れを防ぎ、スムーズな経理業務を維持できます。
ミスや紛失などが起こりやすい
立替精算では領収書の紛失や金額の記載ミスといったトラブルが起こりやすいため、管理体制を整える必要があります。例えばタクシーのレシートをなくしてしまうと、精算できず従業員が自己負担になることもあります。
手作業で申請をまとめると数字の転記ミスも生じやすく、経理担当者の確認作業が増える原因になります。こうしたリスクを減らすために、領収書の撮影保存や自動計算機能のある精算システムを導入すると、記録の正確性が高まり、業務全体の効率化にもつながります。
まとめ
立替精算は従業員が業務上必要な費用を一時的に負担する仕組みであり、適切な運用が欠かせません。交通費や出張費など日常的に発生する経費も対象となるため、申請期限や上限額をあらかじめ設定しておくとスムーズです。
ただし、ルールが曖昧だと精算漏れや処理遅延が起こりやすく、従業員の負担や不満にもつながります。そのため、精算スピードを意識し、必要に応じて仮払い制度を併用することで、従業員のキャッシュフローを守りつつ経理処理の正確性も確保できます。また、業務全体の効率化を図るためにも、システム導入や管理体制の見直しを検討するとよいでしょう。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
立替精算に関するよくあるご質問
立替精算についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、立替精算に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
立替精算とはどういう意味ですか?
立替精算とは、従業員が業務上必要な費用を一時的に自己資金で支払い、後日会社からその金額を精算してもらう仕組みです。例えば出張時の交通費などが対象で、会社は領収書や申請書類を確認したうえで払い戻しを行います。立替精算は仮払いと異なり、事前に会社から資金を受け取らずに従業員が先に支払います。
従業員が立て替える経費には何がありますか?
従業員が立て替える経費には、交通費や出張費、消耗品費、会議費、交際費、通信費、福利厚生費などがあります。例えば取引先訪問での電車代や宿泊費、会議で必要な弁当代、急ぎで購入した文房具や消耗品など、業務に必要な支出が対象です。領収書や明細を添付して申請することで、経理部門が適切に処理し精算されます。
立替払い(立替経費)は違法ですか?
立替払いは法律上違法ではなく、会社が従業員に一時的に費用を負担させることは認められています。例えば営業担当者が取引先訪問の交通費を立て替え、後日会社が精算するケースも日常的です。ただし、過度な負担が従業員にかかることを防ぐため、精算のスピードを早める、仮払い制度を併用するなどの工夫が必要です。




