
企業の経営において「棚卸し」は、在庫を正確に把握し、事業の実態を明らかにするための欠かせない業務です。帳簿上の在庫数と実際の数量に差異があれば、経営判断を誤る原因にもなります。棚卸しを行うことで、在庫過多や在庫不足、不良在庫の有無を確認し、適切な在庫管理や利益計算に役立てることができます。
また、実施のタイミングや頻度、採用する方式や評価方法によって、棚卸しの精度や効率は大きく変わります。本記事では、棚卸しの基本的な意味から進め方、評価方法、効率化のポイントまでをわかりやすく解説します。
目次
棚卸しとは?
棚卸しとは、企業が保有する在庫の数量や状態を確認し、結果を帳簿と照合する一連の作業を指します。例えば、倉庫に保管している商品や原材料を一つひとつ確認し、帳簿上の数字と一致しているかを確かめることで、在庫の過不足や不良品の有無を把握できます。
棚卸しは単なる数合わせではなく、企業の財務状況を正確に反映させる重要な会計手続きでもあります。正確な棚卸しを行うことで、損益計算書の原価や利益が適切に算出され、経営判断の精度向上にもつながります。
棚卸しの頻度とタイミング
棚卸しの実施頻度やタイミングには厳密な法律上の決まりはありませんが、少なくとも年に1回、決算期末に行うことが一般的です。決算前に在庫の実数を確定させておくことで、売上原価や利益を正確に算出できます。
また、業種によっては、より短いサイクルで棚卸しを行うケースもあり、飲食業や小売業では月に1回の棚卸しを習慣化している企業もあります。棚卸しの頻度を高めることで、在庫の鮮度や回転率を把握しやすくなり、過剰在庫の防止や適正在庫の維持にも役立ちます。
なお、決算についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
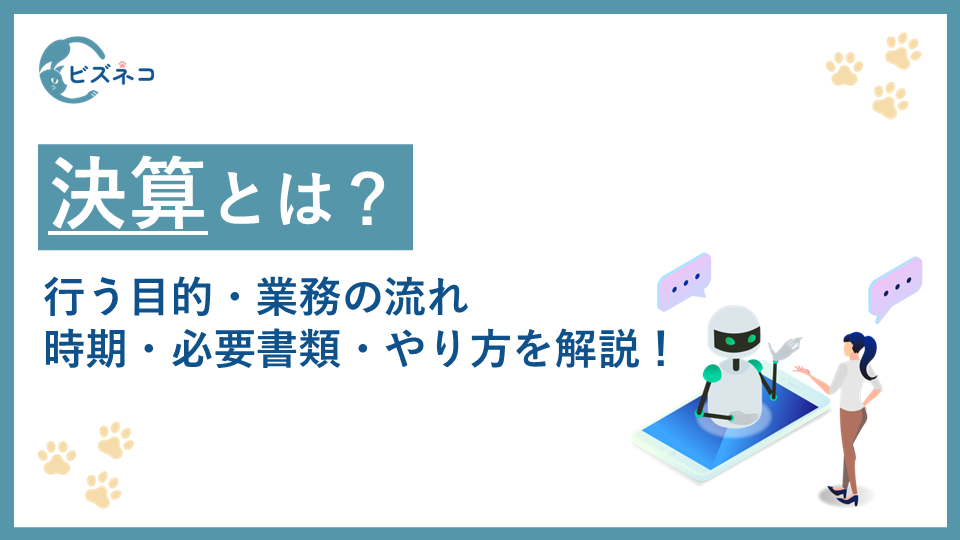
棚卸資産とは?
棚卸資産とは、販売を目的として保有されている商品や製品、製造途中の仕掛品、あるいはそれらの製造に用いる原材料など、企業の営業活動に直接関係する在庫を指します。例えば、製造業であれば完成品だけでなく、原材料や半製品も棚卸資産に含まれます。法人税法上では、棚卸資産は次の5つに分類されます。
| 分類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 商品・製品 | 販売または引渡しを目的とする完成品 | 店頭販売商品・完成製品 |
| 半製品 | 製造途中で一部工程が完了しているもの | 組立途中の部品・加工途中の製品 |
| 仕掛品 | 製造工程中で未完成のもの | 加工中の材料・未完成製品 |
| 原材料 | 製品の製造や加工に使用する素材 | 板金・樹脂・布地 |
| 貯蔵品・消耗品 | 製造や販売活動に付随して使用するもの | 包装資材・事務用品・燃料 |
企業が棚卸しを実施する理由
企業が棚卸しを実施する理由として、以下のような点があげられます。
- 帳簿上の在庫数と実在庫数を照合するため
- 在庫の品質や状態が問題ないか確認するため
- 在庫過多や在庫不足を確認するため
- 正確な事業利益を把握するため
ここでは、それぞれの理由について具体的に紹介します。
帳簿上の在庫数と実在庫数を照合するため
棚卸しを行う目的のひとつは、帳簿上の在庫数と実際の在庫数を照合し、差異を明確にすることです。例えば、入出庫の記録漏れや誤計上があると、帳簿上の在庫と実際の数量が一致しなくなります。
在庫数と実在庫数のズレを放置すると、売上原価や利益の計算に影響し、経営判断を誤る可能性があります。定期的に棚卸しを実施することで、記録の正確性を保ち、不正やミスの早期発見にもつながります。正しい在庫数を把握することは、信頼性の高い会計処理を行ううえで欠かせない基本といえるでしょう。
在庫の品質や状態が問題ないか確認するため
棚卸しは、単に数量を数えるだけでなく、在庫の品質や状態を確認するためにも実施されます。例えば、長期間保管されている商品が劣化していたり、賞味期限が近づいていたりする場合には、販売可能な在庫として扱うことができません。
在庫の劣化などの状態を見落とすと、実際には使えない在庫を資産として計上してしまい、財務上の正確性を損ねるおそれがあります。棚卸しの際に在庫の品質を確認することで、不良品の早期発見や廃棄判断が可能となり、適切な在庫評価にもつながります。
在庫過多や在庫不足を確認するため
棚卸しを通じて在庫の数量を把握することは、過剰在庫や在庫不足の防止に直結します。例えば、需要の変動を読み違えて在庫を抱えすぎると、保管コストが増加し、資金繰りにも影響します。
逆に、在庫が不足すれば販売機会を逃すリスクが生じます。棚卸しを定期的に行うことで、在庫の偏りを早期に把握し、仕入れや生産計画を調整できます。そのため、適正在庫を維持することは、経営資源を有効に活用し、無駄のない事業運営を実現するための重要な取り組みといえるでしょう。
正確な事業利益を把握するため
棚卸しは、企業が正確な利益を算出するためにも欠かせない手続きです。例えば、期末時点の在庫額が正確に反映されていなければ、売上原価や利益の金額も誤って計上される可能性があります。
特に製造業や小売業など、在庫を多く扱う企業では、棚卸し結果が決算書の信頼性を左右します。実際の在庫を正確に評価し、帳簿へ反映することで、財務諸表の精度が高まり、経営分析や税務申告の根拠も明確になります。棚卸しは、事業の健全性を保つための重要な確認作業なのです。
棚卸しにおける2つの実施方法
棚卸しの進め方には、大きく分けて「一斉棚卸」と「循環棚卸」の2種類があります。どちらも在庫を正確に把握するための方法ですが、実施のタイミングや対象範囲、業務への影響が異なります。自社の業態や在庫量に合わせて適した方法を選ぶことが、効率的な棚卸しの第一歩といえるでしょう。
一斉棚卸
一斉棚卸とは、特定の日を定めて全ての在庫を一度に確認する方法です。例えば、決算期末に営業を一時的に止め、全社的に在庫数をカウントするケースが該当します。
一斉棚卸の方法は、すべての在庫を同じタイミングで把握できるため、期末時点の在庫額を正確に計上するのに適しています。ただし、業務を一時的に停止する必要があるため、生産や販売への影響を最小限に抑える計画性が求められます。事前に担当者を配置し、棚卸しルールを共有することで、作業の精度と効率を高めることができます。
循環棚卸
循環棚卸は、在庫を複数のグループに分け、一定期間ごとに順番に棚卸しを行う方法です。例えば、倉庫内のエリアごとに月単位で在庫確認を行うといった形で実施します。
循環棚卸の方法では、業務を止めずに継続的な棚卸しが可能となり、在庫管理の精度を保ちながら日常業務への影響を軽減できます。また、定期的に在庫の状態を把握できるため、記録のずれや不良在庫の発生を早期に発見しやすい点も特徴です。継続的な在庫管理体制を築くうえで、循環棚卸は有効な手段のひとつといえます。
棚卸しにおける2つの方式
棚卸しの現場で用いられる主な方式には、「リスト方式」と「タグ方式」があります。どちらも在庫数を正確に把握するための方法ですが、作業の流れや記録の仕方が異なります。自社の業務規模や在庫管理体制に合った方式を選ぶことで、棚卸しの効率と精度を両立させることができます。
リスト方式
リスト方式は、あらかじめ用意された在庫リストをもとに、実際の数量を確認して記入する棚卸し方法です。例えば、在庫管理システムから印刷したリストを持参し、現物を確認しながら数量を記録していく形で進めます。
リスト方式は、帳簿上の在庫数を前提として作業を行うため、差異を見つけやすく、短時間で結果を集計できるのが特徴です。ただし、リストの内容が古かったり、記録ミスがあったりすると、誤った在庫数で集計されるおそれもあります。そのため、リストの更新やチェック体制を整えることが重要です。そのため、リスト方式は、在庫量が多く定期的に棚卸しを行う企業に適した方式といえるでしょう。
タグ方式
タグ方式は、在庫品ごとにタグやラベルを貼り付け、実際の数量を現場で直接カウントして記録する方法です。例えば、倉庫内の商品一つひとつに番号付きのタグを取り付け、数を確認しながらタグを回収や集計をする流れで進めます。
タグ方式では、帳簿上の在庫に依存せず、現物を基準に正確な数量を把握できる点がメリットです。そのため、在庫の差異が発生しやすい環境や、初めて棚卸しを行う場合にも有効です。一方で、作業量が多く人手や時間を要するため、効率化のためにはチームで役割を明確に分担することが求められます。そのため、タグ方式は、正確さを重視する棚卸しにあった方式といえるでしょう。
棚卸在庫における2種類の評価方法
棚卸しで把握した在庫は、会計上の資産として評価する必要があります。その際に用いられる代表的な方法が「原価法」と「低価法(時価法)」です。どちらの方法を採用するかによって、決算時の利益額や資産額が変わるため、在庫の性質や市場環境に合わせた評価が求められます。
原価法
原価法とは、在庫を取得した際の購入価格や製造原価をもとに評価する方法です。例えば、仕入れ値が1個あたり500円の商品を10個保有していれば、その在庫価値は5,000円として計上されます。
原価法では、在庫を取得した時点のコストを基準に評価するため、会計上の一貫性を保ちやすく、損益計算を安定させる効果があります。ただし、物価の変動や市場価格の下落があっても、原価ベースで評価するため、実際の時価とかけ離れる場合もあります。そのため、継続して原価法を用いる際には、原価の算定方法を明確にし、適切な基準を維持することが重要です。
低価法(時価法)
低価法(時価法)は、在庫の原価と時価を比較し、どちらか低い金額で評価する方法です。例えば、仕入れ時に1個500円だった商品が、市場の変動で400円まで値下がりした場合、評価額は400円として計上します。
低価法(時価法)を採用することで、在庫の実際の価値を反映しやすく、将来的な損失を早期に計上できる点が特徴です。特に、商品価格の変動が大きい業種や、陳腐化しやすい在庫を扱う企業に適しています。ただし、時価の判断には一定の主観が伴うため、評価基準を明確にし、継続的な運用ルールを設けることが信頼性確保のために欠かせません。
棚卸しの手順とやり方
棚卸しの手順とやり方は以下の流れで進みます。
- step1:棚卸しの実施方法とスケジュールを決める
- step2:棚卸しの方式を決める
- step3:在庫数をチェックする
- step4:不良在庫を仕分ける
- step5:評価方法に沿って結果を報告する
ここでは、それぞれのやり方について具体的に解説します。
step1:棚卸しの実施方法とスケジュールを決める
棚卸しを始める際には、まず実施方法とスケジュールを明確にすることが重要です。例えば、決算期末に全ての在庫を一度に確認する「一斉棚卸」を採用する場合、営業を一時的に停止する必要があるため、業務への影響を最小限に抑える計画を立てる必要があります。
一方で、業務を止めずに定期的に実施する「循環棚卸」を選ぶ場合は、エリアや品目ごとに棚卸しの順序や担当を決め、年間を通じて継続的に在庫を管理します。どちらの方法を取るにしても、作業日程や担当者、確認範囲を事前に共有しておくことで、棚卸しの精度と効率が高まり、後の集計や報告もスムーズに進めることができます。
step2:棚卸しの方式を決める
棚卸しを円滑に進めるためには、リスト方式かタグ方式のどちらを採用するかを決めておくことが欠かせません。例えば、在庫管理システムで在庫リストを出力し、そのデータをもとに実数を記録する場合は「リスト方式」が適しています。
一方で、現物を基準に数を確認したい場合には、商品一つひとつにタグやラベルを貼り付けて管理する「タグ方式」がおすすめです。どちらの方式にもメリットがあり、リスト方式は集計が早く、タグ方式は正確性に優れます。自社の在庫規模や人員体制に合わせて最適な方式を選定することが、作業効率とデータ精度を両立させるポイントです。
step3:在庫数をチェックする
実際の棚卸し作業では、倉庫や店舗にある在庫の数量をひとつずつ確認していきます。例えば、商品や部品を棚ごとに区分けし、担当者が現物を確認しながら数量を記録していくと、漏れや重複が防げます。
このとき、現場の混乱を避けるために、作業範囲や担当を明確に分けておくことが重要です。また、棚卸し中に出庫や移動が発生すると数が合わなくなるため、一時的に在庫の動きを止めて作業を行うことが望まれます。正確な在庫数を把握することは、帳簿との照合や評価の基礎となるため、確認の際には慎重な対応が求められます。
step4:不良在庫を仕分ける
棚卸しの過程では、数量だけでなく在庫の状態を確認し、不良在庫を見極めることも大切です。例えば、長期間動きのない商品や破損や変色など品質に問題がある在庫は、通常の販売在庫とは区別して仕分けます。これにより、帳簿上での資産評価を正確に行うことができ、不要な在庫を抱え続けるリスクも軽減されます。
また、不良在庫を明確にすることで、今後の仕入れや生産計画の見直しにも役立ちます。棚卸しは在庫量の確認だけでなく、経営資源の最適化にもつながる重要な機会であるため、在庫の状態をしっかりと見極める姿勢が求められます。
step5:評価方法に沿って結果を報告する
棚卸し作業の最終段階では、確認した在庫数と状態をもとに、適切な評価方法で結果をまとめます。例えば、取得時のコストを基準に資産を評価する「原価法」を採用すれば、安定した利益計算が可能になります。
一方、市場価格が下落している在庫については、原価と時価を比較して低い方で評価する「低価法(時価法)」を適用することで、実態に即した財務状況を反映できます。どちらの方法を用いるかは、業種や在庫の性質、会計方針によって異なります。評価結果を正確に報告し、会計帳簿に反映させることで、経営判断の信頼性を高め、企業の財務管理を適正に保つことができます。
効率的に棚卸しを進めるポイント
棚卸しは正確さが求められる一方で、時間や人手を多く必要とする業務でもあります。限られたリソースの中で効率的に進めるには、事前の計画やルール作りが欠かせません。担当者の配置や作業手順を明確にすることで、ミスを防ぎ、スムーズな棚卸しを実現できます。
計画的に人員と時間を確保する
棚卸しを円滑に進めるには、十分な人員と時間をあらかじめ確保しておくことが大切です。例えば、棚卸し当日に人員が不足すると作業が遅れ、確認漏れや誤記入といったミスが発生するおそれがあります。効率的な進行のためには、在庫の量や保管場所を考慮し、担当範囲を明確に割り振ることが重要です。
また、通常業務との兼ね合いを踏まえて、作業時間を無理なく確保するスケジュールを立てることも求められます。事前にリハーサルや共有会を行えば、当日の混乱を防ぎ、作業全体の正確性とスピードを両立させることができます。
棚卸しのルールを策定しておく
効率的な棚卸しを行うには、作業前に明確なルールを策定し、全員で共有しておくことが不可欠です。例えば、在庫を数える順序や記録方法、確認の手順などを事前に統一しておくことで、担当者ごとの判断のばらつきを防ぐことができます。
ルールがないまま進めると、重複計上や漏れといったトラブルが生じやすく、結果の信頼性にも影響します。そのため、作業開始前にマニュアルやチェックリストを整備し、参加者全員が理解した上で取り組むことが理想的です。また、ルールを明文化しておくことで、次回以降の棚卸しにも活用でき、継続的な効率化にもつながります。
なお、日ごろから経理業務の業務フローを定めておくこともおすすめです。業務フローの作成方法や効率化のポイントについては、こちらの記事をご覧ください。

まとめ
棚卸しは、在庫の実態を正確に把握し、企業の経営や会計の信頼性を支える重要な業務です。帳簿上の数字と実際の在庫に差異があれば、利益計算や経営判断に誤りが生じるおそれがあります。そのため、定期的に棚卸しを実施し、在庫の数量や品質を確認することで、過剰在庫の削減や資金の有効活用にもつながります。
また、実施方法や評価基準を明確にし、作業の効率化を図ることで、正確かつ負担の少ない棚卸しを実現できるでしょう。棚卸しは単なる在庫確認ではなく、企業の健全な経営基盤を支えるための大切なプロセスといえるでしょう。加えて、棚卸しに関わる決算業務は、経理代行会社に相談することもひとつの手です。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
棚卸しに関するよくあるご質問
棚卸しについてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、棚卸しに関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
棚卸しとはどういう意味ですか?
棚卸しとは、企業が保有している在庫の数量や状態を確認し、帳簿上の在庫データと照合する作業を指します。例えば、倉庫や店舗にある商品や原材料をひとつずつ確認し、実際の数量が記録と一致しているかを確かめます。正確な棚卸しは、在庫過多や不足、不良在庫の有無を把握し、原価計算や利益算出に役立ちます。
棚卸しはどのようなやり方で進めますか?
棚卸しの進め方には、「一斉棚卸」と「循環棚卸」の2つの方法があります。一斉棚卸は決算期などに全在庫を一度に確認する方式で、正確な期末在庫を把握しやすいのが特徴です。循環棚卸は、倉庫のエリアや品目ごとに定期的に確認を行う方法で、日常業務を止めずに実施できます。自社の業種や在庫量に合わせて選びましょう。
棚卸しで在庫を数えるときの正しい方法は何ですか?
棚卸しで正確に在庫を数えるためには、ルールを決めましょう。例えば、倉庫の棚ごとに担当者を分け、同じ商品を重複して数えないようにします。また、リスト方式なら在庫表を見ながら実数を記録し、タグ方式なら商品ごとにラベルを貼って数量を確認します。作業前に在庫の動きを止め、記録漏れを防ぐことも大切です。




