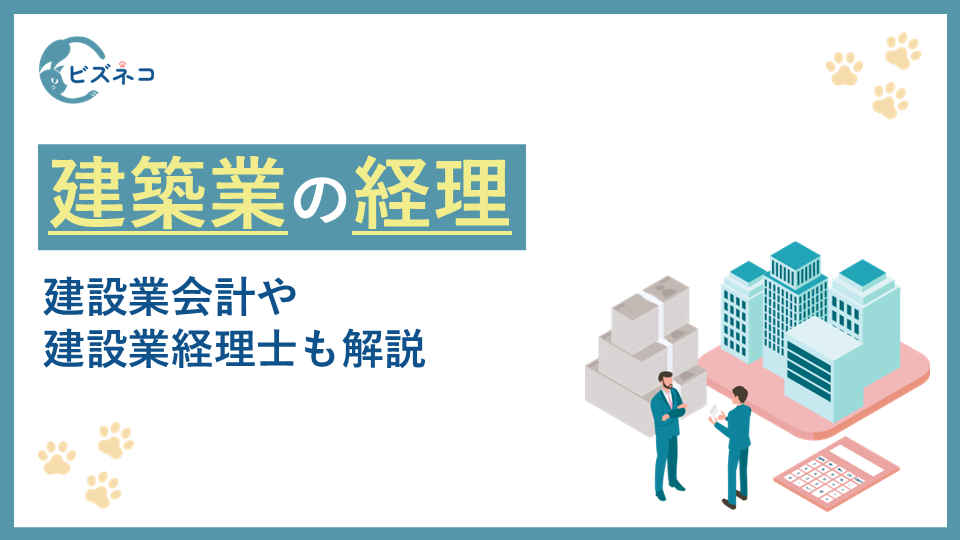
建設業における経理は、一般的な企業の経理とは異なり、工事ごとの原価管理や収益計上など、建設業界に特有のルールが存在します。経理業務が複雑になりますが、適切な会計処理を行うことで、会社の財務状況を正しく把握し、健全な経営を支える役割を担っています。
本記事では、建設業の経理の仕事内容や、建設業会計と一般会計の違い、さらに専門資格である建設業経理士について詳しく解説します。建設業の経理について理解を深め、実務に活かしましょう。
目次
建設業の経理の仕事内容とは?
建設業における経理の仕事内容は、日次業務、月次業務、年次業務にわけられます。経理業務をスケジュールにわけて考えることで、整理して考えることができます。ここでは、それぞれの経理業務について詳しく解説していきます。
建設業における経理の日次業務(毎日の仕事)
建設業の経理が日々行う業務には、現金管理や伝票処理、請求書の確認などが含まれます。例えば、現場で発生した経費の領収書を整理し、適切な勘定科目で仕訳を行うことは重要な作業です。また、資材の購入や下請け業者への支払いがある場合、それらの取引を正しく記録し、必要に応じて承認を得る必要があります。
さらに、売掛金や買掛金の管理も日々の業務の一環であり、支払いの遅れがないようにスケジュールを調整することが求められます。加えて、銀行口座の入出金を確認し、帳簿と照らし合わせることで、資金の動きを正確に把握することも欠かせません。これらの業務を適切に行うことで、財務状況を正しく反映させ、会社の資金繰りを円滑に進めることができます。
建設業における経理の月次業務(毎月の仕事)
月次業務では、日々の経理処理を集計し、月単位での財務状況を整理することが求められます。例えば、各工事の進捗に応じた収益や原価の計上を行い、適切なタイミングで売上を計上することが重要です。また、給与計算や社会保険料の支払いも月次業務の一部であり、従業員への給与振込が遅れることのないよう、計算ミスを防ぐための確認作業が必要になります。
さらに、月末には試算表を作成し、会社全体の収支バランスを把握することが求められます。これにより、経営者は資金繰りや今後の事業計画について適切な判断を下すことができます。また、取引先への請求や支払い業務も月次で整理し、売掛金や買掛金の残高を正しく管理することが求められます。こうした毎月の業務を着実に進めることで、建設業特有の資金の流れを管理して、安定した経営につなげることができます。
建設業における経理の年次業務(毎日の仕事)
年次業務では、1年間の経理データを総括し、決算処理や税務申告を行うことが主な仕事となります。例えば、1年間に発生した工事ごとの収益や費用を整理し、決算書を作成することで、会社の経営成績を明確に示すことが求められます。決算に向けては、未収金や未払金の精査、減価償却費の計算、税務調整など、多くの確認作業が必要になります。
また、税務申告に向けた準備も重要な業務のひとつです。法人税や消費税の計算を正確に行い、期限内に申告や納付をすることで、税務リスクを回避することができます。
さらに、決算書の内容をもとに、来期の経営計画や資金計画を立てることも重要です。金融機関や取引先に対して経営状況を説明するため、財務諸表を適切に作成し、信頼性のある情報を提供することが求められます。年次業務は会社の財務状況を正しく示し、今後の経営方針を決定する上で非常に重要な役割を果たします。
建設業会計とは?
建設業会計とは、建設業に特有の会計処理を行うための仕組みを指し、工事ごとの収支や原価管理を適切に把握することを目的としています。一般的な企業会計では、商品の仕入れや販売といった単純な取引が中心となりますが、建設業では工期が長期にわたる工事が多く、収益や費用の計上時期が重要なポイントとなります。
ここでは、建設業会計と一般会計の違いについて詳しく解説します。
建設業会計と一般会計の違い
建設業会計と一般会計の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 建設業会計 | 一般会計 |
|---|---|---|
| 勘定科目の違い | 「未成工事支出金」「完成工事高」「工事未払金」など工事特有の勘定科目がある | 「売上」「仕入」「買掛金」など一般的な勘定科目を使用する |
| 原価計算の違い | 工事ごとに費用を管理する「個別原価計算」が主流 | 製品ごとに費用を計算する「総合原価計算」が主流 |
| 工事収益計上基準の違い | 進捗に応じて収益を計上する「工事進行基準」と完成時に計上する「工事完成基準」がある | 商品販売時に売上を計上する「発生主義」が基本 |
ここでは、それぞれの違いについて詳しく解説していきます。
勘定科目の違い
建設業会計では、一般会計にはない独自の勘定科目が存在します。例えば、工事が完了するまでに発生した費用を一時的に計上する「未成工事支出金」という勘定科目があります。これは、工事が進行中である間は費用として処理せず、完成後に「完成工事原価」として計上するためのものです。
一方、売上に関しては、完成した工事の売上を「完成工事高」として計上し、通常の売上とは区別します。また、工事の請負契約に基づき、発注者から前受金を受け取った場合には「未成工事受入金」として処理し、工事の進捗に応じて売上に振り替える必要があります。
さらに、建設業では材料費や労務費、外注費などの原価管理が重要であり、「工事未払金」などの科目を活用して、支払い予定の費用を管理します。このように、建設業ならではの勘定科目を理解し、適切に仕訳を行うことが、正確な会計処理につながるでしょう。
原価計算の違い
建設業の原価計算は、一般的な製造業や小売業とは異なり、工事ごとに詳細な管理が求められます。例えば、製造業では同じ商品を大量生産するため、材料費や労務費を一括して計上することが一般的ですが、建設業では工事ごとに異なる材料や人件費が発生するため、それぞれの工事ごとに原価を細かく分類し、管理する必要があります。
そのため、「個別原価計算」が採用されることが多く、各工事の直接費や間接費を適切に振り分け、正確な工事原価を算出することが重要です。例えば、大規模なマンション建設と小規模なリフォーム工事では、使用する資材や人件費が大きく異なるため、それぞれの工事の原価を明確に区別し、適切に計算しなければなりません。
また、工事の進捗状況に応じて原価を集計し、収益とのバランスを見ながら適切な利益率を確保することも求められます。このような原価計算の正確性が、建設業の経営の安定につながります。
工事収益計上基準の違い
工事収益の計上基準には、建設業特有のルールがあり、工事の進捗に応じた適切なタイミングで収益を認識する必要があります。一般的な企業では、商品を販売した時点で売上を計上しますが、建設業では工事が長期間にわたるため、「工事進行基準」や「工事完成基準」といった方法が用いられます。例えば、1年半かかる建設プロジェクトでは、完成するまで売上を計上しない「工事完成基準」を採用すると、途中の収益が一切認識されず、決算書上の売上が不安定になってしまいます。
そのため、工事の進捗率に応じて売上を計上する「工事進行基準」を適用し、適切なタイミングで収益を分割計上する方法が一般的です。特に、大規模な工事では進行基準の採用が推奨されており、財務状況の安定性を確保する上で重要な役割を果たします。どの基準を適用するかによって、企業の利益計上のタイミングや税務上の処理が変わるため、建設業の経理担当者はこれらのルールを理解し、適切な会計処理を行う必要があります。
建築業会計でよく使う勘定科目と仕訳例
建設業会計でよく使う勘定科目を表にまとめました。
| 勘定科目 | 概要 |
|---|---|
| 完成工事高 | 工事が完了して請負代金として得た収益を計上する科目 |
| 完成工事原価 | 完成した工事にかかった直接費や間接費を計上する科目 |
| 完成工事総利益 | 完成工事高から完成工事原価を差し引いた利益 |
| 未成工事支出金 | 工事が完了するまでに発生した費用を一時的に計上する科目 |
| 完成工事未収入金 | 工事が完成し売上を計上したが、まだ入金されていない金額を計上する科目 |
| 未成工事受入金 | 工事が完了する前に受け取った前受金を管理する科目 |
| 工事未払金 | 工事に関連する支払いが未完了の費用を管理する科目 |
ここでは、それぞれの勘定科目について詳しく解説していきます。
完成工事高
完成工事高とは、工事が完了し、請負契約に基づいて確定した売上を計上する勘定科目です。例えば、1,000万円の建設工事が完了し、請求書を発行した場合、その時点で「完成工事高」として売上を計上します。この勘定科目は、工事完成基準や工事進行基準に基づき、適切なタイミングで認識される必要があります。工事が長期間に及ぶ場合は、進捗に応じた売上計上が求められることもあります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 完成工事未収入金 | 10,000千円 | 完成工事高 | 10,000千円 |
完成工事原価
完成工事原価とは、完成した工事にかかった直接費や間接費を計上する勘定科目です。例えば、建設工事において材料費や外注費、人件費などが合計で800万円発生した場合、それを「完成工事原価」として記録します。これにより、売上に対する適切な原価を明確にし、工事の利益を正しく算出することができます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 完成工事原価 | 8,000千円 | 未成工事支出金 | 8,000千円 |
完成工事総利益
完成工事総利益とは、完成工事高から完成工事原価を差し引いた利益のことを指します。例えば、1,000万円の工事を請け負い、工事原価が800万円だった場合、完成工事総利益は200万円となります。この利益は、企業の経営状況を示す重要な指標となるため、適切な原価管理が求められます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 完成工事高 | 10,000千円 | 完成工事総利益 | 2,000千円 |
| 完成工事原価 | 8,000千円 |
未成工事支出金
未成工事支出金とは、工事が完了するまでに発生した費用を一時的に計上するための勘定科目です。例えば、工事中に材料費や労務費が発生した場合、完成するまで「未成工事支出金」として記録し、完成時に「完成工事原価」へ振り替えます。これにより、工事進行中のコストを適切に管理できます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未成工事支出金 | 5,000千円 | 現金預金 | 5,000千円 |
完成工事未収入金
完成工事未収入金とは、工事が完了し売上を計上したものの、まだ入金されていない金額を記録するための勘定科目です。例えば、500万円の工事が完了し、請求書を発行したが、入金が翌月になる場合、「完成工事未収入金」として処理します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 5,000千円 | 完成工事未収金 | 5,000千円 |
未成工事受入金
未成工事受入金とは、工事が完了する前に受け取った前受金を管理する勘定科目です。例えば、着工前に契約金の一部として500万円を受領した場合、「未成工事受入金」として記録し、工事完成後に売上として計上します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 5,000千円 | 未成工事受入金 | 5,000千円 |
工事未払金
工事未払金とは、工事に関連する支払いが未完了の費用を管理するための勘定科目です。例えば、外注業者へ支払う予定の1,200万円が決済待ちの場合、一時的に「工事未払金」として計上します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 12,000千円 | 工事未払金 | 12,000千円 |
建設業経理士(建設業経理事務士)とは?
建設業経理士(建設業経理事務士)とは、建設業に特化した会計や財務の知識を持つ専門資格であり、工事ごとの収益計算や原価管理、税務処理などを適切に行う能力が求められます。
例えば、一般的な経理業務では売上や仕入れの管理が中心となりますが、建設業では工事ごとの収益計上基準や未成工事支出金の管理など、業界特有の経理処理が必要となります。そのため、建設業経理士の資格を持つことで、専門的な知識を証明でき、経理担当者としてのスキルアップにつながります。
建設業経理士と日商簿記の違い
建設業経理士と日商簿記はどちらも会計知識を証明する資格ですが、それぞれの目的や学習内容には大きな違いがあります。例えば、日商簿記は製造業や小売業など幅広い業界に対応した会計の基礎を学ぶのに対し、建設業経理士は建設業に特化した経理知識を身につけることを目的としています。
特に、工事ごとの収益計上や未成工事支出金の管理、原価計算の手法など、建設業独自の会計処理を深く学ぶ点が特徴です。また、試験内容にも違いがあり、日商簿記は貸借対照表や損益計算書の作成が中心ですが、建設業経理士では工事台帳の作成や工事進行基準に基づく売上計上など、より実務的な知識が求められます。このように、建設業経理士は建設業界での経理実務を専門的に習得したい人に向いている資格といえます。
建設業経理士の試験内容と受験資格
建設業経理士の試験は、等級によって難易度や内容が異なり、1級から4級までのレベルに分かれています。
| 級別 | 試験内容 |
|---|---|
| 1級 | 建設業原価計算・財務諸表・財務分析 |
| 2級 | 建設業の簿記・原価計算・会社会計 |
| 3級 | 建設業の簿記・原価計算 |
| 4級 | 簿記のしくみ |
例えば、4級や3級では建設業の基礎的な会計処理や仕訳が中心となり、簿記の基本を理解することが求められます。一方、2級では財務諸表の作成や原価計算の知識が必要となり、より実務的なスキルが問われます。最も難易度の高い1級では、建設業会計の専門知識に加え、税務や財務分析など、経営管理に関する内容も含まれます。
なお、受験資格に関しては、特に制限がなく、誰でも受験することが可能で、飛び級もできます。しかし、上位級の試験に合格するには、実務経験や建設業に関する知識が求められるため注意しましょう。
建設業経理士を取得するメリット
建設業経理士の資格を取得することで、建設業界でのキャリアアップや企業の競争力向上につながる多くのメリットがあります。資格を取得することで、企業の信用度向上にもつながり、取引先や金融機関からの評価が高まる要因となることもあります。
また、資格を持つことで専門知識が証明され、経理担当者としての信頼性が向上し、昇進や給与アップの可能性が高まることもあります。さらに、建設業界では経理の専門人材が不足しているため、資格取得者は転職市場においても有利な立場に立つことができます。このように、建設業経理士は自身のスキルを高めるだけでなく、企業の経営にも大きく貢献できる資格といえます。
まとめ
建設業の経理では建設業に特有の会計処理を行うため、工事ごとの収支や原価管理を適切に把握することが求められます。そのため、建設業会計は一般的な企業会計とは異なり、工期が長期にわたる工事が多く、収益や費用の計上時期が重要なポイントとなります。
また、「完成工事高」や「完成工事原価」など、建設業特有の勘定科目や仕訳も発生するため、日商簿記以外にも建設業経理士の資格取得など、日々スキルアップをしておくこともおすすめです。なお、建設業の経理における人材不足や、業務負担の解消には経理代行会社の活用もおすすめです。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
建設業の経理に関するよくあるご質問
建設業の経理についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、建設業の経理に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
建設業の経理の仕事内容は何ですか?
建設業の経理は、一般的な経理業務に加え、工事ごとの原価管理や収益計上など、建設業特有の会計処理を行います。例えば、工事が進行中の費用を「未成工事支出金」として管理し、工事完成後に「完成工事原価」として計上するなど、長期間にわたる工事の収支を適切に管理する必要があります。
建設業経理士は難しいですか?
建設業経理士の難易度は等級によって異なります。例えば、3級や4級は基礎的な簿記の知識があれば比較的に合格しやすいですが、2級以上になると財務諸表の作成や工事原価計算、税務知識などが求められ、難易度が上がります。特に1級は合格率も低めであるため、実務経験や専門的な学習が必要となるでしょう。
建設業会計と一般会計の違いは何ですか?
建設業会計と一般会計の違いは、収益計上や原価管理の方法にあります。例えば、一般会計では商品を販売した時点で売上を計上しますが、建設業では工事の進捗に応じた「工事進行基準」や、完成後に売上を計上する「工事完成基準」が適用されます。また、「未成工事支出金」「完成工事高」など、特有の勘定科目があります。




