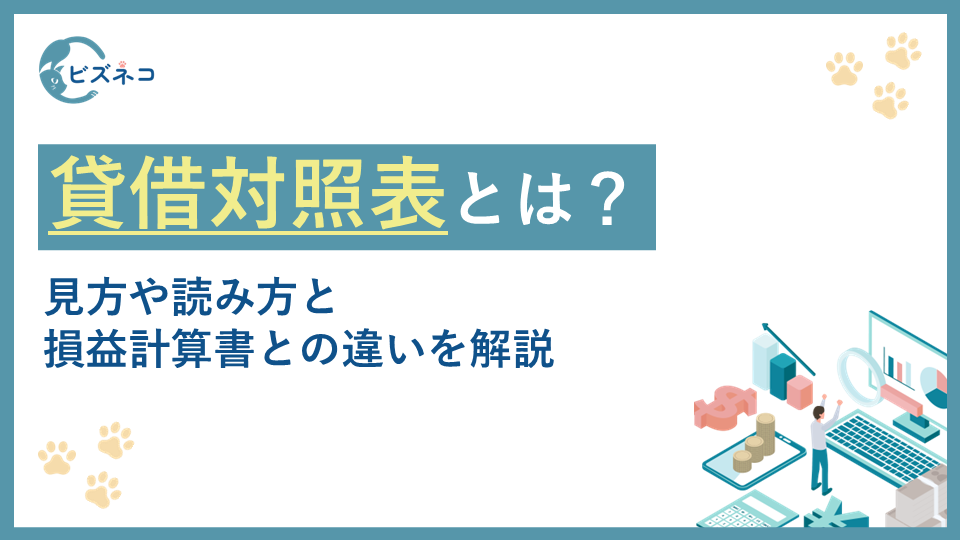
貸借対照表(B/S:バランスシート)は、企業の財務状況を正しく把握するうえで欠かせない資料のひとつです。資産・負債・純資産の3つの要素を左右に分けて記載し、企業が保有する財産や負っている義務、その差額としての純資産を一覧できます。
貸借対照表は損益計算書やキャッシュフロー計算書と並ぶ「財務三表」の一種であり、それぞれの違いを理解することは経営判断や資金計画において重要です。本記事では、貸借対照表の構成や見方、損益計算書やキャッシュフロー計算書との違い、分析方法について詳しく解説します。
目次
貸借対照表(バランスシート)とは?
貸借対照表(B/S:バランスシート)とは、企業の財政状態を一定時点で示す財務諸表です。左側に資産、右側に負債と純資産を記載し、全体のバランスから企業の安定性や支払い能力を把握できます。
例えば、現金や売掛金は流動資産、建物や機械は固定資産に分類され、右側には借入金や買掛金、資本が並びます。貸借対照表は過去の取引結果を積み上げた姿であり、損益計算書のように期間の収益や費用を示すものではありません。経営判断や融資審査など、多くの場面で基礎となる資料として活用されます。
財務三表とは?
財務三表とは、企業の経営状況を多角的に示すための3種類の財務諸表で、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を指します。それぞれ役割が異なり、例えば貸借対照表は財政状態を、損益計算書は一定期間の収益と費用の関係を、キャッシュフロー計算書は現金の流れを示します。
財務三表を総合的に読み解くことで、利益の大きさだけでなく、資金繰りや財務の健全性も把握できます。投資家や金融機関、経営者は財務三表を組み合わせて分析し、将来の戦略や資金計画に反映します。
なお、財務三表についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
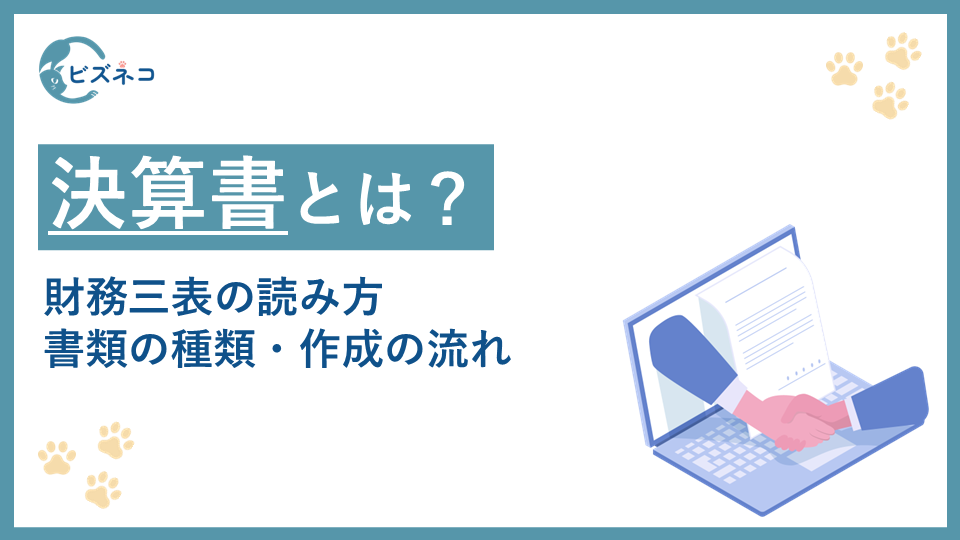
貸借対照表と損益計算書の違い
貸借対照表と損益計算書は、示す情報の性質が異なります。貸借対照表は期末時点の資産、負債、純資産の残高を表すのに対し、損益計算書は一定期間の売上や費用、利益の動きを示します。
例えば、同じ「現金」でも、貸借対照表では残高を、損益計算書では入金や支出の原因となった取引を表します。貸借対照表は企業の「状態」を、損益計算書はその期間の「成果」を映し出すため、両者を合わせて確認することで、儲かっているかだけでなく、安定性や将来のリスクも見極められます。
なお、損益計算書については以下の記事で解説しています。
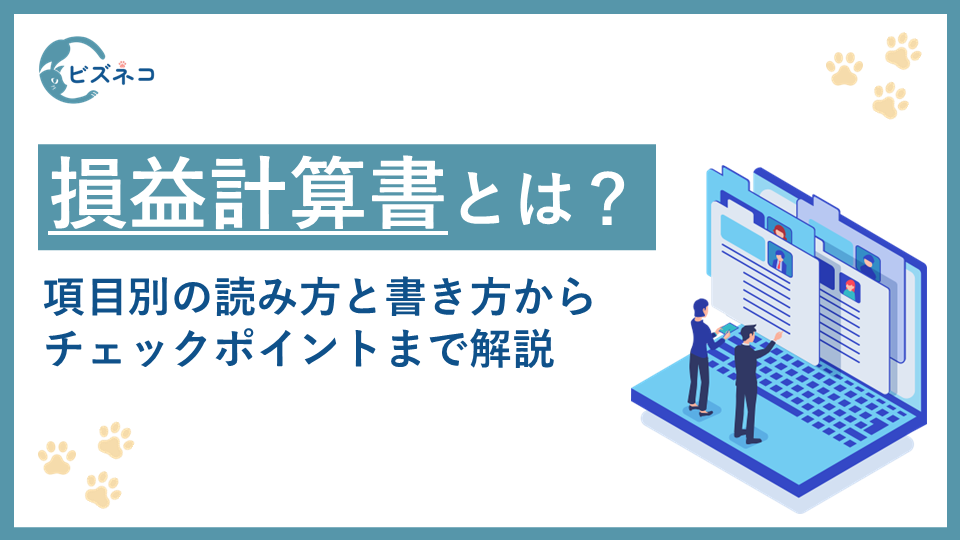
貸借対照表とキャッシュフロー計算書の違い
貸借対照表とキャッシュフロー計算書は、いずれも財務三表に含まれますが、視点が異なります。貸借対照表は期末時点の資産・負債・純資産を一覧できるのに対し、キャッシュフロー計算書は期間中の現金や預金の増減理由を示します。
例えば、利益が出ていても貸借対照表だけでは資金繰りの実態が分かりませんが、キャッシュフロー計算書を見れば、営業活動や投資活動、財務活動による資金の動きが把握できます。両者を併せて分析することで、利益と資金のバランスや企業の健全性をより正確に判断が可能になります。
なお、キャッシュフロー計算書については以下の記事で解説しています。
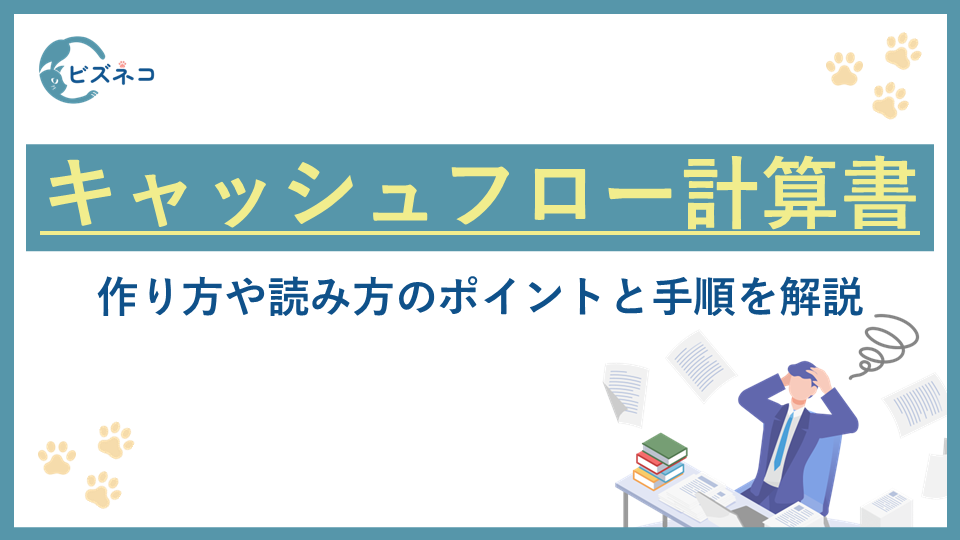
貸借対照表の構成における3つの種類
貸借対照表は、資産・負債・純資産の3つの種類から成り立ち、企業の財政状態をひと目で把握できる形で構成されています。資産の部は会社が持っている財産、負債の部は他人から調達した資金、純資産の部は返済義務のない自己資本を示します。
【左側】資産の部
資産の部は、企業が保有しているすべての財産を示し、貸借対照表の左側に配置されます。ここには現金や売掛金といった短期間で現金化できる資産から、土地や建物など長期的に保有する資産までが含まれます。
例えば、製造業では原材料や完成品の在庫も資産に計上されます。資産の部は流動資産、固定資産、繰延資産の3分類に分かれ、保有期間や流動性の違いによって整理されます。これにより、企業がどのような形で財産を保持し、事業活動を支えているのかがわかります。
流動資産
流動資産は1年以内に現金化される資産を指し、日常的な資金繰りや事業運営の基盤となります。例えば、現金・預金、売掛金、商品在庫などが該当します。流動資産は短期間で現金化できるため、企業の支払能力や運転資金の余裕度を判断する重要な要素です。
流動資産は貸借対照表の資産の部の上部に表示され、経営者や投資家にとっては企業の短期的な財務健全性を確認する手掛かりとなります。そのため、内容や金額の変化は継続的に把握しておく必要があります。
固定資産
固定資産は1年以上にわたり事業活動に使用される資産を指し、生産やサービス提供の基盤を形づくります。例えば、土地、建物、機械設備などが含まれます。これらはすぐに現金化されることは少ないものの、企業活動を継続するうえで欠かせない存在です。
定資産は有形・無形に分類され、有形には工場や車両、無形には特許権やソフトウェアなどがあります。貸借対照表では流動資産の下に表示され、長期的な投資や成長戦略を反映する項目として重要視されます。
繰延資産
繰延資産は、支出した金額を将来の利益獲得にわたって配分するために計上する資産です。例えば、会社設立時の開業費や社債発行費が該当します。
繰延資産は現金や物的資産のように直接形として残らないものの、一定期間にわたり効果を発揮するため、費用を一度に計上せず、期間按分して処理します。貸借対照表では固定資産の下部に表示され、特殊な性質を持つため、企業の会計方針や事業の活動内容を把握するうえで参考になる項目です。
【右側】負債の部
負債の部は、企業が他者から借り入れた資金や将来支払う義務のある金額を示し、貸借対照表の右側上部に配置されます。負債には短期的に返済が必要な流動負債と、長期的に返済する固定負債があります。
例えば、買掛金や短期借入金は流動負債、社債や長期借入金は固定負債に分類されます。負債の部は、資金の調達方法や返済スケジュールを明確にする役割を持ち、企業の財務リスクや資金繰りの安定性を判断するための重要な情報源となります。
流動負債
流動負債は、1年以内に返済または支払義務が生じる負債を指します。例えば、買掛金、未払金、短期借入金、未払費用などが含まれます。流動負債は日常的な取引や短期的な資金調達に伴って発生し、企業の運転資金に影響します。
流動負債の額や構成は、短期的な支払能力や資金繰りの安定度を測る指標として重要です。貸借対照表では負債の部の上段に表示され、流動資産とのバランスを見ることで、企業の短期的な財務上の健全性を判断する手掛かりになります。
固定負債
固定負債は、返済期限が1年を超える負債を指し、長期的な資金調達の結果として計上されます。例えば、長期借入金、社債、退職給付引当金などがこれに含まれます。
固定負債は企業の成長投資や大型設備の購入資金として活用されることが多く、短期的な資金繰りへの影響は少ない一方、長期的な返済負担を伴います。固定負債は貸借対照表の負債の部の下段に表示され、企業の財務構造や将来の資金負担を理解するうえで重要な指標となります。
【右側】純資産の部
純資産の部は、企業が保有する資産のうち負債を差し引いた残りの部分で、返済義務のない自己資本を示します。例えば、資本金や利益剰余金、その他の包括利益累計額などが該当します。
純資産は企業の安定性や将来の成長余力を表す重要な項目であり、投資家や金融機関にとっては経営基盤を評価する指標となります。貸借対照表では負債の部の下に表示され、資産=負債+純資産の関係を成立させる構成要素として、財務諸表全体のバランスを保つ役割を担っています。
貸借対照表の見方と分析方法
貸借対照表の見方として、以下のような分析方法があります。
- 流動資産・流動負債分析
- 流動比率分析
- 当座比率分析
- 自己資本比率分析
- 自己資本利益率分析
- 固定比率分析
- 負債比率分析
ここでは、それぞれの見方や分析方法について詳しく解説します。
流動資産・流動負債分析
流動資産・流動負債分析は、企業の短期的な支払能力や資金繰りの健全性を把握するための基礎となります。流動資産は1年以内に現金化できる資産であり、例えば現金、預金、売掛金、商品在庫などが含まれます。
一方、流動負債は1年以内に返済すべき義務であり、買掛金や短期借入金などが該当します。流動資産・流動負債の両者を比較することで、短期的な資金余裕度を判断できます。流動資産が流動負債を上回っていれば、返済能力に余裕があるといえ、反対に下回る場合は資金繰りに注意が必要です。
流動比率分析
流動比率分析は、企業の短期的な支払能力を数値化して判断する方法です。流動比率は、下記の計算式で導くことができます。
- 流動比率(%)=流動資産÷流動負債×100
例えば、流動資産が1,200万円で流動負債が800万円の場合、流動比率は150%となり、短期的な返済余力が比較的高いと評価できます。一般的に100%以上が望ましいとされますが、業種や取引条件によって適正水準は異なります。そのため、単一の数値だけで判断せず、過去との比較や他社とのベンチマークも行うことが重要です。
当座比率分析
当座比率分析は、在庫のようにすぐ現金化できない資産を除いた、より厳格な短期支払能力を測る指標です。当座比率は、下記の計算式で求められます。
- 当座比率(%)=当座資産÷流動負債×100
例えば、現金や預金、売掛金、有価証券などが当座資産にあたります。この比率が高いほど、短期間で返済に充てられる資金が多いことを示します。一般的な目安は100%以上とされますが、業種特性や在庫回転率により適正水準は異なります。流動比率と併せて分析することで、資金繰りの安全性をより精密に把握できます。
自己資本比率分析
自己資本比率分析は、企業の総資産に占める自己資本の割合を測り、財務の安定性を評価する方法です。自己資本比率は、下記の計算式で導きます。
- 自己資本比率(%)=自己資本÷総資産×100
例えば、総資産が5,000万円で自己資本が2,000万円の場合、この比率は40%となります。高い比率は借入依存度が低く、経営の安定性が高いことを示します。一方で、低すぎる場合は返済負担や金利リスクが増加します。業種や成長段階によって望ましい水準は異なるため、単純比較ではなく複合的な分析が必要です。
自己資本利益率分析
自己資本利益率分析は、株主から預かった自己資本をどれだけ効率的に利益へ変えているかを測定する指標です。自己資本利益率(ROE)は、下記の計算式で求められます。
- 自己資本利益率(%)=当期純利益÷自己資本×100
例えば、自己資本が3,000万円で当期純利益が300万円の場合、ROEは10%となります。高いROEは資本を効率的に活用していることを示しますが、過剰な負債による一時的な押し上げもあるため注意が必要です。他の指標と組み合わせて、収益性と財務健全性のバランスを確認することが重要です。
固定比率分析
固定比率分析は、固定資産を自己資本でどの程度まかなえているかを示し、長期的な財務の安定性を判断します。固定比率は、下記の計算式で求められます。
- 固定比率(%)=固定資産÷自己資本×100
例えば、固定資産が4,000万円で自己資本が3,000万円の場合、固定比率は133%となり、自己資本だけでは固定資産を賄えず負債に依存している状態です。100%以下が望ましいとされますが、成長投資の段階では一時的に高くなることもあります。長期的な資本構成を評価するうえで欠かせない指標です。
負債比率分析
負債比率分析は、自己資本に対してどの程度の負債を抱えているかを示し、財務リスクの大きさを測ります。負債比率は、下記の計算式で導きます。
- 負債比率(%)=負債÷自己資本×100
例えば、負債が6,000万円で自己資本が3,000万円の場合、この比率は200%となり、負債依存度が高い状態です。比率が高いと返済や利息負担が経営を圧迫するリスクがありますが、適度な借入は成長資金として有効です。業種や経営方針に応じた適正水準を見極めることが大切です。
まとめ
貸借対照表(B/S:バランスシート)とは、企業の財政状態を一定時点で示す財務諸表です。左側に資産、右側に負債と純資産を記載し、全体のバランスから企業の安定性や支払い能力を把握できます。
貸借対照表は過去の取引結果を積み上げた姿であり、損益計算書のように期間の収益や費用を示すものではありません。経営判断や融資審査など、多くの場面で基礎となる資料として活用されます。なお、貸借対照表や経理業務でお困りの際は、経理代行会社に相談することもおすすめです。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
貸借対照表(バランスシート)に関するよくあるご質問
貸借対照表(バランスシート)についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、貸借対照表(バランスシート)に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
貸借対照表はいつ作るのですか?
貸借対照表は、通常は決算時に作成します。企業では会計年度末に合わせて作るのが一般的ですが、四半期や月次で作成する場合もあります。経営状況を早期に把握したい場合や金融機関への提出が必要なときには、中間期にも作成します。作成時点の資産や負債、純資産の状況を正確に示すため、最新の取引記録を基に作成します。
貸借対照表の作り方のポイントは何ですか?
貸借対照表を作る際のポイントは、資産・負債・純資産を正確に分類し、必ず貸方と借方の合計が一致するように整理することです。資産の部では現金や売掛金、負債の部では買掛金や借入金を正しい金額で記載します。また、期末残高を基に作成するため、帳簿や明細との突合を行い、計上漏れや誤計上がないかを確認しましょう。
貸借対照表の作成はどのような手順で行いますか?
貸借対照表の作成は、まず帳簿から期末時点の資産・負債・純資産の残高を集計することから始まります。次に、それらを決められた区分ごとに整理し、資産なら流動資産・固定資産に分け、負債は流動負債・固定負債に分類します。その後、金額を貸方と借方に振り分け、形式に沿って清書し、決算書の一部として完成させます。




