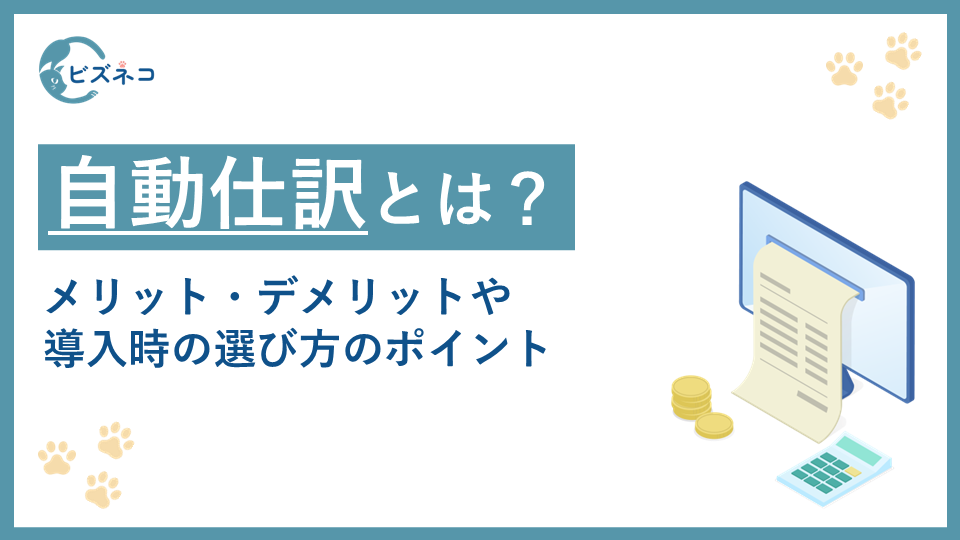
現在では、経理の業務もペーパーレス化やIT化が進んでいます。会計システムのなかには、自動仕訳が搭載されているものもあるため、記帳や仕訳の業務を効率化することができます。しかし、自動仕訳がどういう仕組みであるかわからないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、自動仕訳の仕組みやルールとメリット・デメリットについて詳しく解説します。また、会計システムを導入する際の選び方のポイントも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
自動仕訳とは?
自動仕訳とは、日々の取引データをもとに、会計ソフトなどが仕訳の処理を自動で行ってくれる仕組みのことを指します。例えば、クレジットカードでの経費精算や銀行口座の入出金情報が取り込まれると、内容に応じた勘定科目や金額が自動的に判別され、仕訳帳に記録されるという流れで進みます。
従来であれば担当者が一つひとつの取引内容を確認し、仕訳を手入力していた作業が省略されるため、業務の効率化や人的ミスの防止につながります。また、自動仕訳機能はクラウド型の会計システムなどに多く搭載されており、リアルタイムでの情報反映やデータ連携も可能になる点がメリットです。そのため、会計処理のスピードと正確性を求められる現代の業務環境において、自動仕訳は有効な仕組みといえるでしょう。
自動仕訳のルールと仕組み
自動仕訳の仕組みは、取引情報をもとに会計システムが仕訳処理を自動化するものです。あらかじめ設定された区分や勘定科目、過去の仕訳データをAIが学習し、それに基づいて分類と記録を行います。
自動仕訳のルールと具体的な流れは以下のとおりです。
- 1:仕訳をおこなう
- 2:内容をチェックする
- 3:問題がなければ登録する
- 4:次回に同様の取引が発生した際はAIが前回と同様に処理する
- 5:仕訳に誤りがあれば修正してAIが学習する
- 6:学習を繰り返す
- 7:仕訳の精度が向上していく
例えば、同じ取引先からの振込が毎月ある場合、初回に適切な仕訳を設定すれば、次回からはAIが自動で対応してくれるようになります。こうして手作業による仕訳の負担が減り、より効率的な経理業務が実現できます。
自動仕訳のメリット
経理において自動仕訳のメリットとして以下のような点があげられます。
- 仕訳入力の手間を削減できる
- 入力における人的ミスを防止できる
- ペーパーレス化でコスト削減になる
- AIで不正を事前に検知できる
- 経理の未経験者でも仕訳ができる
ここでは、それぞれのメリットについて具体的に解説していきます。
仕訳入力の手間を削減できる
自動仕訳を導入するメリットのひとつが、日々の仕訳入力作業を大幅に削減できる点です。例えば、銀行取引やクレジットカードの明細が会計ソフトと連携していれば、取引内容を自動で取り込み、勘定科目まで自動で判別して仕訳してくれます。
これにより、経理担当者の方が一件一件手動で入力する手間が省かれ、時間的にも精神的にも負担が軽くなります。また、繰り返し発生する取引に対しては一度ルールを設定すれば、その後はほとんど確認だけで済むようになるため、業務全体の効率化につながります。
さらに、月末月初の集中処理の負荷も軽減でき、繁忙期でも安定した経理業務が可能になります。全体的な作業時間の短縮によって、ほかのコア業務にも注力できるようになる点は魅力です。
入力における人的ミスを防止できる
手作業による仕訳入力では、どうしても数字の打ち間違いや勘定科目の選択ミスといった人的ミスが避けられません。しかし、自動仕訳を活用すれば、そのような入力ミスを大幅に防ぐことができます。
例えば、毎月決まった請求書の処理を自動化すれば、毎回同じ仕訳内容が自動で反映されるため、確認作業だけで済みます。AIが過去の正しい仕訳ルールを学習していくことで、精度も徐々に高まり、ヒューマンエラーの発生率が低下します。
結果として、帳簿の正確性が向上し、後からの修正や確認の手間も減るでしょう。ミスや間違いを未然に防げる体制が整えば、決算や監査の場面でも安心感が高まり、経理部門の信頼性向上にもつながります。
ペーパーレス化でコスト削減になる
自動仕訳はデジタルデータを活用するため、従来の紙ベースでの処理が不要になり、ペーパーレス化を推進できます。例えば、紙の領収書や請求書をスキャンして会計システムに取り込めば、そのまま仕訳処理が行われ、物理的な書類の保管や整理の手間がなくなります。
これにより、紙代や印刷代だけではなく、書類を保管するスペースやファイリング作業にかかる人件費も削減可能です。環境面への配慮と同時に、業務のコストパフォーマンスも高められる点が、企業にとってメリットになります。
さらに、クラウド型の会計システムと連携すれば、物理的な資料の郵送や回覧も不要となり、支店や各地の拠点での情報共有や承認業務もスムーズに行えるようになります。
AIで不正を事前に検知できる
自動仕訳には、AIによる不正検知機能が搭載されていることも多く、経理処理に潜む異常を早期に察知できるというメリットがあります。例えば、通常の支払いパターンと異なる金額や、過去に使用されていない勘定科目が使われている場合など、AIが違和感を覚えた取引に対してアラートを出すことがあります。
このようにして、ミスや不正の兆候を初期段階で把握できれば、重大なトラブルを未然に防ぐことが可能になります。単なる作業の自動化だけでなく、リスク管理にもつながる点が、自動仕訳の価値といえるでしょう。また、過去には気づかなかった経費の重複計上や不自然な支出の傾向なども、AIによって見える化することもできます。
経理の未経験者でも仕訳ができる
自動仕訳の導入により、経理の専門知識がない人でもスムーズに仕訳作業を行えるようになります。例えば、現場担当者が経費を登録する際でも、領収書の画像や取引内容を入力すれば、システムが自動的に勘定科目を判断し、仕訳まで完了させてくれます。
そのため、これまで経理部門に頼らざるを得なかった業務の一部が分担でき、業務効率の向上にもつながります。属人化の解消や、業務の標準化を図るうえでも、自動仕訳は有効な手段といえるでしょう。
特に、スタートアップ企業や小規模な組織にとっては、限られた人員で経理業務をカバーする際にも役立ち、安定した業務運営の実現につながるでしょう。
自動仕訳のデメリット
経理分野の自動仕訳にも以下のようなデメリットがあるため注意しましょう。
- 会計システムの導入作業が面倒くさい
- 情報漏洩の恐れがある
- 手動で記帳作業が発生する場合もある
- 業務フローの見直しが必要になる
- 人による最終確認は必要になる
ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。
会計システムの導入作業が面倒くさい
自動仕訳を利用するには、会計システムの導入が必要ですが、初期設定や導入作業に手間がかかる点はデメリットといえます。例えば、既存の業務ソフトとの連携設定や、勘定科目のマッピング、取引先情報や取引ルールの登録といった作業には多くの時間と労力がかかります。
また、社員への操作研修やマニュアル整備も必要になるため、短期的にはかえって業務負担が増えるケースもあるでしょう。システム選定の段階でも、どの製品が自社に最適かを比較と検討をしなければならず、その過程で判断が難航することもあります。
特に、ITリテラシーが高くない企業では、導入のハードルが高く感じられるかもしれません。結果として、導入を先延ばしにしてしまう企業も少なくないため、自社にあった会計システムの選定が求められます。なお、クラウド型の会計システムのメリット・デメリットについてはこちらの記事も参考にしてください。
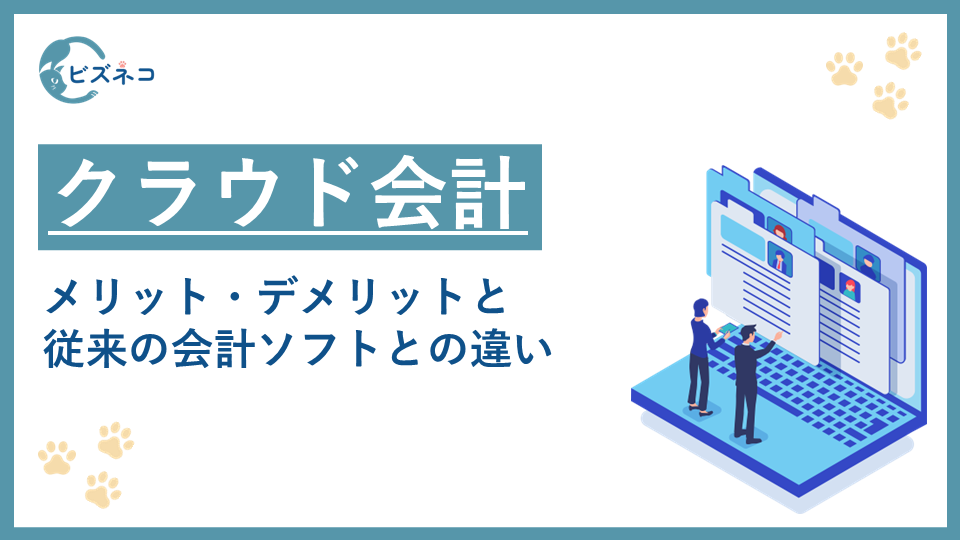
情報漏洩の恐れがある
自動仕訳を支える会計システムの多くは、クラウド上で取引データを管理しています。そのため、セキュリティ対策が万全でない場合、情報漏洩のリスクが存在します。
例えば、社内でのアクセス管理が適切に行われていない場合や、パスワードの管理がずさんだった場合、不正アクセスにより顧客情報や取引データが外部に漏れる可能性があります。また、サイバー攻撃やシステム障害といった外的リスクも無視できません。
特に、会計データは企業の重要な機密情報であり、漏洩すれば信用を失い、損害賠償につながる恐れがあります。そのため、自動仕訳が便利な一方で、セキュリティ面への十分な配慮と継続的な対策は欠かせません。便利さとリスク管理をどう両立するかが、導入時の大きな課題となるでしょう。
手動で記帳作業が発生する場合もある
自動仕訳は多くの業務を効率化できる一方で、すべての取引が完全に自動化されるわけではありません。例えば、新規の取引先やイレギュラーな取引、経費の立替精算など、ルールが未登録のケースでは、仕訳の自動処理が行えず、手動で記帳作業を行う必要が生じます。
また、AIの判断が間違っている場合には、人の手で修正を加えなければなりません。こうした例外的な対応は、業務全体の効率を下げる要因にもなってしまいます。さらに、法令改正や勘定科目の変更があった場合には、自動仕訳ルールの見直しや再設定も求められます。
そのため、自動仕訳は万能ではなく、常に人の関与が必要になるという点を理解しておく必要があります。完全に自動だと思い込んでしまうと、かえって業務に支障をきたす恐れもあるので注意しましょう。
業務フローの見直しが必要になる
自動仕訳を導入する際には、これまでの経理業務の流れを見直す必要があることも大きな課題です。例えば、紙の領収書を使った手作業中心のフローから、データ入力や電子承認を前提としたデジタル業務に移行するためには、現場の理解と協力が必要になります。
部門間での役割分担の変更や、申請と承認のプロセスの再構築も求められることがあり、結果として一時的に混乱を招く可能性があります。また、従来の方法に慣れているスタッフからは抵抗感が生まれることもあり、スムーズな移行には丁寧な説明と時間をかけた調整が必要です。
このように、自動化による効率化の裏側では、既存の業務フローを再設計し、新たな運用体制を整える負担が発生する点に注意が必要です。なお、経理の業務フローについてはこちらの記事も参考にしてください。

人による最終確認は必要になる
自動仕訳は高い精度で仕訳処理を行えるようになってきていますが、それでも完全に人のチェックを省けるわけではありません。例えば、一見同じように見える取引でも、文脈や背景によって勘定科目の選定が異なるケースがあり、AIが誤った判断をすることもあります。
AIのミスが発生する場合に備え、経理担当者が最終的に内容を確認し、適切な修正を加える工程は欠かせません。特に、決算期や監査対応など、正確性が重視される場面では、人的確認の重要性がより高まります。
また、ミスを放置すれば、後々の修正に余計な時間と手間がかかることにもなりかねません。自動化されたからといって「確認しなくても大丈夫」という油断は禁物であり、あくまで人とシステムの役割分担を明確にした運用が求められます。
自動仕訳システム導入における選び方のポイント
自動仕訳システムを導入する際における選び方のポイントとして以下のような点があげられます。
- 自社の業種・業態にあったシステムを選ぶ
- 他システムとの連携できるシステムを選ぶ
- 担当者が操作しやすいシステムを選ぶ
- 月額コストと機能のバランスでシステムを選ぶ
ここでは、それぞれのポイントを具体的に紹介します。
自社の業種・業態にあったシステムを選ぶ
自動仕訳システムを選定する際には、まず自社の業種や業態に適した機能を備えているかを確認することがポイントです。例えば、製造業であれば仕掛品や原価計算に対応しているか、小売業であれば多店舗展開に対応した仕訳処理が可能かなど、業種特有の会計処理に柔軟に対応できるかどうかが判断のポイントになります。
また、医療や福祉などのように特有の勘定科目や補助科目が存在する業界では、汎用的な会計ソフトでは対応しきれないケースもあるため、業界特化型のシステムを選ぶことが望ましいでしょう。
導入後にカスタマイズが困難な場合、運用上の不便が大きなストレスになるため、最初の選定段階で自社の業務にどれだけあっているかを見極めることが成功につながります。
他システムとの連携できるシステムを選ぶ
自動仕訳システムの選定では、他の業務システムとの連携性が高いかどうかも非常に重要なポイントです。例えば、経費精算システムや販売管理ソフト、請求書発行ツールなど、日常的に利用している業務アプリケーションとスムーズにデータをやり取りできる環境が整っていれば、仕訳入力の自動化や二重入力の防止が実現できます。
反対に、連携がうまく取れないシステムを選んでしまうと、データの手動転記やエクスポート作業が増え、かえって業務効率が低下するおそれもあります。特にクラウドサービスを中心に運用している企業では、API連携がスムーズであることや、標準連携先の多さが大きな判断材料になります。
日々の業務の中でストレスなく活用できるかを、システム間の相性も含めてしっかり確認しておきましょう。なお、経費精算システムの選び方についてはこちらの記事も参考にしてください。
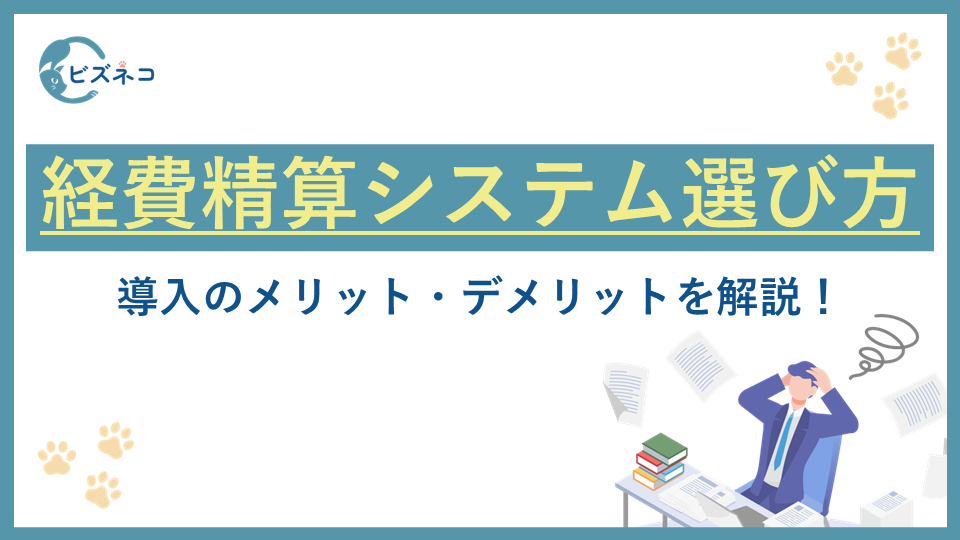
担当者が操作しやすいシステムを選ぶ
担当者が操作しやすいシステムを選ぶことも大切なポイントです。どれだけ高性能な自動仕訳システムであっても、実際に使う担当者が使いにくいと感じてしまえば、効果は半減してしまいます。
例えば、画面構成が複雑で必要な機能にたどり着くのに時間がかかってしまう場合や、専門用語ばかりで直感的に理解しづらいインターフェースでは、日常業務でストレスがたまりがちです。経理に慣れていない社員でも扱える設計か、マニュアルやサポートが整っているか、などの観点で実際に操作してみることが重要です。
多くの自動仕訳システムや会計ソフトでは、無料トライアル期間を設けているため、その期間中に操作性をしっかりチェックしましょう。また、スマートフォンやタブレットでも利用できるかどうかといった点も、在宅勤務や外出先での業務を想定する企業にとっては見逃せない選定基準となります。
月額コストと機能のバランスでシステムを選ぶ
自動仕訳システムの導入にあたっては、月額コストと提供される機能のバランスが取れているかを慎重に見極める点もポイントです。例えば、低価格なプランでも基本的な自動仕訳機能が使えれば十分というケースもあれば、部門別管理や経営分析機能まで求める企業では、ある程度のコストをかける価値があります。
重要なのは、自社の業務規模や運用体制に対して、過不足のない機能構成であるかという点です。高機能だからといって使わない機能が多ければ、コストパフォーマンスは下がりますし、逆に安すぎて必要な機能がなければ運用に支障をきたす可能性もあります。
クラウド型システムでは利用人数に応じて課金されるものも多いため、将来的な拡張性も考慮しながら慎重に選びましょう。
まとめ
自動仕訳とは、日々の取引データをもとに、会計ソフトなどが仕訳の処理を自動で行ってくれる仕組みのことを指します。自動仕訳があることで、入力における人的ミスを減らし、ペーパーレスでコスト削減につながる点がメリットです。また、経理の未経験者でも仕訳ができることも魅力といえるでしょう。
一方で、自動仕訳にはデメリットもあります。そもそもの会計システムの導入が大変である点や、手動での記帳作業が発生してしまうこともあります。加えて、人による最終確認が必要になる点も心得ておきましょう。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
自動仕訳に関するよくあるご質問
自動仕訳についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、自動仕訳に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
自動仕訳とは何ですか?
自動仕訳とは、各種取引データや外部システムの情報をもとに、会計ソフトなどが仕訳を自動的に作成する仕組みのことです。これまで経理担当者が取引内容を確認し、勘定科目や金額を手動で入力していた作業を省略できるため、作業の効率化やミスの削減が期待されます。また、ルールに従った処理で精度向上にもつながります。
自動仕訳ルールとは何ですか?
自動仕訳ルールとは、特定の取引パターンに対して、どのような勘定科目や補助科目を使って仕訳を自動作成するかをあらかじめ定義した設定です。経費精算や毎月の支払いなど、繰り返し発生する取引を自動で仕訳できます。ルールを適切に設定することで、正確で効率的な会計処理が可能になります。
自動仕訳のメリットは何ですか?
自動仕訳のメリットには、業務効率化、入力ミスの防止、業務の属人化回避などがあります。ルールに従って機械的に処理するため、担当者ごとの判断差やミスを防げます。また、大量の仕訳を一括処理できるため、決算期の業務負荷を軽減できる点もメリットです。さらに、自動化により経理担当者がコア業務に注力できます。




