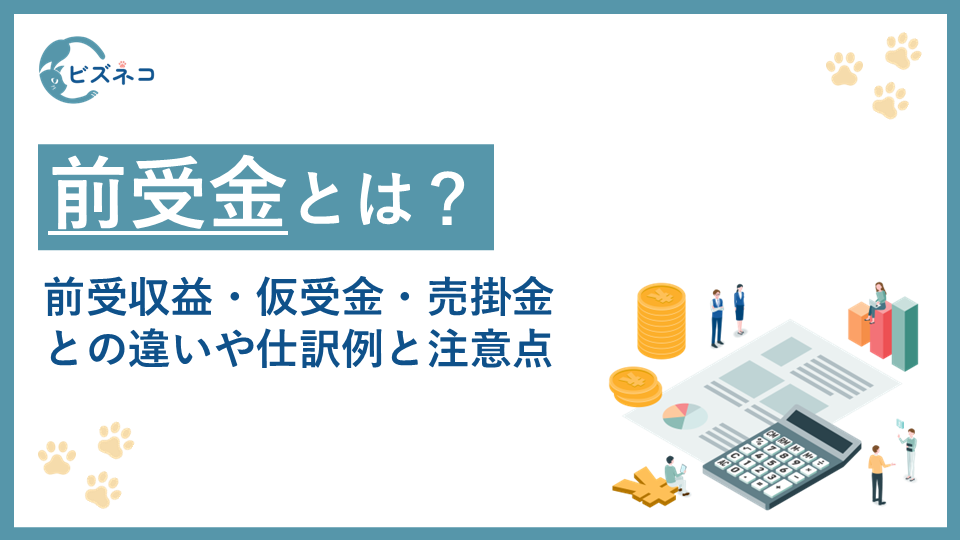
前受金は、取引先から商品やサービスを提供する前に受け取った代金を指し、会計上は「負債」として扱われます。予約販売や前払い契約などで一時的に現金を受け取る場面が典型的です。ただし、前受金は収益とは異なり、まだ取引が完了していないため売上には計上できません。この点を理解していないと、誤って損益を操作してしまう恐れがあります。
また、前払金や仮受金、前受収益など、似た性質を持つ勘定科目と混同しやすい点も注意が必要です。本記事では、前受金の基礎知識から仕訳例、前受収益・仮受金・売掛金・預り金との違いをまとめています。
目次
前受金とは?
前受金とは、将来の取引を前提として一時的に受け取ったお金を処理するための勘定科目です。まだ商品を引き渡していない、あるいはサービスを提供していない段階で受領した代金であるため、企業の立場から見ると収益ではなく未履行の約束に基づく一種の義務となります。
例えば、イベントのチケット代を事前に受け取った場合、その入金は直ちに売上に計上されるのではなく、前受金として区分されます。このように、前受金は取引が完了して初めて収益に振り替えられる性質を持つため、正しいタイミングで処理を行うことが求められます。
前受金は「負債」で扱う
前受金は、会計処理において「負債」として分類されます。商品やサービスをまだ提供していない段階で代金を受け取っているため、企業にとっては一時的に返すべき義務を負っている状態とみなされるからです。
例えば、旅行会社が旅行代金を事前に受け取った場合、その代金は旅行が実施されるまで収益とは認められず、前受金として処理されます。こうした考え方を理解していないと、売上の計上時期を誤り、利益が過大に表示されるなどの問題を引き起こしかねません。
前受金と対になる勘定科目は「前払金」
前受金と対をなす勘定科目として「前払金」があります。両者は性質が似ていますが、企業の立場によって処理が反対になる点に特徴があります。前受金は企業が先に受け取ったお金を表すのに対し、前払金は企業が取引先に先に支払ったお金を表します。
例えば、オフィス賃料を数ヵ月分まとめて払った場合は前払金として処理され、時間の経過に応じて費用へ振り替えられます。一方、同じ契約において貸主側が受け取った金額は前受金として扱われます。このように、どちらも取引が未完了の段階で生じる資金の動きを示す点で共通しており、資産か負債かという違いを見極めることが重要です。
前受金と間違えやすい勘定科目
前受金と間違えやすい勘定科目として「前受収益」「仮受金」「売掛金」「預り金」があります。以下の表ではそれぞれの特徴をまとめています。
| 勘定科目 | 分類 | 概要 |
|---|---|---|
| 前受金 | 負債 | 商品やサービスを提供する前に受け取った代金を処理する科目 |
| 前受収益 | 負債 | 将来の収益に振り替えるべき金額を示す科目 |
| 仮受金 | 負債 | 入金の内容が未確定な場合に一時的に処理する科目 |
| 売掛金 | 資産 | 商品やサービスを提供済みで代金をまだ受け取っていない場合に計上する科目 |
| 預り金 | 負債 | 税金や社会保険料など他人のために一時的に預かっているお金を処理する科目 |
前受収益
前受収益は「収益の前倒し」で発生する勘定科目で、分類上は負債にあたります。前受金と同様にまだ提供していないサービスや商品に対して代金を受け取った際に使われますが、性質としては将来に収益化される金額を表しています。
例えば、雑誌の年間購読料を事前に受け取った場合、その代金はすぐに売上とせず、前受収益として処理されます。前受金と混同しやすいですが、前受金が主に金銭の受領を示すのに対し、前受収益は損益計算書に関連して収益の認識を調整する意味を持つ点で違いがあります。
仮受金
仮受金は「処理未確定の一時的なお金」を示す勘定科目で、分類は負債です。入金の内容がまだ特定できない場合に暫定的に計上されるため、最終的には正しい勘定科目に振り替える必要があります。
例えば、取引先からの振込に金額の記載はあるが、どの売掛金に対応するかが不明なとき、まずは仮受金として処理します。前受金と異なり、取引条件に基づいてあらかじめ受け取ったものではなく、内容未確定の入金である点が特徴です。放置すると残高が増えて決算に影響するため、速やかに処理することが求められます。
売掛金
売掛金は「まだ受け取っていない代金」を表し、分類は資産です。商品やサービスを提供したにもかかわらず、代金の回収が後日となる場合に計上されます。
例えば、卸売業で商品を納品し、代金は翌月末払いとする契約を結んだとき、その代金は売掛金として処理されます。前受金が将来の取引に対して先に受け取ったお金を負債として扱うのに対し、売掛金は既に提供が完了しているものの代金をまだ受け取っていないため資産となる点で正反対です。
なお、売掛金については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

預り金
預り金は「他人から一時的に預かっているお金」を意味し、分類は負債に含まれます。企業が自社の収益として自由に使えるものではなく、特定の目的に従って処理しなければならない性質があります。
例えば、給与から天引きした所得税や社会保険料は従業員に代わって企業が預かっているお金であり、預り金として計上されます。前受金と同じく負債に分類されますが、前受金が取引先との契約に基づく入金であるのに対し、預り金は税金や保険料など他者のために管理している資金という点で性質が異なります。
なお、その他の勘定科目についてはこちらの記事を参考にしてください。
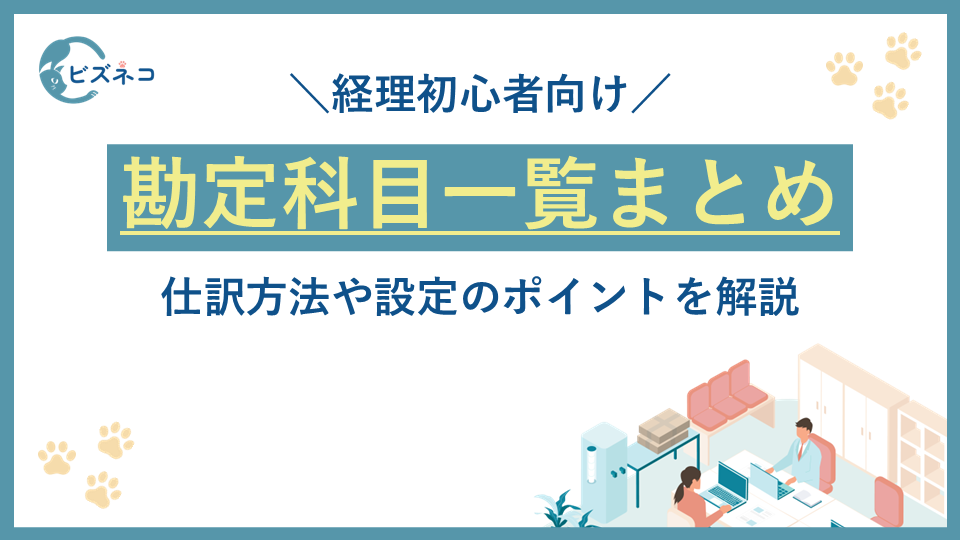
前受金の仕訳例
前受金を正しく処理するためには、取引の流れに応じた仕訳を理解しておくことが欠かせません。前受金は代金を受け取った時点では負債として扱われ、商品やサービスを提供した時点で初めて売上に振り替えられます。例えば、将来の商品納品に先立って代金を受け取る場合、次のような仕訳になります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 300,000 | 前受金 | 300,000 |
その後、商品やサービスの提供が完了した時点で、前受金を売上に振り替えます。例えば、1か月後に商品を納品した場合は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前受金 | 300,000 | 売上 | 300,000 |
このように、受領時と提供完了時で異なる仕訳を行うことが正しい収益認識につながり、決算書の信頼性を確保するポイントとなります。
前受金を見分けるポイント
前受金は似た勘定科目と混同されやすいため、仕訳や決算処理の正確性を保つには見極めが重要です。分類や損益への影響を手掛かりに判断することで、誤った処理を防ぐことができます。ここでは、前受金を見分けるポイントについて詳しく解説します。
勘定科目が「資産」か「負債」で考える
前受金を判別する際には、その勘定科目が資産なのか負債なのかを確認することが基本となります。前受金は提供前に代金を受け取っているため、将来的に商品やサービスを引き渡す義務がある点から負債として扱われます。
例えば、売掛金は提供済みで代金を回収していない資産であり、前払金は代金を先に支払った資産です。これに対し、前受金は「先に受け取った代金」という性質上、返還義務や履行義務が生じるため負債に分類されます。このように資産か負債かを意識して確認することで、前受金と類似科目を整理して判断でき、仕訳の正確性を確保することができます。
勘定科目が損益に影響するかを考える
前受金を見分けるもうひとつの視点は、勘定科目が損益に直結するかどうかです。前受金は提供が終わるまで収益に計上されないため、損益計算書には影響を与えません。例えば、売上は商品やサービス提供時に損益へ反映されますが、前受金はその前段階にあるため、一時的に貸借対照表の負債として記録されます。
一方で、前受収益も同じく負債に属し、将来的に収益として認識される性質を持ちます。損益に関与するかどうかを意識することで、勘定科目を正しく切り分けることができ、財務諸表の信頼性を損なう処理のミスを防げます。
前受金が用いられる主な帳簿一覧
前受金が用いられる主な帳簿を以下の一覧表にまとめました。
| 帳簿名 | 概要 |
|---|---|
| 前受金元帳 | 前受金の入金や消込を取引ごとに管理する帳簿 |
| 債権元帳 | 売掛金や前受金を取引先ごとに整理する帳簿 |
| 前受残高一覧表 | 前受金の残高を取引先別に集計した帳簿 |
| 債権残高一覧表(売掛金残高一覧表) | 未回収の売掛金残高を一覧化した帳簿 |
| 入金予定一覧表 | 将来の入金予定額や時期をまとめた帳簿 |
| 売掛金年齢表 | 売掛金を経過日数ごとに区分して管理する帳簿 |
ここでは、それぞれの帳簿について詳しく解説します。
前受金元帳
前受金元帳は、前受金の入金や消込を詳細に管理するための帳簿です。前受金は一時的に負債として計上され、提供完了時に売上に振り替えられるため、個別の取引ごとに残高を明確に把握する必要があります。
例えば、複数の顧客からそれぞれ先に代金を受け取った場合、どの顧客の分がまだ未消化なのかを前受金元帳で確認できます。前受金元帳があることで、返金が発生した際や、売上計上のタイミングを正確に判断する際の根拠となり、決算や監査の場面でも信頼性を高める役割を果たします。
債権元帳
債権元帳は、売掛金や前受金といった取引先ごとの債権や債務の動きを整理するための帳簿です。取引が複雑になると、どの入金がどの売掛金や前受金に対応するのかを明確にしなければ、正しい残高管理ができなくなります。
例えば、同じ取引先から複数の契約に基づいて入金があった場合、それぞれを区分して記録することで、未回収分や未消化分がひと目で把握できます。債権元帳を利用することで、回収状況や前受金の残高を体系的に管理でき、資金繰りや与信管理の精度を高める効果も期待できます。
前受残高一覧表
前受残高一覧表は、各取引先ごとの前受金残高をまとめて把握するために用いられる帳簿です。前受金は提供完了まで売上に振り替えられないため、どの取引先にどの程度の前受金が残っているのかを整理することが欠かせません。
例えば、ある顧客に対して継続的にサービスを提供する契約を結んでいる場合、その前受金の消化状況を一覧表で確認できます。前受残高一覧表があれば、返金リスクの把握や売上計上時期の見通しを立てやすくなり、取引全体の進捗を経理担当者が正確に管理することに役立ちます。
債権残高一覧表(売掛金残高一覧表)
債権残高一覧表(売掛金残高一覧表)は、売掛金など未回収の債権残高を一括して確認するための帳簿です。前受金が未提供分の入金であるのに対し、売掛金は提供済みで未回収の代金を示すため、双方を対比して把握することは資金管理の上で大切です。
例えば、複数の取引先に納品を終えているにもかかわらず、代金がまだ入金されていない場合、その残高を一覧で確認できます。債権残高一覧表は、売掛金の回収漏れを防ぐだけでなく、取引先ごとの信用状況を把握する資料にもなり、経営判断に役立つ帳簿といえるでしょう。
入金予定一覧表
入金予定一覧表は、今後入金が見込まれる金額や時期をまとめる帳簿で、資金繰りの計画を立てる際に欠かせない役割を果たします。前受金や売掛金の消込スケジュールを確認することで、資金の流れを先読みできるようになります。
例えば、月末に大口の売掛金が入金される予定であれば、その資金をどのように運用するかをあらかじめ検討できます。入金予定一覧表を活用することで、急な資金不足を防ぎ、支払計画を安定的に立てられるようになります。そのため、経理業務の中で資金管理を強化するために不可欠な帳簿のひとつといえます。
売掛金年齢表
売掛金年齢表は、売掛金の発生からどの程度の期間が経過しているかを分類して管理する帳簿です。例えば、30日以内、60日以内、90日以上といった区分により、どの取引先の入金が遅れているかを把握できます。これにより、回収リスクの高い売掛金を特定し、対応を早めることが可能となります。
前受金が未提供分の入金を管理するのに対し、売掛金年齢表は未回収の代金を時間軸で管理する点が特徴です。資金繰りの見通しや貸倒れリスクの予測に役立つため、企業にとって重要な管理資料といえるでしょう。
なお、その他の会計帳簿の種類についてはこちらの記事も参考にしてください。
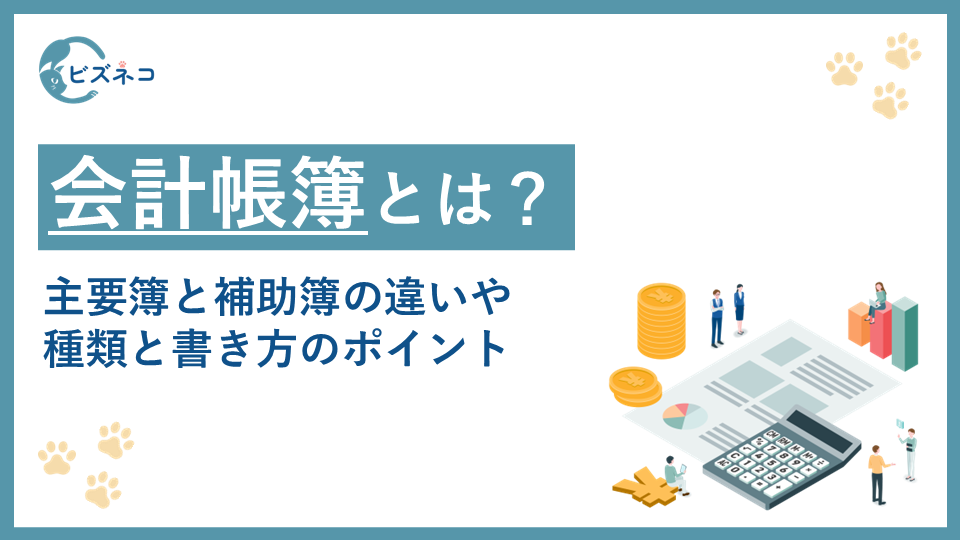
前受金の処理における注意点
前受金は、現金を受け取った時点で売上とならず、将来の取引を見越して計上される性質を持っています。そのため、処理の方法を誤ると利益の計上時期がずれ、税務申告や財務諸表に影響を及ぼす可能性には注意してください。
売上計上は商品やサービス提供後のタイミングになる
売上計上は、商品やサービスを提供した後のタイミングで行うことが正しい処理です。例えば、前受金として顧客から代金を受け取っていても、まだ提供が完了していなければその時点では売上に含めることはできません。
提供が完了した時点で前受金から売上へ振り替えることで、収益認識の原則に沿った適切な会計処理となります。前受金の処理のタイミングを誤ると、期間損益の把握がずれ、経営判断に影響を及ぼす恐れがあるため注意しましょう。
前受金では消費税が課税されない
前受金は、商品やサービスがまだ提供されていないため、消費税の課税対象にはなりません。例えば、契約時に代金を受け取ったとしても、課税が発生するのは実際に商品を引き渡した時点やサービスを提供した時点です。
もし、誤って前受金を課税売上に含めてしまうと、消費税の申告内容に差異が生じてしまいます。その結果、後の修正申告や追徴の対象となる可能性があります。会計処理と税務上の扱いを一致させ、適切に管理することが求められるため注意しましょう。
まとめ
前受金は、商品やサービスの提供前に受け取った代金を処理する勘定科目で、会計上は「負債」に分類されます。売上への振替は提供完了後であり、処理のタイミングを誤ると損益計算に影響が出るため注意が必要です。また、前払金・前受収益・仮受金・売掛金・預り金など、似た科目と混同しやすい点にも気を付ける必要があります。正確な仕訳と帳簿管理を行うことで、財務の信頼性を確保し、経営判断の精度を高めることができます。そのため、経理代行会社や記帳代行会社に相談することもおすすめです。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
前受金に関するよくあるご質問
前受金についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、前受金に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
前受金の勘定科目は何ですか?
前受金は、商品やサービスを提供する前に顧客から受け取った代金を処理するための勘定科目で、会計上は「負債」に分類されます。企業にとって将来提供すべき義務を伴うお金であり、まだ収益ではないためです。例えば、旅行代金を事前に受け取った場合は提供完了まで前受金として処理され、完了後に売上に振り替えられます。
前受金と売掛金の違いは何ですか?
前受金と売掛金は、いずれも取引に関わる勘定科目ですが、性質が正反対です。前受金は商品やサービス提供前に代金を先に受け取るため負債に分類されます。一方、売掛金はすでに商品やサービスを提供済みで、代金を後日受け取る権利を示すため資産に分類されます。前受金は「義務」、売掛金は「請求権」といえます。
前受金は返金されますか?
前受金は本来、将来の商品やサービスの提供で消化されますが、契約が解除された場合や提供が不可能になった場合には返金されることがあります。例えば、イベントのチケット代を前受金とした後にイベントが中止になれば、代金は顧客へ返金しなければなりません。前受金は必ずしも売上にならない点に注意しましょう。




