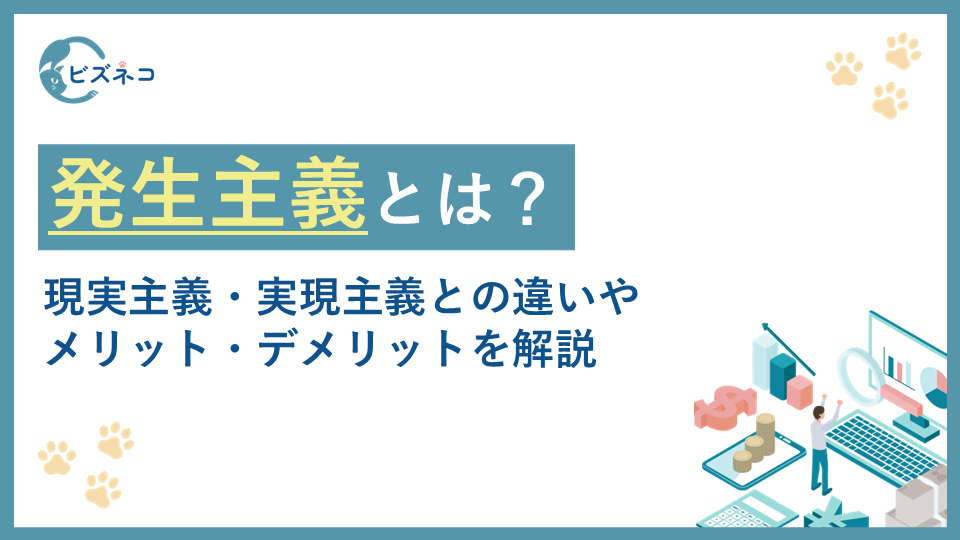
企業の経理処理において重要な考え方のひとつに「発生主義」があります。発生主義は、実際の現金の出入りとは関係なく、取引が発生したタイミングで収益や費用を計上する会計基準です。現金の受け渡しを基準にする「現金主義」や、収益が確実に実現された時点で認識する「実現主義」とは異なる特徴を持ち、期間損益の正確な把握や経営分析に役立つ一方で、記帳の手間や粉飾リスクなどの課題も抱えています。
本記事では、発生主義の基本的な考え方から現金主義や実現主義との違い、導入によるメリット・デメリットを解説します。また、実際の会計処理の流れも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
発生主義とは?
企業の取引を会計帳簿に記録する際、いつ収益や費用を認識するかによって、会計の方法は異なります。その中でも「発生主義」は、現金の受け渡しにかかわらず、取引が発生した時点で会計処理を行う考え方です。
例えば、仕入を行って代金の支払いが翌月になる場合でも、仕入の事実が発生した月に費用として計上します。発生主義により、売上に対応する費用を同じ期間に記録でき、事業の実態をより正確に反映することが可能となります。発生主義は多くの企業で採用されている基準であり、財務諸表の信頼性や比較可能性を高める役割を果たしています。
発生主義・現金主義・実現主義の関係
| 基準 | 収益の認識時点 | 費用の認識時点 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 発生主義 | 発生時(契約・役務提供時) | 発生時(債務確定時など) | 損益を対応させやすく財務分析に効果的 |
| 現金主義 | 現金受取時 | 現金支払時 | シンプルで小規模事業者に向いている |
| 実現主義 | 収益が確実に実現された時点(商品が届いた時など) | 発生主義と併用されることが多い | 会計上の収益認識の基本的な考え方 |
会計処理の基準には複数の考え方があり、「発生主義」「現金主義」「実現主義」は、代表的な3つの基準です。発生主義・現金主義・実現主義は、収益や費用を計上するタイミングに違いがあり、それぞれの特徴を理解することで会計上の判断がより明確になります。
例えば、現金主義は入金や出金があったときに処理するためシンプルですが、損益対応が不正確になる傾向があります。発生主義は実態に沿った損益を把握できる一方で、現金の動きとズレることもあります。また、実現主義は収益が確定的となった時点で計上するのが特徴で、収益認識の基本とされています。
発生主義と現金主義の違い
発生主義では取引が発生した時点で記帳しますが、現金主義は実際に現金が動いたタイミングで記録されます。例えば、10月にサービスを提供し11月に入金がある場合、発生主義では10月、現金主義では11月に売上を計上します。
発生主義は損益の対応を正確に行えるため、企業の経営状態を的確に把握しやすい一方で、現金の流れと一致しないことから資金繰りの把握には工夫が必要です。現金主義は会計処理が簡便で、小規模事業者などに向いていますが、会計管理の正確性に劣る側面があります。
なお、現金主義については、こちらの記事でも解説しています。

発生主義と実現主義の違い
発生主義は取引が発生した時点で記帳しますが、実現主義では収益が外部との取引により確定した段階で記録されます。例えば、商品を出荷しても返品の可能性がある場合、発生主義では出荷時点で売上を計上しますが、実現主義では返品リスクが解消された時点で売上とします。
発生主義と実現主義の違いは、収益を早期に計上するか、確実性を重視して慎重に計上するかという方針の違いともいえます。実務では両者を併用することも多く、特に収益認識基準の適用場面では、実現主義の概念が重視される傾向があります。
なお、実現主義については、こちらの記事でも紹介しています。

発生主義のメリット
発生主義のメリットとして以下のような点があげられます。
- 期間損益の正確な把握ができる
- 現金の動きに依存せず会計処理ができる
- 経営分析や事業計画の決定に役立つ
- 資金繰りや回収状況が把握しやすい
- グローバル視点での財務報告ができる
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
期間損益の正確な把握ができる
発生主義を採用することで、期間ごとの損益を正確に把握することが可能になります。発生主義では、取引の実態に即して収益や費用を計上するため、特定の会計期間に発生した経済活動が、正確に帳簿に反映されるためです。
例えば、売上は計上されたのに、対応する仕入れが翌月に現金払いだったとしても、発生主義では売上と費用の両方を同じ期間に記録します。このように収益と費用を正しく対応させることで、月次や四半期ごとの業績を正確に比較や分析することができ、事業の実態把握や経営判断の精度を高めることにつながります。
現金の動きに依存せず会計処理ができる
発生主義は、現金の動きに関係なく会計処理を行えるというメリットがあります。取引が発生した事実に基づいて記録するため、実際の入出金タイミングに左右されずに、経済活動を正確に反映できます。
例えば、売掛金や買掛金など、将来的に現金のやり取りが予定されている取引も、発生時点で会計処理が可能です。発生主義の仕組みにより、資金の出入りに時差がある中でも、企業活動の全体像をより適切に表現できるようになります。特に、信用取引が多い企業にとっては、事実ベースの管理ができる点で大きなメリットといえるでしょう。
経営分析や事業計画の決定に役立つ
発生主義は、経営分析や事業計画の立案に役立つ情報を提供できる点もメリットです。収益と費用を発生した時点で記録することで、各期間の実際の成果とコストが明確になり、事業の現状を的確に捉えることができます。
例えば、ある商品の売上が伸びているにもかかわらず、それに伴う広告費や仕入費が当月に反映されていないと、誤った黒字感覚に陥る可能性がありますが、発生主義ではそうしたミスを防げます。このように、時期をそろえた損益データが揃うことで、部門別の収益性分析や将来の資金計画にも活用しやすくなり、実効性の高い経営戦略の立案にもつながるでしょう。
資金繰りや回収状況が把握しやすい
発生主義は、未収金や未払金といった債権・債務の管理がしやすく、資金繰りの見通しにも効果的です。会計上で売上や仕入を発生時に記録することで、将来的な入金や支払の予定が帳簿上に明示され、キャッシュフローの予測が立てやすくなります。
例えば、月末に多くの売掛金が計上されていれば、翌月の入金見込みが把握でき、資金の手当てもしやすくなります。また、取引先ごとの未回収リスクや滞留債権の状況も見える化され、早期の対応が可能になります。発生主義は単なる損益計算のためだけでなく、資金管理の精度を高める実務的な効果も持ち合わせています。
グローバル視点での財務報告ができる
発生主義は、国際的な会計基準に準拠した財務報告を行ううえで不可欠な考え方です。多くの国で採用されているIFRS(国際財務報告基準)やUS GAAP(米国会計基準)では、取引の発生を基準にした会計処理が求められます。
例えば、日本企業が海外子会社を持ち連結決算を行う場合、各社が異なる基準で記帳していると、正確な財務情報の集約が難しくなります。その点、発生主義を共通ルールとすることで、国境を超えた財務報告の一貫性が保たれ、投資家や株主との信頼関係の維持にもつながります。グローバル展開を進める企業にとって、発生主義の導入は避けて通れない要素といえるでしょう。
発生主義のデメリット
発生主義のデメリットとして、以下のような点があげられます。
- 現金の流れとズレが生じてしまう
- 記帳の手間と時間がかかる
- システムの導入や人材の育成が必要になる
- 貸倒れなどのリスクを把握しづらい
- 粉飾決算につながる恐れがある
ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。
現金の流れとズレが生じてしまう
発生主義では、現金の動きと帳簿上の処理が一致しないことがあります。取引の発生時点で収益や費用を記録するため、実際の入出金とは異なるタイミングで会計処理が行われます。
例えば、売上を月末に計上しても、入金が翌月末である場合、帳簿上は黒字でも現金はまだ手元にない状態となります。このようなズレがあると、キャッシュフローの感覚と帳簿上の数字が一致せず、資金繰りの判断を誤るおそれがあります。企業の実態を正確に把握するには、発生主義による記帳と現金の動きの両方を把握する必要があります。
記帳の手間と時間がかかる
発生主義では、取引発生の都度正確に処理を行う必要があり、記帳作業が煩雑になります。現金主義であれば入出金ベースで記録するだけで済みますが、発生主義では売上や仕入、未払い費用などをタイミングに応じて正しく仕訳しなければなりません。
例えば、経費の未払い分や前払いの保険料など、発生したけれど現金の動きがない項目についても都度記録が求められます。このように帳簿の正確性を保つための業務が増えることで、会計担当者の負担が大きくなり、ミスの発生リスクも高まります。そのため、発生主義の制度的な正確性の裏には、実務の手間という課題が伴う点に注意しておきましょう。
システムの導入や人材の育成が必要になる
発生主義を正確に運用するには、専用の会計システムや適切な人材の育成が必要です。取引の発生タイミングを細かく把握し、複雑な仕訳を正確に処理するには、手作業では限界があります。
例えば、売掛金や未払費用、減価償却費の自動計上などは、クラウド会計ソフトやERPシステムがあってこそスムーズに対応できます。また、それらのツールを使いこなせる知識や、発生主義に基づいた会計処理のルールを理解している人材も不可欠です。こうした設備投資や教育にはコストと時間がかかり、特に中小企業では導入のハードルが高くなることがあります。
貸倒れなどのリスクを把握しづらい
発生主義では、売上計上後に回収できないリスクを見落としやすくなります。取引が成立した時点で収益を計上するため、実際に代金が回収されるかどうかは別の問題となってしまうのです。
例えば、取引先が倒産して売掛金が未回収になったとしても、計上済みの売上は帳簿に残り、見かけ上は業績が良好に見えることもあります。こうした「未回収リスク」は、帳簿上の数値からは読み取りづらく、実際の経営状況を正しく把握するためには、別途、債権管理や貸倒引当金の設定が求められます。そのため、数字だけでは判断できないリスク管理が求められる点が課題といえるでしょう。
粉飾決算につながる恐れがある
発生主義の運用次第では、意図的に業績をよく見せる粉飾決算の温床となる可能性があります。収益や費用の計上時期を会計担当者が判断できるという性質上、意図的に売上の先取りや費用の後倒しを行うことが技術的には可能です。
例えば、実際には納品していない商品を「出荷済み」として売上計上したり、今期に発生した広告費を翌期に繰り延べたりといった手法です。こうした操作は短期的には利益を大きく見せられるかもしれませんが、後々の決算で歪みが表面化し、信頼性を損なうことにつながります。そのため、正しく透明性のある運用が求められる会計基準といえるでしょう。
発生主義が用いられるシーン
発生主義が用いられるシーンとして、主に以下のようなシーンがあります。
- 未払金
- 掛仕入
- 引当金
- 減価償却
それぞれどのように発生主義が用いられるのか、具体的に解説していきます。発生主義を導入される際はぜひ参考にしてください。
未払金
未払金は、発生主義の考え方を適用して処理される典型的な項目です。商品やサービスの提供を受けたものの、支払いがまだ行われていない場合でも、費用が発生したタイミングで記帳する必要があります。
例えば、設備の購入をした際に、実際の支払いが翌月であっても、契約や納品が完了していれば当月に費用として処理されます。このように、実際の現金の支出とは切り離して費用計上することで、企業の活動実態に基づいた損益を正確に把握できる点が、発生主義の基本的な特徴といえます。
掛仕入
掛仕入は、発生主義の処理によって仕入時点で費用が計上されます。現金で即時に支払わない仕入取引では、取引の発生時点で費用計上を行うのが会計上の基本です。
例えば、月末に商品を仕入れて翌月に代金を支払う場合でも、発生主義ではその月の仕入として計上され、売上原価として損益に反映されます。これにより、売上とそれに対応する仕入コストの時期を一致させることができ、月次・四半期の損益計算が正確になります。掛取引が多い業種では、掛仕入の処理が重要な役割を果たします。
引当金
引当金の計上も、発生主義の考え方に基づいて行われます。将来的に発生する可能性のある費用を、事前に見積もって今の会計期間に計上することで、損益をより正確に反映することが目的です。
例えば、貸倒引当金は、まだ実際に債権が回収不能になっていない段階でも、一定のリスクがある場合に備えて計上します。これにより、将来にわたって損失が発生しても、当初から費用が見込まれていたという形で、期間損益の公平性が保たれます。そのため、発生主義の運用において重要な見積り項目のひとつといえるでしょう。
減価償却
減価償却は、発生主義に基づいて固定資産の価値を費用として分割計上する処理です。企業が長期にわたり使用する設備や建物などの固定資産は、購入時に一括して費用にするのではなく、使用期間にわたって少しずつ費用配分します。
例えば、1,000万円の機械を10年間使用する場合、毎年100万円ずつ費用計上することで、資産が収益を生み出す期間とコストの対応が図られます。この処理により、当期の損益を不自然に大きく変動させることなく、実態に即した会計処理が可能になります。
発生主義の会計処理のやり方と流れ
発生主義の会計処理では、取引が発生した時点と実際の支払いが行われた時点の2段階で記帳を行います。発生主義の考え方に基づく処理では、支払いの有無にかかわらず費用や収益を発生時点で認識し、後日、現金の動きがあったタイミングで出金や入金を別途記録します。
例えば、9月10日に仕入れを行い、支払いが翌月末だった場合でも、費用は9月に、支払いは10月31日に記帳します。このように、実際のキャッシュフローとは異なるタイミングで会計処理が発生するため、仕訳が複数に分かれます。以下に、処理の全体的な流れを表形式で示します。
| 日付 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月10日 | 仕入高 | 100,000円 | 買掛金 | 100,000円 | 仕入発生時の費用計上 |
| 10月31日 | 買掛金 | 100,000円 | 現金 | 100,000円 | 支払時の出金処理 |
step1:取引発生日に費用を計上する
発生主義では、費用は実際の支払い時ではなく、取引が発生した日を基準に計上されます。これは、収益と費用を同じ期間に記録するという期間損益の原則に基づく考え方です。
例えば、9月10日に仕入を行い、実際の支払いが翌月末になるケースでも、9月10日に仕入費用を帳簿に記録します。この処理を行うことで、売上とそれに対応する仕入を同じ会計期間に集約できるため、経営成績の適切な把握が可能になります。以下は、このケースにおける仕訳の例です。
| 日付 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月10日 | 仕入高 | 100,000円 | 買掛金 | 100,000円 | 仕入発生時の費用計上 |
このように、費用の認識は現金の動きとは無関係に処理されます。
step2:引き落とし日に出金を記録する
発生主義では、実際の支払いが行われたタイミングで出金の処理を行います。すでに費用は取引発生日に計上されているため、支払日には残っている債務(買掛金など)を消し、現金の支出を記録するという形式になります。
例えば、9月10日に仕入れた商品代金を10月31日に支払う場合、10月31日には買掛金を減少させ、同時に現金の減少も記録します。この処理を行うことで、債権債務の状況や資金繰りの実態も正確に帳簿に反映されます。以下の表は、この支払処理の仕訳例です。
| 日付 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 | 買掛金 | 100,000円 | 現金 | 100,000円 | 支払時の出金処理 |
このように、発生主義では「発生時」と「決済時」の両方で仕訳が必要になります。
まとめ
企業の取引を会計帳簿に記録する際、いつ収益や費用を認識するかによって、会計の方法は異なります。その中でも「発生主義」は、現金の受け渡しにかかわらず、取引が発生した時点で会計処理を行う考え方です。
発生主義は会計の基本となる考え方であり、経営分析や事業計画の決定に役立ち、資金繰りや回収状況を把握しやすい点がメリットです。一方で、記帳の手間と時間がかかる点が課題となります。そのため、経理代行会社に依頼することもひとつの手です。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
発生主義に関するよくあるご質問
発生主義についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、発生主義に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
発生主義とはどういう意味ですか?
発生主義とは、取引が発生した時点で収益や費用を記録する会計処理の基準です。現金の受け渡しとは関係なく、契約やサービス提供などの取引が「発生」したタイミングで帳簿に記載するのが特徴です。発生主義では、実際の経済活動に基づいた損益を正確に把握できるため、多くの企業が採用しています。
発生主義の問題点は何ですか?
発生主義には、現金の動きと帳簿上の処理のタイミングがズレやすいという問題点があります。例えば、売上を計上しても入金が後日になると、帳簿上では黒字でも手元に現金がないという状況が起こり得ます。また、取引内容を正確に記録するための仕訳が複雑になり、記帳に手間がかかる点も課題です。
発生主義と現金主義の違いは何ですか?
発生主義は取引の発生時点で会計処理を行うのに対し、現金主義は実際に現金の出入りがあった時点で処理する点で違いがあります。例えば、10月にサービスを提供し、11月に入金がある場合、発生主義では10月に売上を計上しますが、現金主義では11月に記録します。発生主義は損益を正確に反映できる点がメリットです。




