
経理の業務フローとは、企業の会計や財務に関する一連の処理の流れを可視化したものです。日々の入出金処理から、月次や年次の決算まで、経理は幅広い業務をこなす必要があります。
本記事では、経理の業務フローの全体像を解説し、作成手順や効率化のポイントを具体的に紹介します。また、ペーパーレス化やキャッシュレス化といった最新の動向についても触れています。
経理業務における属人化の解消や、急な担当者の退職への対応、ミス防止など、経理業務の効率化を目指す企業の方はぜひ最後までご覧ください。
目次
経理の業務フローとは?
経理の業務フローとは、企業活動において資金の流れや会計記録を管理し、正確な財務情報を維持するための一連の作業プロセスを指します。経理業務は、日次、月次、年次といったサイクルで構成され、具体的には取引の記録や仕訳、帳簿の作成、資金の管理、税務対応などを含みます。
効率的な業務フローを構築することで、経営判断に必要なデータを迅速かつ正確に提供できます。また、業務の見える化がされることで、法令遵守の観点からも有効になります。
なお、企業規模や業種によって求められる具体的な内容には違いがあります。しかし、基本的なフローを確立して、自動化やデジタルツールを活用することで、経理の生産性と正確性を向上させることが可能です。
日次における経理の業務フロー
日次における経理の業務フローとしては、日々の取引記録と資金管理を中心に行われます。具体的には、現金や預金の入出金を確認し、領収書や請求書などの関連書類を収集して仕訳を行い、会計ソフトに記録する作業が含まれます。
また、売掛金や買掛金の管理も重要な日次業務の一環です。日々の資金繰り状況を正確に把握し、資金不足や過剰な支出を未然に防ぐことができます。
さらに、不明金が発生した場合には即座に原因を特定し、修正することが求められます。そのため、正確な日次業務の実施は、月次および年次業務の基盤を形成し、経理全体の効率性を確保する上で欠かせない業務といえるでしょう。
月次における経理の業務フロー
月次における経理の業務フローでは、日々の記録をもとに月単位の集計や報告を行います。月末における未処理の伝票や仕訳の確認、各勘定科目の残高の照合、売掛金や買掛金の締め処理が含まれます。
また、試算表の作成を通じて、収益や費用、利益の状況を把握することも行われます。さらに、月次決算資料を基に、経営陣に対して業績報告を行うことで、戦略的な意思決定を支援する役割も担います。
毎月定期的に実施される経理業務は、経営に必要な財務情報を提供するだけでなく、翌月以降の業務計画や改善策の立案に貢献します。そのため、継続的かつミスなく正確に遂行される必要があります。
年次における経理の業務フロー
年次における経理の業務フローでは、1年間の会計データをまとめて、税務申告や外部への報告に対応します。具体的には、期末決算の準備として、棚卸資産や固定資産の評価、減価償却費の計算、各種引当金の設定を行います。
その後、損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を作成し、税務申告書の作成と提出を行います。加えて、法定監査を受ける場合は、必要な資料を準備し、監査人との調整を進めます。
さらに、年次業務では来期の予算編成や計画策定に向けたデータ分析も重要な役割を果たします。年次業務をミスなく正確に遂行することで、会社の信頼性を高めるとともに、長期的な経営戦略に貢献することが可能となります。
経理の業務フローを作成するメリット
経理の業務フローを作成することは、以下のようなメリットにつながります。
- 経理業務の属人化を解消できる
- 急な経理担当者の退職に対応できる
- 記帳などの業務におけるミスが減る
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
経理業務の属人化を解消できる
経理業務の属人化は、特定の担当者の方しか業務内容や手順を把握していない状況を指し、企業の運営にリスクをもたらす要因となります。明確で効率的な業務フローを作成することで、属人化の問題を解消することが可能です。
具体的には、業務手順や必要なツール、記録方法を文書化し、全員が理解しやすい形で共有することで、誰もが一定の基準で業務を行える環境を整えることができます。さらに、業務フローが明確である場合、新しい担当者の方でも短期間で業務を引き継ぎやすくなり、担当者間での知識やスキルの偏りを防ぐことができます。
急な経理担当者の退職に対応できる
経理担当者が急に退職することは、企業にとって深刻な問題となります。しかし、業務フローが整備されている場合、リスクへ柔軟に対応することが可能です。
業務フローには、日常的な業務から月次や年次決算まで、各作業の手順や使用するツール、締め切りなどが詳細に記載されています。これにより、新たな担当者や外部のスタッフが速やかに業務を引き継ぎ、混乱を最小限に抑えることができます。
また、経理業務が標準化されていることで、既存の従業員がチームとして対応することも簡単になります。急な退職への備えがあることで、業務の継続性が確保され、担当者変更が業績や信用に悪影響を及ぼすリスクを減らすことが可能です。
記帳などの業務におけるミスが減る
経理業務のフローを確立することで、記帳や仕訳といった業務におけるミスを大幅に減らすことができます。明確な業務手順が整備されている場合、どのような取引をどのタイミングで、どの形式で記録するかが一目でわかります。そのため、手作業に伴う記入ミスや入力漏れが防止されます。
また、フローの中にチェック体制を組み込むことで、ダブルチェックを行い、ヒューマンエラーをさらに抑えることが可能です。さらに、業務フローがデジタルツールや会計ソフトと連携している場合、手作業でのプロセスが削減されることで、人的なミスが起きるリスクを減らすことが可能です。
経理の業務フローを作成する手順
経理の業務フローを作成するには、以下の手順で進めましょう。
- 手順1:業務フローを作成する目的を決める
- 手順2:業務の担当者を明確にする
- 手順3:担当者のタスク(作業)を洗い出す
- 手順4:タスクを分類する
- 手順5:タスクを時系列に沿って並べる
- 手順6:完成した業務フローを検証する
手順1:業務フローを作成する目的を決める
経理の業務フローを作成する際における最初のステップは、業務フローを作成する目的を明確にすることです。経理業務の効率化を目指すのか、属人化の解消を図るのか、それとも人的ミスを減らして業務の正確性を向上させるのか、目的を具体的に定めることで、フロー作成の方向性も決まります。
目的が曖昧なままでは、業務フローの内容がブレてしまい、実際の運用で十分な効果を得られない可能性があります。そのため、目的をはっきりさせることで、必要な情報やプロセスを選定しやすくなり、作成後のフローが目指すべき成果に直結した実用的なものとなります。
手順2:業務の担当者を明確にする
経理の業務フローを構築する際には、どの業務が誰の責任で行われているかを明確にすることも大切です。誰が何をするのか、担当者を決めていき、作業の流れを具体的に洗い出すことで、役割分担の偏りや曖昧さを解消するきっかけとなります。
また、業務を実行している担当者に直接ヒアリングを行うことで、実際に業務に見合った詳細な情報を収集できます。同時に、 チームメンバーの能力に応じた、適切な作業配分も可能になります。
その結果、担当者を明確にすることで、フロー作成後の実運用時にも責任の所在がわかりやすくなり、トラブル時の対応もスムーズになるでしょう。
手順3:担当者のタスク(作業)を洗い出す
次に、各担当者が行っているタスクを具体的に洗い出します。作業の洗い出しプロセスで得た情報は、最終的な効率化に直結するため重要です。
洗い出しの段階では、日次、月次、年次の区分にとらわれず、すべての業務内容を可能な限り詳細にリストアップすることが重要です。例えば、請求書の処理や現金出納の確認、帳簿への記録など、担当者が行う作業一つひとつを把握します。
これにより、業務全体の全貌が明らかになり、無駄な作業や重複している業務の発見にもつながります。洗い出しの作業がしっかり行われることで、フローの構築に必要な正確な情報を得ることができます。
手順4:タスクを分類する
洗い出したタスクを、それぞれの内容や目的に応じて分類します。たとえば、取引の記録や仕訳は日常業務に該当し、月次決算や予算管理は定期業務として別のカテゴリーに分けることができます。
タスクを分類する作業により、作業の優先順位や頻度が明確になり、効率的なフローを構築するための基盤が整います。また、タスクの分類を通じて、不要な業務や非効率な作業プロセスが浮き彫りになることもあり、業務全体の改善につながる可能性があります。
分類の結果は、各作業の負担軽減にも役立つでしょう。そのため、分類を丁寧に行うことで、フロー全体の質を向上させることができるのです。
手順5:タスクを時系列に沿って並べる
分類されたタスクを、実際に行う順番に基づいて時系列に並べていきます。時系列で整理することで、業務進行の見通しが良くなります。
時系列に並べる際には、各作業がどのように連動しているかを意識し、タスク間の依存関係やタイミングを考慮することが重要です。たとえば、請求書の処理は支払い手続きの前に完了している必要があります。また、月次業務として締め作業を行うには、日次業務として記帳を正確に終わらせておく必要もあるでしょう。
そのため、時系列に沿って並べることで、業務の全体像が視覚的に整理され、担当者間の連携がスムーズになるため、フローの実用性が高まります。
手順6:完成した業務フローを検証する
経理の業務フローは作成したら終わりではありません。検証を重ねてブラッシュアップしていくことが大切です。作成した業務フローを検証し、実際の運用に適しているかを確認します。担当者や関係者と共有し、内容に漏れや不備がないか、現場の実態に即しているかを徹底的にチェックします。
検証の際には、フローを試験運用して課題を洗い出し、必要に応じて修正を加えることで、実務で役立つ業務フローに仕上げることができます。検証プロセスを経ることで、作成したフローの精度が向上し、長期的に活用可能な仕組みが完成します。
経理の業務フローを効率化するポイント
経理の業務フローを効率化するには、以下のようなポイントを意識することがおすすめです。
- 書類のペーパーレス化を進める
- 支払いのキャッシュレス化を取り入れる
- 経理代行やアウトソーシングを利用する
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
書類のペーパーレス化を進める
経理業務を効率化するうえで、書類のペーパーレス化は有効です。紙の書類は管理が煩雑で、スペースを必要とするだけでなく、情報の検索や共有に時間がかかることがあります。
一方、デジタル化された書類であれば、クラウド上での一元管理が可能となり、必要な情報を瞬時に検索できるため、作業のスピードが向上します。また、電子データはバックアップも簡単で、災害や紛失時のリスクを軽減することができます。
さらに、ペーパーレス化により印刷や保管コストの削減が期待でき、環境保護にもつながります。業務全体の効率を高めるだけでなく、企業の持続可能性を高める取り組みとしても重要です。
なお、経理のペーパーレス化についてはこちらの記事も参考にしてください。
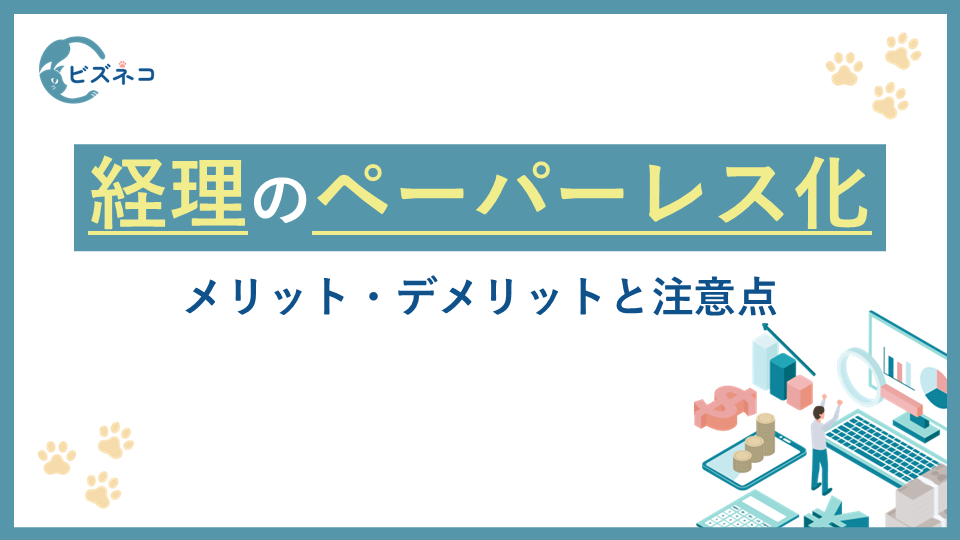
支払いのキャッシュレス化を取り入れる
支払い業務のキャッシュレス化を取り入れることも、経理の業務フローを改善するポイントです。現金を使用する場合、手作業での金額確認や釣り銭の管理、出納帳への記録など、多くの手間がかかります。
一方、クレジットカードやオンライン決済を利用することで、取引記録が自動的にデジタル化され、仕訳の手間を大幅に削減できます。また、支払い履歴が正確に残るため、不正防止にも効果的です。
さらに、キャッシュレス化は従業員や取引先にとっても利便性が高く、全体の業務効率が向上します。こうした仕組みを導入することで、時間やコストの無駄を排除し、経理部門の生産性を大きく向上させることが可能になります。
経理代行やアウトソーシングを利用する
経理業務を効率化するために、経理代行やアウトソーシングを利用するのも効果的な方法です。専門業者に業務を委託することで、従業員が本来の業務に集中でき、企業全体のパフォーマンス向上につながります。
特に、煩雑な記帳や税務申告の作業をプロに任せることで、ミスのリスクが減少し、正確な会計データが得られる点が大きなメリットです。また、最新の会計ソフトや専門知識を持つ業者に依頼することで、法改正への対応もスムーズに行えます。
アウトソーシングを活用することで、コスト削減と業務効率化を同時に実現し、経営資源をより効果的に活用することが可能となります。なお、経理のアウトソーシングについてはこちらの記事も参考にしてください。
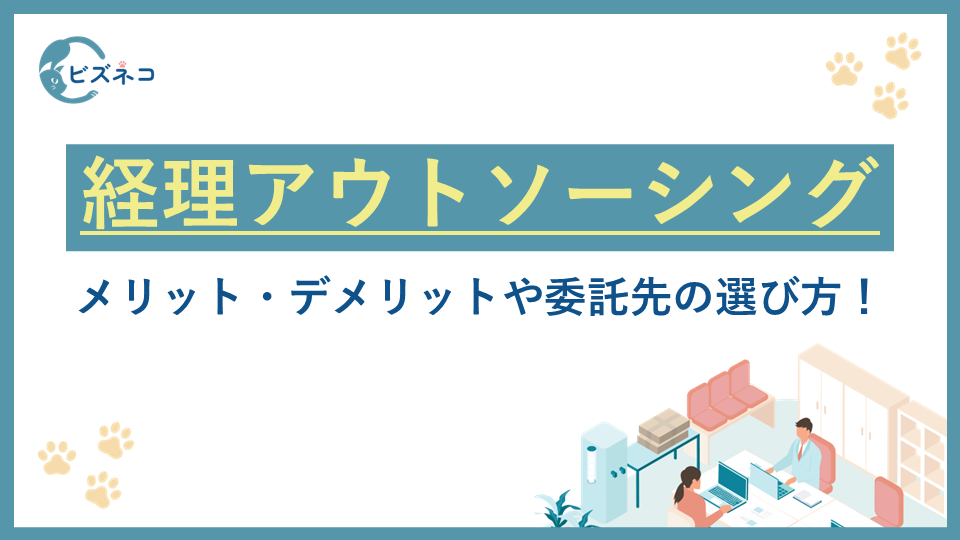
まとめ
経理の業務フローは、企業の財務状況を正確に把握し、効率的な経営を行うために欠かせません。本記事では、経理の業務フローの基礎から、作成手順、効率化のポイントまでを詳しく解説しました。
日々の入出金処理から、月次や年次の決算まで、経理は幅広い業務を担っています。業務フローを作成することで、属人化の解消やミスの防止、急な担当者の退職への対応など、様々なメリットが得られます。
また、ペーパーレス化やキャッシュレス化といった最新の動向を取り入れ、経理部門のデジタル化を推進することで、さらなる効率化が期待できます。そして、経理代行会社へ相談することもひとつの手です。
弊社では、経理代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な経理業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
経理の業務フローに関するよくあるご質問
経理の業務フローについてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは経理の業務フローに関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
業務フローとは何ですか?
業務フローとは、ある仕事がどのように行われているのかを、図や文章を用いて可視化したものです。誰が、いつ、どんな作業を行い、どのような結果が出るのかを明確にすることで、業務の効率化や改善、標準化を図ることができます。いわば、仕事の「設計図」のようなものであり、業務改善では欠かせません。
業務フローとフローチャートの違いは何ですか?
フローチャートは業務フローの一部です。フローチャートとは、 業務の流れを図形や矢印を使って視覚的に表現したものです。一方で、業務フローとは、図形や矢印で表現されたフローチャートに加えて、業務の目的、担当者、使用するツールなど、必要な情報を細かく盛り込んだものです。
業務フローとマニュアルの違いは何ですか?
業務フローは、業務全体の流れや手順を簡潔に示したもので、プロセス全体の概要や関係性を把握するのに役立ちます。一方、マニュアルは各作業の詳細な手順や操作方法を具体的に記載したもので、個別のタスクの実行に重点を置いています。業務フローは全体像の理解を目的とし、マニュアルは具体的な作業を説明する資料です。




