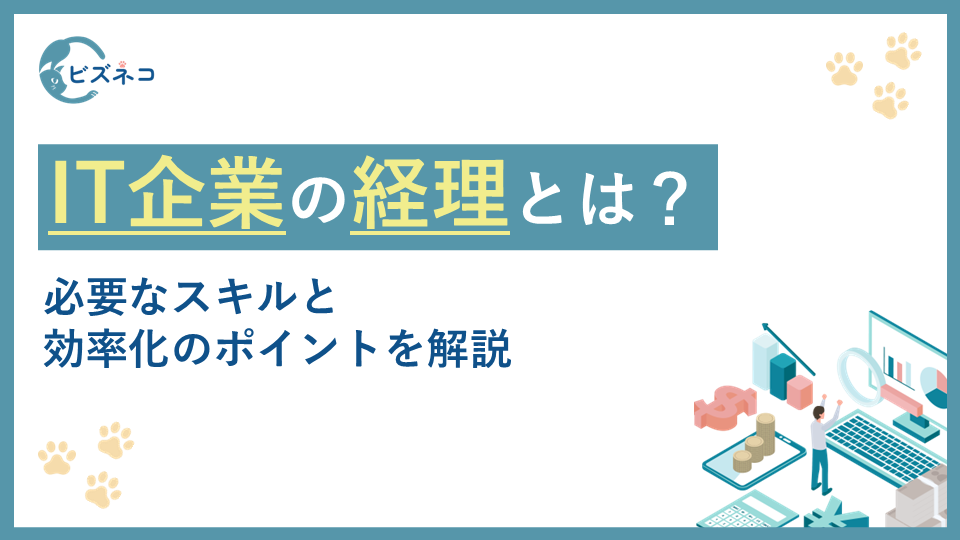
IT企業の経理業務は、サブスク型の売上構造やエンジニアの人件費の適正な配分、補助金・助成金の活用など、他業種と比べて独自の課題が多いのが特徴です。さらに、開発費の分割払いが発生するなど、資金管理も複雑になっています。
本記事では、IT企業における経理業務の特徴や課題をまとめて、必要なスキルや効率化のポイントを解説します。経理担当者の方や経営者の方は、経理業務をスムーズに進め、企業の成長を支えるための参考にしてください。
目次
IT企業の経理の特徴と課題
IT企業の経理には、業界特有の課題として以下のような点があげられます。
- サブスク型で売上が複雑になる
- エンジニアの人件費の管理が難しい
- 補助金や助成金を考慮する必要がある
- 開発費の分割払いが発生する
ここでは、それぞれの特徴と課題について詳しく解説します。
サブスク型で売上が複雑になる
IT企業の多くは、サブスク型(サブスクリプション型)のビジネスモデルを採用しており、継続的な収益が見込める一方で、売上の計上が複雑になりやすいという課題を抱えています。
例えば、月額課金や年額一括払いなどの異なる支払い方法が混在すると、それぞれの契約に応じた収益認識を適用しなければならず、売上の管理が煩雑になります。さらに、解約やプラン変更が発生すると、過去の売上を調整する必要があり、適切な仕訳処理を怠ると会計上のズレが生じるリスクがあります。
複雑な収益認識を適切に処理するためには、会計基準の理解を深めるとともに、サブスク管理に特化したシステムを導入し、正確な売上計上ができる仕組みを整えることが重要です。
エンジニアの人件費の管理が難しい
IT企業の経理業務において、エンジニアの人件費管理は難しい課題のひとつです。例えば、複数の開発プロジェクトが同時に進行する場合、各エンジニアの稼働時間を正確に把握し、それぞれのプロジェクトの原価として適切に計上する必要があります。
しかし、エンジニアの業務は単純な時間管理では測りづらく、進捗状況や作業の難易度によって生産性が大きく異なるため、現場の状況に即したコスト管理が求められます。さらに、正社員、業務委託、フリーランスなど、雇用形態もさまざまであり、給与計算の方法や契約内容に応じた支払い管理も複雑になりがちです。
人件費の課題を解決するためには、労務管理システムや工数管理ツールを導入し、リアルタイムで稼働状況を把握できる仕組みを整えることがおすすめです。
補助金や助成金を考慮する必要がある
IT企業では、新規事業の開発やDX推進に活用できる国や自治体の補助金や助成金があります。補助金や助成金を上手く活用することで資金繰りを改善できます。
例えば、IT導入補助金を活用すれば、自社の業務効率化のためのシステム導入費用を一部補助してもらえるため、経費削減につながります。しかし、補助金や助成金は要件が細かく設定されており、申請時に事業計画書や見積書の作成が求められるだけでなく、適正な会計処理を行わなければならない点が経理担当者の負担となります。
また、補助金を受け取った後に適切な報告を怠ると、返還を求められるリスクがあるため、制度の詳細を把握し、慎重に管理することが必要です。
開発費の分割払いが発生する
IT企業のシステム開発案件では、開発費の分割払いが発生することが一般的であり、経理業務も複雑になります。例えば、大規模なソフトウェア開発では、契約時に着手金を受け取り、開発の進捗に応じて中間金や納品後の最終支払いを受け取るケースが多く見られます。
分割払いでは売上をいつ計上するのかを慎重に判断する必要があり、特に長期プロジェクトでは複数年度にまたがる収益認識が求められるため、会計処理の正確性が重要になります。また、プロジェクトが完了しているにもかかわらず、入金が遅れると資金繰りに支障をきたし、運転資金の確保が課題となる懸念があります。リスクを回避するためには、契約時に支払い条件を明確にし、分割払いによるキャッシュフローの影響を把握したうえで、適切な資金計画を立てることが重要です。
IT企業における経理の業務内容
IT企業における経理の業務内容は主に「日次業務(毎日の仕事)」「月次業務(毎月の仕事)」「年次業務(毎年の仕事)」にわけられます。
ここでは、それぞれの経理担当者が行う業務内容について詳しく解説します。
IT企業の経理の日次業務
IT企業の経理における日次業務は、毎日の金銭取引を正確に記録し、資金の流れを適切に管理することが求められます。例えば、売上や経費の仕訳入力を行い、取引先や社内の関係部署と連携しながら、未処理の請求書や支払いの確認を進める作業が発生します。
また、銀行口座の入出金を確認し、キャッシュフローに影響が出ないよう資金の管理を徹底することも大切な仕事です。特にIT企業では、クラウドサービスの利用料やサーバー維持費などの支払いが月単位や年単位で発生することが多く、未払いがないかを常にチェックする必要があります。
これらの日次業務を円滑に進めるためには、経理システムを活用して自動化を進め、ミスのない正確なデータ入力を心掛けることが大切です。
IT企業の経理の月次業務
IT企業の経理における月次業務では、毎月の取引を集計し、正確な財務状況を把握することが求められます。例えば、売上や費用の計上漏れがないかを確認し、サブスク型の収益モデルで発生する前受金や未収収益の処理を適切に行う必要があります。
また、エンジニアの工数管理や人件費の把握も重要な業務のひとつであり、プロジェクトごとに適正なコスト配分がされているかをチェックすることが求められます。
さらに、クライアントへの請求書発行や未回収の売掛金の確認も欠かせません。例えば、支払いサイトが長い取引先がある場合、未入金が発生しやすいため、適宜リマインドを送るなどの対応が必要です。
これらの業務を正確に遂行することで、会社の財務状況を適切に管理し、経営判断に役立つデータを提供できるようになります。
IT企業の経理の年次業務
IT企業の経理の年次業務では、年間の財務状況を総括し、決算や税務申告を適切に行うことが求められます。例えば、決算処理に向けて、売上や経費の計上漏れがないかを再確認し、税務上の調整が必要な項目については、会計士や税理士と連携しながら処理を進める必要があります。
また、減価償却費や未払い費用の精査を行い、正確な財務諸表を作成することが重要になります。特にIT企業の場合、ソフトウェア開発に関する支出が多く、研究開発費として処理できるかどうかの判断が必要になるケースもあります。
例えば、自社開発のシステムに関する費用の一部は資産計上が求められるため、処理を誤ると決算内容に影響を及ぼす可能性があります。
年次業務は膨大な作業量となるため、日次業務や月次業務の段階からデータを整理し、スムーズに決算作業を進められるよう準備することが重要です。
IT企業の経理担当者に求められるスキルと知識
IT企業の経理担当者に求められるスキルと知識には、おもに以下のようなものがあげられます。
- 簿記や会計に関する資格の取得
- プロジェクトの原価管理に関する知識
- 経理のDX化に関する知識
- 自社の収益モデルの理解
ここでは、それぞれのスキルや知識について詳しく解説します。
簿記や会計に関する資格の取得
IT企業の経理担当者にとって、簿記や会計の資格を取得することは、正確な財務管理を行う上で大きな強みとなります。例えば、日商簿記を取得していれば、決算書の作成や財務諸表の分析ができるため、会社の経営状況を数値で把握する力が身につきます。
特にIT企業では、売上の認識が複雑になりがちなサブスク型のビジネスや、前受金の処理、未収収益の管理などが発生するため、仕訳処理の正確さが求められます。
資格の取得は、経理業務の幅を広げるだけでなく、経営層との会話においても財務的な視点から適切な提案ができるようになるため、キャリアアップの観点からも大きなメリットがあります。
プロジェクトの原価管理に関する知識
IT企業では、ソフトウェア開発やシステム導入のプロジェクトが多く、経理担当者には原価管理の知識が求められます。例えば、受託開発では、エンジニアの工数や外注費を把握し、プロジェクトごとの採算を把握することが重要になります。
また、プロジェクトが長期にわたる場合、進行基準で売上を計上するのか、完成基準で認識するのかによって、財務状況の見え方が変わるため、適切な会計処理が必要になります。例えば、大規模システム開発の案件では、開発初期の段階ではコストが先行し、売上が後から計上されるため、キャッシュフロー管理が難しくなることがあります。そのため、プロジェクトごとに収支を正確に把握し、コストが適切に管理されているかを定期的にチェックする仕組みが必要です。
経理担当者が原価管理の知識を持っていれば、経営陣に対して利益率の改善策を提案したり、コスト削減のアドバイスを行うことも可能になり、会社全体の経営効率向上につながります。
経理のDX化に関する知識
IT企業の経理業務を効率化するためには、DX(デジタルトランスフォーメーション)に関する知識が欠かせません。例えば、経費精算システムを導入することで、社員が手作業で行っていた領収書の管理や仕訳入力を自動化し、業務の負担を大幅に軽減できます。また、AIを活用した経理システムを導入すれば、過去のデータを分析して経費の異常値を検出したり、売掛金の回収リスクを予測することも可能になります。
例えば、クラウド会計ソフトを活用することで、リアルタイムで財務データを共有し、リモートワーク環境でもスムーズに決算処理を進めることができます。
さらに、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入すれば、繰り返し発生する仕訳入力や請求書の処理を自動化し、人的ミスを削減できるメリットもあります。そのため、経理のDX化を推進することで、単なる記帳作業にとどまらず、より戦略的な経営支援が可能となり、企業の成長をサポートする役割を果たせるようになります。
なお、経理のDX化についてはこちらの記事も参考にしてください。
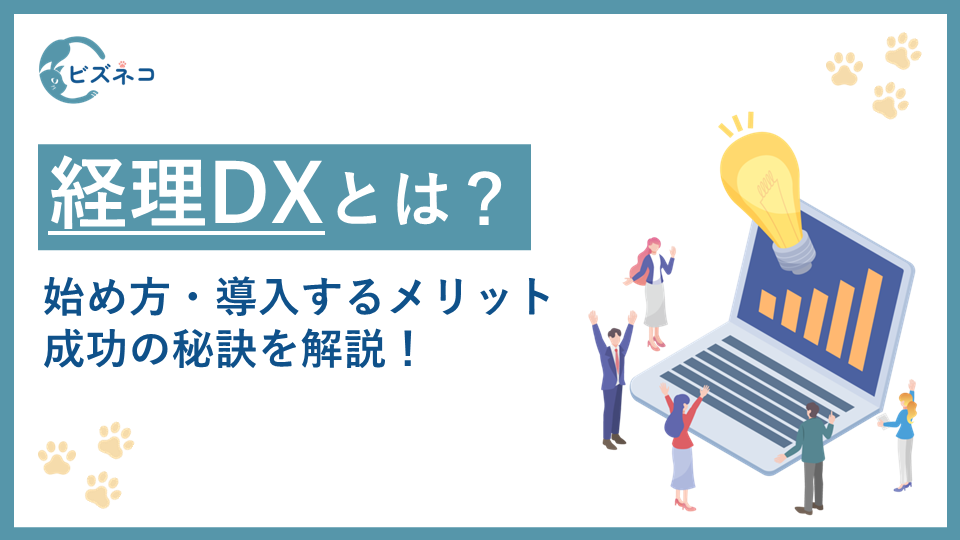
自社の収益モデルの理解
IT企業の経理担当者は、単に会計処理を行うだけでなく、自社の収益モデルを深く理解することが求められます。例えば、サブスク型のビジネスを展開している場合、月額課金と年額一括払いの違いを理解し、それぞれの会計処理が適切に行われるように管理する必要があります。
また、IT企業では、開発費用をどのタイミングで回収するのか、ライセンス販売によるロイヤリティ収益がどのように発生するのかといった点も重要なポイントになります。例えば、自社開発のソフトウェアをSaaS(Software as a Service)として提供する場合、初期費用が少なく、長期的に収益を積み上げるモデルになるため、キャッシュフローの見通しをしっかり立てることが必要になります。
一方で、受託開発の場合、案件ごとに売上が発生するため、プロジェクトの進捗状況に応じた売上計上が求められます。こうした収益構造の違いを理解し、経営陣に適切な財務データを提供することで、より戦略的な経営判断をサポートできる経理担当者としての価値を高めることができます。
IT企業の経理を効率化するポイント
IT企業の複雑な経理業務を効率化するには、以下のような点を意識してみましょう。
- 経費精算システムでフローを自動化する
- 工数や人件費を見える化する
- AIを経理にも活用してみる
- 経理代行会社に相談する
ここでは、それぞれの効率化のポイントを具体的に解説します。
経費精算システムでフローを自動化する
IT企業の経理業務を効率化するためには、経費精算システムの導入がポイントです。例えば、従業員が出張費や交際費を精算する際、手書きの領収書を貼り付けて申請する方法では、経理担当者が手入力で仕訳を行う必要があり、確認や承認の手間が増えてしまいます。
しかし、経費精算システムを導入すれば、スマートフォンで領収書を撮影するだけでデータ化され、自動で仕訳処理が行われるため、手作業を大幅に削減できます。
また、承認フローもシステム上で完結するため、経理担当者が紙の申請書を管理する手間がなくなり、リアルタイムで申請状況を把握できるようになります。経費のデータが自動的に集計されることで、月次決算のスピードも向上し、企業全体の業務効率化につながります。
なお、経費精算は経理代行会社に依頼することも可能です。経費精算代行についてはこちらの記事も参考にしてください。
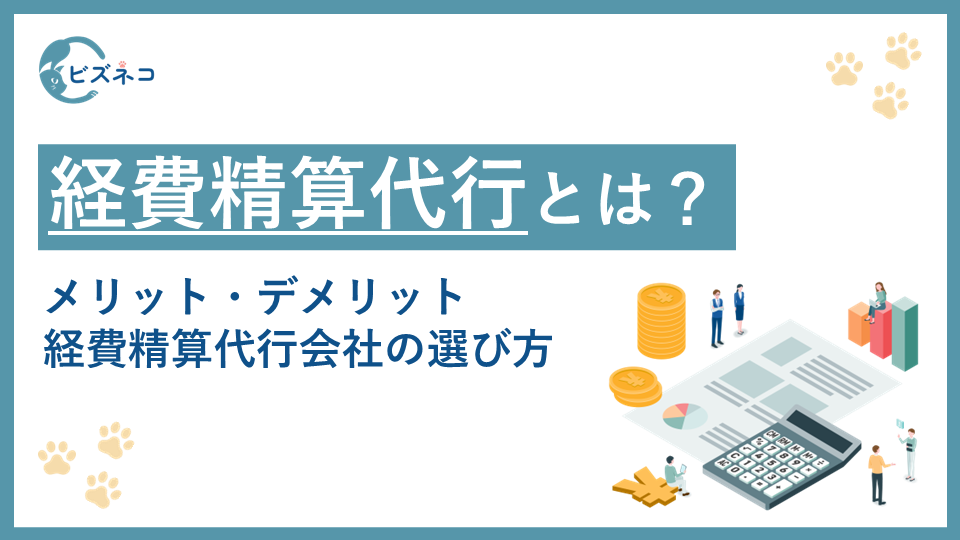
工数や人件費を見える化する
IT企業では、エンジニアの人件費が大きなコストを占めるため、工数管理を徹底し、プロジェクトごとの収益性を明確にすることが重要です。例えば、開発案件ごとにエンジニアの工数を記録し、給与データと連携させることで、プロジェクト単位での正確な人件費を算出できます。
特に、受託開発や大規模なシステム構築では、実際にかかった工数と予算の乖離が発生しやすいため、リアルタイムで工数を管理することで、予算オーバーを未然に防ぐことができます。
工数や人件費を見える化することで、経営層も正確なデータをもとに意思決定ができるようになり、より収益性の高い事業運営が可能になります。
AIを経理にも活用してみる
AI技術を活用することで、経理業務の効率化と精度向上を同時に実現することができます。例えば、AIを活用したOCR(光学文字認識)機能を使えば、紙の請求書や領収書を自動でデータ化し、手入力の負担を大幅に削減できます。
また、AIが過去の仕訳データを学習し、適切な勘定科目を自動で提案することで、仕訳作業の時間短縮や入力ミスの防止につながります。例えば、頻繁に利用する取引先の請求書を登録しておけば、AIが取引内容を分析し、適切な仕訳を自動生成するため、経理担当者は最終確認を行うだけで済みます。
AIを経理業務に取り入れることで、単純作業の負担を軽減し、より高度な分析業務や経営支援に時間を割くことができるようになります。
なお、経理とAIの関係については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
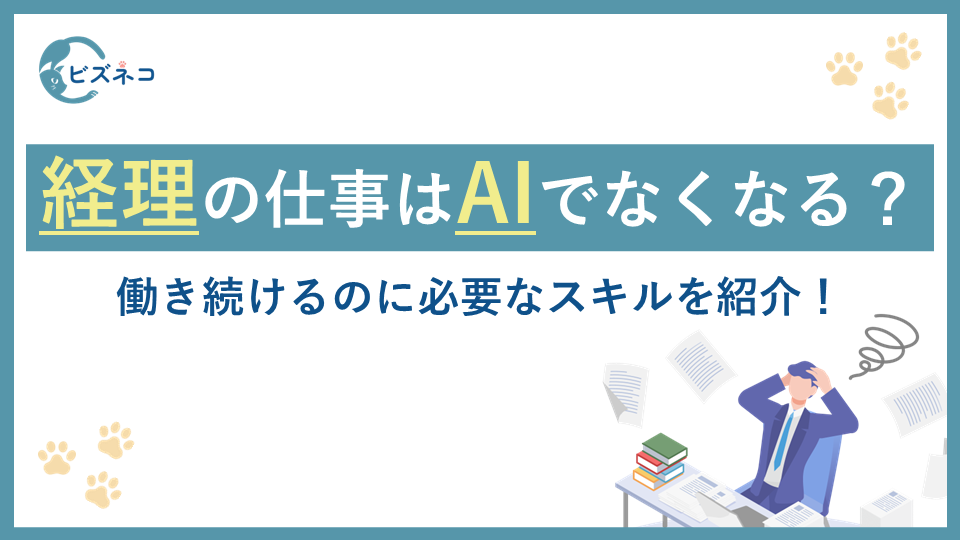
経理代行会社に相談する
経理業務の負担が大きい場合、経理代行会社に一部の業務を委託することも有効な手段です。例えば、日次の仕訳入力や請求書発行、支払業務などを外部に依頼することで、経理担当者は月次決算や財務分析といったより重要な業務に集中できます。
特に、スタートアップや中小規模のIT企業では、専任の経理担当者を雇う余裕がないケースも多いため、経理代行を活用することで業務の効率化とコスト削減を両立できます。
また、クラウド会計ソフトと連携した経理代行を利用すれば、リアルタイムで経理データを共有しながら業務を進めることができるため、社内での業務負担を最小限に抑えることができます。経理代行を上手に活用することで、コア業務に集中できる環境を整え、企業の成長を支える経理体制を構築することが可能になります。
なお、経理代行サービスについては、こちらの記事も参考にしてください。
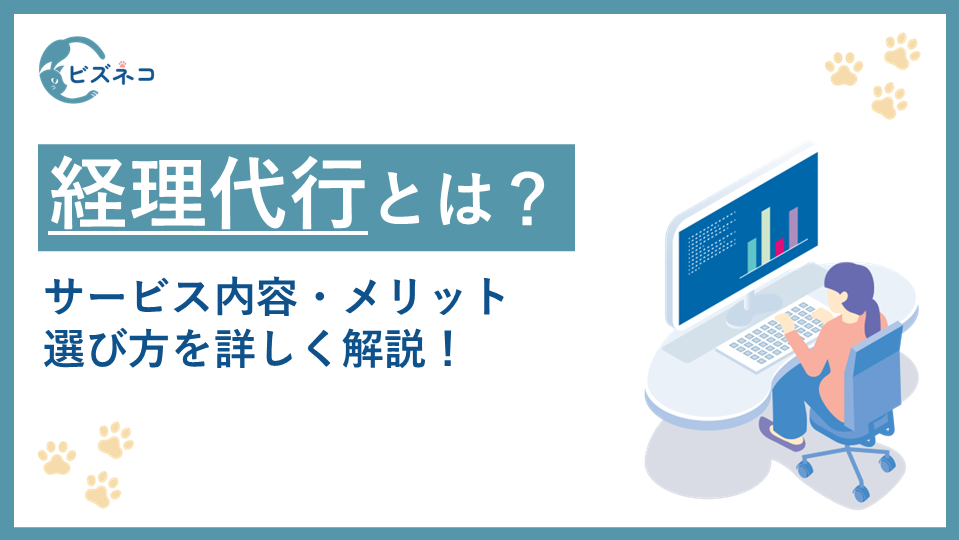
まとめ
IT企業では、サブスク型の収益モデルや大規模な開発プロジェクトなど、収支のバランスが複雑化してしまうことが課題です。月次や年次の決算を正確に行うためには、日々の記帳業務を正確に行うことが大切です。
そのため、IT企業の経理担当者には、簿記や会計の知識だけではなく、自社の収益モデルに関する理解やDX化に関する知識も求められるでしょう。また、複雑な経理業務を効率化するためには、経費精算システムやAIの活用がおすすめです。なお、経理代行会社を導入して、経理担当者の方の負担を削減することもおすすめです。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
IT企業の経理に関するよくあるご質問
IT企業の経理についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、IT企業の経理に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
IT企業の経理に必要な資格は何ですか?
IT企業の経理担当者には、日商簿記2級以上の資格があると、財務諸表の作成や仕訳処理を適切に行う力が身につきます。また、IT企業特有のプロジェクト原価管理を理解するために、管理会計やファイナンスの知識を深める資格として、ビジネス会計検定や中小企業診断士の取得も役立ちます。
経理に必要なITスキルは何ですか?
経理業務の効率化のためには、会計ソフトの操作スキルが必要です。例えば、クラウド会計ソフトを活用することで、リアルタイムで財務状況を把握できます。また、Excelの関数やマクロを使いこなせば、データ処理の自動化が可能になります。さらに、RPAやAIの知識があると、経理DXの推進に役立ちます。
経理のIT化とは何ですか?
経理のIT化とは、会計ソフトやクラウドサービスを活用し、経理業務の自動化や効率化を図ることを指します。例えば、経費精算システムを導入すれば、領収書の管理や仕訳入力が自動化され、業務負担が軽減されます。また、AIを活用した請求書処理やRPAによる自動化により人的ミスを減らし、コア業務に注力できます。




