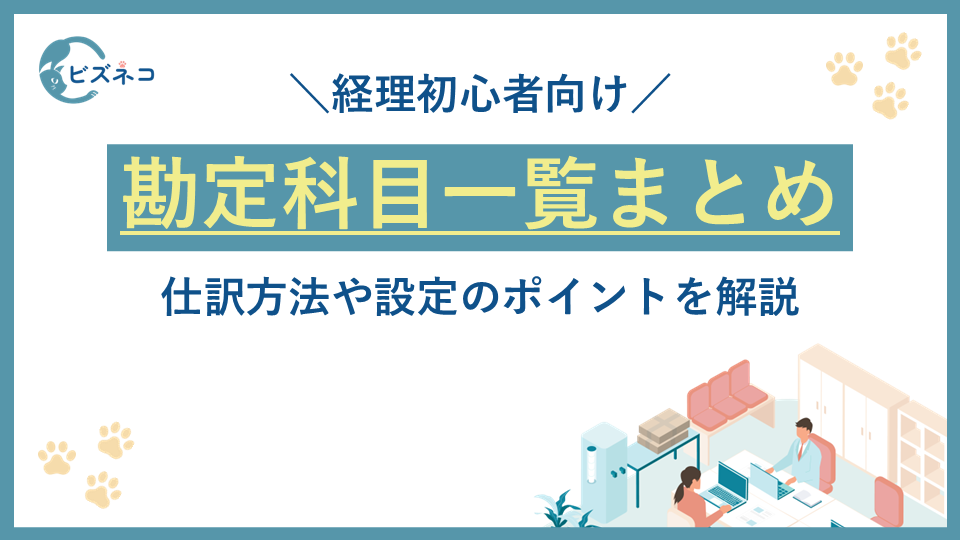
経理の基本となる勘定科目とは、日々の取引を正しく記録し、会社の財務状況を把握するために欠かせない項目です。初めて経理に携わる方にとっては、数ある勘定科目の種類や仕訳のルールに戸惑うことも多いかもしれません。
本記事では、勘定科目の基本的な役割や使用目的と、資産・負債・純資産・収益・費用といった分類ごとの勘定科目一覧をまとめています。また、具体的なシーン別の仕訳例や、実務に活かせる勘定科目の設定ルール、運用時の注意点まで紹介します。
目次
勘定科目とは?
勘定科目は、企業活動に伴う取引を分類や記録をするための基本的な項目です。仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿で取引内容を記録する際に、「現金」「売上」「仕入」「旅費交通費」などの勘定科目を用いて処理します。
例えば、商品を販売した場合には「売上」、その際に現金を受け取ったなら「現金」というように、複数の勘定科目を組み合わせて記録します。勘定科目を正しく使うことで、取引の内容を簡潔かつ明確に整理できるだけでなく、帳簿の読みやすさや精度も向上します。そのため、経理業務の基本を押さえるうえで、勘定科目の理解は欠かせません。
勘定科目を使用する目的
勘定科目を使用する目的として、以下のような点があげられます。
- 取引内容の分類や整理のため
- 財務諸表を作成するため
- 経営判断を円滑に進めるため
- 税務申告に対応するため
ここでは、それぞれの目的について詳しく解説していきます。
取引内容の分類や整理のため
取引内容を正確に把握するためには、内容ごとに分類と整理する仕組みが必要です。そこで活躍するのが勘定科目です。例えば、従業員への給料支払いと、会社用の備品購入では性質が異なるため、それぞれ「給与手当」や「消耗品費」といった異なる勘定科目を使って記録します。
取引内容を分類しておくことで、後から帳簿を見返したときに、どのような費用がどれだけ発生していたかをすぐに把握でき、業務の見直しや改善にも役立ちます。そのため、勘定科目は、日々の取引を整理する「ラベル」のような役割を果たしており、帳簿管理の土台となる存在です。
財務諸表を作成するため
財務諸表は、企業の財務状況や経営成績を外部に示す重要な資料です。財務諸表を正確に作成するためには、勘定科目を適切に使って日々の取引を記録しておく必要があります。
例えば、売上や経費の勘定科目を正しく分類しないと、損益計算書で本来の利益を正確に算出できなくなってしまいます。同様に、資産や負債の勘定科目に誤りがあると、貸借対照表の内容にも影響が出ます。つまり、勘定科目は、財務諸表という「会社の成績表」を構成する要素のひとつであり、経理処理の精度に直結する重要な仕組みといえるでしょう。
経営判断を円滑に進めるため
企業が正しい経営判断を行うためには、現状の収支状況や費用の内訳などを正確に把握することが欠かせません。会計情報を整理する際に役立つのが、勘定科目です。
例えば、販促費が増えていると気づいたときに、「広告宣伝費」や「交際費」などの勘定科目で明細を追えば、具体的な費用の使い方を把握できます。売上やコストの傾向を勘定科目ごとに分析することで、利益改善のための施策も検討しやすくなります。そのため、日々の経理記録が、経営判断という大きな目的にもつながっているのです。
税務申告に対応するため
税務申告においては、会社の収支状況や経費の内容を正確に記録や提出をすることが求められます。勘定科目は税務申告に必要な情報を整理するための基本となっており、正しい申告のためには欠かせません。
例えば、交際費や福利厚生費など、税務上の制限や控除が関係する科目では、明確な分類が重要です。帳簿が曖昧なままだと、税務調査の際に根拠を示すことが難しくなる場合もあります。日常の取引を勘定科目ごとにきちんと管理しておくことで、スムーズな税務対応とリスクの低減につながります。
【分類別】勘定科目一覧まとめ表
勘定科目の分類は主に「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つにわけられます。以下の表ではそれぞれの特徴をまとめています。
| 分類名 | 概要 |
|---|---|
| 資産 | 現金や建物など企業が保有する財産や権利 |
| 負債 | 買掛金や借入金など将来的に支払い義務のある債務 |
| 純資産 | 資産から負債を差し引いた企業の正味の価値 |
| 収益 | 商品販売やサービス提供によって得た利益 |
| 費用 | 収益を得るために必要となる支出やコスト |
ここでは、それぞれの分類について、主な勘定科目を一覧で詳しく解説していきます。
【分類:資産】主な勘定科目一覧
資産は、企業が保有する財産的価値を持つものを示す分類です。現金や預金、売掛金といった流動性の高いものから、建物や機械といった長期的に使用される固定資産まで、多様な項目が含まれます。資産に分類される主な勘定科目を以下の表に一覧でまとめました。
| 科目名 | 内容の説明 |
|---|---|
| 現金 | 企業が保有している紙幣・硬貨 |
| 普通預金 | 銀行に預け入れている資金 |
| 売掛金 | 商品・サービスを提供した未回収の代金 |
| 棚卸資産 | 販売目的で保有している商品・製品・原材料など |
| 建物 | 事業に使用する建物(店舗・事務所など) |
| 備品 | オフィス機器や工具など、長期的に使用する資産 |
例えば売掛金は、商品やサービスを提供した後に受け取るべき代金を指し、日常的な取引で頻繁に使われる項目です。これらの勘定科目を正しく理解し、適切に分類することで、企業の財務状況を的確に把握する土台が整います。資産科目は帳簿の基礎となる情報のひとつであり、経理業務における出発点といえます。
なお、売掛金についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

【分類:負債】主な勘定科目一覧
負債は、将来的に支払い義務がある債務を示す分類で、他人資本とも呼ばれます。負債に分類される主な勘定科目を以下の表に一覧でまとめました。
| 科目名 | 内容の説明 |
|---|---|
| 買掛金 | 商品・サービスを受け取ったが未払いの代金 |
| 未払金 | 費用や債務などの未払い分(例:水道光熱費など) |
| 未払費用 | 利息や給与など発生しているが未払いの費用 |
| 借入金 | 金融機関などからの借入による負債 |
| 預り金 | 社会保険料や源泉所得税など従業員から預かっている金額 |
例えば買掛金は、商品やサービスを受け取ったがまだ支払っていない代金を表し、仕入れ業務などで日常的に発生します。このほか、短期借入金や未払金など、支払期限や性質に応じてさまざまな科目があります。
負債の科目を適切に管理することは、資金繰りの安定や信用管理に直結するため、経営面でも重要な意味を持ちます。財務諸表では、資産と対になる存在として位置づけられるため、正確な記録が求められます。
なお、買掛金についてはこちらの記事で解説しています。
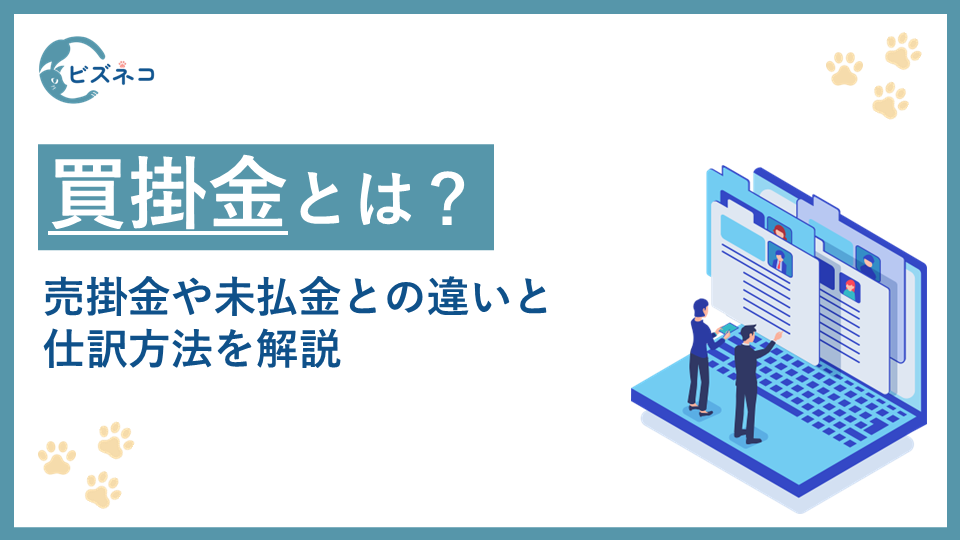
【分類:純資産】主な勘定科目一覧
純資産は、資産から負債を差し引いた残りの部分で、企業の自己資本に相当します。純資産に分類される主な勘定科目を以下の表に一覧でまとめました。
| 科目名 | 内容の説明 |
|---|---|
| 資本金 | 出資された資金で、会社設立や増資により形成 |
| 資本剰余金 | 資本金以外の出資や資本取引で発生した剰余 |
| 利益剰余金 | 過去の利益の蓄積で、配当や内部留保の原資 |
| 自己株式 | 自社が取得した自社株で、純資産から控除される項目 |
例えば資本金は、会社設立時や増資によって出資された金額を指し、企業の基礎的な財源として位置づけられます。また、利益剰余金は過去の利益の蓄積を表しており、配当や内部留保などの意思決定にも関係します。
純資産の内容を把握することは、企業の健全性や継続性を評価するうえで欠かせない要素です。外部からの信用にも影響するため、正確な分類と開示が重要となります。
【分類:収益】主な勘定科目一覧
収益は、企業が事業活動を通じて得た利益を示す項目で、売上や受取利息などが代表的です。収益に分類される主な勘定科目を以下の表に一覧でまとめました。
| 科目名 | 内容の説明 |
|---|---|
| 売上高 | 商品やサービスを提供した対価 |
| 受取利息 | 預金や貸付などに対して受け取る利息 |
| 受取配当金 | 保有する株式などから受け取る配当金 |
| 雑収入 | 主たる事業以外で得られた少額の収益 |
例えば売上高は、製品やサービスを顧客に提供した対価として得られる金額であり、企業の業績を示す重要な指標となります。収益科目は、営業活動や財務活動によって発生するため、分類と記録を誤ると利益の把握に大きな影響を及ぼします。経営者が実態を正しく把握し、戦略的な判断を行うためにも、収益項目の構造を理解しておくことが求められます。
【分類:費用】主な勘定科目一覧
費用は、事業活動を行う上で発生する支出を示す項目です。収益に分類される主な勘定科目を以下の表に一覧でまとめました。
| 科目名 | 内容の説明 |
|---|---|
| 給与手当 | 従業員に支払う給与や各種手当 |
| 広告宣伝費 | 宣伝・販売促進のために使った費用 |
| 旅費交通費 | 出張や移動にかかる交通費・宿泊費など |
| 減価償却費 | 長期資産の価値を期間ごとに配分した費用 |
| 水道光熱費 | 電気・水道・ガスなどのインフラ使用にかかる費用 |
例えば給与手当は、従業員に支払う対価であり、継続的に発生する主要な費用にあたります。その他にも、広告宣伝費や減価償却費など、性質や発生頻度に応じた多くの科目が存在します。
費用を正確に分類することは、損益の把握や経営分析の基礎となるため、経理実務において非常に重要です。費用項目の理解を深めることで、無駄な支出の把握や改善にもつなげることが可能になります。
【シーン別】勘定科目の使い方と仕訳例
勘定科目の使い方として、以下のシーンにおける仕訳例を紹介します。
- シーン1:売るためではなく自社で使う備品を購入したとき
- シーン2:売るための商品を仕入れたとき
- シーン3:受けたサービスの利用料を支払うとき
ここでは、それぞれの仕訳例について具体的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
シーン1:売るためではなく自社で使う備品を購入したとき
業務に必要な物品を購入する場面は、日常的に発生しますが、それが販売目的のものではなく自社内で使用する備品である場合、仕訳の方法が異なります。購入金額や物品の性質によって、使用する勘定科目は「消耗品費」や「備品」、あるいは「新聞図書費」などに分かれます。
例えば、13万円のノートパソコンを預金から購入した場合では、以下のように仕訳されます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 備品 | 130,000円 | 普通預金 | 130,000円 |
また、書籍などの購入についても、業務に関連するものであれば経費として処理できます。このように、同じような備品の購入という行為でも、内容によって使う勘定科目が異なるため、状況に応じた適切な判断が求められます。
シーン2:売るための商品を仕入れたとき
販売用の商品や製品を購入する場面では、主に「仕入」や「材料費」といった勘定科目が使われます。小売業が商品を買い付けて販売する場合は「仕入」、製造業が製品をつくるための原材料を購入する場合には「材料費」などが用いられます。また、支払い方法によっても貸方の勘定科目が異なり、現金払いであれば「現金」、後払いであれば「買掛金」として処理する必要があります。
例えば、イヤホンのような完成品を後払いで仕入れた場合の仕訳例は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕入 | 7,000円 | 買掛金 | 7,000円 |
原価計算や在庫管理にも直結し、企業の利益管理にも影響を与えます。そのため、適切な勘定科目の選定は、後の集計や財務分析にも大きく関わってくるのです。
シーン3:受けたサービスの利用料を支払うとき
企業活動のなかでは、物品だけでなく各種サービスの利用に対しても支出が発生します。こうした支払いについては、内容ごとに異なる勘定科目を使い分けることが重要です。
インターネットを使うための費用は「通信費」、交通機関の利用なら「旅費交通費」、配送サービスを使った場合には「荷造運賃」などが適しています。実際の支払い方法は現金だったり預金引き落としだったりするため、仕訳の貸方には選択した決済手段が反映されます。
例えば、今月分のインターネット使用料が預金から引き落とされた場合に適用される勘定科目と処理方法は以下の仕訳例のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 4,000円 | 普通預金 | 4,000円 |
サービスの仕訳は一見シンプルに見えても、積み重ねると月次決算や費用集計の精度に影響を与えるため、正確な処理が求められます。
実用性のある勘定科目を設定するルール
実用性のある勘定科目を設定するためには、以下のようなルールを設定しましょう。
- ルール1:取引内容がひと目で分かる名称にする
- ルール2:一度決めた勘定科目を継続して使う
- ルール3:細かく分類しすぎないようにする
ここでは、それぞれのルールについて具体的に解説します。
ルール1:取引内容がひと目で分かる名称にする
勘定科目は、取引の内容がすぐに把握できるような名称であることが重要です。例えば「消耗品費」や「会議費」といった科目名を見るだけで、どのような支出であるかを想像できれば、記帳する側だけでなく帳簿を確認する側にとっても負担が少なくなります。
わかりにくい名前や抽象的な表現を使ってしまうと、内容の確認に時間がかかり、ミスや誤解のもとになることもあります。特に複数の人が帳簿に関わるような現場では、誰が見ても理解できるようにしておくことが求められます。勘定科目の名称は、単なるラベルではなく、業務の効率や精度を左右する要素のひとつとして捉えることが大切です。
ルール2:一度決めた勘定科目を継続して使う
勘定科目は一度設定したら、同じ取引には同じ科目を使い続けることが大切です。例えば、昨年は「交際費」として処理していた取引を、今年は「会議費」として記帳してしまうと、比較可能なデータが得られず、経費の傾向や経営判断の精度に影響を及ぼします。
勘定科目の運用に一貫性がないと、後から修正が必要になったり、外部の税理士や会計監査人との認識にズレが生じたりするリスクもあります。また、継続性を保つことで、過去の会計データとの比較がしやすくなり、経営状況の変化を読み取りやすくなるというメリットもあります。そのため、組織内で共通のルールを共有し、科目の使い方にブレが出ないよう意識することが求められます。
ルール3:細かく分類しすぎないようにする
勘定科目を細かく分類しすぎると、かえって記帳や管理が煩雑になるおそれがあります。例えば「文房具費」「コピー用紙費」「名刺作成費」といったように、それぞれを個別に科目として設定してしまうと、仕訳のたびにどれを使うべきか迷ってしまう場面が増えてしまいます。
また、財務諸表を確認する際にも情報が細分化されすぎると全体像がつかみにくくなり、分析や判断の妨げになることもあります。実務では「消耗品費」といったある程度広い範囲をカバーできる名称を使い、必要に応じて補助科目や摘要欄などで具体的な内容を記録する方法がおすすめです。分類のしすぎは正確さよりも手間を増やしてしまうことがあるため、バランス感覚が求められます。
勘定科目を使用する際のポイント
勘定科目を使用する際には、以下のようなポイントを意識しましょう。
- 勘定科目の意味を正しく理解する
- 定期的に勘定科目の見直しを行う
- 経理代行会社に相談する
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
勘定科目の意味を正しく理解する
勘定科目は、取引の内容を記録や分類をするための基本的な枠組みです。どの科目を使えば適切かを判断するには、それぞれの勘定科目がどんな取引に対応しているかを理解しておくことが欠かせません。
例えば「通信費」と「消耗品費」はどちらも経費に分類されますが、使用用途や範囲が異なります。意味を正確に把握していないと、記帳ミスや誤解を生む原因にもなりかねません。会計処理の精度を高めるためには、勘定科目ごとの定義を知識として蓄積し、運用上の判断基準をチーム内で統一しておくことが大切です。
定期的に勘定科目の見直しを行う
勘定科目は一度決めたら終わりではなく、事業の変化に応じて柔軟に見直すことが必要です。例えば新しいサービスを開始した場合、既存の科目だけでは費用や収益を適切に管理できないケースもあります。そうしたときに対応できるよう、定期的に使用している科目の妥当性をチェックする習慣を持っておくと、管理の精度が高まります。
また、重複しているような科目やほとんど使われていない科目を整理することで、帳簿全体の可読性も向上します。変化する事業環境に合わせて、勘定科目も改善していくという意識が重要です。
なお、経理の業務フローの見直しについてはこちらの記事をご覧ください。

経理代行会社に相談する
自社で勘定科目を管理するのが難しい場合は、経理代行会社に相談するのもひとつの手です。例えば、新規に立ち上げた会社では、どの勘定科目を使えばよいのか判断がつかず、会計処理に時間がかかることも少なくありません。
勘定科目で困った際には、外部の専門家から実用的な勘定科目の設計や運用ルールについてアドバイスを受けることで、業務効率を大きく改善できます。また、日々の取引の仕訳に迷うことがあっても、経理代行会社がサポートしてくれることで、不安なく処理を進められる環境が整います。
なお、経理代行については、こちらの記事で詳しく解説しています。
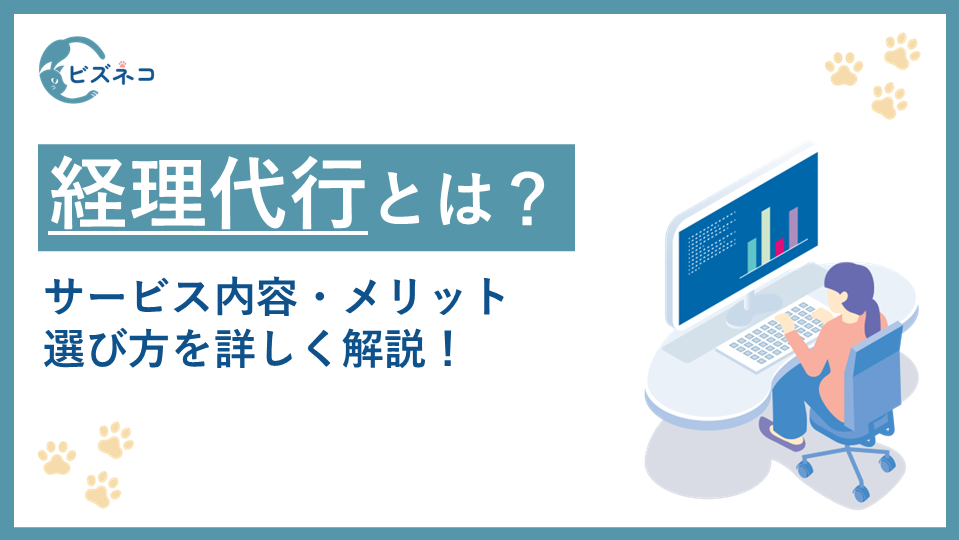
まとめ
勘定科目は、企業活動に伴う取引を分類や記録をするための基本的な項目です。仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿で取引内容を記録する際に用いられます。「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」といった5つの分類に分けられ、正確に分類することで経営状況を把握しやすくなります。
勘定科目では、取引内容がひと目で分かる名称にして、一度決めた勘定科目を継続して使い、細かく分類しすぎないようにすることをルールにしてみましょう。しかし、定期的に見直すこともポイントです。なお、勘定科目で疑問点がある場合には、経理代行会社に相談することもひとつの手です。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
勘定科目に関するよくあるご質問
勘定科目についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、勘定科目に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
5大勘定科目とは何ですか?
5大勘定科目とは、企業の取引を分類する基本項目で、資産・負債・純資産・収益・費用が該当します。資産は会社が保有する現金や建物などの財産を指し、負債は将来支払う借入金や買掛金を示します。純資産は資産から負債を差し引いた企業の価値で、収益は商品販売などで得た利益、費用は事業活動で発生する支出を指します。
一般的な勘定科目は何ですか?
一般的な勘定科目には、資産の現金・普通預金・売掛金、負債の買掛金・借入金、純資産の資本金・利益剰余金」、収益の売上高・受取利息、費用の給与手当・旅費交通費などがあります。これらは日々の取引を具体的に記録する際に使われ、現金の受け取りや支払い、従業員給与の支払いなどに分類されます。
借方と貸方はどちらがプラスですか?
借方と貸方は単純にプラス・マイナスの関係ではなく、勘定科目の種類によって増減の意味が異なります。例えば資産や費用の勘定科目では借方が増加を示し、貸方が減少となります。一方で負債や純資産、収益の勘定科目では貸方が増加を意味し、借方が減少を表します。取引内容に応じてどちらに記入するかを判断します。




