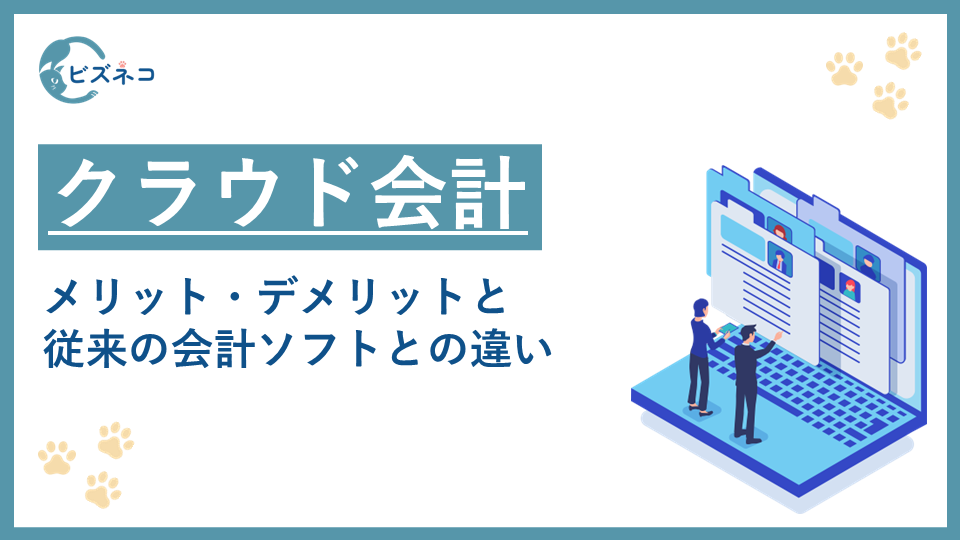
近年、企業を取り巻く環境は急速に変化しており、会計業務の効率化が求められています。クラウド会計は、こうしたニーズに応えるべく登場した革新的な会計システムです。
本記事では、クラウド会計の導入が企業の会計業務にどのような影響を与えるのか、メリットとデメリットを具体的に解説します。リスクや導入時の注意点について、クラウド会計の導入を検討している企業の経営者や経理の担当者の方に向けてまとめて紹介します。ぜひ、最後までご覧ください。
目次
クラウド会計とは?
クラウド会計とは、インターネットを通じて提供される会計ソフトであり、データはクラウド上に保存されます。ユーザーはインターネット環境があればどこからでも会計データにアクセスできるため、従来のPCにインストールするタイプの会計ソフトに比べて、非常に高い柔軟性と利便性があります。
例えば、外出先や移動中でも、スマートフォンやタブレットを使ってデータ入力や確認が可能で、経営者や担当者が業務の合間に素早く対応できる点が大きなメリットです。
また、データのバックアップやソフトのアップデートはすべてクラウド側で自動的に行われるため、ユーザーはこれらの作業を意識することなく、常に最新の状態でシステムを利用できます。そのため、クラウド会計は、経理業務の効率化やコスト削減、セキュリティの強化を目的として、多くの企業で採用が進んでいます。
なお、そもそも会計処理のやり方についてはこちらの記事も参考にしてください。
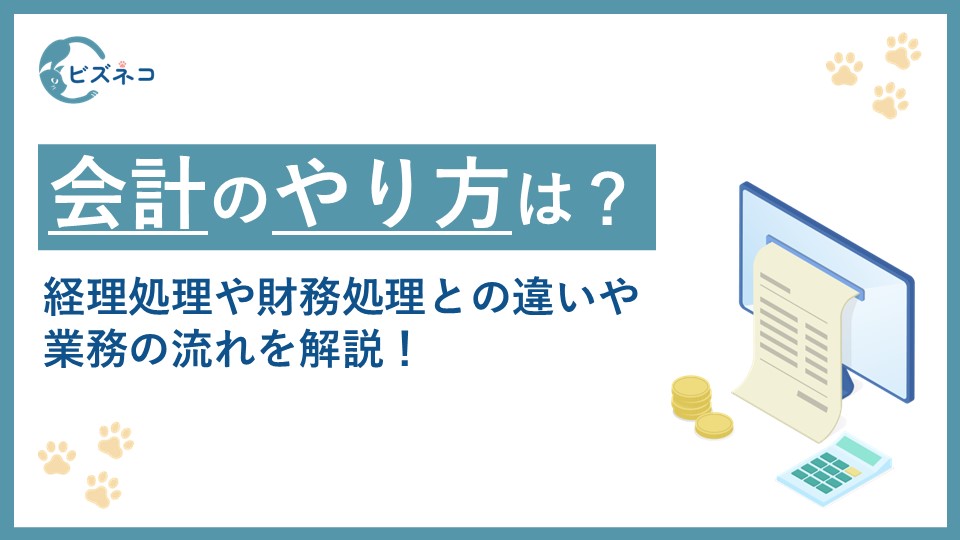
クラウド会計ソフトと従来の会計ソフトの違い
クラウド会計ソフトと従来の会計ソフトの最も大きな違いは、データの保存場所とアクセス方法にあります。
従来の会計ソフトは、PCにインストールして使用する形態で、データはそのPCに保存されます。そのため、PCを持ち歩かないとデータにアクセスできず、リモートでの作業や複数人での同時編集が難しい場合が多いです。
一方、クラウド会計ソフトでは、データはインターネット上のクラウドサーバーに保存され、インターネット環境があればどこからでもアクセスできます。このため、外出先でもデータを確認したり、入力したりできるメリットがあります。
また、複数のユーザーが同時に作業できるため、チームでの作業効率も向上し、業務のスピードが大幅に改善されます。なお、会計ソフトの選び方についてはこちらの記事も参考にしてください。
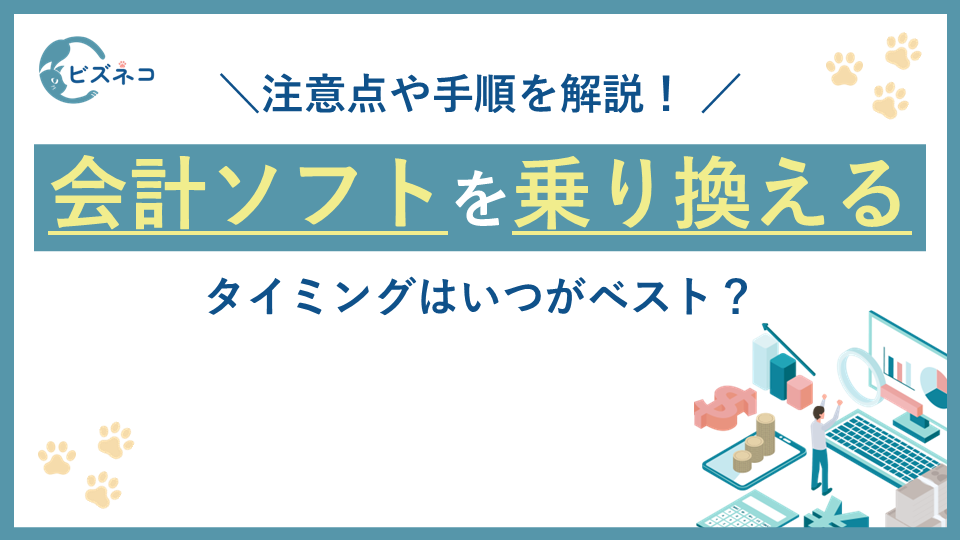
クラウド会計ソフトのメリット
クラウド会計ソフトには以下のようなメリットがあります。
- いつでもどこでも入力と承認ができる
- 最新の法改正にもすぐに対応できる
- データのバックアップが不要
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
いつでもどこでも入力と承認ができる
クラウド会計ソフトにけるメリットのひとつは、インターネット環境があれば、場所を問わずいつでも会計データの入力や承認ができる点です。従来の会計ソフトでは、PCにインストールしたソフトを使うため、特定の場所や端末に依存することがありました。
しかし、クラウド会計ソフトでは、スマートフォンやタブレットなどさまざまなデバイスを通じてアクセスできるため、移動中や外出先からでもスピーディに対応することができます。これにより、業務の進行がスムーズになり、経営者や担当者が場所に縛られることなく、時間を有効に活用できます。
最新の法改正にもすぐに対応できる
クラウド会計ソフトは、税制や法改正にもスピーディに対応できるため、常に最新の法規に基づいた処理が可能です。税制や法律が変更されるたびに、会計ソフトを手動で更新する必要がある従来のソフトとは違い、クラウド会計ソフトは自動的にアップデートされるため、ユーザーが意識することなく新しいルールに対応できます。
これにより、税務申告や帳簿作成の際に法的なミスが発生するリスクを減らすことができます。特に、税制の改正が頻繁に行われる日本では、この機能が非常に重要で、常に最新の状態で会計業務を行うことができるため、企業にとって安心にもつながります。
データのバックアップが不要
クラウド会計ソフトでは、データがインターネット上のサーバーに保存されるため、ユーザー自身がバックアップを取る必要がありません。従来の会計ソフトでは、データの保存場所やバックアップ方法を個別に管理しなければならず、もしもの場合にデータ損失のリスクが伴いました。
しかし、クラウド会計ソフトでは、システムの運営側が自動的にバックアップを行っており、万が一のトラブルやシステム障害が発生しても、データが失われることはありません。
これにより、バックアップ管理にかかる手間が省け、データの保護についての不安を減らすことができます。
クラウド会計ソフトのデメリット
クラウド会計ソフトにも以下のようなデメリットがあります。
- オフラインでは使用できない
- セキュリティ面で不安がある
- 月額費用などのコストがかかる
ここでは、それぞれのデメリットやリスクについて詳しく解説していきます。
オフラインでは使用できない
クラウド会計ソフトのデメリットのひとつは、インターネット接続がないと使用できない点です。データがクラウド上に保存されているため、インターネットにアクセスできない状況では、会計ソフトを起動したりデータの入力や承認を行ったりすることができません。
特に、インターネット環境が不安定な場所や外出先での使用時に、接続が途切れると作業が中断される可能性があります。そのため、急ぎの業務を処理する際に不便を感じることがあり、常に安定したインターネット環境が整っていることが前提となります。オフラインで使用する必要がある場合、従来型の会計ソフトに戻すか、オフラインでも使える他のシステムを検討する必要があります。
セキュリティ面で不安がある
クラウド会計ソフトは、インターネットを通じてデータを保存し管理するため、セキュリティ面に対する懸念がつきまといます。企業の機密情報や会計データがインターネット上に保存されることで、外部からのサイバー攻撃や不正アクセスのリスクが存在します。
たとえば、ハッキングやフィッシング攻撃などによって、データが漏洩したり改ざんされたりする可能性があります。もちろん、クラウドサービスの運営側は高いセキュリティ対策を行っています。しかし、完全にリスクを排除することは難しいため、企業側もパスワード管理や多要素認証の導入などを検討する必要があります。
月額費用などのコストがかかる
クラウド会計ソフトは、初期費用と月額費用など利用料がかかるため、長期的に見るとコストがかさむ可能性があります。従来の会計ソフトでは一度購入するだけで済むことが多いのに対し、クラウド型は毎月一定の費用を支払い続ける必要があります。
これにより、中小企業や個人事業主にとっては、予算管理が厳しくなることがあります。料金プランや機能に応じて費用が異なるため、必要な機能を見極めて最適なプランを選択する必要もあるでしょう。また、利用するユーザー数やデータ容量の増加に伴って、費用が変動する場合もあり、コストが予想以上に高くなるリスクも考慮しなければなりません。
クラウド会計ソフトを導入するための準備
クラウド会計ソフトを導入する際には、以下の手順で準備を進めていきましょう。
- step1:顧問税理士が対応できるか確認する
- step2:勘定科目をカスタマイズする
- step3:銀行口座やクレジットカードを連携する
- step4:既存の会計ソフトからデータを移行する
ここでは、それぞれのステップを詳しく解説していきます。
step1:顧問税理士が対応できるか確認する
クラウド会計ソフトを導入する前に、顧問税理士がそのソフトに対応できるかどうかを確認することは重要です。税理士が既存の会計ソフトに精通している場合、クラウド会計ソフトへの移行がスムーズに進まない可能性があるでしょう。
税理士側が新たなシステムに対する理解や対応が求められるため、事前に顧問税理士に相談して、使用するソフトが現状の帳簿の形式に対応できるかを確認しましょう。税理士が対応可能であれば、スムーズに導入と運用が期待でき、万が一の問題が発生した場合にもスピーディに対応しやすくなります。また、税理士の意見を取り入れて、より適切なソフトを選ぶことができるため、導入後のトラブルも防ぎやすくなります。
step2:勘定科目をカスタマイズする
クラウド会計ソフトでは、標準的な勘定科目が用意されていますが、企業ごとに必要な項目をカスタマイズすることが重要です。特に、業種や企業の規模により必要な勘定科目が異なるため、あらかじめ自社の会計ニーズに合わせて設定を行うことが必要です。
例えば、売上や仕入れに関連する勘定科目を追加したり、独自の取引に対応した項目を設けたりすることで、経理業務の効率化が進みます。また、カスタマイズが不十分だと、取引データの入力ミスや不正確な集計が発生することがあります。そのため、慎重に設定を行い、後の業務に支障をきたさないようにすることが大切です。導入前に設定作業を完了させておくことで、運用開始後にスムーズに移行できます。
step3:銀行口座やクレジットカードを連携する
クラウド会計ソフトに銀行口座やクレジットカードとの連携をしていきましょう。連携することで、取引データが自動的に会計ソフトに取り込まれ、手作業での入力が減り、作業効率が大幅に向上します。
そのため、導入前には、自社が利用している銀行口座やクレジットカードが対応しているかを確認し、必要な連携設定を行いましょう。多くのクラウド会計ソフトでは、銀行のオンラインサービスと連携できる機能を提供しています。しかし、対応する金融機関によっては設定が複雑になることもあるため注意しましょう。連携に必要な情報や手順を事前に確認し、必要な設定を完了させておくことで、運用開始後の混乱を防ぐことができます。
step4:既存の会計ソフトからデータを移行する
各種設定が完了したら、既存の会計ソフトからデータを移行するステップに移ります。既存の会計ソフトからデータを移行することは重要なステップです。これにより、過去の会計データを新しいシステムでも引き継ぎ、整合性の取れた帳簿を維持することができます。
移行作業には、取引履歴や仕訳帳などのデータを手動で入力する場合もあります。しかし、多くのクラウド会計ソフトでは、既存の会計ソフトとのデータ連携機能があるため活用していきましょう。連携機能を利用することで、データの移行がスムーズに進み、誤入力や二重入力を防ぐことができます。ただし、移行作業は慎重に行い、完了後にはデータの正確性を確認し、帳簿の確認を行うことがおすすめです。
なお、スピーディなクラウド会計ソフトの導入には、経理代行会社へ依頼することもひとつの手です。
弊社では、経理代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な経理業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
クラウド会計ソフトを使用する際の注意点
クラウド会計ソフトを使用する際には、以下のような点に注意しましょう。
- e-Taxに対応できるようにしておく
- あらかじめ権限を付与するメンバーを決めておく
- 動作が遅い場合があることを念頭に置く
ここでは、それぞれの注意点について詳しく解説していきます。
e-Taxに対応できるようにしておく
クラウド会計ソフトを使用する際は、e-Tax(電子申告)に対応できるように設定を整えておくことが重要です。e-Taxを利用することで、税務申告がオンラインで完結し、手間を大幅に削減することができます。
しかし、クラウド会計ソフトがe-Taxと連携できるかどうかは、ソフトの種類によって異なるため、導入前にその対応状況を確認する必要があります。もし対応していない場合、別途ソフトを導入したり、手作業での申告を行う必要が出てくることもあります。
さらに、e-Taxを使うためには、マイナンバーカードや電子証明書の準備が必要になることもあるため、これらの手続きを事前に進めておくことが求められます。申告期限を守るためにも、e-Taxをスムーズに利用できる体制を整えておくことが大切です。
あらかじめ権限を付与するメンバーを決めておく
クラウド会計ソフトを導入する際には、誰がどのような権限でアクセスするかをあらかじめ決めておくことが重要です。特に、複数のメンバーが使用する場合、管理者や経理担当者、チェック担当者など、それぞれの役割に応じた権限設定を行うことで、セキュリティや業務効率を高めることができます。
権限を明確にし、アクセスできる範囲を限定することで、不必要なデータの閲覧や操作ミスを防ぐことができ、データの正確性や機密性を保つことができます。また、役割に応じた権限を設定することで、業務がスムーズに進行し、トラブルや誤操作を未然に防ぐことができます。
動作が遅い場合があることを念頭に置く
クラウド会計ソフトを利用する際には、インターネット接続状況によっては、動作が遅くなることがある点を念頭に置いておく必要があります。クラウド型のソフトは、全てのデータがインターネット上のサーバーに保存され、そこにアクセスして作業を行うため、通信速度やサーバーの負荷によっては、処理が遅れることがあります。
特に、大量のデータを取り扱う場合や、同時に多くのユーザーがアクセスしている場合には、レスポンスが遅くなり、業務の効率に影響を与える可能性もあります。遅延を避けるためには、高速なインターネット接続を確保することが重要であり、もし遅延が頻発する場合は、システムの運用元に問い合わせて、サーバー側の改善策を検討することが求められます。
まとめ
クラウド会計ソフトは、インターネットを通じてデータを管理し、どこからでもアクセスできる点が特徴です。利便性やコスト削減、法改正へのスピーディな対応などのメリットがあります。一方で、オフラインで使用できない点などのデメリットも存在します。そのため、導入には、顧問税理士との確認や勘定科目のカスタマイズ、データ移行などが必要になるでしょう。
なお、スピーディなクラウド会計ソフトの導入には、経理代行会社へ依頼することもひとつの手です。
弊社では、経理代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な経理業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
クラウド会計のメリットに関するよくあるご質問
クラウド会計のメリットについてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、クラウド会計のメリットに関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
三大クラウド会計ソフトとは何ですか?
日本でのシェアの高い三大クラウド会計ソフトは、「弥生会計」「マネーフォワードクラウド会計」「freee会計」の3つです。大手企業だけではなく、中小企業やベンチャー企業、フリーランスの方まで幅広く活用されています。シェアの高い会計ソフトはシステムの改善も頻繁に行われるため、使いやすい点が特徴です。
クラウド型とインストール型の違いは何ですか?
クラウド型とインストール型の違いは利用方法にあります。クラウド型会計ソフトは、インターネットを介してデータをクラウド上で管理し、どこからでもアクセスできます。リアルタイムで複数人が同時に作業できる点も特徴です。一方で、インストール型はPCにソフトをインストールし、データがPCに保存されます。
クラウド会計の問題点は何ですか?
クラウド会計の主な問題点は、インターネット接続が必須で、オフラインでの利用ができないことです。また、セキュリティ面で不安があり、サイバー攻撃や不正アクセスのリスクがあります。さらに、月額費用が発生するため、長期的に見るとコストがかかり、中小企業や個人事業主にとっては負担となることがあります。




