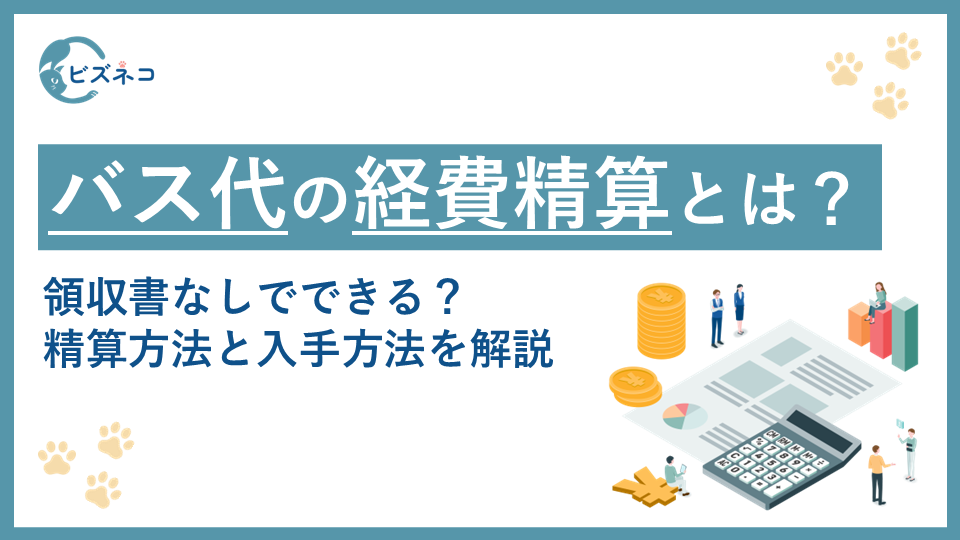
結論、バス代の経費精算は一定の条件を満たせば領収書なしで精算が可能です。業務で移動する際、バスを利用することは珍しくありません。しかし、現金払いやICカード利用など、支払い方法がさまざまなため、「領収書がないと経費精算できないのでは?」と悩む方も多いでしょう。
バス代の経費精算では、経路や支払い金額を証明する手段を準備し、社内ルールに沿って申請することが求められます。この記事では、バス代を経費として処理する際の基本から、領収書を入手する方法、領収書なしで精算する際の注意点までを詳しく解説します。
目次
バス代の経費精算は領収書なしでできる?
結論から言えば、バス代の経費精算は領収書がなくても可能です。ただし、金額が3万円未満であることが基本的な前提となります。例えば、日常的な営業活動で利用する路線バスや短距離の移動であれば、ICカードの利用履歴や経路メモなどを証拠として提出することで十分に精算が認められます。
一方で、出張や長距離の移動など金額が大きくなる場合は、領収書の提出が求められることもあります。領収書がないからといって必ずしも経費として認められないわけではありませんが、正確な経路や支払金額を説明できる証拠を残しておくことが重要です。経理処理の手間を減らすためにも、日常的に利用するICカードの履歴を確認・保存しておく習慣をつけるとよいでしょう。
交通費精算の基本的なルール
交通費精算の基本的なルールとして、以下の点を心得ておきましょう。
- ルール1:業務に必要な移動のみを対象とする
- ルール2:実際に支払った金額で精算する
- ルール3:領収書や経路を証明として提出する
- ルール4:定期券区間や通勤経路との重複を避ける
- ルール5:社内規定に基づいた申請期限を守る
ここでは、それぞれのルールについてまとめて紹介します。
ルール1:業務に必要な移動のみを対象とする
交通費として精算できるのは、業務上の必要な移動に限られます。私的な外出や通勤のついでに立ち寄った場合など、業務と関係のない移動は経費として認められません。
例えば、顧客訪問や打ち合わせ、研修への参加など、会社の指示や業務目的が明確であれば精算の対象となります。一方で、休日の外出や私用を兼ねた移動は対象外です。経理では業務目的が確認できるかどうかを重視するため、出発地や目的地を明確に記録しておくことが大切です。あいまいな申請は差し戻しの原因にもなるため、どの移動が業務に必要だったのかを説明できるよう意識しておく必要があります。
ルール2:実際に支払った金額で精算する
交通費精算は、実際に支払った金額に基づいて行うのが原則です。定期券区間を含めた金額やおおよその見積もりで申請してしまうと、経理上の不正確な処理につながるおそれがあります。
例えば、バスや電車を利用した場合は、実際に支払った運賃をICカードの履歴や運賃表などで確認し、その金額を正確に記載します。実費精算を徹底することで、経理処理の正確性が保たれ、社員間の公平性も確保されます。また、経費として認められるかどうかの判断材料にもなるため、支払金額の根拠を明確にしておくことが重要です。
ルール3:領収書や経路を証明として提出する
交通費の精算では、領収書や利用経路の証明が欠かせません。例えば、バスや電車を利用した場合、領収書がないときはICカードの利用履歴や経路検索の結果を提出することで代替できます。経理担当者は、実際にその経路で業務が行われたかどうかを確認するため、証拠資料の提出を求めるのです。
領収書がない場合でも、経路や日時、目的を正確に記録していれば、十分に精算が認められるケースがあります。証明資料は単なる形式ではなく、会社の信頼性を保つうえでも大切な役割を果たすため、提出を怠らないようにしましょう。
ルール4:定期券区間や通勤経路との重複を避ける
交通費を精算する際は、定期券区間や通勤経路と重複しないよう注意が必要です。定期券を持っている場合、その区間はすでに会社から交通費として支給されているため、重複申請すると二重払いになってしまいます。
例えば、自宅から最寄駅までが定期区間に含まれている場合、その部分の運賃は精算の対象外となります。経理担当者は、定期区間の申請内容を確認したうえで差額を計算することが多いため、申請者側も自分の定期区間を正確に把握しておくことが大切です。重複を防ぐことで、経費の透明性を維持し、社内の信頼関係を保つことにもつながります。
ルール5:社内規定に基づいた申請期限を守る
交通費精算は、社内で定められた申請期限を守ることが求められます。例えば、月末締めの翌月末日までといった期限がある場合、過ぎると経費として認められないこともあります。経理部門は一定期間ごとに帳簿を締めて処理を行うため、遅延が発生すると会計全体の進行にも影響します。
申請者自身の管理が不十分だと、後で精算ができず自己負担となるケースもあるため注意が必要です。日々の業務が忙しくても、出張や移動の記録をその日のうちに残し、早めに申請を済ませる習慣をつけておくことが、スムーズな経費処理につながるでしょう。
バスを利用した際に領収書をもらう方法
バスを利用した際の経費精算では、領収書の有無が大きなポイントになります。現金払いやICカード利用、事前決済など、支払い方法によって領収書の入手方法は異なります。
例えば、路線バスでは車内で発行してもらえるケースもあれば、高速バスや貸切バスでは予約サイトや事業者から受け取ることが一般的です。ここでは、支払い方法ごとに領収書の取得方法を詳しく見ていきましょう。
路線バスを利用した際に領収書をもらう方法
路線バスの領収書は、支払い方法によって対応が異なります。例えば、現金で支払う場合は運転手にその場で申し出ることで発行してもらえることが多いですが、ICカードを利用した場合は履歴を印字して証拠とする方法が一般的です。どちらのケースでも、経費精算に使う場合は日付や区間が分かる形で記録を残しておくことが大切です。
現金で支払った場合
現金で路線バスの運賃を支払った場合、領収書は運転手に依頼すればその場で発行してもらえるケースがあります。ただし、すべてのバス会社が対応しているわけではなく、走行中や混雑時にはすぐに発行できないこともあります。
例えば、都市部の一部バス会社では、後日営業所で領収書を受け取る対応を行っていることもあります。そのため、経費精算に必要な場合は、乗車前に領収書発行の可否を確認しておくと安心です。どうしても発行が難しい場合は、利用日時や区間、金額をメモに残し、上長や経理部門に報告しておくことで、証拠として代用できる場合もあります。
ICカードで支払った場合
ICカードで路線バスの運賃を支払った場合は、領収書の代わりに利用履歴を印字して提出するのが一般的です。例えば、駅の券売機や交通系ICカードの専用サイトから、乗車区間や日付が記載された履歴を出力できます。
利用履歴を経費精算書に添付することで、支払いの証拠として認められることが多いです。ただし、複数の交通機関を利用している場合は、どの履歴がバス利用分なのかを明確にしておくことが重要です。ICカードは利便性が高い一方で、明細の確認を怠ると誤った精算につながる恐れもあるため、定期的に履歴を確認しておくとよいでしょう。
高速バスを利用した際に領収書をもらう方法
高速バスを利用する場合、路線バスとは異なり、事前予約やオンライン決済など、支払い方法がさまざまあります。例えば、現金で購入した際は窓口で領収書を受け取り、ネット予約ならメールやマイページから発行できます。
支払い方法ごとに取得方法が変わるため、経費精算を想定してチケット購入時に領収書の発行手段を確認しておくことが大切です。
現金で支払った場合
高速バスを現金で支払った場合は、購入した窓口やチケット売り場で領収書を受け取ることができます。例えば、バス会社のカウンターで現金払いをすると、乗車券と一緒に領収書を発行してもらえるのが一般的です。
もし発行を忘れた場合でも、購入時の控えやレシートを提示すれば、後日再発行に応じてもらえるケースもあります。経費精算に利用する場合は、宛名や但し書きを正確に記載してもらうことも忘れずに行いましょう。なお、車内で現金払いを行う高速バスでは領収書を即時発行できないこともあるため、事前に乗車案内やバス会社のサイトで対応可否を確認しておくと安心です。
ICカードで支払った場合
ICカードで高速バスの運賃を支払う場合、利用履歴を印字して提出することが基本となります。例えば、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードで対応している高速バスでは、券売機や駅端末、ウェブサイトから履歴を出力できます。
ただし、高速バスの場合は乗車区間の特定が難しいケースもあるため、申請時に目的地や利用日を明記しておくと良いでしょう。また、ICカードのシステム上、複数の交通機関が混在して記録されることもあるため、精算に使う履歴部分を明確にして提出することが重要です。経費処理の正確性を保つためにも、定期的にデータを保存しておくと安心です。
事前決済で支払った場合
インターネットで事前決済した高速バスの領収書は、予約完了後にメールやマイページからダウンロードできます。例えば、クレジットカードや電子マネーで決済した場合、バス会社や予約サイトから電子領収書が発行されるのが一般的です。
印刷して紙の領収書として提出するか、社内規定で認められている場合はPDFデータを添付して申請する方法もあります。支払い方法によって発行元が異なるため、どのサイト経由で購入したかを明確にしておくことが大切です。もし領収書の再発行が必要になった場合は、決済履歴や予約番号をもとに申請できる場合もあるため、記録を残しておくとスムーズに対応できます。
貸切バスを利用した際に領収書をもらう方法
貸切バスを利用した場合の領収書は、基本的に契約時や運行終了後にバス会社から発行されます。例えば、旅行や社内イベントなどでバスを貸し切る場合は、見積書や請求書の形で金額が提示され、支払い完了後に正式な領収書を受け取ります。
支払い方法は現金・振込・カード決済などさまざまですが、どの場合も宛名や但し書きを明確に記載してもらうことが重要です。特に、参加者の送迎を目的とする場合は「業務出張用」など具体的な用途を記載しておくと、経費精算時の確認がスムーズになります。万が一、領収書を紛失した場合は、支払い明細や請求書を代替資料として提出できることもあります。
なお、社用車などで出張や営業に高速道路を利用する際にETCを利用した際の経費精算については、こちらの記事も参考にしてください。

領収書なしでバス代を経費精算する際のポイント
領収書なしでバス代を経費精算する際のポイントとして、以下の点を意識しておきましょう。
- 日付・区間・金額を明記する
- 社内規定に従って上長の承認を得る
- 交通系ICカードの利用履歴を添付する
ここでは、それぞれのポイントについて具体的に解説します。
日付・区間・金額を明記する
領収書がない場合でも、日付・区間・金額を明確に記載していれば経費精算は可能です。例えば、営業先への移動でバスを利用した場合、「〇月〇日・新宿駅から渋谷駅まで・210円」といったように、具体的な情報を記録しておくことが求められます。
これらの情報がそろっていれば、経理担当者は実際に業務に必要な移動であったかを確認しやすく、証憑としても十分な信頼性を持ちます。また、複数の移動をまとめて申請する際は、日ごとに整理して記録を残しておくと、後から確認が必要になった場合にもスムーズです。あいまいな記載は差し戻しの原因になるため、可能な限り具体的に書くことを心がけましょう。
社内規定に従って上長の承認を得る
領収書がない状態で経費を精算する場合、必ず社内規定に従って上長の承認を得ることが重要です。例えば、規定で「領収書を紛失した場合は申請書を提出する」や「金額の上限を3,000円とする」と定められている場合、規定に沿った手続きを踏まなければ精算は認められません。
上長の承認は、業務上の移動であることを会社として正式に認める意味を持ちます。そのため、申請の際には目的や経路、金額などを正確に伝え、承認が得られるように丁寧に説明することが大切です。こうしたルールを守ることで、経理処理の透明性が保たれ、不正防止にもつながります。
交通系ICカードの利用履歴を添付する
交通系ICカードを利用した場合、利用履歴を提出することで領収書の代わりにできます。例えば、SuicaやPASMOの履歴を駅の券売機や専用サイトから印字すれば、日付や区間、金額が明確に記載された公式な証拠となります。
利用履歴を経費申請書に添付すれば、経理側も正確な支払い内容を確認しやすくなり、領収書がなくてもスムーズに精算が進みます。ただし、複数の交通機関を利用している場合は、どの履歴が業務利用なのかを自分で明示する必要があります。特に私用と業務の履歴が混在している場合は、経費対象外のものを除いて提出することが大切です。
ICカードでバス代を経費精算する際の注意点
ICカードでバス代を経費精算する際の注意点として、以下のような点があります。
- 用途不明の利用履歴がないか確認する
- 物品購入の履歴がないか確認する
- 区間や期間が間違っていないか確認する
ここでは、それぞれの注意点について詳しく解説します。
用途不明の利用履歴がないか確認する
ICカードを使ってバス代を経費精算する際は、用途不明の履歴が含まれていないかを確認することが大切です。例えば、業務目的で利用した乗車履歴の中に、私用での移動が混在していると、経費として認められないだけでなく、誤って申請したと疑われるリスクもあります。
特に同じICカードを通勤や買い物などにも使用している場合、履歴を精査しないまま提出すると、経理側で確認に時間がかかることがあります。業務に関連する乗車日や経路を明確にし、私用分をあらかじめ除外しておくことで、スムーズな承認につながります。用途があいまいなまま申請しないよう、利用前後の目的をしっかり記録しておく習慣をつけることが重要です。
物品購入の履歴がないか確認する
ICカードの利用履歴には、バスや電車の運賃だけでなく、駅ナカの店舗や自動販売機での買い物履歴が記録される場合があります。例えば、出張の際に飲み物を購入した支払いが交通費の履歴と並んで記録されているケースもあるでしょう。そのまま経費申請してしまうと、交通費として不適切な支出を含めてしまうおそれがあります。
経理部門では、経路や金額の整合性を確認しており、誤った履歴を含めると差し戻しや再提出が必要になることもあります。申請前に履歴をよく確認し、交通費以外の利用を除外しておくことで、申請内容の正確性が保たれます。特にICカードを複数用途で使う場合は、経費専用カードの使用を検討するのもおすすめです。
区間や期間が間違っていないか確認する
ICカードの利用履歴をもとにバス代を経費精算する場合、区間や期間に誤りがないかを確認することが欠かせません。例えば、バスを乗り継いだ際に自動で区間が正しく反映されていなかったり、同じ日に複数回利用した履歴が重複して記録されていたりすることがあります。
こうしたミスを放置したまま申請すると、経理処理の整合性が取れず、差し戻しの原因となることがあります。また、過去分の履歴をまとめて申請する際には、利用日が精算期限内であるかも合わせて確認する必要があります。日付や区間を正確に把握し、不要な記録を削除したうえで提出すれば、経理担当者も確認しやすく、スムーズな精算につながります。
まとめ
バス代の経費精算は領収書の有無にかかわらず、正確な記録と社内ルールの遵守が大切です。例えば、日常的な営業活動で利用する路線バスであれば、ICカードの利用履歴や経路メモでも証拠として十分に認められます。重要なのは、業務に必要な移動であることを明確にし、日付・区間・金額を具体的に残すことです。
領収書が発行できない場合でも、利用履歴や申請書を添付し、上長の承認を得ることで適切に処理できます。また、ICカードを利用する際は私用の履歴や誤記録を除外し、経費対象分のみを明示することが求められます。日常的に履歴を保存しておく習慣をつけることで、精算ミスや差し戻しを防ぎ、スムーズな経理処理を実現できるでしょう。なお、経費精算の課題は経理代行会社に相談することもおすすめです。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
バス代の経費精算に関するよくあるご質問
バス代の経費精算についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、バス代の経費精算に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
バス代の経費精算はできますか?
はい、業務に必要な移動であればバス代も経費精算ができます。営業先への訪問や出張など業務目的が明確な場合は、経費として認められます。領収書がない場合でも、ICカードの利用履歴や経路メモなどで支出を証明すれば問題ありません。ただし、私用の移動や通勤経路と重なる部分は対象外となるため注意しましょう。
バスで支払いをしたら領収書はもらえますか?
バスでは、運転手や窓口で依頼すれば領収書を発行してもらえることもあります。路線バスでは乗車時または降車時に運転手へ「領収書をください」と伝えると、その場で金額・日付入りの領収書が発行されます。ただし、発行に対応していない地域や路線もあるため、事前確認や、ICカードの利用履歴での対応がおすすめです。
バス代の領収書の但し書きは何ですか?
バス代の領収書の但し書きには、一般的に「バス代」や「乗車料金」と記載します。「営業訪問のための交通費」といった具体的な内容を補足しても問題ありません。領収書の発行元によっては但し書き欄が印字形式になっていることもありますが、手書きで記入する場合は支払い内容が明確に分かる表現を選びましょう。




