
事業を継続するうえで欠かせないのが「運転資金」です。日々の仕入れや人件費、家賃など、売上を得るために必要な経費をまかなうための資金であり、企業の血液ともいえる存在です。
多くの経営者が頭を悩ませるのが「いくら確保すべきか」という点ですが、一般的には売上または経費の3か月分を目安とするのが安心とされています。本記事では、運転資金の基本的な考え方から、計算式や内訳、種類、さらに資金を調達する方法までをわかりやすく解説します。運転資金の全体像をつかみ、安定した経営を実現するための第一歩としてぜひ参考にしてください。
目次
運転資金(所要運転資金)とは?
運転資金とは、企業が日々の事業活動を円滑に行うために必要な資金を指します。例えば、商品を仕入れて販売するまでの間に発生する仕入代金や人件費、家賃、光熱費など、営業を続けるうえで欠かせない経費をまかなうための資金です。売上が発生しても代金の入金までにはタイムラグがあるため、その間の資金を補う役割を果たします。
こうした運転資金の確保は、資金繰りの安定につながり、経営を持続させるための基盤となります。十分な運転資金を把握や管理をすることは、企業の健全なキャッシュフローを維持し、突然の支出にも対応できる体制を整えるうえで欠かせません。
運転資金と設備資金の違い
運転資金と設備資金の違いは、使い道と回収期間にあります。運転資金は、例えば仕入代金や人件費、家賃など日々の営業活動に必要な短期的な資金を指すのに対し、設備資金は工場や店舗の建設、機械の導入など長期的な投資に使われる資金です。
運転資金は日常的に動く性質があり、売上によって循環する一方で、設備資金は一度支出すると長期間にわたり回収していく特徴があります。このように両者を明確に区別して管理することは、資金計画を立てるうえで重要です。経営の安定には、短期・長期の資金バランスを意識した戦略的な資金運用が求められます。
運転資金は売上か経費の3か月分が目安
運転資金は、一般的に売上または経費の3か月分を確保しておくのが目安とされています。これは、売上の入金までに時間がかかる場合や、急な支出が発生したときでも事業を安定して続けられるようにするためです。
例えば、取引先からの入金が月末締め翌月末払いの場合、実際に現金が入るまで1〜2か月のズレが生じます。その間も従業員の給与や家賃、仕入代金などの支払いは待ってくれません。こうした資金のタイムラグを乗り切るためには、数か月分の運転資金を確保しておくことが重要です。3か月という目安は、一般的な企業の資金回転期間を踏まえたバランスのよい基準として、多くの経営者に採用されています。
運転資金を求めるための計算式
運転資金を求めるには、以下の計算式を用います。
- 売掛金+在庫資産-買掛金
この式は、企業が実際に手元に置いておくべき資金量を示すもので、資金の流れを数値として明確にするのに役立ちます。例えば、売掛金は将来的に入金される予定の資金であり、在庫資産はまだ現金化されていない商品です。
一方、買掛金は仕入先への支払い義務を表します。これらを組み合わせることで、事業運営に必要な正味の資金がどの程度かを把握できます。この計算によって、余裕資金があるか不足しているかを判断でき、資金繰りの改善策を検討する際の重要な指標となります。定期的に計算し、変動に応じて資金計画を見直すことが安定経営につながるでしょう。
なお、売掛金についてはこちらの記事も参考にしてください。

買掛金についてはこちらをご覧ください。
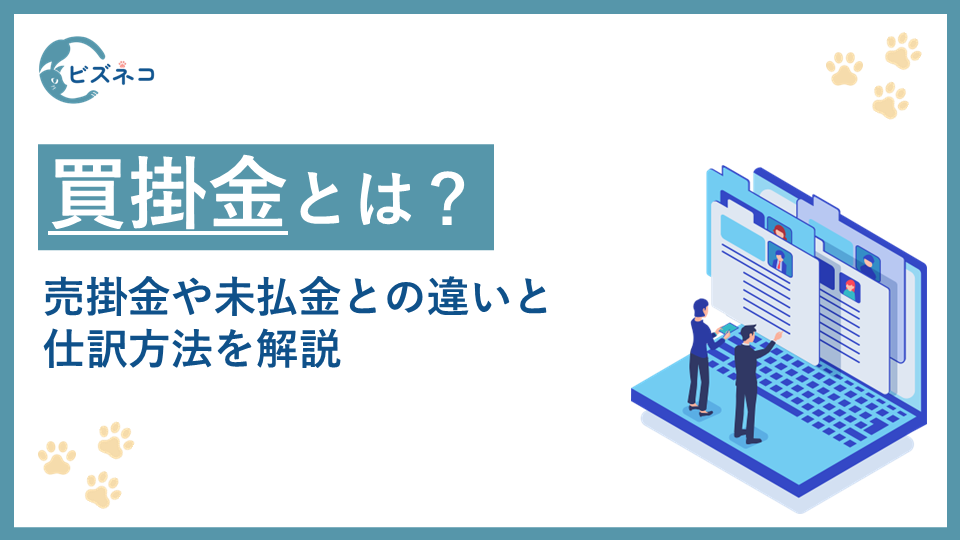
運転資金の内訳を把握するための2つの経費
運転資金の内訳を把握するためには、「変動費」と「固定費」に分類して考えることが大切です。変動費は売上や生産量の増減に応じて変化する費用を指し、固定費は売上や生産量の増減に関係なく、一定額発生し続ける費用を指します。ここでは、それぞれの違いについて具体的に解説します。
変動費
変動費とは、売上や生産量の増減に応じて変化する費用を指します。例えば、製品を多く作れば原材料費や外注費、販売に伴う送料などが増えるように、事業活動の規模に比例して動く性質を持っています。変動費の特徴を理解することで、売上の変化に対してどの程度のコストが発生するのかを把握でき、利益率の分析にも役立ちます。
運転資金を考えるうえでは、この変動費の割合が大きいほど資金繰りに影響しやすくなるため、適切なコスト管理が重要です。定期的に変動費を見直し、仕入価格の交渉や外注コストの最適化を行うことで、資金の余裕を確保しやすくなります。
固定費
固定費とは、売上や生産量の増減に関係なく、一定額発生し続ける費用を指します。例えば、毎月の家賃や人件費、通信費、保険料などがこれにあたります。事業を継続する限り支払いが必要となるため、運転資金を見積もる際には特に注意が必要です。
固定費が多い企業は、売上が減少しても支出が変わらないため、資金繰りが厳しくなるリスクが高まります。逆に、固定費を抑えることができれば、景気の変動や売上減少時にも柔軟に対応できます。運転資金を安定的に確保するためには、固定費と変動費のバランスを把握し、支出構造を見直すことが重要です。
運転資金の回転期間とは?
運転資金の回転期間とは、企業が投入した資金を回収するまでにかかる期間を示す指標です。例えば、商品を仕入れてから販売し、その代金を回収するまでの一連の流れに要する日数を指します。回転期間が短いほど、資金が効率的に循環しているといえ、逆に長い場合は資金が滞留している可能性があります。
運転資金の回転期間を把握することは、資金繰りを安定させるうえで欠かせません。売掛金の回収が遅れたり、在庫が増えすぎたりすると、手元資金が不足しやすくなるため、経営リスクも高まります。定期的に回転期間を確認し、仕入や販売条件の見直しを行うことで、資金の流れを健全に保ち、安定した事業運営につなげることができます。
運転資金の種類
運転資金には、以下のような種類があります。
- 経常運転資金(正味営業運転資金)
- 増加運転資金
- 減少運転資金
- 季節運転資金(賞与資金・決算資金・季節資金)
ここでは、それぞれの運転資金の種類や役割について具体的に解説します。
経常運転資金(正味営業運転資金)
経常運転資金とは、企業が日常的に事業活動を行ううえで常に必要となる資金のことを指します。例えば、仕入代金の支払いや人件費、光熱費など、売上を得るための通常の営業活動に伴う支出が該当します。
経常運転資金は、事業が継続する限り常に発生するため、短期的な一時資金とは異なり、安定して確保しておく必要があります。売掛金の回収や在庫の変動などによって資金が一時的に不足することもあるため、経常運転資金を把握しておくことは資金繰りの基礎となります。そのため、適切な管理を行うことで、日々の業務を安定的に進めることができ、予期せぬ資金不足を防ぐことにもつながります。
増加運転資金
増加運転資金とは、売上の拡大や事業の拡張に伴って新たに必要となる運転資金を指します。例えば、新規取引先が増えたり、生産量が増加したりする場合、仕入や人件費、在庫の確保にかかる支出が一時的に増えることがあります。
こうした事業の拡大期には、入金よりも支払いが先行するケースが多く、資金繰りに負担がかかりやすくなります。そのため、成長戦略を立てる際には、増加運転資金の確保を事前に計画しておくことが重要です。金融機関からの融資や内部留保の活用など、複数の調達手段を組み合わせることで、資金循環を維持しながら事業拡大を実現できます。
減少運転資金
減少運転資金とは、売上の減少や在庫削減などによって運転資金の必要額が減ることを指します。例えば、取引規模を縮小したり、効率的な在庫管理を導入したりすることで、仕入や支払いにかかる資金を抑えることができます。こうした状態では手元資金に余裕が生まれるため、新たな投資や借入金の返済に充てることも可能です。
ただし、減少が一時的なものであった場合、再び資金需要が高まるリスクもあるため、慎重な資金管理が求められます。減少運転資金は、経営の効率化を図る上での成果指標にもなり、無駄のない運営体制を築くための重要なポイントといえます。
季節運転資金(賞与資金・決算資金・季節資金)
季節運転資金とは、特定の時期にだけ必要となる一時的な資金のことを指します。例えば、夏や冬の繁忙期に向けた仕入増加、年末の賞与支給、決算期に伴う税金の支払いなどがこれにあたります。
季節運転資金の支出は定期的に発生する一方で、通常の経常運転資金とは異なり、期間限定の性質を持っています。そのため、毎年の資金需要を見越して計画的に準備することが重要です。季節運転資金を正しく把握しておけば、繁忙期の資金不足を防ぎ、余裕を持った資金繰りが可能になります。特に売上が季節に左右されやすい業種では、年間を通じた資金計画が経営の安定につながります。
運転資金の主な項目
運転資金には主に以下のような項目があります。
- 人件費
- 事業所や店舗の維持費
- 仕入代金
- 備品費
- 営業諸経費
ここでは、それぞれの項目について具体的に解説します。ぜひ、自社の運転資金を見直す際の参考にしてみてください。
人件費
人件費は、企業の運転資金の中でも最も大きな割合を占める支出のひとつです。例えば、従業員の給与や賞与、社会保険料、福利厚生費などがこれに含まれます。これらは毎月一定額発生する固定的な費用であり、売上の増減に関係なく支払いが必要です。
そのため、資金繰りの計画を立てる際には人件費の支出時期と入金サイクルのズレを把握しておくことが重要です。また、従業員数の増加や賞与支給時期には一時的に支出が膨らむため、あらかじめ予算に組み込み、余裕を持って資金を確保しておくことが安定経営につながります。
事業所や店舗の維持費
事業所や店舗の維持費は、事業を継続するうえで欠かせない固定的な経費のひとつです。例えば、毎月の家賃や共益費、電気・水道・ガスなどの光熱費、清掃や警備の委託費などが該当します。
事業所や店舗の維持費は売上が少ない月でも発生するため、安定的な支払いを行うためには運転資金としての備えが不可欠です。また、店舗やオフィスの規模が大きいほど維持費も増加するため、コスト削減の観点から契約条件の見直しや省エネ設備の導入を検討することもおすすめです。維持費を正確に把握し、計画的に管理することが、資金繰りの健全な成長につながります。
仕入代金
仕入代金は、商品や原材料を調達する際に支払う資金であり、運転資金の中核を担う要素です。例えば、商品を販売する前に先に仕入代金を支払う必要がある場合、売上が発生するまでの期間に資金のギャップが生じます。
そのため、支払いサイトと入金サイトのバランスを考慮しながら、資金繰りを調整することが重要です。仕入先との取引条件を交渉し、支払期日を延ばしたり分割払いを活用したりすることで、資金の流れを安定させることができます。仕入代金の管理は、事業の成長と安定したキャッシュフローを維持するための基礎といえるでしょう。
備品費
備品費は、事業運営に必要な机やパソコン、プリンター、事務用品などの購入にかかる費用を指します。例えば、新入社員の入社や新規事業の立ち上げ時には、こうした備品の購入が一時的に増えることがあります。
備品費は一度に大きな支出となる場合もあるため、運転資金の中でも計画的な支出管理が求められます。また、備品は一度購入すれば長期間使用できるものも多いため、コストを平準化するためにリース契約を活用するのもおすすめです。日常的な消耗品の補充と区別して、定期的に備品費の見直しを行うことで、資金の無駄を防ぎ、効率的な経営を実現できます。
営業諸経費
営業諸経費は、事業活動を維持や拡大するために発生するさまざまな経費の総称です。例えば、交通費や通信費、広告宣伝費、接待交際費などが含まれます。営業所経費は直接的に売上を生むわけではないものの、取引先との関係構築や顧客獲得、業務効率化に欠かせない経費です。
その一方で、支出内容の幅が広いため、使途の透明性を確保し、費用対効果を意識した管理が必要です。営業諸経費は削減しすぎると売上機会を失うおそれもあるため、事業の状況に合わせて適正な水準を保つことが、健全な資金運用につながるでしょう。
運転資金の調達方法
運転資金の調達方法として、以下のような方法があります。
- 日本政策金融公庫からの借り入れ
- 金融機関からの借り入れ
- 自治体の補助金・助成金の活用
- クラウドファンディング
- ファクタリング
ここでは、それぞれの調達方法について具体的に解説します。
日本政策金融公庫からの借り入れ
日本政策金融公庫からの借り入れは、中小企業や個人事業主が運転資金を確保するうえで代表的な方法のひとつです。公的機関ならではの信頼性と支援体制が魅力です。例えば、創業直後で実績が少なく、民間金融機関からの融資が受けにくい場合でも、公庫の制度を活用することで資金を調達できます。
金利が比較的低く、返済期間も柔軟に設定できるため、長期的な資金繰りの安定に役立ちます。また、運転資金専用の融資制度や、女性・若者・シニア向けなど目的別の支援も整備されています。事業計画書や資金繰り表を作成して提出することで、審査をスムーズに進めることができます。
金融機関からの借り入れ
金融機関からの借り入れは、運転資金の調達手段として幅広く利用されています。例えば、銀行や信用金庫、信用組合などが提供する融資制度を通じて、短期的な資金不足や事業拡大に対応できます。取引実績がある金融機関であれば、決算内容や資金繰りの状況を踏まえた柔軟な条件で融資を受けられることもあります。
金利は日本政策金融公庫より高めになることもありますが、信用力が高まればより有利な条件で借入が可能です。融資を申し込む際は、返済計画を明確にし、資金の使途や回収見込みを説明できるよう準備しておくことが重要です。適切な借入は、事業を支える安定した資金源になります。
自治体の補助金・助成金の活用
自治体が実施する補助金や助成金の活用は、返済不要で運転資金を確保できる有効な手段です。例えば、設備投資や雇用促進、販路拡大などを目的とした制度があり、地域ごとに内容や対象条件が異なります。これらは審査があり、申請書類や事業計画書の提出が求められるため、事前の準備が欠かせません。
採択されれば、事業に必要な資金の一部を賄えるだけでなく、行政の支援を受けることで信用力向上にもつながります。申請時期が限定されている場合も多いため、自治体や商工会議所の情報を定期的に確認し、チャンスを逃さないことが大切です。
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、インターネットを通じて多くの支援者から資金を集める方法です。例えば、新商品の開発や地域活性化プロジェクトなど、社会的な共感を得やすい内容であれば、短期間で目標額に到達することもあります。融資とは異なり、返済が不要な「購入型」や「寄付型」もあり、資金調達と同時にプロモーション効果も得られる点が特徴です。
一方で、魅力的な企画内容やリターン設計、広報活動が成功のポイントです。そのため、クラウドファンディングは、資金面だけでなく顧客との関係づくりにも活用できる柔軟な調達手段といえます。
ファクタリング
ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に売却して早期に現金化する資金調達方法です。例えば、取引先からの入金までに時間がかかる場合でも、売掛金を買い取ってもらうことで資金繰りを改善できます。借入ではないため、負債を増やさずに手元資金を確保できる点がメリットです。
審査期間も短く、すぐに資金化できるケースが多いため、急な支払いに対応したいときに有効です。ただし、手数料が発生するため、コスト面とのバランスを考慮することが大切です。そのため、適切に活用すれば、資金の流れをスムーズにし、経営の安定につなげられる手段といえるでしょう。
なお、ファクタリングの仕組みについてはこちらの記事で解説しています。

まとめ
運転資金は、企業経営の安定を支える基盤であり、日々の資金繰りを円滑にするうえで欠かせない要素です。例えば、売上が好調でも入金が遅れれば、支払いに必要な資金が不足する可能性があります。そのため、運転資金を正確に把握し、適切な目安をもとに計画的な管理を行うことが重要です。
また、必要に応じて融資や補助金、ファクタリングなどの調達手段を柔軟に組み合わせることで、資金繰りの安定と事業成長の両立が可能になります。経営者にとって運転資金の理解と活用は、企業の持続的な発展を実現するための第一歩といえるでしょう。なお、資金繰りの管理には、経理代行会社のサポートを受けることもおすすめです。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
運転資金に関するよくあるご質問
運転資金についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、運転資金に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
運転資金の計算式は何ですか?
運転資金は、企業が日常の営業活動を行うために必要な資金量を示す指標で、「運転資金=売掛金+在庫資産-買掛金」という式で求めます。売掛金や在庫は将来的に現金化される資産ですが、買掛金は支払い義務を示す負債です。手元にどれだけの資金を確保すべきかを把握し、資金繰りを安定させる目安として活用されています。
運転資金の目安はいくらですか?
運転資金の目安は、一般的に売上高または経費の3か月分とされています。売上代金の入金までに時間がかかる場合でも、給与や仕入代金、家賃などの支払いを滞りなく行うための安全ラインです。売掛金の回収が1〜2か月後になる企業では、この3か月分の余裕資金があることで急な支出や入金遅延にも対応できます。
運転資金とは具体的に何ですか?
運転資金とは、企業が日々の営業活動を行う際に必要となる資金を指します。例えば、仕入代金の支払い、人件費、家賃、光熱費、広告費など、事業を継続するために欠かせない経費が含まれます。売上が発生しても入金までにはタイムラグがあるため、その間に支払いを行うための資金を確保する必要があります。




