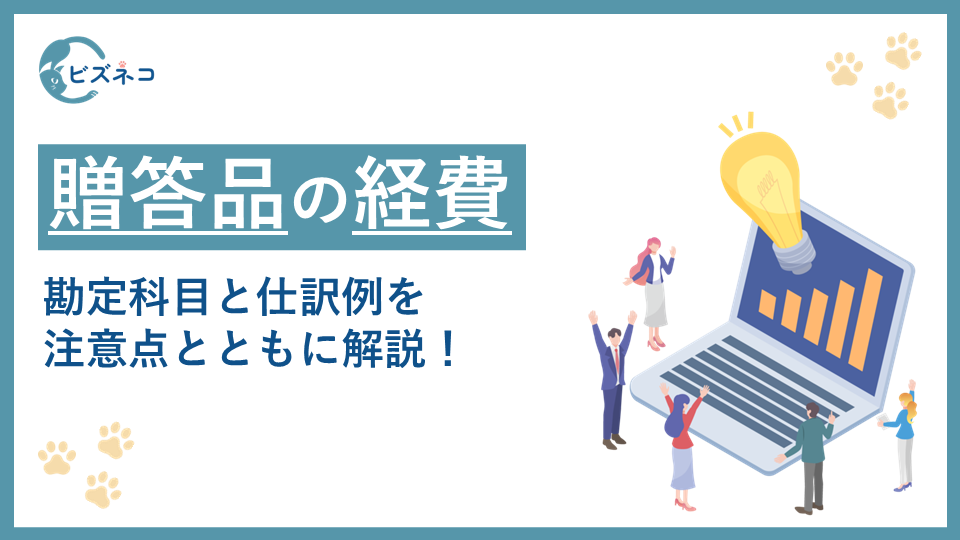
取引先へのお中元やお歳暮、取引開始時の手土産、社員へのお祝い品など、ビジネスシーンでは贈答品やプレゼントを贈る機会が少なくありません。しかし、これらの支出はすべてが経費になるわけではなく、目的や相手、金額によって勘定科目や処理方法が異なります。
経費として認められるかどうかを誤ると、税務調査で否認されるリスクもあるため注意が必要です。本記事では、贈答品やプレゼント代を経費として正しく処理するための基本から、勘定科目別の仕訳例、経費にならないケースや注意点までを詳しく解説します。
目次
そもそも贈答品とは?
贈答品とは、感謝やお祝い、挨拶などの気持ちを伝えるために相手へ贈る品物を指します。例えば、取引先へのお中元やお歳暮、契約成立時の手土産、開店祝いなど、ビジネスの場でも贈答品は円滑な人間関係を築くための重要な手段として用いられます。
ただし、目的や贈る相手によって、意味合いや扱いは大きく異なります。仕事上の付き合いを円滑にするためのものなのか、個人的な贈り物なのかによって、経費として認められるかどうかの判断も変わります。そのため、贈答品の正しい定義を理解しておくことは、経理処理や税務上の対応を適切に行うための第一歩といえるでしょう。
経費として計上できる品物やプレゼント
経費として計上できる品物やプレゼントとして、以下のようなものがあります。
- お祝い品・返礼品
- お中元・お歳暮
- 謝礼品
- 手土産
ここでは、それぞれの品物やプレゼントについて具体的に解説します。ぜひ、経費として判断する際の参考にしてください。
お祝い品・返礼品
お祝い品や返礼品は、取引先や関係者との信頼関係を深めるために贈ることが多い贈答品です。例えば、取引先の開業祝いや担当者の昇進祝いなどに花束や記念品を贈るケースがあります。これらは業務上のつながりを円滑にする目的が明確であれば、経費として計上できる場合があります。
一方で、個人的な交友関係に基づく贈り物や高額すぎるものは経費として認められない可能性があります。そのため、お祝い品や返礼品を経費処理する際は、贈る目的や相手との関係性を整理し、接待交際費や福利厚生費など適切な勘定科目を選ぶことが大切です。
お中元・お歳暮
お中元やお歳暮は、日頃の感謝や今後の取引継続の意思を示すために贈る季節的な贈答品です。例えば、長く取引のある得意先に食品や日用品を贈るケースが代表的です。これらは営業活動の一環として位置づけられるため、通常は「接待交際費」として経費計上が可能です。
ただし、贈り先が取引関係のない個人であったり、金額が過大である場合には経費として認められないこともあります。お中元やお歳暮は形式的な贈り物であっても、企業の印象を左右する要素であるため、品物の内容や金額のバランスにも注意が必要です。
謝礼品
謝礼品は、講演や取材への協力、アンケート回答、紹介などに対して感謝の気持ちを表すために贈られる品物です。例えば、取引先にセミナー登壇を依頼した際に贈る記念品が該当します。
謝礼の性質を持つため、通常は「交際費」や「広告宣伝費」として経費処理されますが、金額が高額すぎる場合や個人的な贈答目的を含む場合は、経費として認められないこともあります。贈る理由が明確であり、業務遂行上の必要性が説明できるかどうかがポイントです。そのため、支出目的を明確にし、領収書などの証憑(しょうひょう)をしっかり残しておくことが求められます。
手土産
手土産は、訪問先や来客対応時の印象を良くするために用意される贈り物で、ビジネスシーンで最も身近な贈答品のひとつです。例えば、取引先を訪問する際に和菓子や焼き菓子などを持参するケースが一般的です。
こうした手土産は、取引関係を円滑にするためのものであれば「接待交際費」として経費計上が認められることがあります。ただし、私的な贈答や個人的な好意に基づく支出は経費にはなりません。手土産は少額でも企業イメージを左右することがあるため、品選びだけでなく、支出の目的や範囲を明確にしておくことが重要です。
なお、ご祝儀やお祝い金、慶弔費も経費として計上できます。以下の記事を参考にしてください。
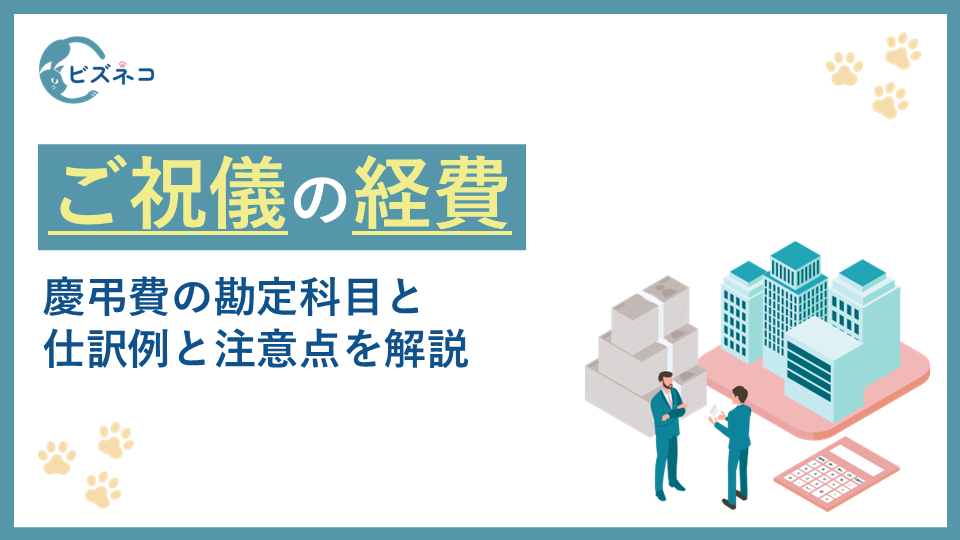
贈答品やプレゼント代の勘定科目と仕訳例
贈答品やプレゼント代の勘定科目は、基本的に「接待交際費」になります。しかし、誰に何を贈るかによって、「接待交際費」以外に「広告宣伝費」や「福利厚生費」として仕訳されることもあります。ここでは、それぞれの勘定科目について仕訳例とともに解説します。
贈答品が接待交際費となるケース
贈答品を取引先や仕入先などの事業関係者に贈る場合、支出は「接待交際費」として処理します。例えば、日頃から取引のある得意先にお中元やお歳暮を贈るケースがこれにあたります。接待交際費とは、法人が取引関係の維持や発展を目的として行う接待や贈答などの支出を指し、ビジネス上の信頼関係を深めるための費用として認められます。
ただし、贈答品の金額が過度に高額であったり、私的な目的を含んでいたりすると、経費として否認される可能性があります。経費処理を行う際は、贈答の目的や相手を明確にし、領収書などをきちんと保存しておくことが大切です。
贈答品を接待交際費とした場合の仕訳例
贈答品を接待交際費とした場合の仕訳例は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 接待交際費 | 9,000円 | 現金 | 9,000円 |
贈答品が広告宣伝費となるケース
贈答品を「宣伝目的」で多数の顧客に配布する場合は、「広告宣伝費」として処理します。例えば、新規オープン時に来店者へ店名入りのタオルを配布したり、キャンペーン中に購入者全員へ記念品を贈ったりするケースが該当します。
このような支出は、特定の相手への接待ではなく、広く不特定多数への販売促進を目的としているため、交際費ではなく広告宣伝費に分類されます。広告宣伝費は、売上拡大を意図した支出として全額損金算入が可能なため、税務上のメリットもあります。ただし、贈答の目的が曖昧だと交際費扱いになるおそれがあるため、企画書や配布記録を残すなど、目的を明確にしておくことが重要です。
贈答品を広告宣伝費とした場合の仕訳例
贈答品を広告宣伝費とした場合の仕訳例は以下のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 145,000円 | 普通預金 | 145,000円 |
贈答品が福利厚生費となるケース
従業員やその家族に対して贈答品を贈る場合は、「福利厚生費」として処理します。例えば、従業員の子どもの入学祝いや結婚祝いなど、会社全体の慶弔制度に基づいて贈る品物が該当します。
福利厚生費は、従業員の士気向上や福利の充実を目的とした支出として認められます。ただし、特定の従業員のみを対象にする場合や個人的な関係で贈る場合は、給与扱いとなり課税対象になるおそれがあります。そのため、贈答の基準や対象を明確にし、社内規程を整えておくことが望まれます。経理処理では、贈答の理由や対象者を記録し、福利目的であることを証明できるようにしておくことが重要です。
贈答品を接待交際費とした場合の仕訳例
贈答品を接待交際費とした場合の仕訳例は以下のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
なお、経理処理でよく使われる勘定科目については、以下の記事で一覧で紹介しています。
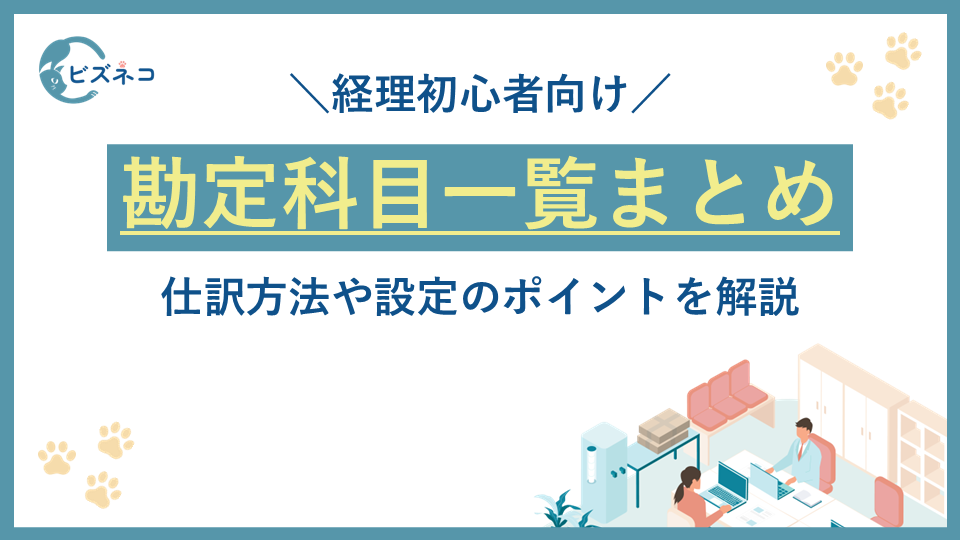
贈答品でも経費に計上できない場合もある
贈答品でも経費に計上できない場合として、以下のようなシーンがあります。
- 贈答品を自分で使用するために購入する場合
- 事業関係者ではない相手に贈る場合
- 個人事業主が福利厚生費として処理する場合
ここでは、それぞれのシーンについて具体的に解説します。
贈答品を自分で使用するために購入する場合
贈答品を経費として計上できるのは、あくまで事業活動に関連した支出である場合に限られます。例えば、取引先への贈り物として購入した商品を自分で使用した場合、その支出は私的利用とみなされ、経費として認められません。
経費とは事業のために必要な支出であり、個人的な消費や趣味的な購入は対象外です。領収書に贈答品としての名目があっても、実際に自社や個人で使用していれば税務上は否認されるリスクがあります。こうした誤った処理を防ぐためには、購入目的と使用先を明確にし、事業との関連性を説明できるように記録を残しておくことが重要です。
事業関係者ではない相手に贈る場合
贈答品は、基本的に事業活動に関連する取引先や関係者に贈る場合に限り、経費として計上することができます。例えば、友人や家族など、事業と関係のない個人的な相手に贈り物をした場合、支出は事業経費ではなく「個人的支出」として扱われます。
名目上は取引先への贈答としたとしても、実際に事業に無関係であれば税務上は否認される可能性があります。経費として認められるかどうかは「事業との明確な関係性」が判断基準となるため、贈り先の立場や贈答目的をはっきりさせておくことが大切です。そのため、個人的な交友関係と業務上の付き合いを混同しないよう注意が必要です。
個人事業主が福利厚生費として処理する場合
個人事業主が贈答品を福利厚生費として経費処理する場合は注意が必要です。例えば、家族や自分自身に対してプレゼントを贈り、それを「従業員への福利厚生」として処理した場合、税務上は経費として認められません。
福利厚生費は、従業員全体の福利向上を目的とした支出であり、従業員を雇っていない個人事業主が自分のために使うことはできません。また、従業員がいる場合でも、一部の人だけを対象とした贈答は不公平と判断されることがあります。贈答の対象や内容を明確にし、業務目的が正当であることを示せるようにしておくことが大切です。
贈答品やプレゼント代を経費として計上する際の注意点
贈答品やプレゼント代を経費として計上する際の注意点として、以下のような点があげられます。
- 品物が高額すぎる場合は経費にできない
- 商品券など換金性の高い品物は経費にできない
- 内容と贈り先が不明瞭であると否認されてしまう
- 消費税の課税区分に注意して判断する
- 私利私欲に経費を使ってはいけない
ここでは、それぞれの注意点について具体的に解説します。
品物が高額すぎる場合は経費にできない
贈答品の金額が高額すぎる場合、支出は経費として認められない可能性があります。例えば、高級腕時計やブランドバッグなどを取引先に贈った場合、贈り物の範囲を超えた「贈与」とみなされることがあります。
税務上、経費として認められるのは「社会通念上妥当な金額」であり、過度に高価な品物は業務関連の支出ではなく個人的な贈り物と判断されるおそれがあります。贈答の目的がビジネス上の関係維持であっても、金額が常識の範囲を超えると経費として否認されるリスクが高まるため、贈る品の価格や内容は慎重に選ぶことが大切です。
商品券など換金性の高い品物は経費にできないことがある
商品券やギフトカードなど、現金に近い性質を持つ贈り物は、経費として認められないこともあります。例えば、取引先へのお礼の品として商品券を贈った場合でも、税務上は「金銭の贈与」と判断されることがあります。これは、商品券が換金可能であり、受け取った側が自由に使用できるためです。
広告宣伝費や交際費として処理しても、実態が現金支給に近い場合は否認されるリスクがあります。贈答の意図を明確に示すためには、現物品や社名入りのノベルティなど、換金性の低い品物を選ぶことが望ましいでしょう。
内容と贈り先が不明瞭であると否認されてしまう
贈答品の内容や贈り先が不明確な場合、税務調査で経費として認められないことがあります。例えば、領収書に「贈答品代」とだけ記載され、誰に何を贈ったかが不明な場合には、私的な支出と判断される可能性が高まります。
経費として計上するには、贈答の目的や相手先、品目、金額を明確に記録し、領収書や納品書などの証憑(しょうひょう)と一緒に保管しておくことが重要です。記録があいまいなままだと、たとえ事業関連の贈り物であっても、後から正当性を証明できず否認されてしまうおそれがあります。そのため、透明性のある経理処理を心がけましょう。
消費税の課税区分に注意して判断する
贈答品を購入する際は、消費税の課税区分にも注意が必要です。例えば、取引先へのお歳暮として購入した食品などは「課税仕入れ」に該当しますが、一定の条件を満たさない場合は仕入税額控除の対象外になることがあります。
交際費や福利厚生費として処理する場合にも、課税・非課税・不課税の判断を誤ると、後から修正申告が必要になることがあります。消費税の取扱いは贈答品の性質や用途によって変わるため、購入時の目的を明確にし、会計処理の段階で正しい区分を適用することが大切です。
私利私欲に経費を使ってはいけない
贈答品の購入が事業とは関係なく、自分のための支出である場合は、経費として認められません。例えば、自身の友人や家族へのプレゼントを「交際費」や「福利厚生費」として処理した場合、私的流用と判断されるおそれがあります。
経費はあくまで事業活動に必要な支出であり、個人的な目的のために会社の資金を使うことは不適切です。税務署はこうした支出に敏感であり、内容が不自然な場合は調査対象となることもあります。そのため、贈答品の経費処理では、公私の区別を明確にし、事業目的が説明できる支出に限定することが重要です。
贈答品やプレゼント代はいくらまで経費に認められるのか?
贈答品やプレゼント代はいくらまで経費に認められるのか気になる方も多いのではないでしょうか。贈答品やプレゼント代が経費に認められる額は、法人か、個人および個人事業主かによって異なります。ここでは、それぞれいくらまで経費に認められるかを紹介します。
法人の場合
法人が贈答品を経費として計上する場合、税法上は「交際費等」として扱われるのが一般的です。例えば、取引先へのお歳暮やお中元、取引成立時の記念品などは、事業関係者との関係を円滑にする目的があるため、交際費等として認められるケースが多いです。
ただし、法人税法では交際費等の損金算入に上限が設けられています。資本金1億円以下の中小法人であれば、年間800万円または飲食費の50%のいずれか多い金額まで損金算入が可能ですが、資本金が100億円を超える大企業は全額が対象外となります。贈答品の支出がどの勘定科目に該当するのかを正確に判断し、限度額を超えないように計画的に経理処理を行うことが重要です。
個人や個人事業主の場合
個人や個人事業主の場合、贈答品に関して法人のような損金算入の上限は設けられていません。例えば、得意先へのお礼や取引継続のための贈答など、事業遂行に必要と認められる支出であれば、原則として全額を経費に計上できます。
ただし、贈答の目的が明確でない場合や、私的な関係に基づく支出は経費として認められません。個人事業主は公私の線引きがあいまいになりやすいため、贈答先・目的・金額を帳簿やメモに残し、事業関連の支出であることを示せるようにしておく必要があります。税務上のトラブルを避けるためにも、贈答品を購入する際は「事業との関連性」を常に意識して判断することが大切です。
まとめ
ビジネスにおける贈答品やプレゼントは、取引先との信頼関係を深めたり、従業員の士気を高めたりする重要な役割を果たします。しかし、すべての贈答が経費として認められるわけではありません。贈る相手や目的によって、「接待交際費」「広告宣伝費」「福利厚生費」など、適切な勘定科目を選ぶ必要があります。
また、金額が高額すぎる場合や私的な贈り物と判断される場合は、税務上否認されるおそれもあります。経費として正しく処理するためには、贈答の目的や相手を明確にし、領収書や記録をきちんと残すことが重要です。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
贈答品の経費処理に関するよくあるご質問
贈答品の経費処理についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、贈答品の経費処理に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
贈答品はいくらまで経費として認められますか?
贈答品の経費としての限度額は、税法上明確に定められていません。ただし、社会通念上は常識的な範囲であることが求められます。例えば、取引先へのお中元などは1万円以下が妥当であり、高くても5万円以内におさめることが妥当でしょう。一方で、あまりに高額な品物は接待交際費としても認められないため注意しましょう。
贈答品はどの勘定科目で処理しますか?
贈答品の勘定科目は、贈る目的や相手によって異なります。取引先への贈り物は「接待交際費」、販売促進を目的に不特定多数へ配る場合は「広告宣伝費」として処理します。また、社員への慰労や季節の贈り物などは「福利厚生費」に該当する場合があります。同じ贈答品でも扱いを誤ると税務上問題になるため注意しましょう。
個人事業主が贈答品をもらった場合は経費にできますか?
個人事業主が受け取ったプレゼントでも、事業に関係がある場合は経費として処理できます。一方で、誕生日や私的な贈り物など、プライベートな目的で受け取ったプレゼントは経費にはできません。もちろん、贈る場合も同様です。そのため、事業用か私用かの線引きを明確にし、根拠を示せるよう記録を残すことが大切です。




