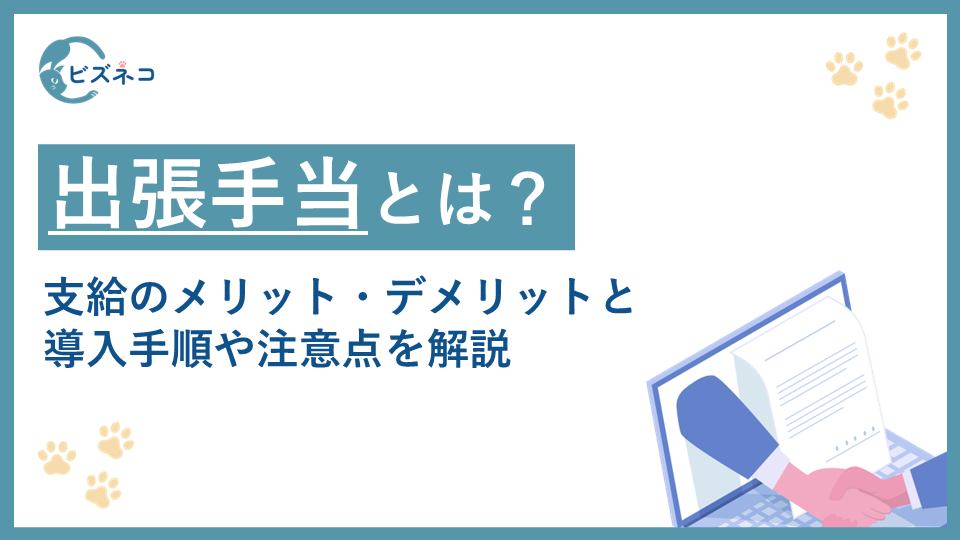
出張手当とは、従業員が業務で出張する際に支給される手当のことで、交通費や宿泊費とは異なり、出張に伴う日当や雑費の補助を目的としています。企業が出張手当を導入することで、経費精算の手間を減らしつつ、従業員の負担軽減やモチベーション向上を図ることができます。
一方で、規程を定めずに支給すると不公平や不正受給のリスクが生じるため、制度づくりには慎重さが求められます。本記事では、出張手当の基本から導入の流れ、注意点やポイントまでをわかりやすく解説します。
目次
出張手当とは?
出張手当とは、従業員が業務で自宅や勤務先を離れて出張する際に支給される日当のことです。交通費や宿泊費といった実費とは別に、食費や雑費などの出張に伴う負担を補う目的で支給されます。
例えば、地方への出張では食事代やちょっとした移動費など、領収書の取りづらい支出が多く発生します。出張手当をあらかじめ定額で支給しておくことで、こうした経費精算の手間を省き、従業員にもわかりやすい制度づくりが可能になります。結果として、経理業務の効率化や従業員の満足度向上にもつながる点が特徴です。
出張手当と出張費の違い
出張手当と出張費の違いは、支給目的と費用の性質にあります。出張手当は、出張に伴う食費や雑費などを補う「日当」として定額で支給されるのに対し、出張費は交通費や宿泊費など、実際にかかった金額を会社が負担する「実費精算」です。
例えば、新幹線やホテルの領収書をもとに経費申請を行うのは出張費に該当します。一方、領収書が不要な定額支給の部分が出張手当です。このように、両者を明確に区別しておくことで、経費処理の混乱を防ぎ、税務上のトラブルを避けることができます。
出張手当と交通費の違い
出張手当と交通費の違いは、補助の対象となる支出内容にあります。交通費は、出張先までの移動に要した実際の費用を会社が精算するのに対し、出張手当は現地での食事代や雑費など、領収書を取りづらい支出をカバーするための定額支給です。
例えば、タクシーや電車の料金は交通費として実費精算されますが、出張中の飲食や細かな雑費は出張手当で賄われます。両者を正しく区別し、社内規程で明確に定義しておくことにより、経理処理の整合性を保ち、従業員間の不公平感を防ぐことができます。
出張手当は課税対象外
出張手当は、一定の条件を満たす場合に限り課税対象外として扱われます。これは、出張中の食費や雑費など、業務の遂行に必要な実費を補うために支給されるものとみなされるためです。
例えば、会社があらかじめ出張旅費規程を定め、その範囲内で支給している場合には、給与として課税されることはありません。一方で、支給額が社会通念上の範囲を超えていたり、実際には出張を伴わない支給を行っていたりすると、給与扱いとして課税対象になるおそれがあります。したがって、非課税扱いを維持するには、金額の妥当性や規程の整備、支給実態の管理が欠かせません。そのため、税務上の取り扱いを理解したうえで、適正な運用を行うことが重要です。
出張手当を支給するメリット
出張手当を支給するメリットとして、以下のような点があげられます。
- 法人税・所得税・社会保険料の負担軽減
- 従業員のモチベーションアップにつながる
- 経費計算の手間が削減される
ここでは、それぞれのメリットについて具体的に解説します。
法人税・所得税・社会保険料の負担軽減
出張手当を適切に支給することで、法人税・所得税・社会保険料の負担を抑えることができます。出張手当は、一定の条件を満たせば「非課税」として扱われ、給与とは異なる性質を持つため、課税所得や社会保険料の計算に含まれません。
例えば、実費精算では給与扱いになる部分を出張手当として支給すれば、企業と従業員の双方の税負担を軽減できます。ただし、金額や支給条件が不適切な場合は課税対象となるため、社内規程を整えた上での運用が重要です。正しく制度設計を行うことで、節税効果を得ながら経理上の透明性も保つことができます。
従業員のモチベーションアップにつながる
出張手当の支給は、従業員のモチベーション向上にもつながります。出張は移動や宿泊など心身の負担が大きい業務であり、手当の支給はその労をねぎらう意味を持ちます。
例えば、出張先での食事や雑費を自腹で負担しなければならない場合、従業員に不満が生じやすくなりますが、あらかじめ定額の手当が支給されていれば安心して業務に集中できます。また、手当の金額が明確に定められていることで、公平性のある評価制度として機能する点もメリットです。こうした制度は従業員の働きやすさを高め、企業への信頼にもつながります。
経費計算の手間が削減される
出張手当の導入によって、経費計算や精算処理の手間を大幅に削減できます。通常、出張時の経費は領収書の収集・申請・承認といった複数の工程を経る必要がありますが、定額の手当を支給することでその手間が不要になります。
例えば、食事代や細かな交通費など、金額が少なく証憑(しょうひょう)を集めづらい支出も出張手当で包括的に処理できます。その結果、経理担当者の入力作業や確認業務も軽減され、処理スピードが向上します。従業員にとっても申請負担が減るため、全社的な業務効率化につながる制度といえるでしょう。
出張手当を支給するデメリット
出張手当を支給するデメリットとして、以下のような点があげられます。
- 企業の支出が増加する
- 出張旅費規程を定める必要がある
- 不正受給の恐れがある
ここでは、それぞれのデメリットについて具体的に解説します。ぜひ、出張手当を導入する際に意識してください。
企業の支出が増加する
出張手当を導入すると、企業の支出は増加します。なぜなら、交通費や宿泊費などの実費精算に加え、日当として定額の手当を支給するためです。例えば、出張が多い営業職や技術職が多い企業では、支給回数が増えるほど年間の総支出が膨らむ可能性があります。
また、手当額の設定が高すぎると、節税効果を得るどころかコスト増につながるおそれもあります。そのため、出張手当の導入時には、業種や出張頻度、従業員数などを踏まえた現実的な金額設定が必要です。経費の透明性と公平性を保ちつつ、過剰な支出を抑える仕組みづくりが求められます。
出張旅費規程を定める必要がある
出張手当を支給するためには、出張旅費規程を定める必要があります。規程がなければ、支給の根拠が曖昧になり、税務上も給与として扱われるリスクが生じます。例えば、「どの地域に行った場合はいくら支給するのか」「宿泊の有無で金額を変えるのか」といった基準を明確にしておくことで、従業員間の不公平を防ぐことができます。
また、規程の存在は社内統制の観点からも重要で、出張費の精算ルールや支給範囲を一元的に管理できます。導入にあたっては、法令を踏まえつつ、自社の実情にあわせた規程づくりが欠かせません。
不正受給の恐れがある
出張手当には、不正受給のリスクがある点にも注意が必要です。定額支給であるため、実際に出張を行っていなくても支給を受けられる仕組みになっていると、不正が起こる可能性があります。
例えば、出張申請を虚偽で提出したり、日帰り出張にもかかわらず宿泊手当を申請したりするケースが考えられます。こうした問題を防ぐには、出張報告書の提出や経理部門でのチェック体制を整えることが重要です。また、出張旅費規程に具体的な支給条件を明記しておくことで、不正の抑止効果が高まります。制度を正しく運用するためには、透明性のある管理が欠かせません。
出張手当を導入する流れ
出張手当の導入は、以下のような流れで進みます。
- step1:導入する目的や課題を洗い出す
- step2:出張旅費規程を定める
- step3:経理への申請フローを整える
- step4:社内で周知して運用をスタートする
- step5:予想外のトラブルを改善する
ここでは、それぞれの手順について具体的に解説します。
step1:導入する目的や課題を洗い出す
出張手当を導入する際は、まず制度を設ける目的や現状の課題を明確にすることが重要です。例えば、「経費精算の手間を減らしたい」「従業員の負担を軽減したい」といった具体的な目的を整理することで、制度設計の方向性が定まります。
目的があいまいなままでは、金額設定や支給基準が不適切となり、社内の不満やコスト増につながるおそれがあります。そのため、経理部門や人事部門が中心となり、現行の精算フローや出張頻度などを分析し、制度導入の効果を見極めることが大切です。そのため、明確な目的意識が、運用しやすい仕組みづくりの第一歩といえるでしょう。
step2:出張旅費規程を定める
目的や課題を洗い出したら、出張手当を支給するための根拠となる「出張旅費規程」を定めます。規程がないまま支給すると、税務上は給与とみなされ課税対象になるおそれがあるため、制度の信頼性を確保するためにも明文化が欠かせません。
例えば、「宿泊を伴う場合はいくら」「日帰りはどの地域までを対象とするか」といった基準を細かく設定しておくことで、公平かつ透明な運用が可能になります。また、社会通念上妥当な金額であるかも確認し、他社事例などを参考に検討するのがよいでしょう。明確な規程は、従業員の理解促進にもつながるため大切です。
step3:経理への申請フローを整える
出張手当の支給には、スムーズな申請と承認の仕組みを整えることが欠かせません。例えば、出張申請書や経費精算システムを活用し、出張前後の手続きを明確にしておくことで、経理担当者の負担を軽減できます。
フローが不明確だと、申請漏れや二重支給といったトラブルが発生しやすくなります。そのため、申請時に必要な情報や添付資料、承認者の範囲などをあらかじめ定め、社内システム上で一元管理することが望ましいです。経理部門と現場の連携を意識し、実務の流れに沿った仕組みを構築することが重要です。
step4:社内で周知して運用をスタートする
制度づくりと申請フローが整ったら、社内への周知を行い、運用を開始します。制度の理解が不十分なまま運用を始めると、誤った申請や支給漏れが起こる可能性があります。
例えば、説明会や社内ポータルで出張旅費規程を共有し、具体的な支給条件や注意点を明示しておくと、従業員が正しく制度を活用できます。また、経理部門や上長が質問を受け付ける体制を整えることで、初期段階の混乱を防ぐことができます。制度を定着させるには、単なる告知ではなく、理解を深めるための丁寧な情報発信が欠かせません。
step5:予想外のトラブルを改善する
制度導入後は、実際の運用を通じて浮かび上がる課題を継続的に改善していくことが重要です。例えば、出張の種類によって手当額が合わない、申請ルールが複雑で現場が混乱しているといった声が上がることもあります。こうした問題を放置すると、不公平感や不正受給の温床になるおそれがあります。
そのため、導入後も定期的にフィードバックを収集し、制度内容や運用手順を見直す体制を整えることが大切です。実態に合わせて柔軟に調整することで、出張手当制度をより使いやすく、健全に運用できます。
出張手当を定める際の注意点とポイント
出張手当を定める際の注意点とポイントとして、以下のような点があげられます。
- 不公平にならないようあいまいな設定を避ける
- 二重払いを防ぐルールを整える
- 地域差や宿泊の有無を踏まえて現実的な金額にする
- 従業員への支給が遅れないようにする
ここでは、それぞれの注意点やポイントについて具体的に解説します。
不公平にならないようあいまいな設定を避ける
出張手当を定める際は、支給基準をあいまいにせず、誰が見ても分かるよう明確に設定することが重要です。基準が不明確だと、同じ業務内容でも支給額に差が出て不公平感を生み、従業員の不満につながるおそれがあります。
例えば、「遠方出張」「長距離出張」といった曖昧な表現ではなく、具体的な距離や地域名で区分を定めると、公平性が保たれます。また、役職や職種によって金額に差をつける場合も、理由を明文化しておくことが望ましいです。全社員が納得できるルールを設けることで、制度への信頼性を高めることができます。
二重払いを防ぐルールを整える
出張手当を導入する際は、交通費や宿泊費などとの「二重払い」を防ぐルールを整備する必要があります。例えば、出張手当の中に宿泊補助が含まれているにもかかわらず、別途ホテル代を精算してしまうと、重複支給となり経費の不正処理とみなされる可能性があります。
こうした事態を避けるためには、出張手当の支給範囲を明確に定め、「手当でカバーする費用」と「別途精算する費用」をきちんと区分することが大切です。また、経理部門がチェック体制を整えることで、申請段階での誤りも防げます。透明性の高いルールづくりが、制度運用の安定につながります。
地域差や宿泊の有無を踏まえて現実的な金額にする
出張手当の金額は、地域差や宿泊の有無を考慮して現実的に設定することが重要です。例えば、都市部と地方では食事や交通のコストが異なり、同一金額では実態に合わないケースがあります。
また、宿泊を伴う出張と日帰り出張では負担の程度も異なるため、区分を分けて支給額を調整することが望ましいです。金額設定が実情とかけ離れていると、従業員にとって負担が大きくなったり、逆に過大支給による税務リスクが発生したりする可能性もあります。地域や業務内容に応じて柔軟に見直すことで、納得感のある制度を維持できます。
従業員への支給が遅れないようにする
出張手当の支給は、従業員への負担を軽減するためにも遅延なく行うことが大切です。出張のたびに立て替えが続くと、金銭的なストレスがかかり、制度の目的である負担軽減が果たせなくなります。
例えば、出張後の経費精算を月末締めにしている場合、支給が翌月になると出張が多い社員ほど自己負担が増える傾向にあります。こうした問題を防ぐには、出張前の前払い制度や迅速な承認フローを設けるなど、柔軟な運用体制を整えることが効果的です。支給のタイミングを明確にし、従業員が安心して出張できる環境を整えることが求められます。
まとめ
出張手当は、従業員の出張負担を軽減しながら経理業務の効率化を図れる制度です。しかし、適切に設計や運用をしなければ不公平や不正の温床にもなりかねません。例えば、金額設定が実態に合わないと社員の不満が生じたり、旅費規程が不十分だと課税リスクが高まったりすることもあります。
そのため、導入前には目的を明確にし、支給基準や申請フローを丁寧に整備することが大切です。導入後も、現場の声をもとに制度を見直しながら改善を重ねることで、出張手当は企業全体の生産性を支える仕組みとして定着していきます。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
出張手当に関するよくあるご質問
出張手当についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、出張手当に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
出張手当と出張費の違いは何ですか?
出張手当と出張費の違いは、支給目的です。出張費は、交通費や宿泊費など実際にかかった経費を精算する実費補填です。一方、出張手当は、出張中に発生する食費や雑費などを補うための定額支給であり、実費とは関係なく一定額が支払われる点が特徴です。出張手当と出張費を使い分けることで、従業員の負担を削減できます。
出張手当がないのは違法ですか?
出張手当がないこと自体は違法ではありません。企業が必ず支給しなければならない法的義務はなく、交通費や宿泊費などを実費精算で補う形でも問題ありません。ただし、出張の負担が大きい場合や立て替えが多い環境では、手当を設けた方が従業員の負担軽減やモチベーション維持につながるため、制度化を検討しましょう。
一般的な出張手当の相場はいくらですか?
一般的な出張手当の相場は1日あたり2,000円〜3,000円程度が妥当とされています。ただし、金額は企業規模や業種、出張先の地域差で異なります。例えば、都市部への出張では食費や雑費がかさむため、上限を高めに設定する企業もあります。重要なのは、実態に見合った金額設定で公平なルールを整えることです。




