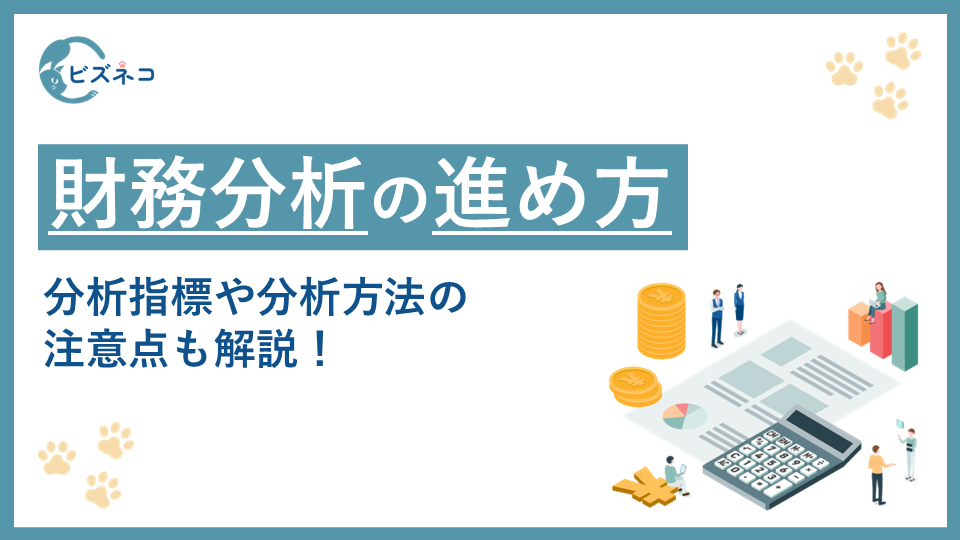
企業の経営状態を正しく把握するために欠かせないのが財務分析です。財務分析では、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書といった財務三表を活用し、収益性や安全性、生産性、成長性といった複数の視点から企業の強みや課題を明らかにします。
また、生産性や成長性に注目することで、組織の効率や将来性を把握することも可能です。本記事では、財務分析の基本的な進め方と4つの視点、具体的な指標の活用方法や分析時の注意点について詳しく解説します。
目次
財務分析とは?
財務分析とは、企業の財務諸表を基に経営の健全性や収益力を多面的に評価する手法です。例えば売上や利益の推移から収益性を見たり、負債と資本の割合から安全性を判断したりと、数字を通じて経営の課題や強みを浮き彫りにします。
単なる数値の確認にとどまらず、競合他社との比較や業界全体の動向を踏まえて活用することで、戦略的な意思決定に役立ちます。さらに将来の資金計画や投資戦略を考える上でも財務分析は欠かせず、経営改善や投資判断に直結する重要なプロセスといえるでしょう。
なお、財務の仕事についてはこちらの記事でも解説しています。
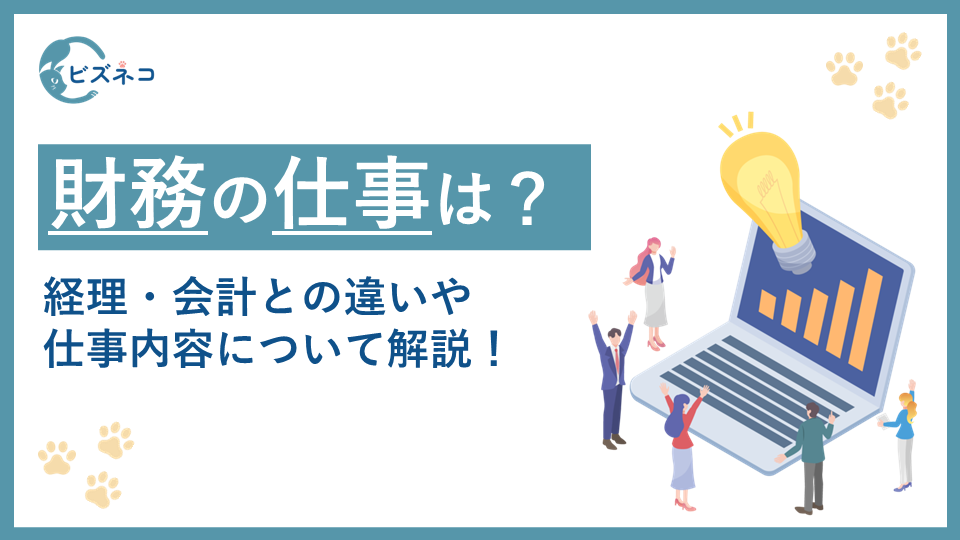
財務分析に必要な財務三表
財務分析を行う際には、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書という3つの財務諸表が欠かせません。例えば損益計算書では利益の構造を把握でき、貸借対照表では資産と負債のバランスを確認できます。さらにキャッシュフロー計算書を用いれば、資金の流れを通じて実際の経営体力を見極められます。
これら三表を総合的に読み解くことで、数字が示す表面的な結果だけでなく、その背景にある経営の仕組みや課題を理解できるのです。加えて、三表を相互に照らし合わせることでより正確な分析につなげられます。
損益計算書(P/L)
損益計算書は、企業の一定期間における収益と費用を整理し、最終的な利益を示す財務諸表です。例えば売上総利益や営業利益といった各段階の利益を確認することで、どこでコストがかかり、どこで利益が生まれているのかを把握できます。
売上が伸びていても費用が増加していれば利益率が下がる可能性があるため、損益計算書の分析は経営の収益構造を理解する上で重要です。さらに、過去数期分を比較することで、収益性の変化や改善の効果を確認することもでき、財務分析の第一歩として必ず目を通すべき資料といえるでしょう。
なお、損益計算書についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
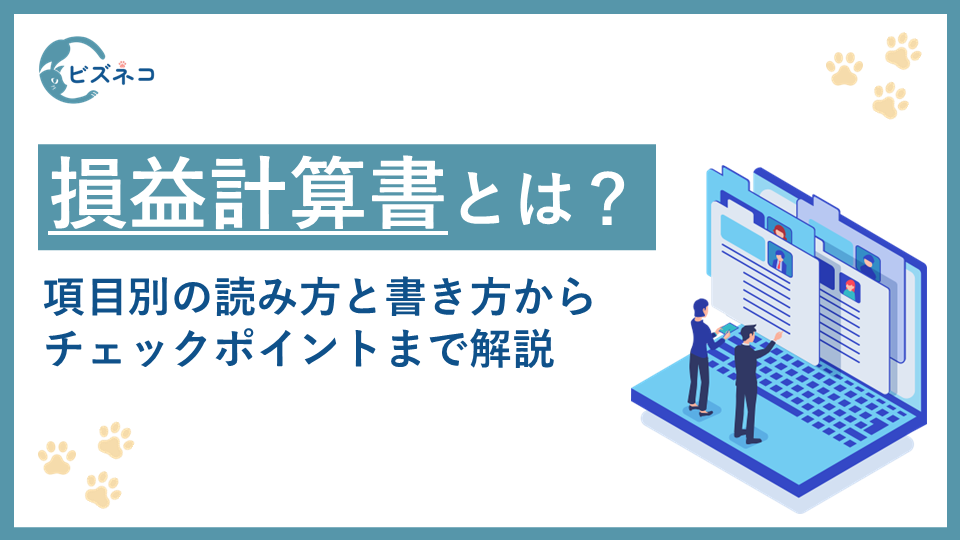
貸借対照表(B/S)
貸借対照表は、企業のある時点における資産・負債・純資産の状況を示す財務諸表です。例えば現金や売掛金などの流動資産と、借入金などの負債とのバランスを確認することで、財務の安全性や資金繰りの余裕を判断できます。
また、純資産の割合が大きいほど自己資本による経営基盤が安定していると考えられます。貸借対照表は単なる数字の羅列ではなく、企業の体力や持続性を映し出す鏡のような役割を果たしています。さらに、同業他社との比較を行うことで、自社の立ち位置や改善の余地を把握できる点も大きな特徴です。
なお、貸借対照表についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
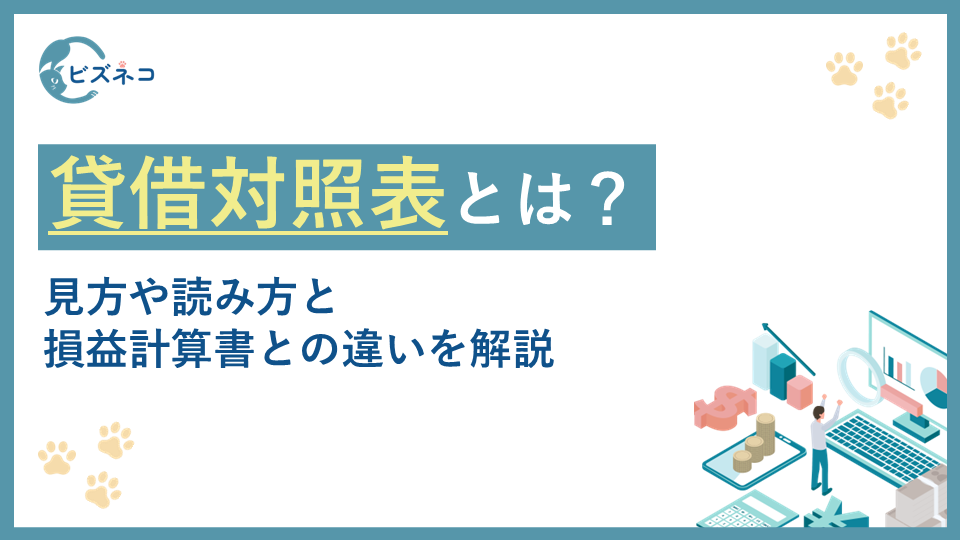
キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書は、企業の資金の流れを営業・投資・財務の三つの活動に分けて示す財務諸表です。例えば営業キャッシュフローが黒字でも投資や財務活動によって資金が減少していれば、資金繰りの不安が潜む可能性があります。
このように利益と実際の現金の動きが必ずしも一致しない点を補うのがキャッシュフロー計算書の役割です。資金の流れを的確に把握することで、企業の健全性や将来の成長余力を判断する助けになります。さらに、投資家や金融機関からの信頼性を高める資料としても重要な位置づけを持っています。
なお、キャッシュフロー計算書についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
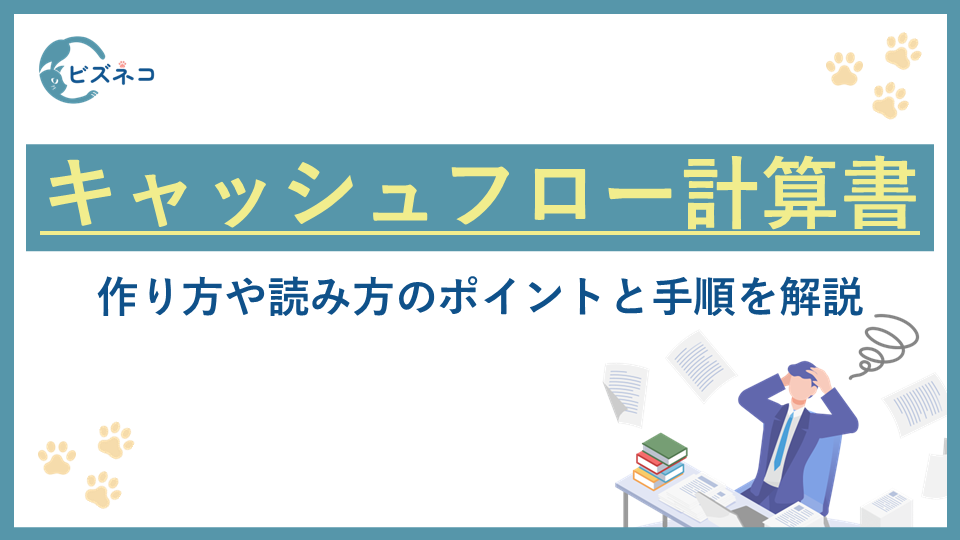
財務分析の4つの視点と種類
財務分析には4つの視点と種類があります。
- 視点1:収益性分析
- 視点2:安全性分析
- 視点3:生産性分析
- 視点4:成長性分析
ここでは、それぞれの視点や分析方法について具体的に紹介します。ぜひ、財務分析の参考にしてください。
視点1:収益性分析
収益性分析は、企業が投入した資本や資源からどれだけ効率的に利益を生み出しているかを確認するための視点です。例えば総資本利益率(ROA)を用いれば、資産全体を活用して得られる利益水準を把握でき、自己資本利益率(ROE)では株主が投じた資本に対する収益力を確認できます。
また売上高経常利益率を見ることで、営業活動の効率性やコスト構造の健全性を評価することが可能です。収益性分析は、企業が持続的に利益を生み出せる体制を整えているかを判断する基礎となる重要な分析領域といえます。
総資本利益率(ROA:Return On Assets)
総資本利益率(ROA:Return On Assets)は以下の計算式で算出されます。
- ROA(%)=利益÷総資産✕100
総資本利益率(ROA)は、企業が保有する総資産をどれだけ効率的に活用して利益を生み出しているかを示す指標です。例えば同じ利益額でも資産規模が大きければROAは低く、小規模の資産で高い利益を得られればROAは高くなります。
この数値を確認することで、資産の使い方が効率的かどうかを把握でき、経営全体の収益力を測る基準となります。短期的な利益水準を見るだけではなく、資産投資の成果や経営資源の有効活用を評価するために重要な役割を果たします。
自己資本利益率(ROE:Return On Equity)
自己資本利益率(ROE:Return On Equity)は、以下の計算式で算出されます。
- ROE(%)=当期純利益÷自己資本(純資産)×100
自己資本利益率(ROE)は、株主から預かった資本をどれだけ効率的に運用し、利益を生み出しているかを示す指標です。例えば同じ純利益でも自己資本が小さい場合にはROEは高くなり、逆に資本規模が大きい場合には数値が低くなります。
このことからROEは株主にとっての投資効率を表す数値ともいえ、投資家が企業の魅力を判断する際の重要な材料になります。ただし一時的な負債増加によって高く見える場合もあるため、他の指標と併せて総合的に評価することが望まれます。
売上高経常利益率
売上高経常利益率は、以下の計算式で算出されます。
- 売上高経常利益率(%)=経常利益÷売上高×100
売上高経常利益率は、売上に対してどれだけ経常利益を確保できているかを示す指標です。例えば売上が伸びても原価や販管費が増加すれば利益率は低下し、効率的な経営ができていないと判断されます。
一方で同業他社と比較して高い水準を維持していれば、コスト管理や営業活動がうまく機能していると考えられます。この数値は本業の収益力だけでなく、金融収支などを含めた経営全体の効率を測る上で有効です。安定した経常利益率を確保することは、持続的な成長の基盤を築くうえで重要な意味を持ちます。
視点2:安全性分析
安全性分析は、企業が財務的にどの程度安定しているかを判断するための視点です。例えば流動比率や当座比率を用いれば、短期的な支払い能力を確認でき、自己資本比率や株主資本比率を通じて長期的な安定性を把握できます。さらに固定比率や固定長期適合率をチェックすることで、資産と資本のバランスが適切かどうかを評価できます。
安全性分析は、単に債務返済能力を確認するだけでなく、外部からの信用や資金調達力にも直結します。健全な経営を続けるために欠かせない重要な視点といえるでしょう。
流動比率
流動比率は、以下の計算式で算出されます。
- 流動比率(%)=流動資産÷流動負債×100
流動比率は、企業が短期的に負債を返済できる能力を示す指標で、流動資産を流動負債で割って算出します。例えば流動資産に現金や売掛金など換金性の高いものが多ければ比率は高まり、支払い能力が強いと判断できます。
一方で比率が低い場合には、資金繰りに不安があるとみなされる可能性があります。ただし高ければ必ず健全というわけではなく、在庫が過大に積み上がっている場合などは注意が必要です。そのため流動比率は、他の安全性指標と組み合わせて確認することが大切です。
当座比率
当座比率は、以下の計算式で算出されます。
- 当座比率(%)=当座資産÷流動負債×100
当座比率は、流動資産の中でも現金や預金、受取手形、売掛金など短期間で現金化しやすい資産を基準に算出する指標です。例えば在庫のように売却まで時間を要する資産を除外するため、より厳密に企業の支払い能力を測定できます。
数値が高ければ短期的な資金繰りに余裕があると考えられますが、低い場合は突発的な支出や返済に耐えにくい状況を意味します。流動比率とあわせて確認することで、実際にどれだけ迅速に負債を返済できるかを判断するうえで有効な指標です。
自己資本比率
自己資本比率は、以下の計算式で算出されます。
- 自己資本比率(%)=純資産÷総資本×100
自己資本比率は、総資本に対する純資産の割合を示す指標で、企業の長期的な安定性を測る上で重要です。例えば自己資本比率が高ければ、借入金に頼らずに経営を維持できる体力があると判断できます。
一方で比率が低ければ、外部からの借入に依存しており、景気変動や金利上昇の影響を受けやすい状況を意味します。投資家や金融機関は、この数値を通じて企業の健全性や信用力を評価することが多いため、持続的な成長を目指す上でも注目すべき指標といえます。
株主資本⽐率
株主資本⽐率は、以下の計算式で算出されます。
- 株主資本⽐率(%)=株主資本÷総資産×100
株主資本比率は、総資産のうち株主資本がどの程度を占めているかを示す指標です。例えば株主からの出資や内部留保によって蓄積された資本が多ければ、この比率は高くなり、財務の安定性が強いと判断されます。
逆に低い場合には負債に依存している度合いが高く、経営リスクが増すと考えられます。株主資本比率は、自己資本比率と似た側面を持ちながらも、株主が投じた資金の比率をより直接的に示す点が特徴です。外部からの信用力を測る際にも重要な目安となります。
固定比率
固定比率は、以下の計算式で算出されます。
- 固定比率(%)=固定資産÷自己資本×100
固定比率は、自己資本に対して固定資産がどれだけ投資されているかを示す指標です。例えば自己資本を超えて固定資産を保有している場合、その不足分を借入金で賄っている可能性があり、資金繰りの安全性が下がると判断されます。
比率が低いほど、自己資本で固定資産を賄えているといえ、長期的な財務の健全性を示すことにつながります。ただし業種によって必要な設備投資の水準が異なるため、同業他社と比較しながら評価することが重要です。
固定長期適合率
固定長期適合率は、以下の計算式で算出されます。
- 固定長期適合率(%)=固定資産÷(自己資本+固定負債)×100
固定長期適合率は、自己資本に加えて固定負債も含めた長期資金が、固定資産をどの程度カバーしているかを示す指標です。例えば自己資本だけでは固定資産を賄えなくても、長期借入金で補えていれば数値は安定し、資金調達のバランスが取れていると評価されます。
逆に比率が高すぎる場合には、固定資産を短期資金で賄っている可能性があり、資金繰りのリスクが高まります。固定長期適合率は、固定比率とあわせて確認することで、企業の長期的な財務安定性をより正確に把握できます。
視点3:生産性分析
生産性分析は、企業が保有する人材や資源をどれだけ効率的に活用して成果を上げているかを測定するための視点です。例えば労働生産性を確認すれば、一人当たりの売上や利益を把握でき、組織の効率性を数値で評価することができます。
また、労働分配率を用いると、利益が従業員にどの程度還元されているかを確認でき、企業の持続可能性や働きやすさの指標にもつながります。生産性分析は、単に効率を高めることを目的とするのではなく、人的資源の活用度合いと企業全体の健全な成長のバランスを考えるうえで不可欠な要素です。
労働生産性
労働生産性は、以下の計算式で算出されます。
- 労働生産性=付加価値額÷労働投入量(従業員数もしくは労働時間)
労働生産性は、企業がどれだけ効率的に労働力を活用して成果を生み出しているかを示す重要な指標です。付加価値額を労働投入量で割って算出され、従業員一人ひとりの生産能力や組織全体の効率性を把握できます。
例えば、同じ規模の従業員数でも、生産性の高い企業はより多くの付加価値を生み出せるため、競争力の高さを裏付ける根拠となります。労働生産性を分析することで、業務改善の余地や人材活用の課題が明らかになり、成長戦略を考えるうえで欠かせない視点となります。
労働分配率
労働分配率は、以下の計算式で算出されます。
- 労働分配率(%)=人件費÷付加価値額×100
労働分配率は、企業が生み出した付加価値をどの程度従業員に還元しているかを示す指標です。人件費を付加価値額で割ることで算出され、労使間の利益配分のバランスを測る目安となります。例えば、労働分配率が高い場合は従業員への還元が厚い一方で、企業の内部留保や投資余力が制約される可能性があります。
逆に低い場合は企業に資金が残る反面、従業員の待遇に不満が生じることもあります。このように、労働分配率は経営と従業員双方の関係性を映し出すものであり、持続的な成長や働き方改革を検討する際に重視すべき要素となります。
視点4:成長性分析
成長性分析は、企業が将来に向けてどの程度発展していく可能性を持っているかを測定するための視点です。例えば売上高成長率を確認すれば、市場での拡大スピードを把握でき、経常利益成長率を見ることで収益力の向上度合いを確認できます。
さらに総資産成長率や売上高研究開発費率を分析することで、企業が資産をどのように増やし、未来への投資を行っているかを評価できます。成長性分析は、短期的な成果だけでなく、長期的な競争力や持続的な発展を見極めるために重要な視点であり、経営戦略や投資判断に直結します。
売上高成長率
売上高成長率は、以下の計算式で算出されます。
- 売上高成長率(%)=(当期売上高−前期売上高)÷前期売上高×100
売上高成長率は、企業が一定期間でどの程度売上を伸ばしたかを示す基本的な指標です。前期と当期の売上高を比較して算出され、事業の拡大スピードを客観的に把握できます。
例えば、新商品がヒットして売上が急増した場合には成長率が大きく上昇しますが、反対に市場縮小や競合の台頭によって売上が落ち込むとマイナス成長を示します。この指標は単なる増減だけでなく、経営戦略の成果や市場環境の影響を読み解くうえで重要な役割を果たし、投資判断や将来の成長性を測る基盤となります。
経常利益成長率
経常利益成長率は、以下の計算式で算出されます。
- 経常利益成長率(%)=(当期経常利益-前期経常利益)÷前期経常利益×100
経常利益成長率は、企業が本業や財務活動を通じてどの程度安定的に利益を拡大しているかを測定する指標です。営業利益に加えて受取利息や支払利息なども含む経常利益を基準とするため、企業の実力をより総合的に反映します。
例えば、売上が伸びても経費増加や金利負担で利益が圧迫されれば成長率は鈍化しますが、効率的なコスト管理や財務体質の改善によって高い成長を維持できることもあります。このように、経常利益成長率は短期的な業績変動ではなく、中長期的な収益力を見極めるうえで欠かせない評価軸となります。
総資産成長率
総資産成長率は、以下の計算式で算出されます。
- 総資産成長率(%)=(当期総資本-前期総資本)÷前期総資本×100
総資産成長率は、企業の総資産がどの程度増加しているかを示すもので、事業規模の拡大や投資活動の成果を把握するために用いられます。例えば、設備投資や研究開発への積極的な取り組みによって資産が増加すれば成長率は高まりますが、不採算事業の整理や資産売却を進めると一時的に低下することもあります。
総資産の増加は必ずしも好ましい状況を意味するわけではなく、負債の拡大を伴う場合には財務リスクが高まる点に注意が必要です。そのため、この指標は売上や利益の成長とあわせて分析し、資産の健全性を評価することが大切です。
売上高研究開発費率
売上高研究開発費率は、以下の計算式で算出されます。
- 売上高研究開発費率(%)=研究開発費÷売上高×100
売上高研究開発費率は、売上高に対して研究開発にどの程度の資源を投じているかを示す指標であり、企業の成長余力や競争力強化の姿勢を測る基準となります。例えば、製薬業界やIT企業のように技術革新が求められる分野では研究開発費率が高い傾向にありますが、短期的な利益を重視する業界では低く抑えられることもあります。
この比率が高ければ将来の新製品やサービスにつながる可能性がある一方、過度に高い場合は収益圧迫の要因ともなります。そのため、業界水準や企業戦略とのバランスを考慮して評価することが重要です。
財務分析の進め方における手順と注意点
財務分析の進め方における手順は以下のように進みます。
- step1:決算書(財務三表)を準備する
- step2:全体像から大まかに自社の課題を見つける
- step3:目的にあわせて細かく分析する
ここでは、進め方の流れや注意点とポイントを解説します。
step1:決算書(財務三表)を準備する
まずは、決算書(財務三表)を準備することから始まります。分析の出発点として、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書を過去数期分そろえることで傾向や一時的なズレを把握できます。
なお、データは機械処理しやすい形式で整え、予算や業界平均と突き合わせることでより正確な仮説形成につなげましょう。さらに監査の有無や修正仕訳、関連当事者取引の開示状況も確認し、必要に応じて販売台帳や顧客別売上と突合して裏付けを取ることで、分析の信頼性を高められます。
なお、決算書の作成方法についてはこちらの記事も参考にしてください。
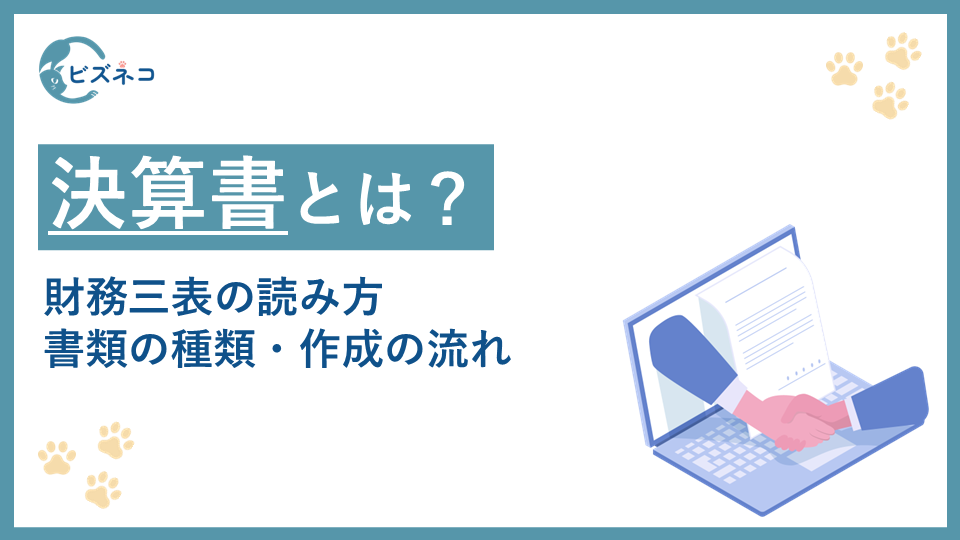
step2:全体像から大まかに自社の課題を見つける
次に、全体像から大まかに自社の課題を見つけていきます。まずは財務三表を俯瞰して主要な指標のトレンドや異常値を見つけ、優先的に調査すべき領域を絞ります。例えば売上に比して在庫や売掛金が増加している場合は資金繰りや回転率に問題がある可能性が高いと判断できます。
この段階では仮説立てを重視し、短絡的な結論を避けるために業界平均や過去の予算と比較して相対的な位置づけを確認します。また、主要指標をグラフ化して視覚的に傾向を把握し、短期的な影響と中長期的な構造課題を分けて評価していきましょう。
step3:目的にあわせて細かく分析する
最後に、目的にあわせて細かく分析していきます。分析目的ごとに着目すべき指標や手法を選び、深掘りの範囲を明確にすることが大切です。例えば収益改善が目的なら、利益率分解や顧客別採算性の分析を行い、どの製品やチャネルがボトルネックかを特定します。
またキャッシュ改善が目的の場合は営業CFや回収サイト、支払サイトの詳細を検証し、感度分析やシナリオ分析で対策の効果を試算します。注意点は相関を因果と誤認しないことと、一時項目や季節性を除外して本質を捉えることです。外部ベンチマークや過去施策と照合し、仮説と検証を繰り返すことで実行可能な改善案を導き出しましょう。
まとめ
財務分析は、企業の経営状態を客観的に把握し、将来の方向性を定めるための重要な手段です。収益性・安全性・生産性・成長性という4つの視点を組み合わせて確認することで、単なる数値の羅列では見えにくい課題や強みを多角的に把握できます。
また、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を総合的に読み解くことで、現状の健全性だけでなく将来に向けた投資や成長余力まで評価できる点も大きな特徴です。財務分析では、正しい手順で進め、注意点を押さえることで、財務分析は経営改善や戦略立案につなげることができます。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
財務分析に関するよくあるご質問
財務分析についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、財務分析に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
財務分析とは何ですか?
財務分析は、企業の財務諸表を基に経営状況や収益力、資金繰りの健全性を多角的に評価すします。例えば損益計算書で利益構造を確認し、貸借対照表で資産と負債のバランスを把握することで、経営課題や強みを明らかにできます。また、キャッシュフロー計算書を活用すれば、実際の資金の流れや将来の投資余力を確認できます。
財務分析の4つの手法は何ですか?
財務分析には主に収益性分析・安全性分析・生産性分析・成長性分析の4つの手法があります。収益性分析では総資本利益率などで利益効率を評価し、安全性分析では流動比率など財務の安定性を確認します。生産性分析では労働生産性を通じて資源活用の効率を測定し、成長性分析では総資産の増加率から将来性を判断できます。
財務分析で見るべきポイントは何ですか?
財務分析で注目すべきポイントは、収益性・安全性・効率性・成長性のバランスです。売上や利益の推移を確認して収益性を評価し、負債比率や流動比率から財務の安定性を判断します。さらに労働生産性などの効率指標の分析や、売上高成長率を通じて将来の成長余力を検討します。これらを総合的に確認することが大切です。




