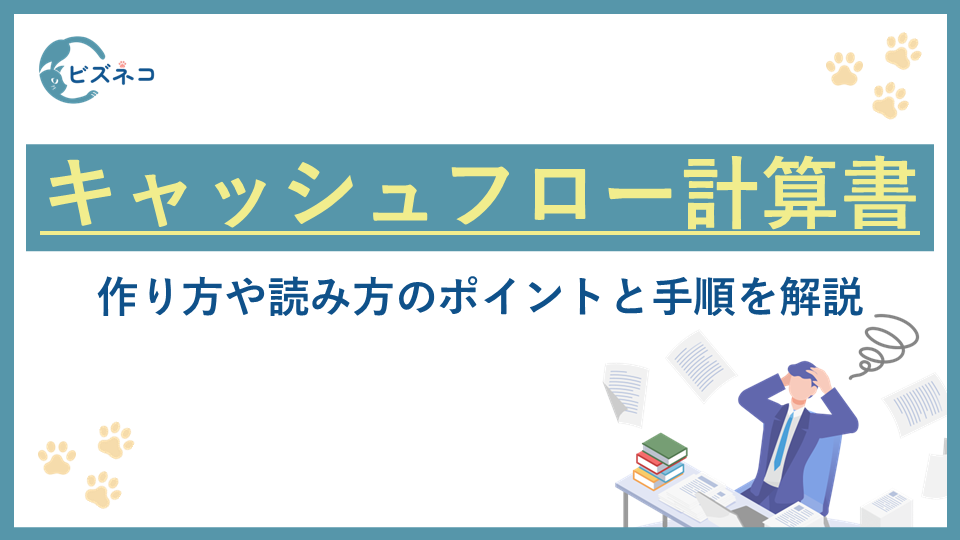
キャッシュフロー計算書は、企業のお金の流れを明確に示す重要な財務書類です。売上や利益だけでは把握しきれない、現金の実際の動きを把握できるため、資金繰りや経営判断の精度を高めるうえで欠かせません。
本記事では、キャッシュフロー計算書の基礎から目的、区分、作成方法までを詳しく解説します。また、経営者や投資家が資金面から企業の健全性を判断できるようになるための読み方のポイントも紹介します。ぜひ、参考にしてください。
目次
キャッシュフロー(C/F)とは?
キャッシュフロー(C/F)とは、企業における現金の流れを把握するための概念です。利益と現金は必ずしも一致せず、黒字でも資金繰りに困るケースがあるため、現金の増減を把握することは経営管理に欠かせません。
例えば、売掛金が増えても現金が入ってこなければ手元資金は不足します。このようにキャッシュフローを理解することで、企業が日々の支払いに対応できるか、投資や借入に余力があるかなどを確認でき、健全な経営判断につなげることができます。
キャッシュフロー計算書とは?
キャッシュフロー計算書とは、一定期間における現金の出入りを営業活動、投資活動、財務活動の3つに区分して示す財務諸表です。損益計算書や貸借対照表と異なり、実際の資金の動きを明確に表すため、資金繰りの実態を把握する手がかりとなります。
例えば、利益は出ているのに資金が不足している企業は、営業活動によるキャッシュフローがマイナスである場合が多いです。この計算書を確認することで、将来の資金調達の必要性や事業活動の健全性を判断することができます。
財務三表とは?
財務三表とは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の3つを指し、企業の経営状態を総合的に把握するために用いられます。それぞれ役割が異なり、貸借対照表は資産と負債のバランスを示し、損益計算書は収益と費用を明らかにし、キャッシュフロー計算書は資金の流れを表現します。
例えば、利益は大きくても借入金が増えている場合には財務体質が健全とは言えません。財務三表を組み合わせて分析することで、数字の一面だけでは見えない企業の全体像をつかむことができます。
なお、財務三表についてはこちらの記事も参考にしてください。
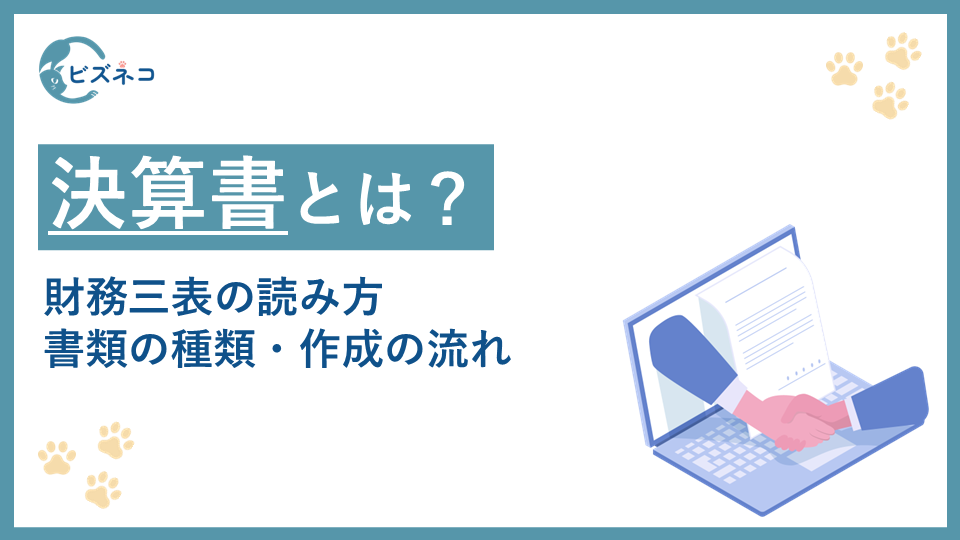
キャッシュフロー計算書と貸借対照表の違い
キャッシュフロー計算書と貸借対照表は、いずれも財務諸表ですが、示す内容が大きく異なります。貸借対照表はある時点の資産、負債、純資産の状況を一覧化したものに対し、キャッシュフロー計算書は一定期間の現金の流れを明らかにします。
例えば、貸借対照表で資産が増加していても、それが売掛金であれば実際に現金が増えているとは限りません。一方でキャッシュフロー計算書では、現金の増減が具体的に示されるため、資金繰りの健全性を確認するうえで重要な指標となります。
なお、貸借対照表についてはこちらの記事も参考にしてください。
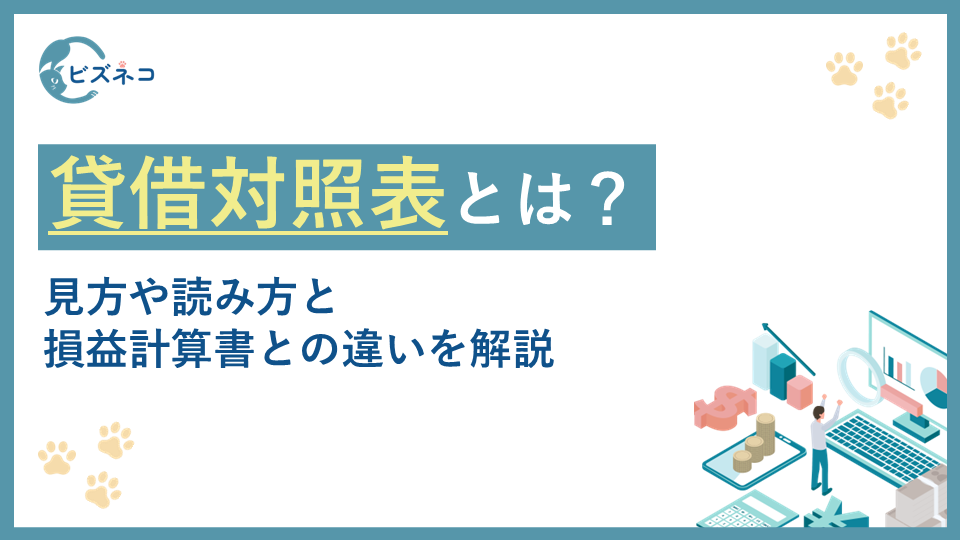
キャッシュフロー計算書と損益計算書の違い
キャッシュフロー計算書と損益計算書は、どちらも企業の経営状況を理解するうえで不可欠ですが、着目点が異なります。損益計算書は収益と費用を集計し、一定期間の利益を示すものです。一方、キャッシュフロー計算書は利益の有無にかかわらず、現金が実際に増えたのか減ったのかを明確にします。
例えば、損益計算書で黒字でも、売掛金の回収が遅れていれば現金は不足します。このように両者を比較して確認することで、利益と資金のバランスを正しく理解し、安定した経営判断を下すことができます。
なお、損益計算書についてはこちらの記事を参考にしてください。
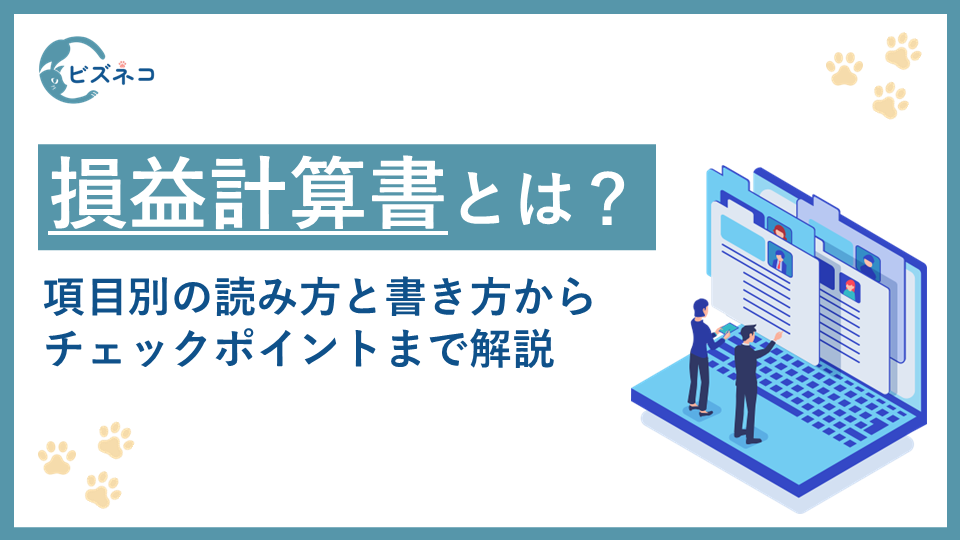
キャッシュフロー計算書を作成する目的
キャッシュフロー計算書を作成する目的として、以下のような点があげられます。
- 資金の流れを把握するため
- 企業の支払能力や財務状況を判断するため
- 経営判断や投資判断に役立てるため
ここでは、それぞれの目的について具体的に解説していきます。
資金の流れを把握するため
キャッシュフロー計算書を作成する目的のひとつは、企業における資金の流れを正確に把握することです。損益計算書では利益が出ていても、実際に現金が不足していれば日々の支払いに支障をきたす可能性があります。
例えば、売掛金が多く計上されていても、現金化されるまでには時間がかかり、その間は手元資金が増えないことがあります。キャッシュフロー計算書では営業活動や投資活動、財務活動ごとに現金の動きを整理できるため、資金の増減を明確に確認でき、経営における資金繰りの見通しを立てやすくなるのが特徴です。
企業の支払能力や財務状況を判断するため
キャッシュフロー計算書を活用する目的には、企業の支払能力や財務状況を判断することがあります。黒字であっても、現金が十分に確保されていなければ仕入代金や借入金の返済に遅れが生じる可能性があり、経営の安定性を欠く要因となります。
例えば、営業活動によるキャッシュフローが長期にわたりマイナスであれば、本業で資金を生み出せていないことを示し、資金調達やコスト管理の改善が必要と考えられます。このようにキャッシュフロー計算書は、利益だけではわからない資金面の健全性を示し、外部の投資家や金融機関にとっても重要な判断材料となります。
経営判断や投資判断に役立てるため
キャッシュフロー計算書を作成する目的には、経営判断や投資判断に役立てるという側面もあります。資金の流れを確認することで、企業がどの程度の余力を持ち、新たな投資や借入に対応できるかを把握できます。
例えば、営業活動で安定的に現金を得られていれば、設備投資や人材採用に積極的に資金を回すことが可能です。一方、投資活動による支出が増えても、それを補うだけの営業キャッシュフローがあれば長期的な成長につながると判断できます。こうした分析を行うことで、経営者は将来に向けた戦略を立てやすくなり、外部の投資家にとっても企業の将来性を見極める手掛かりとなります。
キャッシュフロー計算書の区分
キャッシュフロー計算書の区分には、主に以下の4種類があります。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフロー
- フリーキャッシュ・フロー
基本的には「営業」「投資」「財務」の3つであり、それ以外のものが「フリーキャッシュ・フロー」に分けられます。それぞれの違いや役割について詳しく解説します。
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフローは、本業の事業活動を通じて現金がどのように増減したかを示すものです。売上による入金や仕入、人件費などの支払いが含まれ、企業の資金力を測るうえで最も注目される部分です。
例えば、利益が計上されていても、売掛金の回収が遅れていれば営業活動によるキャッシュフローはマイナスになる可能性があります。営業活動によるキャッシュフローという指標は、企業が日常的に資金を生み出せているかどうかを判断するための重要な材料であり、安定した経営基盤の有無を確認するうえで欠かせない要素となります。
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフローは、企業が将来の成長のためにどのような投資を行い、それが現金の増減にどう影響したかを示します。設備投資や有価証券の取得、子会社株式の購入などによる支出が主な内容であり、場合によっては資産売却による収入も含まれます。
例えば、新しい工場建設に伴う支出が増えれば投資活動によるキャッシュフローはマイナスになりますが、それは必ずしも悪い兆候とは限りません。むしろ将来の収益を生み出すための前向きな資金の使い方であることも多く、投資活動によるキャッシュフローの区分を理解することで企業の成長戦略や投資姿勢を読み解くことができます。
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフローは、資金調達や返済、株主への配当といった財務上の取引による現金の動きを示します。借入金の増減や社債の発行、株式発行による資金調達などが含まれる一方で、借入金の返済や配当金の支払いもここに計上されます。
例えば、新規の借入によって一時的にキャッシュフローがプラスとなっても、その後の返済負担が増える可能性があります。財務活動によるキャッシュフローの指標は、企業がどのように資金を調達し、どのように株主へ還元しているかを理解する手がかりとなり、経営の安定性や財務戦略を評価するうえで欠かせない要素となります。
フリーキャッシュ・フロー
フリーキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュフローから投資活動によるキャッシュフローを差し引いて算出される指標です。企業が自由に使える資金を示すため、株主や投資家から重視される傾向があります。
例えば、営業活動で得た資金が十分にあり、投資活動に必要な支出を差し引いた後でも余剰があれば、その資金を借入返済や配当、さらには新たな成長投資に活用できます。逆にフリーキャッシュ・フローが継続的にマイナスであれば、事業の自立的な成長が難しい状況を示唆します。フリーキャッシュ・フローの指標を確認することで、企業の資金力や投資余力を総合的に理解することができます。
キャッシュフロー計算書の作成方法
キャッシュフロー計算書の作成方法には、現金の流れをそのまま記載する直接法と、利益の数値を現金ベースに置き換える間接法の2種類があります。例えば、直接法は資金の動きを直感的に把握しやすく、間接法は損益計算書とのつながりを理解しやすい特徴があります。どちらの方法を選ぶかによって見える情報が異なるため、目的に応じた活用が重要です。
直接法:現金の出入をそのまま集計する方法
直接法は、企業の現金収入と現金支出をそのまま集計し、営業活動によるキャッシュフローを明らかにする方法です。売上代金の受け取りや仕入代金の支払いなど、実際に現金が動いた取引をひとつずつ積み上げるため、資金の流れを直感的に理解しやすい特徴があります。
例えば、取引先からの入金額や従業員への給与支払い額をそのまま記載するため、どこから現金が入ってきて、どこに出ていったのかを明確に把握できます。一方で、膨大な取引を網羅的に集計する必要があるため作成には手間がかかりますが、現金の実態を詳細に把握するには有効な方法といえるでしょう。
間接法:利益の数字から置き換えて計算する方法
間接法は、損益計算書に示される税引前当期純利益を出発点とし、減価償却費や引当金の増減など現金の動きを伴わない項目を加減して営業活動によるキャッシュフローを求める方法です。例えば、減価償却費は費用として計上されるものの現金支出を伴わないため、利益に加算する必要があります。
このように間接法では、利益の数値を現金ベースに置き換えて計算するため、損益計算書とのつながりが理解しやすいというメリットがあります。ただし、直接法に比べて現金の流れを細かく把握することは難しく、あくまで利益との調整過程を通じて資金の増減を確認する方法となります。
キャッシュフロー計算書を作成する手順
キャッシュフロー計算書を作成する手順は以下のステップで進みます。
- step1:直接法か間接法を選択する
- step2:貸借対照表と損益計算書を用意する
- step3:項目ごとに分類して記入する
ここでは、それぞれの作成の流れについて詳しく解説します。
step1:直接法か間接法を選択する
キャッシュフロー計算書を作成する最初の手順は、直接法と間接法のどちらを採用するかを決めることです。直接法は、現金の収入と支出をそのまま記載するため資金の流れが明確になりますが、作成には手間がかかる特徴があります。
一方、間接法は損益計算書の利益を基準に調整していく方法で、作成の効率性や損益計算書との連携に優れています。例えば、利益に減価償却費を加算して現金の流れに置き換えるのが間接法です。どちらの方法を用いるかは、財務分析の目的や作成のしやすさによって判断されます。
step2:貸借対照表と損益計算書を用意する
キャッシュフロー計算書を作成するには、基礎となる財務諸表を準備することが欠かせません。特に貸借対照表と損益計算書は、現金の流れを把握するための重要な資料となります。
例えば、貸借対照表の資産や負債の増減は現金の出入りと密接に関連しており、売掛金が増えれば現金は減少する要因となります。また、損益計算書に記載された利益を基に調整することで、実際の資金の増減に近づけることができます。貸借対照表と損益計算書の資料を用意することで、キャッシュフロー計算書に必要な数値を正確に導き出せるようになります。
step3:項目ごとに分類して記入する
キャッシュフロー計算書を完成させるには、各取引を営業活動、投資活動、財務活動といった区分に分けて記入していくことが重要です。例えば、商品の販売による入金は営業活動に含まれ、設備の購入は投資活動に、借入金の返済や配当の支払いは財務活動に分類されます。
このように項目ごとに整理することで、資金の流れを明確に把握でき、どの活動が現金を生み出し、どの活動が支出を伴っているかが見えてきます。分類作業を丁寧に行うことは、経営判断や将来の資金計画に役立つキャッシュフロー計算書を作成するための大切なプロセスとなります。
キャッシュフロー計算書の読み方のポイント
キャッシュフロー計算書を正しく読むことは、企業の資金繰りや成長可能性を理解するうえで欠かせません。営業活動で安定的に現金を生み出しているか、投資や財務の動きが健全かを確認することで、利益だけでは見えない経営の実態を把握できます。ここでは、経営者が見るべき自社のキャッシュフローのポイントと、投資家に見られるキャッシュフローのポイントを具体的に解説します。
経営者が見るべきキャッシュフローのポイント
経営者が注目すべきキャッシュフローのポイントは、企業の資金が健全に回っているかを把握することにあります。営業活動によるキャッシュフローが安定してプラスであるかは、本業で資金を稼ぐ力を示すため特に重要です。
例えば、利益が出ていても売掛金の増加によって現金が不足していれば、日常的な支払いに支障をきたす可能性があります。また、投資活動や財務活動によるキャッシュフローを併せて確認することで、将来の成長戦略や資金調達の健全性を見極められます。こうした分析を通じて、経営者は自社の強みや課題を把握し、資金計画に反映させることができます。
投資家に見られるキャッシュフローのポイント
投資家が注目するキャッシュフローのポイントは、企業が将来にわたり安定して資金を生み出せるかどうかにあります。営業活動によるキャッシュフローの継続的なプラスは、企業が自力で資金を稼ぐ力を持つ証拠となり、信頼性を高めます。
例えば、フリーキャッシュフローが十分に確保されていれば、新規投資や株主還元に活用できるため、投資家にとって魅力的な企業と映ります。一方、投資活動によるキャッシュフローがマイナスであっても、それが将来の成長を見据えた投資であれば前向きに評価されることもあります。投資家はこうした視点で企業の財務健全性や成長余力を判断しているのです。
まとめ
キャッシュフロー計算書とは、一定期間における現金の出入りを営業活動、投資活動、財務活動の3つに区分して示す財務諸表です。損益計算書や貸借対照表と異なり、実際の資金の動きを明確に表すため、資金繰りの実態を把握する手がかりとなります。
キャッシュフロー計算書を作る目的としては、資金の流れを把握するためや企業の支払能力や財務状況を判断するためだけではなく、経営判断や投資判断に役立てるためという側面もあるため、正確に作成することが求められます。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
キャッシュフロー計算書に関するよくあるご質問
キャッシュフロー計算書についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、キャッシュフロー計算書に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
キャッシュフロー計算書(C/F)とは何ですか?
キャッシュフロー計算書とは、企業の一定期間における現金や現金同等物の増減を示す財務諸表のひとつです。営業活動・投資活動・財務活動の3つに区分して資金の流れを整理するため、利益だけでは見えない実際の現金の動きを把握できます。利益が出ていても資金繰りに余裕があるとは限らない状況を明らかにします。
キャッシュフロー計算書の提出義務はありますか?
キャッシュフロー計算書の提出義務は、上場企業や金融商品取引法に基づき有価証券報告書を提出する会社などに課されています。一方で、中小企業や個人事業主については法的に必ず作成・提出する義務はありません。ただし、金融機関からの融資を受ける際や経営改善計画を立てる際に求められることが多いです。
貸借対照表とキャッシュフロー計算書の違いは何ですか?
貸借対照表はある時点における資産・負債・純資産の状態を示し、企業の財務状況を静的に表します。一方、キャッシュフロー計算書は一定期間における現金の動きを動的に示す点が異なります。例えば、貸借対照表に多額の売掛金が計上されていても、現金として入金されるまではキャッシュフローに反映されません。




