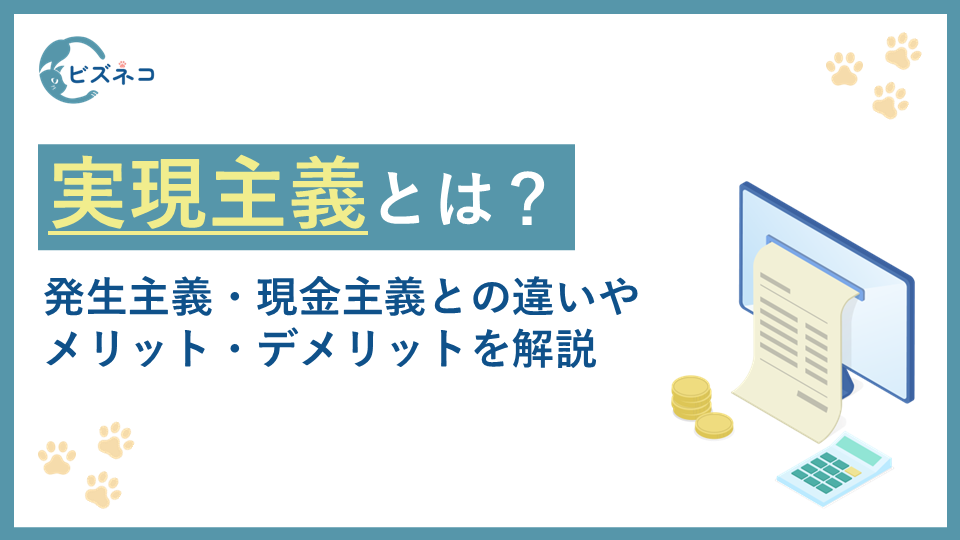
「実現主義」とは、収益を現実に実現した時点で計上する会計基準のことです。企業の経済活動を正確に反映するため、発生主義や現金主義とは異なるタイミングで収益や費用を認識します。実現主義は企業の業績や財務状態を適切に把握するのに有効ですが、代金未回収のリスクや粉飾決算の温床になる可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、実現主義の基本的な考え方や、発生主義・現金主義との違い、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。実現主義の適用基準や具体的な会計処理の流れも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
実現主義とは?
実現主義とは、収益や費用を「実現」したタイミングで会計処理を行う考え方です。具体的には、取引によって成果が確定し、経済的なやり取りが完了した時点で収益を認識します。例えば、商品を出荷し、顧客に納品が完了した段階で売上を計上するのが一般的です。
実現主義の考え方は、企業の経済活動の実態を反映しやすく、業績評価の精度を高めるというメリットがあります。ただし、現金の受け渡しとはタイミングが異なるため、実際の資金繰りとのズレを把握しておくことも重要です。
発生主義・現金主義・実現主義の関係
| 基準 | 収益の認識時点 | 費用の認識時点 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 発生主義 | 発生時(契約・役務提供時) | 発生時(債務確定時など) | 損益を対応させやすく財務分析に効果的 |
| 現金主義 | 現金受取時 | 現金支払時 | シンプルで小規模事業者に向いている |
| 実現主義 | 収益が確実に実現された時点(商品が届いた時など) | 発生主義と併用されることが多い | 会計上の収益認識の基本的な考え方 |
会計処理の基準には複数の考え方があり、「発生主義」「現金主義」「実現主義」は、代表的な3つの基準です。発生主義・現金主義・実現主義は、収益や費用を計上するタイミングに違いがあり、それぞれの特徴を理解することで会計上の判断がより明確になります。
例えば、現金主義は入金や出金があったときに処理するためシンプルですが、損益対応が不正確になる傾向があります。発生主義は実態に沿った損益を把握できる一方で、現金の動きとズレることもあります。また、実現主義は収益が確定的となった時点で計上するのが特徴で、収益認識の基本とされています。
実現主義と発生主義の違い
実現主義と発生主義は、収益や費用を認識するタイミングに違いがあります。どちらも現金の受け渡しではなく、経済的な出来事の発生に着目しますが、実現主義は成果が「実現」されたかどうかに焦点を当てるのに対し、発生主義は権利や義務が「発生」した時点を基準とします。
例えば、商品を出荷した時点で売上を認識するのが実現主義ですが、注文を受けた段階で計上する考え方が発生主義に近いといえます。この微妙な違いが、企業の財務情報の見え方に大きな影響を与えるため、正確な理解が求められます。
なお、発生主義については、こちらの記事を参考にしてください。
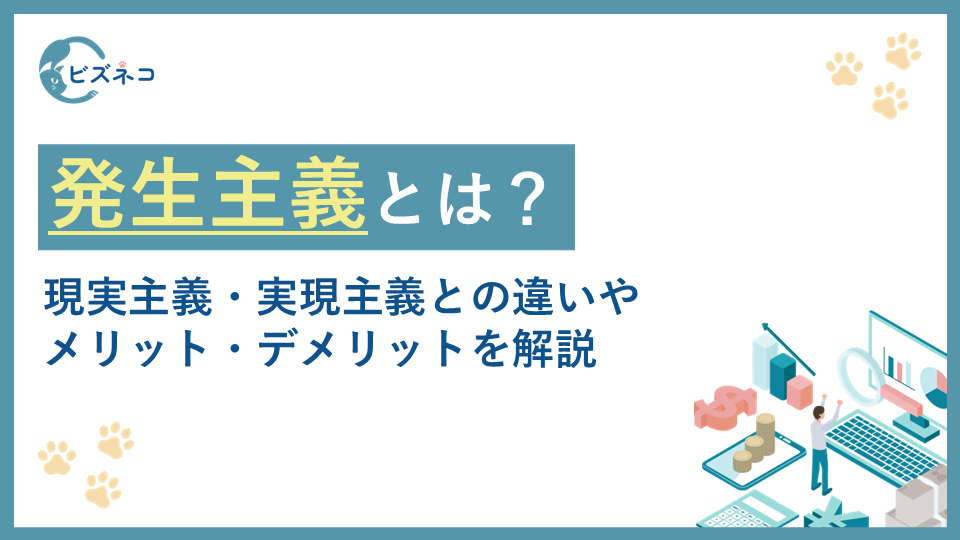
実現主義と現金主義の違い
実現主義と現金主義の最大の違いは、収益や費用を認識する「タイミング」の考え方にあります。現金主義は現金の受け渡しがあった時点で収益や費用を計上するため、実際のキャッシュフローに連動しやすいという特徴があります。
一方、実現主義では、取引が経済的に完了した時点、例えば商品を納品し顧客の受け取りが確認された段階で売上を計上します。これにより、会計帳簿がより実態を反映しやすくなりますが、現金の動きとはズレが生じる可能性もあります。そのため、実現主義と現実主義のそれぞれの特性を踏まえて使い分けることが重要です。
なお、現金主義についてはこちらの記事をご覧ください。

実現主義のメリット
実現主義のメリットとして、以下のような点があげられます。
- 成果が確定した時点での実態がわかる
- 収益の過大評価・過小評価を防ぐ
- 業績予測や経営分析がしやすくなる
- 会計期間ごとの損益がわかりやすい
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
成果が確定した時点での実態がわかる
成果が確定した時点で企業の実態を把握しやすくなる点が、実現主義の大きなメリットです。取引が実際に成立し、成果が確定した段階で収益や費用を記録するため、数字が実態に即しているという安心感があります。
例えば、製品の出荷後に顧客が検収を完了した段階で売上を計上する場合、その時点での取引結果が財務諸表に正しく反映されます。こうした処理により、経営陣や関係者は、進行中のビジネス状況を正確に把握でき、実際の事業活動と帳簿のズレが少なくなるというメリットがあります。
収益の過大評価・過小評価を防ぐ
収益を適切なタイミングで認識できるため、過大評価や過小評価を避けやすくなるのが実現主義のメリットです。収益認識のタイミングを恣意的に操作することが難しくなるため、会計の信頼性が向上します。
例えば、商品をまだ出荷していない段階で売上を計上すれば、実態よりも収益が多く見えることになりますが、実現主義ではそうした処理は認められません。逆に、既に成果が確定しているにもかかわらず収益計上を遅らせることも避けられます。これにより、企業の財務状況をより正確に反映できる点がメリットとなります。
業績予測や経営分析がしやすくなる
業績予測や経営分析に役立てやすいのも、実現主義を採用するメリットのひとつです。収益や費用が「実現」されたタイミングで計上されるため、各期のデータが現実の事業活動と整合し、将来の見通しを立てやすくなります。
例えば、検収をもって売上を認識するルールを徹底していれば、期ごとの売上推移や費用構造が安定し、経営の意思決定にも有効な資料となります。曖昧さの少ない数字が蓄積されることで、分析結果にも説得力が生まれ、企業の戦略策定に活用しやすくなるのです。
会計期間ごとの損益がわかりやすい
会計期間ごとの損益がわかりやすい点が実現主義のメリットです。収益と費用が、実際に成果が確定したタイミングで記録されるため、各会計期間における業績の実態が正確に表れます。
例えば、年度末に納品を終えた契約がある場合、その売上は当年度の業績に正しく計上され、翌期にずれ込むことはありません。これにより、期ごとの損益を比較する際にも数字の連続性が保たれ、経営の安定性や収益構造を明確に把握できるようになります。特に長期的な経営分析においては、この特性が大きな強みとなります。
実現主義のデメリット
実現主義のデメリットとして、以下のような点があげられます。
- 現金収支とのズレが生じてしまう
- 代金の未回収リスクがある
- 粉飾決算につながる恐れがある
- 制度の理解が難しく時間がかかる
ここでは、それぞれのデメリットを詳しく解説します。
現金収支とのズレが生じてしまう
現金の動きと会計上の収益や費用の認識にズレが生じやすい点が、実現主義のデメリットです。収益や費用は成果が「実現」したタイミングで記録されますが、実際の入出金はそれより後になることが多く、キャッシュフローとの乖離が発生する恐れがあります。
例えば、納品完了をもって売上を計上しても、実際の入金は1〜2か月後になるケースがあります。帳簿上では黒字でも、手元資金が足りないといった事態を招く可能性があり、特に資金繰りに敏感な中小企業にとっては注意が必要です。経営判断を行う際は、会計上の損益と実際の現金の動きを区別して把握することが求められます。
代金の未回収リスクがある
代金を回収できるかどうかにかかわらず、収益を計上する必要があるため、未回収リスクを伴うのが実現主義のデメリットです。取引が実現した段階で収益として認識するため、後になって顧客からの支払いが滞った場合でも、すでに計上した売上を訂正するわけにはいきません。
例えば、検収完了をもって売上を計上したものの、その後に取引先が倒産し、代金が回収できなくなることもあります。このような場合、貸倒損失などの処理が必要になりますが、初期段階では損益が実態と乖離することになります。信用管理の徹底や与信判断の精度が、実現主義を導入するうえで重要な要素となります。
粉飾決算につながる恐れがある
収益の認識タイミングが裁量の余地を含むため、粉飾決算に悪用される可能性がある点も実現主義のデメリットです。成果が「実現」されたと判断すれば収益計上ができるため、その判断基準が不明瞭だとあいまいな処理が入りやすくなります。
例えば、出荷基準を採用している企業が、まだ納品していない商品についても売上として計上してしまうと、本来の業績以上によく見せることができます。このような処理は短期的には利益を押し上げるかもしれませんが、長期的には信頼性を損ない、会計監査で問題視されることもあります。そのため、明確な基準に基づく運用と内部統制の強化が求められます。
制度の理解が難しく時間がかかる
収益認識のタイミングや基準が複雑で、制度の理解に時間がかかることも実現主義の課題です。実現主義では、出荷基準・検収基準・役務完了基準など、取引内容に応じた判断が必要となり、単純な現金主義に比べて会計処理の難易度が高くなります。
例えば、サービス業で役務提供の完了をもって収益を認識する場合、その完了時点をどう定義するかは業態や契約条件によって異なります。こうした判断には専門的な知識と経験が求められ、誤解や処理ミスにつながる可能性もあります。企業としては、社内の会計スキルを高める体制づくりが不可欠となります。
実現主義の「実現」の主な基準
実現主義の「実現」の主な基準として、以下の表のようなものがあります。
| 「実現」の基準 | 収益認識のタイミング | 適用されやすい業種 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 出荷基準 | 商品を出荷し顧客に向けて発送した時点 | 製造業・卸売業 | 手続きが明確で処理しやすい |
| 検収基準 | 顧客が商品の受領・検査を完了した時点 | 建設業・設備工事業 | 顧客の確認後に収益認識のため信頼性が高い |
| 納品基準(着荷基準) | 顧客に商品が到着し引き渡しが完了した時点 | 小売業・通販事業 | 返品や未着のリスクに対応しやすい |
| 役務完了基準 | サービスの提供が完了し契約を履行した時点 | サービス業・コンサル業 | モノではなく役務に対して収益認識を行う |
出荷基準
出荷が完了した時点で収益を認識するのが出荷基準です。商品を顧客に送り出した段階をもって「取引が実現した」と判断します。
例えば、注文を受けた商品を倉庫から出荷し、運送業者に引き渡した瞬間に売上を計上するイメージです。出荷基準は処理タイミングが明確なため、製造業や卸売業などに多く採用されていますが、実際に顧客の手元に商品が届いていない時点での収益認識となるため、配送中のトラブルや返品のリスクをどう扱うかが課題になります。そのため、契約条件や業種によって適用の可否を検討する必要があります。
検収基準
顧客が商品の受け取りを確認し、不備がないことを承認した段階で収益を認識するのが検収基準です。納品や設置などの工程を経てから、顧客側の「検収書」や「受領確認」が出された時点をもって収益が実現したとみなす考え方です。
例えば、建設業や設備工事などでは、実際の引き渡し後に検査が行われ、問題がなければそこで取引完了と見なされます。出荷や納品のタイミングに比べて遅い段階での認識になるため、売上の計上が後ろ倒しになる傾向がありますが、その分、実態に即した確実な取引認識が可能です。そのため、契約内容と業務フローに合致しているかを慎重に判断することが求められます。
納品基準(着荷基準)
顧客のもとに商品が到着し、引き渡された段階で収益を認識するのが納品基準(着荷基準)です。出荷しただけでは売上とはならず、顧客側の受領が確認できた時点で収益が実現したと見なされます。
例えば、通販事業者が商品を発送しても、顧客が実際に荷物を受け取らなければ売上を計上できない仕組みです。納品基準は出荷から受領までのリードタイムを含むため、会計処理がやや複雑になりますが、配送過程のリスクを考慮に入れた安全性のある認識方法といえます。特に返品や未着のリスクがある取引では、納品基準が適しているケースもあります。
役務完了基準
サービスや作業が完了し、契約上の義務を果たした段階で収益を認識するのが役務完了基準です。モノの引き渡しではなく、サービスの提供が対象となるため、いつ完了と見なすかの判断が重要になります。
例えば、コンサルティングや研修サービスのように、契約に基づいて一定の役務を提供した後、業務が完結した時点で売上を計上する形になります。役務が継続する場合には、進捗基準と併用されることもありますが、基本的には契約書などで明確に完了条件を定めておくことが望まれます。サービス業においては、実現主義の運用において核となる基準のひとつです
実現主義における会計処理の流れと仕訳例
会計処理において実現主義を適用する場合、収益や費用の認識タイミングが重要になります。実現主義では、契約上の義務が履行され、経済的成果が確定した時点で取引を会計帳簿に反映します。
実現主義の「確定した時点」がいつなのかは、出荷基準や納品基準などの実現基準によって判断されます。例えば、納品基準を採用している企業が、4月5日に商品を出荷し、4月6日に顧客の元に商品が届いたとしましょう。この場合、売上の計上は商品が顧客に到着し、契約上の条件が満たされた4月6日になります。
さらに、実際の入金がその月末、例えば4月30日だったとすると、売掛金の入金処理はその時点で行います。このように、収益と現金収支の間にタイムラグがある点が、実現主義の特徴でもあります。
step1:出荷した商品が顧客に届く(「実現」する)
収益を認識する最初のステップは、実現基準に基づき「収益が発生した」とみなされる条件が満たされたときです。例えば、ある企業が納品基準を採用しており、4月10日に商品を出荷したとします。
その商品が4月11日に顧客に届き、受領の確認が取れた場合、売上は4月11日に実現したと判断されます。この段階で企業は収益を計上し、同時に売掛金として債権を記録します。
ここではまだ現金は受け取っていないものの、将来的な入金が見込まれるため、売上計上が先に行われるのがポイントです。以下のように仕訳されます。
仕訳例:4月11日に商品が納品され、売上が実現した場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
取引が「実現」した時点で収益を計上するのが、実現主義における基本的な処理の考え方です。
step2:売掛金が入金される
商品が顧客に届き売上が計上された後、次のステップとして実際に代金が支払われるタイミングで、売掛金の消し込み処理を行います。例えば、先の例で売掛金として記録した420,000円が、4月30日に銀行口座へ振り込まれたとしましょう。
この場合、売掛金を取り崩し、同額を当座預金として記録する処理が必要です。なお、入金の段階では、現金の受け取りに関するものであり、収益の認識とは別の段階です。現金主義との違いが最も明確に表れる部分でもあり、実現主義ではこの時点ではなく、すでに納品時に売上は認識済みです。以下のように仕訳されます。
仕訳例:4月30日に代金が入金された場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
このように、実現主義では取引の流れに応じて適切なタイミングで仕訳を行い、財務状況を正確に反映させることが求められます。
まとめ
実現主義とは、収益や費用を「実現」したタイミングで会計処理を行う考え方です。具体的には、取引によって成果が確定し、経済的なやり取りが完了した時点で収益を認識します。
実現主義には、成果が確定した時点での実態がわかり、業績予測や経営分析がしやすい点がメリットです。一方で、現金収支とのズレが生じてしまい、代金の未回収リスクがある点がデメリットです。そのため、会計処理や記帳、仕訳でお困りの際は、経理代行会社に相談することがおすすめです。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
実現主義に関するよくあるご質問
実現主義についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、実現主義に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
実現主義とはどういう意味ですか?
実現主義とは、収益や費用を「実現」したタイミングで会計処理を行う会計基準です。たとえば、商品を出荷し顧客の受領が確認された段階など、取引が経済的に完了した時点で収益を認識します。現金の受け取りとは異なるタイミングで処理されるため、資金繰りとのズレが生じることもある点に注意しましょう。
実現主義と発生主義の違いは何ですか?
実現主義と発生主義の違いは、収益や費用を認識する「タイミング」にあります。どちらも現金の動きではなく経済的な出来事に基づいて処理しますが、実現主義は成果が実際に確定した時点(出荷や検収など)を基準とするのに対し、発生主義は契約の成立や役務の提供といった「権利・義務が発生した時点」で認識します。
実現主義と現金主義の違いは何ですか?
実現主義と現金主義の違いは、収益や費用を認識する「根拠」にあります。現金主義は、実際に現金の受け渡しが行われたタイミングで収益や費用を計上するため、キャッシュフローに連動しやすいのが特徴です。一方、実現主義は取引が経済的に成立し確定した時点で収益とするため、実際の入出金とのズレに注意しましょう。




