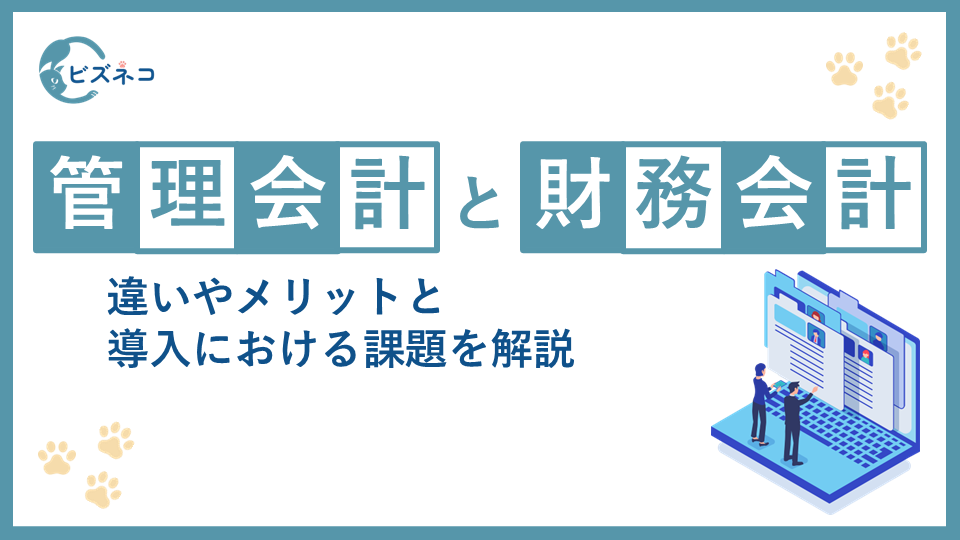
企業の経営を効率的かつ戦略的に進めていくうえで欠かせないのが「管理会計」です。財務会計が外部への報告を目的としているのに対し、管理会計は社内の経営判断や業績管理を支援するための会計手法です。
本記事では、管理会計の基本的な考え方から、財務会計との違い、具体的な業務内容、導入のメリット・デメリット、実務における課題や成功のポイントまでをわかりやすく解説します。これから管理会計を導入したいと考えている方や、基礎から見直したい方はぜひご覧ください。
目次
管理会計とは?
管理会計とは、企業の経営判断を支えるために、主に社内向けに作成や活用がされる会計情報のことを指します。財務会計のように外部報告を目的とするのではなく、企業の現状を把握し、将来の方向性を考える材料として使われる点が特徴です。
例えば、製品別の採算性を分析して事業戦略を見直したり、部門ごとの実績を比較して改善策を練ったりする際に、管理会計は重要な役割を果たします。数字をもとに客観的な判断を下すことで、無駄なコストを抑えたり、経営資源の最適配分につなげたりと、さまざまな経営課題の解決につながります。
管理会計の目的
管理会計の主な目的は、経営者や管理職がスピーディかつ的確に意思決定を行えるよう、必要な情報をすばやく提供することにあります。売上やコストの動向を把握し、課題の早期発見と改善策の立案に役立てることが中心です。
例えば、売上は好調でも利益が思うように出ていない場合、管理会計を通じてコスト構造を見直し、無駄を洗い出すことで収益性を改善する手がかりが得られます。また、予算と実績の差を分析し、今後の経営戦略に反映させることも目的のひとつです。
このように、企業の現状を把握するだけでなく、将来の方向性を導き出すための「経営の羅針盤」として機能するのが管理会計の役割です。
管理会計と財務会計の違い
管理会計と財務会計は、どちらも会計情報を扱うものですが、社内向けか社外向けかの違いがあります。管理会計は社内の意思決定や経営管理のために使われる情報で、形式やルールに縛られず、企業ごとに自由に設計できます。
一方で、財務会計は主に株主や金融機関、税務署など外部の利害関係者に向けて企業の経営成績や財政状態を報告するもので、法律に基づいた形式やルールが求められます。例えば、財務会計では製品別の損益は表示されませんが、管理会計ではそれを細かく把握し、どの製品が利益を生み出しているのかを分析することができます。
管理会計の業務内容
管理会計の業務内容としては、主に以下のような仕事があります。
- 経営分析
- 予実管理
- 原価管理
- 資金繰り管理
ここでは、それぞれの業務内容について、詳しく解説します。ぜひ、管理会計の導入を検討されている企業の方は、参考にしてみてください。
経営分析
経営分析とは、企業の現状や将来の見通しを把握するために欠かせない業務のひとつです。売上や利益、コストの構成、資産の効率性など、さまざまな指標をもとに経営状況を多角的に検証します。
例えば、売上高が増えているにもかかわらず利益が伸び悩んでいる場合には、固定費の比率や原価率に問題がないかを分析し、原因を特定して対策を講じる必要があります。このように、経営分析は現状を「見える化」するだけでなく、経営判断や将来戦略の立案に直結する情報を提供する役割を担います。
予実管理
予実管理とは、あらかじめ設定した予算(予)と実際の業績(実)を比較し、その差異を分析する業務です。企業が目標通りに進捗しているかどうかを確認し、必要に応じて軌道修正するための重要な指標となります。
例えば、営業部門の売上が予算を大きく下回っている場合、その原因が需要の変動なのか、営業活動の不足なのかを検討し、早急な対応を行う必要があります。予実の差異を正確に把握することで、経営層は迅速かつ柔軟な意思決定を行えるようになります。さらに、次期の予算策定にも活用できるため、継続的な改善と成長のサイクルを築く上でも重要な役割を果たします。
原価管理
原価管理は、製品やサービスの提供にかかるコストを把握や分析して、適正な価格設定や利益確保に結びつける業務です。企業にとって利益を最大化するには、売上だけでなく原価のコントロールが欠かせません。
例えば、ある製品の利益率が低下している場合、原材料費や人件費などのコスト構造を分析し、どこに無駄があるのかを見極める必要があります。原価管理は、現場のオペレーションと密接に関わるため、製造部門や調達部門との連携も求められます。細かな数値の管理を通じて、企業全体の効率化やコスト競争力の強化に貢献することができるのです。
資金繰り管理
資金繰り管理は、日々の資金の流れを把握し、必要なタイミングで資金を確保するための業務です。黒字経営であっても、手元資金が不足すれば運転資金の確保に支障をきたし、事業の継続が困難になることもあります。
例えば、売掛金の回収が遅れた場合には、仕入れや人件費の支払いに影響が出る可能性があるため、事前の資金計画と柔軟な対応が求められます。資金繰りを正確に管理することで、余剰資金の活用や金融機関との交渉においても有利に働くことがあります。
管理会計では、こうした日々の資金状況を見える化し、将来の資金不足リスクを回避するための判断材料として資金繰り管理が活用されます。
管理会計のメリット
管理会計のメリットとして、主に以下のような点があげられます。
- スピーディな経営判断につながる
- コスト削減の施策立案がしやすくなる
- 部門別に業績評価ができる
ここでは、それぞれのメリットについて具体的に解説します。
スピーディな経営判断につながる
経営環境の変化が日々かわるなか、企業には迅速な意思決定が求められています。管理会計は、日々の経営状況をタイムリーに把握できる仕組みを提供することで、経営判断のスピードを高める役割があります。
例えば、売上の急な落ち込みがあった際に、リアルタイムで損益情報を把握できれば、その背景をすぐに分析し、販促強化やコスト見直しといった対策を打つことが可能です。このように、管理会計は感覚や過去の経験に頼るのではなく、数値に基づいた判断を行うことで、経営のタイムロスを防ぐ役割を果たします。
コスト削減の施策立案がしやすくなる
企業の収益性を向上させるためには、売上の拡大とともにコストの適正化が欠かせません。管理会計はコスト構造を詳細に分析できる仕組みを備えており、削減すべき無駄を明確にするのに役立ちます。
例えば、製品ごとの原価を把握することで、利益率の低い商品に焦点を当てて製造方法や仕入れ先の見直しを検討することができます。こうした具体的な数値データに基づく分析を通じて、根拠のあるコスト削減施策を立案することが可能になります。また、継続的なコスト管理の仕組みを構築することで、一時的な削減にとどまらず、長期的な経営改善にもつながる点も管理会計の魅力です。
部門別に業績評価ができる
企業全体の業績を把握するだけでなく、部門ごとの貢献度を正確に評価することは、組織の健全な運営にとって大切な視点です。管理会計では、部門別の損益やコストのデータを集計・分析することで、それぞれの部門の業績を可視化することができます。
例えば、営業部門が目標を大きく達成していても、販促費が予算を大幅に超過していれば、利益面では改善の余地があると判断できるでしょう。このように、個別の部門ごとに実績を振り返ることで、成果に応じた評価やインセンティブの設定、改善すべき課題の洗い出しが可能になります。また、現場の責任感を高め、業績意識を促す点でも、部門別管理は組織全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。
管理会計のデメリット
管理会計のデメリットとして、主に以下のような点があげられます。
- 導入や運用に人的リソースがかかる
- 短期的な指標に偏る可能性がある
- 専門知識が必要で属人化しやすい
ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
導入や運用に人的リソースがかかる
管理会計の導入や運用には、一定の人的リソースを必要とする点がデメリットとなることがあります。新たな仕組みを構築するには、社内の体制整備やデータの収集方法の見直しが求められ、担当者にかかる負担も少なくありません。
例えば、部門別に損益を把握するための仕組みを作る場合、それぞれの部門から正確な数値を集め、統一されたフォーマットで管理する必要があり、その準備や教育には時間と労力がかかります。また、運用が軌道に乗るまでは試行錯誤が続くことも多く、日常業務と並行して管理会計の業務をこなすことに負担を感じる担当者もいるでしょう。
短期的な指標に偏る可能性がある
管理会計では、日々の業績やコスト状況を迅速に把握できるというメリットがある一方で、短期的な指標に偏ってしまうデメリットもあります。特に数値に基づいた評価を重視するあまり、長期的な視点や非財務的な価値が見過ごされるケースも少なくありません。
例えば、短期間でのコスト削減を優先するあまり、従業員教育や設備投資といった将来の成長に向けた取り組みが後回しにされると、企業全体の持続的な発展に悪影響を及ぼすことがあります。また、数字で測れないチームの連携力やブランド力などが評価対象から外れてしまうこともあります。
専門知識が必要で属人化しやすい
管理会計は、専門的な知識とスキルを要する領域であるため、社内で対応できる人材が限られている場合、属人化しやすくなるというデメリットがあります。例えば、特定の担当者だけがデータの集計や分析手法を理解している状況では、その人物が異動や退職をした際に業務の継続が難しくなる可能性があります。
また、会計やシステムに関する知識が不十分なまま運用が始まると、数値の解釈ミスや運用トラブルの原因にもなりかねません。属人化を防ぐためには、業務フローのマニュアル化やチーム内での情報共有が欠かせませんが、時間や体制の整備が必要です。
管理会計の導入における企業の課題
管理会計の導入における企業の課題として、以下のような点があげられます。
- 適切な指標を選定することが難しい
- 現場の実行力とギャップが生まれてしまう
- 部門間での情報連携が不足してしまう
ここでは、それぞれの課題について具体的に解説します。
適切な指標を選定することが難しい
管理会計を導入する際、最初の壁となるのが「何を測るか」という指標の選定です。企業が置かれている業種や規模、経営課題によって有効な指標は異なり、汎用的なものをそのまま当てはめても、的確な意思決定にはつながりません。
例えば、営業部門では売上や案件数が重要である一方、製造部門では生産効率や不良率といった指標が重視されるように、それぞれの業務に即した数値を見極める必要があります。しかし、複数の部門の視点を取り入れようとすると指標が複雑になり、かえって分析や運用が難しくなるケースもあります。指標選びは単なる数値設定ではなく、経営目標と現場の実態の間にある情報をどう橋渡しするかという課題でもあります。
現場の実行力とギャップが生まれてしまう
管理会計の仕組みを導入しても、現場で実行されなければ実質的な効果は得られません。数値目標や改善案が整理されていても、現場の理解が浅かったり、実行への負担が大きかったりすることで、経営層の意図と現場の動きにズレが生じることがあります。
例えば、コスト削減のための具体策が提示されても、現場では既存の業務に影響が出るため、消極的な反応に終わってしまうケースです。経営層と現場のギャップは、分析結果を具体的な行動へと転換する過程で発生しやすく、組織全体の成果にも影響を及ぼします。管理会計を有効に活用するには、現場の負担を考慮した運用設計が求められます。
部門間での情報連携が不足してしまう
管理会計では、正確なデータに基づいた意思決定が求められるため、複数の部門からの情報が必要になります。しかし、組織内での情報共有が十分でないと、部門間でデータの整合性が取れず、全体像をつかみにくくなることがあります。
例えば、営業部門が売上見込みを楽観的に見積もっていた場合でも、経理や生産側でその前提が共有されていなければ、在庫や資金繰りに影響が出る可能性があります。このように、情報が分断されたままでは、管理会計の正確性や信頼性が損なわれるばかりか、意思決定のスピードや質にも悪影響を及ぼします。導入を成功させるためには、部門ごとの目的意識をそろえ、共通の視点で情報を扱う体制を整えることが重要です。
管理会計を導入する際のポイント
管理会計を導入する際のポイントとして、以下のような点を意識しましょう。
- 導入する目的を明確にする
- 既存の業務内容にすり合わせる
- 経理代行会社とともに改善を続ける
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
導入する目的を明確にする
管理会計を導入する際には、まず何のためにそれを行うのかという目的をはっきりさせることが重要です。目的が曖昧なまま進めてしまうと、集めるべきデータや分析の方向性がぶれてしまい、実際の運用に結びつきにくくなります。
例えば、「利益率の向上を目指す」や「部門ごとの業績管理を強化したい」といった具体的な狙いがあれば、目的に応じた指標や分析手法を選定しやすくなります。目的が明確であればあるほど、導入時の判断基準もぶれず、関係者の理解や協力も得やすくなります。
また、導入後の成果を評価するためにも、最初に掲げた目的が指針となるため、計画段階での整理が欠かせません。管理会計は万能な仕組みではないからこそ、自社にとっての導入意義を丁寧に見極めることが求められます。
既存の業務内容にすり合わせる
管理会計を効果的に活用するためには、既存の業務プロセスとの整合性を取ることがポイントです。理想的な分析手法や管理体制があっても、現場の業務とかけ離れていれば運用が定着せず、実行性に乏しいものとなってしまいます。
例えば、現場では日報に基づいて業務内容を管理しているにもかかわらず、管理会計では週次のデータしか扱わないとすれば、情報のズレが生じてスムーズな運用が難しくなります。導入段階では、現在の業務の流れや報告体制をしっかりと把握し、無理のない形で管理会計を組み込むことが求められます。
業務と仕組みがかみ合っていれば、自然と現場にも浸透しやすくなり、データの質や分析の正確性も向上します。無理なく、実務に根ざした設計が成功のコツとなるでしょう。
なお、経理の業務フローの効率化については、こちらの記事も参考にしてください。

経理代行会社とともに改善を続ける
管理会計の導入や運用に不安がある場合は、外部の専門家である経理代行会社と連携しながら進めることもひとつの有効な方法です。専門知識を持つパートナーと協力することで、自社だけでは見落としがちな改善点にも気づきやすくなります。
例えば、自社では手間がかかっていた経費の分類や集計作業も、外部の視点を取り入れることで、より効率的な仕組みに見直すことができるかもしれません。また、第三者と定期的に状況を振り返ることで、運用のズレや課題にも早期に気づくことができます。
管理会計は導入して終わりではなく、継続的に改善を加えながら育てていくものです。信頼できるパートナーとともに、少しずつ運用を洗練させていく姿勢が、安定した成果へとつながっていきます。
なお、経理代行会社については、こちらの記事で詳しくまとめています。
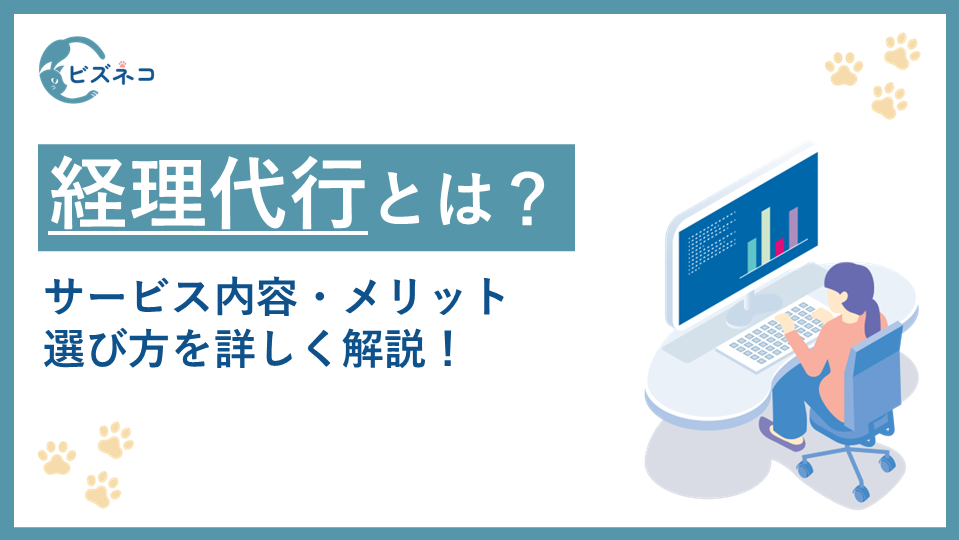
まとめ
管理会計とは、企業の経営判断を支えるために、主に社内向けに作成や活用がされる会計情報のことを指します。財務会計のように外部報告を目的とするのではなく、企業の現状を把握し、将来の方向性を考える材料として使われる点が特徴です。
管理会計を効果的に行うためには、導入する目的を明確にして、既存の業務内容とすり合わせていくことがポイントです。また、導入して終わりではなく、経理代行会社とともに改善を続けることもおすすめです。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
管理会計に関するよくあるご質問
管理会計についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、管理会計に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
管理会計とは何ですか?
管理会計とは、企業内部の意思決定や経営戦略の立案を支援するために用いられる会計手法です。財務会計が外部報告を目的とするのに対し、管理会計は社内の経営層や部門責任者が活用する情報を提供します。事業別の収益性分析や予算と実績の比較などを通じて、経営の現状把握や改善の判断材料を得ることができます。
管理会計と財務会計の違いは何ですか?
管理会計と財務会計は、どちらも会計情報を扱いますが、社内向けか社外向けかの違いがあります。管理会計は社内の経営判断を支援するために活用され、企業独自の基準や視点で柔軟に設計されます。一方で、財務会計は株主や取引先、税務当局など外部関係者への報告が目的で、法的なルールに基づいて作成されます。
管理会計を導入する狙いは何ですか?
管理会計を導入する目的や狙いは、経営に必要な情報を「見える化」し、より的確な意思決定や業績の改善に役立てることです。事業ごとの採算性を分析して非効率な部分を把握したり、予算と実績の差異から改善策を検討したりできます。また、数値に基づいた経営判断を行うことで、感覚に頼らない合理的な経営が実現可能です。




