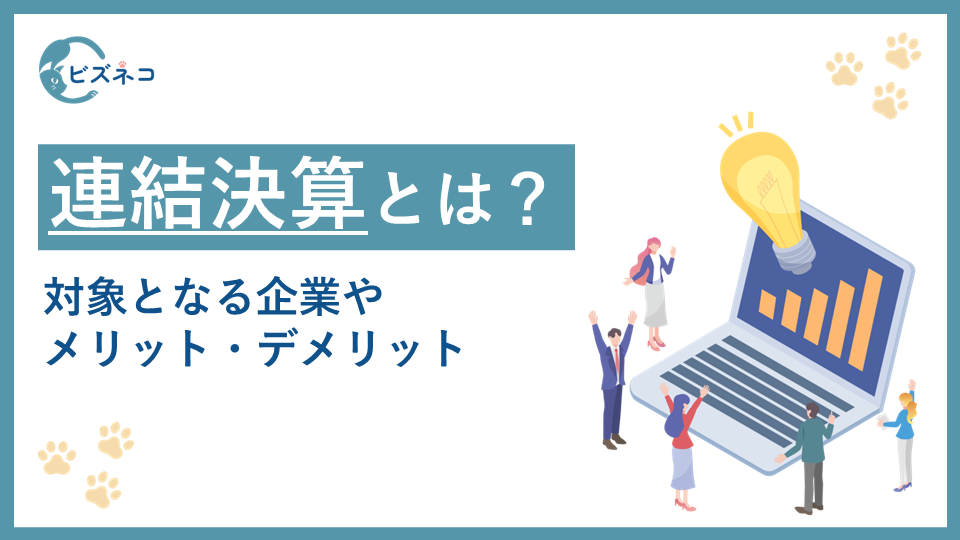
企業が成長し、複数の子会社や関連会社を持つようになると、グループ全体の経営状況を正確に把握する必要が生じます。そこで重要となるのが「連結決算」です。
連結決算とは、親会社と関係会社をひとつの企業体とみなし、財務諸表をまとめて作成する決算方法です。本記事では、連結決算の基本的な仕組みや対象企業、作成される財務諸表の種類を紹介します。また、連結決算の流れや行う際のポイント、メリット・デメリットについてもわかりやすく解説します。
目次
連結決算とは?
連結決算とは、親会社が子会社や関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財政状態を明らかにするために、ひとつの企業として財務諸表を作成する決算方法です。通常の決算では、それぞれの会社が独立して財務諸表を作成しますが、連結決算では親会社とその支配下にある子会社などの個別の会計情報を統合し、グループ全体としての財務状況を明示します。
例えば、親会社が黒字でも、子会社が大きな赤字を出している場合、その赤字がグループ全体にどのような影響を及ぼすのかを把握するには、連結決算が欠かせません。これにより、投資家や金融機関、株主などのステークホルダーは、企業グループ全体の健全性や収益性を判断しやすくなります。
なお、決算についてはこちらの記事も参考にしてください。
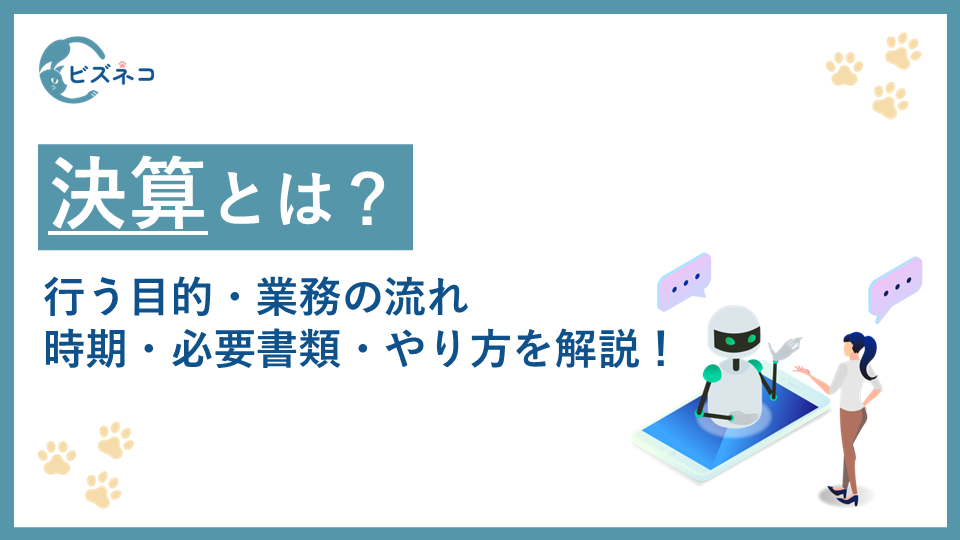
連結決算で作成される財務諸表
連結決算で作成される財務諸表として以下のような種類があります。
- 連結貸借対照表
- 連結損益計算書
- 連結包括利益計算書
- 連結株主資本等変動計算書
- 連結キャッシュ・フロー計算書
- 連結附属明細表
ここでは、それぞれの財務諸表について詳しく解説していきます。
連結貸借対照表
連結貸借対照表は、企業グループ全体の資産、負債、純資産の状況をひとつにまとめて表示する財務諸表です。親会社とすべての子会社の貸借対照表を合算し、グループ間の取引や債権債務を相殺したうえで作成されます。
例えば、親会社が子会社に貸付を行っていた場合、グループ全体では「貸付」と「借入」が同時に存在することになるため、連結上は相殺されます。このような調整によって、企業グループ全体としての正味の財務状況が明確になり、外部のステークホルダーにとってわかりやすい情報を提供することが可能になります。特に、資産規模や負債の内容を正しく把握するためには、連結貸借対照表が重要な役割を果たします。
連結損益計算書
連結損益計算書は、企業グループ全体の売上や費用、最終的な利益を一体化して示す財務諸表です。通常、親会社や子会社はそれぞれ個別に損益計算書を作成しますが、連結ではこれらを合算し、グループ内での売上や仕入れなどの内部取引を除外して、外部との純粋な取引による損益を明らかにします。
例えば、親会社が製品を子会社に販売した場合、売上と仕入は連結上では相殺されるため、グループ全体の実態としての収益や費用が反映されます。これにより、投資家や債権者は企業グループとしての実質的な経営成績を把握できるようになり、より正確な判断材料を得ることができます。
連結包括利益計算書
連結包括利益計算書は、連結損益計算書に記載される当期純利益に加えて、その他包括利益と呼ばれる項目を合算した、より広範な企業グループ全体の成果を示す財務諸表です。その他包括利益には、為替換算差額や有価証券の評価差額など、まだ実現していないが将来の損益に影響を及ぼす可能性のある項目が含まれます。
これにより、単に売上や費用だけでは把握できない、グループ全体の財務的な変動要素が明らかになります。企業の持つリスクや潜在的な利益をより立体的に示すことができるため、株主や金融機関にとって重要な判断材料となります。
連結株主資本等変動計算書
連結株主資本等変動計算書は、企業グループ全体の純資産のうち、特に株主資本に関する増減の動きを明らかにする財務諸表です。資本金や利益剰余金などの各項目がどのように変動したかを、親会社だけでなく子会社の動きも含めて示します。
例えば、子会社が配当を実施した場合、グループ内での資本移動であっても、連結上の株主資本に影響を与える可能性があります。また、新株発行や自己株式の取得などの取引もすべて反映され、資本構成の変化を時系列で追うことができます。これにより、企業グループ全体の資本政策や安定性を評価するうえで、欠かせない情報提供となります。
連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書は、企業グループ全体における現金の流れを、「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つの区分に分けて示す財務諸表です。そのため企業の資金繰りの健全性を判断するうえで重要な指標となります。
例えば、グループ全体で営業活動から十分な現金が得られているなかで、投資活動に多額の支出がある場合、将来の成長に向けた投資と捉えられるかもしれません。一方、営業キャッシュフローがマイナスで、財務活動からの借入で資金を補っているような場合は、短期的な資金繰りにリスクがあると判断される可能性があります。
こうした分析を通じて、企業グループの経営戦略や財務状況をより深く理解することができます。
連結附属明細表
連結附属明細表は、連結財務諸表を補足する情報を詳細に記載する資料であり、主に数値の内訳や会計方針の説明、重要な会計処理の内容などが盛り込まれています。連結財務諸表だけでは伝えきれない背景情報を提供し、グループ全体の財務内容に対する理解をより深める役割を果たします。
例えば、連結貸借対照表の資産項目に記載された「投資その他の資産」がどのような構成になっているのか、また評価基準が何に基づいているのかといった情報は、属明細表で確認することができます。透明性と信頼性を確保するうえで大切な資料であり、投資家や金融機関にとっては意思決定のための重要な参考情報となります。
なお、財務諸表や決算書の読み方については、こちらの記事も参考にしてください。
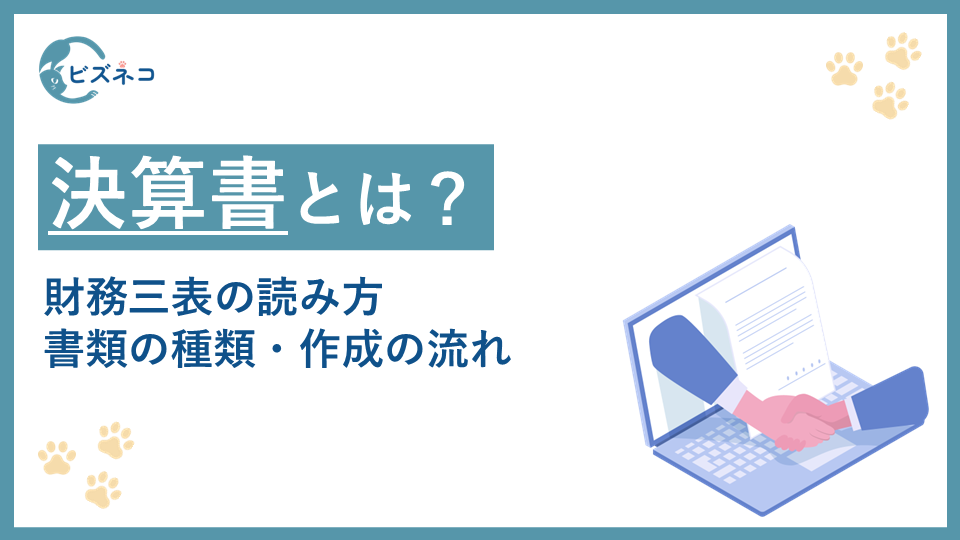
連結決算が必要な理由とメリット
連結決算が必要な理由とメリットとして、主に以下のような点があげられます。
- グループ全体の業績を把握できる
- 子会社・関連会社の不正を防止できる
- 金融機関や投資家から支援を受けやすくなる
ここでは、それぞれの理由やメリットについて詳しく解説します。
グループ全体の業績を把握できる
連結決算のメリットのひとつは、企業グループ全体の業績を一体的に把握できる点です。個別決算では、親会社や子会社それぞれの経営成績しか確認できず、グループ全体の経営実態を正確につかむことは困難です。
例えば、親会社が黒字であっても、複数の子会社が赤字を出していれば、グループ全体としては利益が圧迫されている可能性があります。連結決算を行うことで、こうした収益構造の偏りや資源の集中状況が可視化され、経営判断の精度が向上します。
また、特定の子会社に業績が依存している場合や、不採算部門が全体に与える影響なども明らかになり、経営戦略の見直しや事業再編の判断材料としても有効です。
子会社・関連会社の不正を防止できる
連結決算を通じて、子会社や関連会社の財務状況を本社が定期的に精査する機会が生まれるため、不正の防止にもつながります。例えば、子会社単体では見逃されがちな経費の不正処理や資金の流用といった行為も、連結処理の過程で異常な取引として浮かび上がる可能性があります。
連結決算では、企業間の取引や債権債務の整合性を取る必要があるため、通常の個別決算よりも詳細なチェックが求められます。こうした過程で、不自然な数値や取引の偏りに気づくことができれば、早期に問題の芽を摘むことが可能です。
さらに、グループ全体で内部統制が強化されることで、現場レベルでのコンプライアンス意識も高まりやすくなります。
金融機関や投資家から支援を受けやすくなる
連結決算を行うことで、企業グループ全体の財務内容や業績を包括的に開示できるようになり、金融機関や投資家に対して透明性の高い情報提供が可能となります。例えば、親会社が堅調な経営をしていても、子会社が大きな損失を抱えていた場合、個別決算だけではリスクが見えにくくなります。しかし、連結決算では影響が明確に示されるため、外部のステークホルダーはより実態に即した評価を下すことができます。
その結果、融資や投資に対する信用力が高まり、資金調達の面でも有利になるケースが多く見られます。また、上場企業においては、連結決算が開示の基準とされており、適正な情報開示を継続することで市場からの信頼を得ることにもつながります。
連結決算を行うデメリットと注意点
連結決算を行うデメリットと注意点として以下のような点があげられます。
- 作業が複雑になってしまう
- グループ会社間でスケジュールを組むのが大変
- 業務にかかる人的リソースが足りなくなる
ここでは、それぞれのデメリットや注意点について詳しく解説します。
作業が複雑になってしまう
連結決算を行ううえでの大きな課題のひとつが、作業の複雑さです。親会社と複数の子会社の財務諸表を統合し、さらにグループ内取引や債権債務の相殺処理を行う必要があるため、通常の個別決算とは比べものにならないほどの手間が発生します。
例えば、親会社が子会社に商品を販売し、まだ外部に販売されていない場合、利益分を未実現として控除する処理など、専門的な知識を要する調整が必要になります。また、企業ごとに会計方針や処理方法が異なっていれば、連結基準に合わせて統一しなければならず、細かな修正作業が重なります。
このように、連結決算は高度な会計スキルを求められるだけでなく、正確性とスピードの両立も求められるため、担当者にとって大きな負担となることが多いのです。
グループ会社間でスケジュールを組むのが大変
連結決算では、親会社と子会社、関連会社を含めて、すべての決算作業をほぼ同時に進める必要があり、スケジュール調整が困難になります。例えば、国内にある親会社が月末締めで決算を行う一方、海外子会社が月中締めのスケジュールで動いている場合、データの整合性を確保するために、どちらかの締め日や業務フローを変更する必要が生じます。
また、各社の決算準備状況や担当者のスキル差によって進行速度がばらつき、全体の遅延につながるケースも少なくありません。加えて、時差や言語の壁がある場合には、さらに調整の難易度が上がります。
このように、グループ全体でのスケジュール統一は、実務上大きな労力を伴い、少しの遅れが全体に影響を及ぼすリスクもあるため、慎重な管理が求められます。
業務にかかる人的リソースが足りなくなる
連結決算は高度で専門的な知識と経験が必要な作業であるため、実務に対応できる人材が限られているという点も大きなデメリットです。例えば、通常の経理業務に加えて連結処理まで一部の担当者が兼任している場合、作業が集中してしまい、残業や作業ミスのリスクが高まります。
また、新たに人員を補充しようにも、連結会計に対応できるスキルを持った人材の採用は容易ではなく、育成にも時間がかかります。特に、グループ会社が多い場合や、海外子会社があるケースでは、連携や調整の手間も増えるため、必要なリソースは想像以上に膨らみます。このように、連結決算の導入や運用を安定して行うためには、人的な体制強化が不可欠であり、人材確保と育成が大きな課題となるのです。
連結決算の流れ
連結決算の流れは以下のステップで進みます。親会社と子会社の会計データを統合し、適切な調整処理を行うことが基本的な業務フローとなります。
- ステップ1:子会社や関連会社が個別財務諸表を作成する
- ステップ2:親会社が子会社や関連会社の個別財務諸表収集する
- ステップ3:グループ会社全ての財務諸表を合算する
- ステップ4:連結修正仕訳を行う
- ステップ5:連結財務諸表にまとめる
連結決算ではまず、子会社や関連会社がそれぞれの個別財務諸表を作成し、その内容を親会社が取りまとめるところから始まります。例えば、各社の決算基準日が異なる場合は、連結決算の基準日と一致させるように調整が必要です。続いて、親会社はグループ全体の会計情報を収集し、企業ごとの財務諸表を一括して管理できる状態に整えます。
その後、すべてのグループ会社の財務数値を一度合算したうえで、グループ内の取引や債権債務の相殺、株式持ち合いなどに関する連結修正仕訳を行います。例えば、親会社が子会社から商品を仕入れた取引は、売上と仕入の両方が内部取引となるため、連結上では相殺して表示しないようにします。
こうした調整処理を経て、最終的に連結財務諸表を作成し、企業グループ全体の財務状況を一体的に示すかたちで外部に報告することになります。なお、基本的な経理の業務フローについては、こちらの記事も参考にしてください。

連結決算を行う際のポイント
連結決算を行う際のポイントとして、以下のような点があげられます。
- 親会社と子会社でスケジュールを調整しておく
- グループ全体で会計基準やシステムを統一する
- 連結決算が義務ではない中小企業でも実施する
ここでは、それぞれのポイントを具体的に解説します。
親会社と子会社でスケジュールを調整しておく
連結決算をスムーズに進めるためには、親会社と子会社の決算スケジュールを事前に調整しておくことが重要です。例えば、親会社が月末締めで決算を行っている一方、子会社が四半期ごとに締めをしている場合、親子間でのデータ連携に時間差が生じ、結果として連結決算に遅れが出る可能性があります。
そのため、すべてのグループ会社が同じ決算期を基準にして報告を行えるよう、早めにスケジュール調整をしておく必要があります。また、連結決算を行う際には、グループ全体の決算が締まった後で取引データの集約や相殺仕訳などの作業を一貫して行うため、全ての会社が期限通りに決算を完了させることが求められます。このような調整を欠かすと、決算作業の重複や遅延が発生し、最終的な報告書作成に支障をきたすことになります。
グループ全体で会計基準やシステムを統一する
連結決算を正確に行うためには、グループ全体で会計基準やシステムを統一することがポイントです。例えば、親会社と子会社で異なる会計基準を採用していると、それぞれの財務諸表の比較や調整が難しくなります。そのため、連結決算においては、すべてのグループ企業が共通の会計基準を使用することが求められます。
さらに、会計処理を一貫して行うために、システム面での統一も重要です。異なる企業が個別に異なる会計システムを使用していると、データの収集や集計作業に時間がかかり、ミスが生じやすくなります。例えば、子会社が使用する会計システムが親会社と互換性がない場合、データを手動で入力することになり、連結処理における効率性が大きく低下します。
こうしたリスクを回避するためには、早期に会計基準とシステムの統一を図り、連結決算をスムーズに進行させる体制を整えることが重要です。
連結決算が義務ではない中小企業でも実施する
連結決算は大企業にとって義務となっている場合が多いですが、義務ではない中小企業でも実施する価値があります。例えば、親会社が中小企業であっても、複数の子会社を抱えている場合、その業績を一元的に把握するために連結決算を実施することがおすすめです。
中小企業は通常、個別決算だけでは親子会社間の資金の流れや取引の実態を正確に把握するのが難しいため、連結決算によってグループ全体の経営状態を明確にすることができます。さらに、金融機関や投資家に対して透明性を高めるためにも、連結決算を実施することで信頼性が増し、資金調達がしやすくなることもあります。
もちろん、連結決算には手間やコストがかかりますが、その分、経営資源の最適化やリスク管理が強化されるため、経営者にとっては大きなメリットとなるのです。なお、中小企業の経理のやり方については、こちらの記事も参考にしてください。
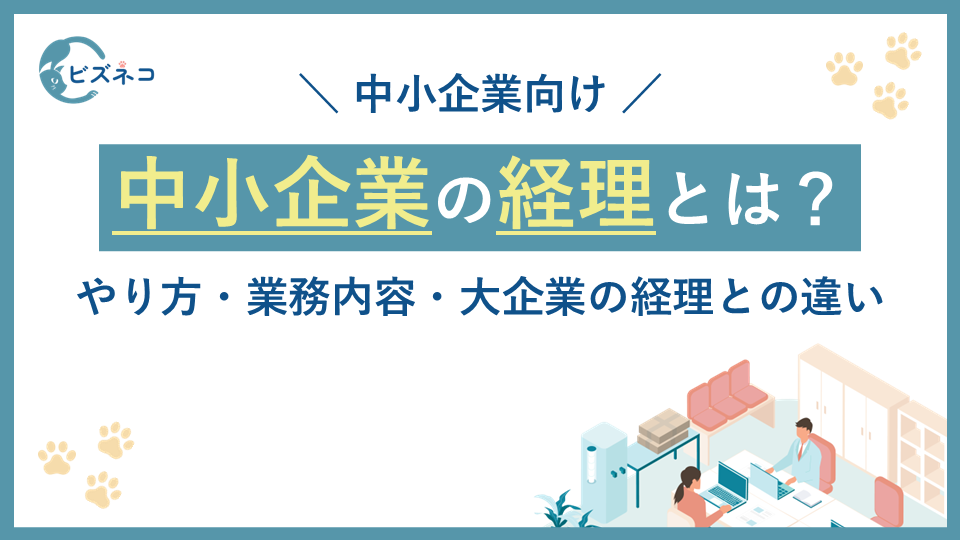
まとめ
連結決算とは、親会社が子会社や関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財政状態を明らかにするために、ひとつの企業として財務諸表を作成する決算方法です。グループ全体の業績を把握でき、子会社や関連会社の不正を防止できる点がメリットです。しかし、業務が複雑になってしまい、人的リソースが足りなくなってしまう点がデメリットです。そのため、連結決算を効率よく行うには、経理代行会社に相談することもおすすめです。
弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
連結決算に関するよくあるご質問
連結決算についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、連結決算に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
連結決算とはどういう意味ですか?
連結決算とは、親会社と子会社を含む企業グループ全体の財務状況を一つの単位としてまとめた決算のことです。個別企業の財務諸表に加え、グループ全体での業績や財務状態を示すため、子会社間での取引や債権債務は相殺処理されます。これにより、外部に対して実際のグループの経済状況を正確に伝えることができます。
連結決算をしなくてもよい会社は何ですか?
連結決算は、親会社が子会社を支配している場合に義務付けられていますが、一定の条件を満たす企業は実施する必要がありません。例えば、親会社が資本金の規模が小さい中小企業で、かつ子会社が少ない場合、連結決算は義務ではなく、親会社単独での決算が許されることがあります。
連結決算を子会社に行うメリットは何ですか?
連結決算を子会社に行うことで、親会社はグループ全体の業績を正確に把握することができます。例えば、個別の子会社だけでは見えにくいリスクや収益源を確認できるため、経営判断がより的確に行えます。また、グループ全体の資産や負債を一元的に管理することで、資金の流れを把握し、効率的な資源配分が可能になります。




